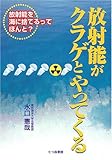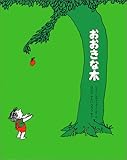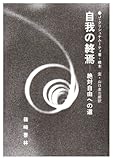情報弱者にならないために
高次元で生きましょう。 私たちは 普段からくだらない情報 つまらない情報に囲まれて生活しています。本当に大切な情報を共有するために 皆様と情報共有していきたいと思います。 再スタート (ブログタイトル変更しました)
最新の記事
月別
ブログ内検索
2009-10-04 16:10:47
子育て支援は・・思い切って 1億円支給を・・
テーマ:持論です♪武田氏は子育て支援の一時金に異を唱えていますが、私はそう思いません。何故ならば 恐らく財源は税金になると思いますが、子育て支援によって損をするのは子育てをしない(つまり産まない)夫婦、結婚しないで独身で一生を通す人たちでしょう。国民全員が子育てをする(経験する)ならば、子育て支援はお金の貸し借りに過ぎず何の損得もないはず。つまり子育て支援は事実上 子どもを産まないカップルから子どもを産むカップルへのお金の徴収(搾取?)に他なりません。 保育園を作る資金こそ重要でその父母に現金を支給とは何事か・・と異論を言う人の気持ちは感情論としては理解できますが、よーく落ち着いて考えて見て下さい。現行の年金制度では 圧倒的に子どもを産まないカップルの方が得をするのです。↓の岩上安身氏の論を読むとよくわかります。
武田邦彦 (中部大学): 「子育て支援」をどう考えるか?

日本人が消滅する日 第3回

このモデルケースで2億円も差が付くのですから、子育て支援としては、微々たる金額じゃなく、子ども1人あたり1億円を支給しても良いと私は思います。
皆様はどう思いますか。
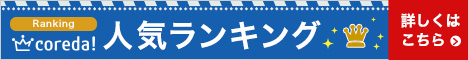

武田邦彦 (中部大学): 「子育て支援」をどう考えるか?

現代の日本は格差が広がり,景気ももう一つであることは確かである。しかし「子育て」のために,保育園などの公共の施設を作るのはともかく,夫婦に「一時金」を渡すというのはどういう論理から来ているのだろうか?
若いときは生活は厳しい.子供のミルクを買うために親が食事を減らすことはある.それこそ人間として最も大切なことではないか?
また,さらに踏み込んでみると,男女が機会均等で同じようなチャンスを持つことは大切で,そのためには子供の保育というのが最大の問題であることは十分,承知している。しかし,子供を保育園に預けることすら,親が最大限の努力をして育てなければならないという「子供の権利」を侵害しているように私には思える。
日本人が消滅する日 第3回

子育てコストの「ただ乗り」を許す現行年金制度
賦課方式の年金制度が、「世代間の不公正」をはらんでいるという批判は、マスメディアもしばしば取り上げている。しかし、子育てをしている世帯と、子育てをしていない世帯との間の格差については、ほとんど取り上げられることがない。
しかし、この賦課方式には、子供をもたずにいる方が経済合理的にはプラスになるという致命的な欠陥がある。保険料さえ支払い続けていれば、子どもを育てるコストを負担しなくても、年金を受給できるからである。そのために自分では子育てのコストを負担せず、他人が産み育てた子供が支払う保険料で年金給付を受け取る「ただ乗り(フリーライダー)」の存在を許してしまう。賦課方式の年金制度は、少子化促進的であり、子育てコストのフリーライダー奨励的なシステムであると言っても過言ではない。
話をわかりやすくするために、年齢や生涯賃金などの条件がまったく同じ二組のカップルがいると仮定しよう。一方の夫婦は妻が子供を二人産み、子育て終了後にパートで働き、もう一方の夫婦はDINKSとして働き続けたとする。その場合、二つの世帯の収支の差額は、2億2千500円~2億4千500万円にもなる。ここから所得税の扶養控除等を差し引いたとしても、2億円以上の差は残るだろう。年金の受給額も、妻が基礎年金(月額6万7千17円)しか受け取れない子育て世帯より、夫婦二人とも厚生年金(標準世帯の平均月額36万7千円)を受給するDINKS世帯の方が上回り、引退後も差がつく。彼らが受給する年金の保険料を負担しているのは、一方の子育て世帯が育てた子供達であるにもかかわらず――。
このモデルケースで2億円も差が付くのですから、子育て支援としては、微々たる金額じゃなく、子ども1人あたり1億円を支給しても良いと私は思います。
皆様はどう思いますか。
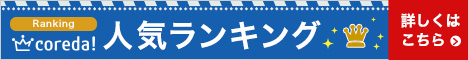
AD
![[プレスブログ]価値あるブログに掲載料をお支払いします。](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww2.pressblog.jp%2Fwatch%2Fpbtag.aspx%3Fpbid%3D7j6aRqB6u%252fE%253d)