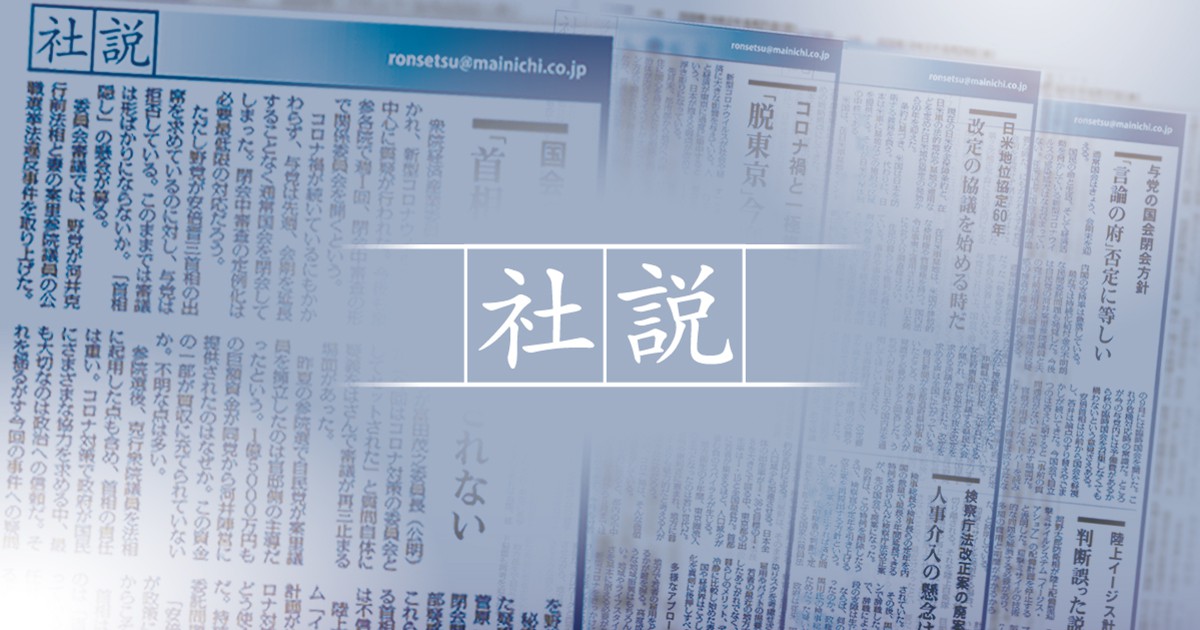-
再審は、再審であって、無罪ではない。理解しがたい、新聞&弁護士。-【毎日社説】袴田さんの再審公判 理解しがたい検察の対応
いや、まあ、タイトルにした通りだな。「再審」とは「審議のやり直し」である。有罪判決が出て確定した裁判に「再審」を命じられたのだから、「有罪判決は覆った。」というのは事実だろうが、「無罪判決が出た」訳では無い。言い替えれば、「再審決定」=「無罪確定」では、無い。「再審決定」で決まったのは、「再審の開始」である。コレは、再審決定した裁判の判決が死刑判決であろうが、その被告が高齢であろうが、関係ない。
「法の前の平等」とは正に、そう言う事、であろうに。元死刑囚だろうが現高齢者だろうが、ナンの関係も無い。
と、考えるのが普通であろうに・・・アカ新聞だとか、「人権派弁護士(大抵アカ)」とか言う連中は、そうは考えない、らしい。
☆
(1)【毎日社説】袴田さんの再審公判 理解しがたい検察の対応
袴田さんの再審公判 理解しがたい検察の対応
https://mainichi.jp/articles/20230711/ddm/005/070/206000c
朝刊政治面
毎日新聞 2023/7/11 東京朝刊 English version 833文字
冤罪(えんざい)からの救済という再審制度の趣旨からすれば、検察の対応は理解しがたい。
袴田巌さんの再審公判で、検察側は有罪を主張し、立証を進める方針を明らかにした。
1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で、80年にいったんは死刑が確定したが、今年3月に再審の開始が決まった。
過去に死刑確定後、再審公判が開かれた4人は、いずれも無罪となっている。袴田さんにも、無罪が言い渡される公算が大きい。
事件から57年がたつ。袴田さんは87歳になった。再審請求人の姉秀子さんも90歳である。
検察側が有罪を主張すれば、弁護側も逐一反論することになる。専門家らの証人尋問を実施する可能性もあり、公判は長期化が避けられない。
再審開始の決め手になったのは、犯人のものとされた衣類に付いていた血痕の色だ。事件の1年2カ月後、みそタンクの中から発見された。
東京高裁は弁護側の鑑定を踏まえ、みそに1年以上漬かれば、赤みは消えるはずだと認定した。
しかし、赤みは残っており、既に身柄を拘束されていた袴田さんが衣類をタンク内に隠すことは不可能だと指摘した。
検察側は血痕の付いた布を1年2カ月間、みそに漬ける実験を実施した。写真を示して「赤みが残っていた」と主張したが、退けられた。
高裁決定について、検察側は最高裁への特別抗告を断念した。再審を受け入れた意味は重い。
15年に及ぶ第2次再審請求の審理で、検察側も主張を尽くし、「血痕の色」を巡る争いは決着した。にもかかわらず、再び争点として持ち出すのは疑問だ。
写真や醸造、法医学の専門家らの意見を根拠に、改めて「赤みが残ることはある」と訴えていくという。弁護側は「蒸し返しだ」と批判した。
高裁決定は、タンクから見つかった衣類について「捜査機関が隠した可能性が極めて高い」と証拠捏造(ねつぞう)の疑いに言及している。
もともと証拠が乏しく、自白強要が疑われるなど捜査の問題点も明るみに出ている。その検証こそ、必要ではないか。
(2)【東京社説】袴田さんの再審 審理を長引かせるな
袴田さんの再審 審理を長引かせるな
https://www.tokyo-np.co.jp/article/262284?rct=editorial
2023年7月11日 07時43分
一九六六年に起きた静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審公判を巡り、検察側が「有罪立証」すると表明した。これまで争点となっていた「衣類の血痕」について反論するというが、審理を長引かせることは避けるべきである。
静岡地検は再審公判で「五点の衣類の血痕」について反論すると静岡地裁に伝えた。この衣類はあくまで犯行時に袴田さんが着ていたものとの主張である。
衣類は袴田さんの勤務先のみそタンクから発見された。当時の捜査資料では血痕の色は「濃赤色」と記されたが、弁護側は実験や鑑定に基づいて「長期間、みそ漬けにされた血痕には赤みは残らない」と主張。東京高裁も認めて再審決定につながった。
静岡地検は十日、「赤みが残ることは不自然ではない」ことを法廷で立証すると明らかにした。
確かに、同じ争点の場合、新証拠の証明力を弾劾する証拠であれば、提出可能とされている。
しかし、既に四十年以上も裁判のやり直しを求めていた事件である。第二次の再審請求審から九年間も「色」を巡る攻防が繰り返されてきた経緯もある。
問題の衣類は、確定判決の決め手だったが、そもそも袴田さんが着られるサイズでなかった。検察は「縮んだ」とも「袴田さんが太ったため」とも…。事件後、何と一年二カ月もたっての発見という経緯にも不自然さが残る。
今回の検察方針は、これまで争点でなかった事実や証拠を再審公判で唐突に持ち出すことには当たらないとしても、同じ論点でこれ以上、時間をかけることが本当に正義にかなうのか。
検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか。
東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性を指摘している。検察は「捏造」の言葉に拒否反応を示しているのかもしれないが、もはや検証すべきは当時の捜査の在り方を巡る問題点にほかならない。
袴田さんはすでに八十七歳になる。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従って、一刻も早く「無罪」の宣告をすべきと考える。
-
(3)検察の、対応こそが、正当だ。「冤罪の冤罪」回避のために。
章題に取った「冤罪の冤罪」ってのは見慣れない表記/聞き慣れない言葉、かも知れない。ひょっとすると、私(ZERO)独自の「造語」かも知れない。が・・・言いたいことは、判るよな?判らないか(*1)?
「実は無罪である者を、誤って有罪としてしまう。」のが、冤罪だ。ならば、「冤罪の冤罪」とは、 「実はは有罪な者を、誤って"冤罪"と判定してしまう。」事。謂わば、「罪の二重否定」であり、「罪の強調・強化」とも言い得よう。
人とは、神ならぬ者であり、間違いも失敗もするモノだ。であるならば、人が人である限り、「冤罪」とは「あってはならないモノ」ながら、「常にあるモノ」であり、ナニをどうやろうとも、「無くなる」なんて事は、(基本的に)無い(*2)。
「冤罪が、無くなることは無い」以上、「冤罪の冤罪もまた、無くなることは無い。」のが道理だ。
今回再審が決まった袴田被告の「冤罪」判定が、「冤罪の冤罪である」可能性も、勿論「ある、と考えるべき」であるのだから、再審は粛々と「審議のやり直し」として開始されるのが筋であり、検察の対応は「完全に法理に適っている」。
それを、「理解しがたい検察の対応」だの、「審理を長引かせるな」だのと批判してしまえるのが、上掲東京新聞&毎日新聞社説である。それは、少なくとも一面、「冤罪の冤罪を、助長している」のだが。
だぁが、此奴ら、「冤罪の冤罪を、助長している」って、意識も自覚も無いのだろうな。
或いは、ハナっから「冤罪の冤罪を助長し、我が国法秩序の弱体化を狙っている。」と考えた方が、安全側かな。
- <注記>
- (*1) 私(ZERO)に言わせれば、明々白々、なのだが。
- (*2) 私(ZERO)が唯一考えつく「冤罪根絶法」は「ありとあらゆる犯罪を罰しない事」だけだ。ありとあらゆる罪が罰されないのだから、冤罪は生じない。
- 無論、その場合、法も法秩序も事実上消滅する、「無法状態」が現出する。