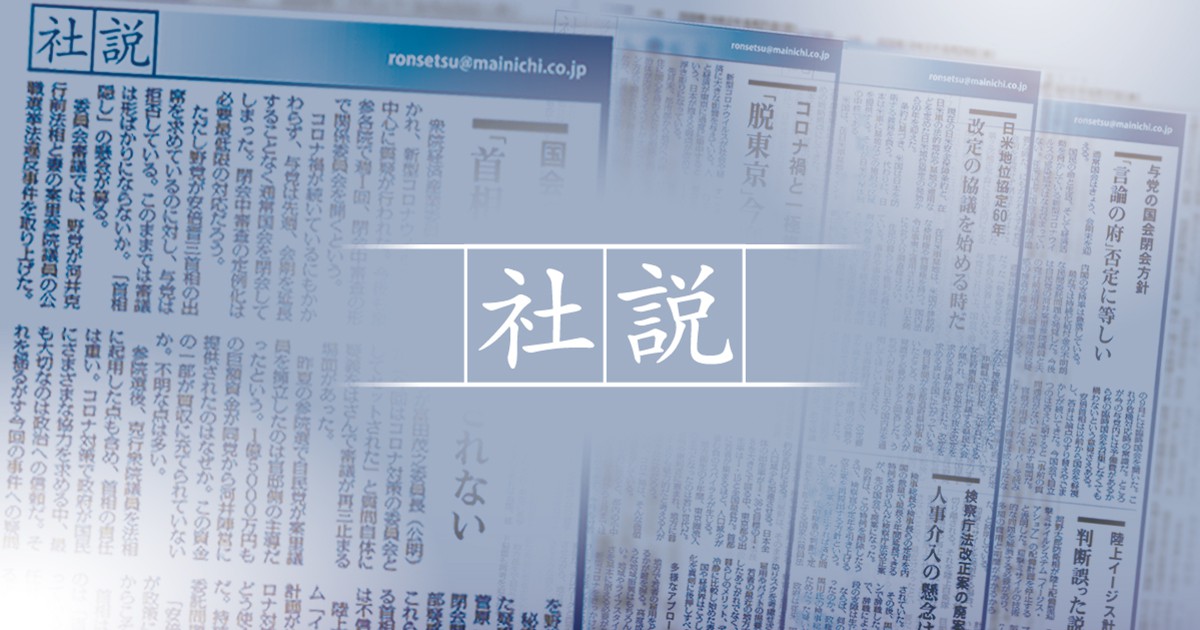-
憲法記念日社説に見る、日本国憲法信者共の騒ぎぶり
諸外国ならいざ知らず。「日本の憲法学者」ってのは「半分(以上)気違いだ。」と、私(ZERO)なんざぁ確信している。「全体の半数(以上)が気違いで、残りの半数(以下)が正気」なのか、全員が「一日の内、半日(以下)は正気を保っているが、半日(以上)は気が違っている」のか、或いはその中間の何処かなのか、には議論の余地もあろうが、「日本の憲法学者の半分(以上)は気違いだ。」と言う私(ZERO)の「確信」には、殆ど「疑義の余地が無い」。
「日本の憲法学者の半分(以上)は気違いだ。」と言う私(ZERO)が断定断言する理由の一つは、「集団的自衛権に対する考え方」だ。アカ新聞どもも「日本の憲法学者の過半数(恐らくは、大半)」も、「基本的国権」とも言うべき集団的自衛権に対して、「日本国憲法は、日本国自身に対して、集団的自衛権の行使を禁じている。」と断定断言して、憚るところが無い。
イヤ、左様な断定断言だけ、ならば、「まあ、そう言う考え方もあるね。」と、異論・異説・異端の一つとして許容も甘受も看過もし得るのであり、「気違いだ。」と断定断言するのも憚られよう。
だが、アカ新聞どもも、日本の憲法学者センセイ方(の過半数)も、「日本国憲法は、日本国自身に集団的自衛権の行使を禁じて居る」が故に、「日本国憲法は素晴らしい。」と絶賛賞賛礼賛してしまうのであるから、これはもう、「気違いだ」としか言いようが無い。諄いようだが繰り返すが「国家にとっての基本的国権」とも言い得る「集団的自衛権の行使」を「(他国なら未だしも)自国に禁じる日本国憲法」を「素晴らしい」と絶賛賞賛礼賛、してしまうんだぞ。
ああ、「日本国は、集団的自衛権の行使せず、基本的国権の一部を欠いても、十分に我が国の主権、我が国の領土領空領海、我が国民の生命財産を守り、保障することが出来る。」という十分説得力のあるロジックとセットならば、「自国自身に集団的自衛権の行使を禁じる日本国憲法」を絶賛賞賛礼賛するのも、「まあ良かろう。」と言うよ。そんなロジックも議論も疑義の提起も、一切無く、たぁだ「自国自身に集団的自衛権の行使を禁じる日本国憲法」の絶賛賞賛礼賛なのだから、「憲法教徒」とか「憲法信者」とか言うシロモノならば致し方なかろうが、「憲法学者」なんて自称出来るのは、「気違いである」としか、私(ZERO)には思えない。
ああ、安保法が法律として可決成立し執行されるまで、「日本国憲法は、日本国自身に集団的自衛権の行使を禁じて居る」のが「日本政府の公式見解だった。」事は知っているさ。ある意味「狂気の時代だった。」と言うことであり、それ即ち日本政府が随分と長い間「日本憲法学者&日本憲法学会の狂気」に感化されており、ある種の「気違いであった」証左・証拠である。「平和ボケ」なんて「美称」の「気違い」だ。
逆に、安保法によって、限定的ではあるが集団的自衛権の行使が可能となった我が国は、「幾らかだが、正気を取り戻した」と言うこと、でもある。
左様な次第であるから、5月3日の「憲法記念日」に寄せるアカ新聞社説と来たら、私(ZERO)の様な「憲法信者ならざる異教徒」には、「笑いの宝庫」となるのではないかと、期待できた。
①【朝日社説】平和憲法と安保3文書 民主主義の形骸化許されぬ
①A【朝日社説】日本国憲法と死刑 今こそ意見を交わすとき
②【毎日社説】憲法と安全保障 平和希求のあり方探る時
③【東京社説】憲法施行から76年 専守防衛は死んだのか
③A【東京社説】憲法記念日に考える 「偶然」と「必然」の赤い糸
④【沖縄タイムス社説】憲法記念日 平和の理念守る行動を
⑤【琉球新報社説】憲法施行76年 拙速な改憲論議はやめよ
☆
1.①【朝日社説】平和憲法と安保3文書 民主主義の形骸化許されぬ
平和憲法と安保3文書 民主主義の形骸化許されぬ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15627121.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年5月3日 5時00分
list
写真・図版
石垣島の自衛隊駐屯地=2023年3月10日、沖縄県石垣市、朝日新聞社機から、迫和義撮影
[PR]
亜熱帯林が広がる山肌が大きく削られ、ベージュ色の隊舎が立ち並ぶ。沖縄本島の南西、台湾に近い八重山諸島の中心である石垣島に3月、陸上自衛隊の駐屯地が開かれた。人口5万人弱のこの島が、ミサイル配備をめぐって揺れている。昨年末、安保3文書に敵基地攻撃能力の保有が明記されたからだ。
■ミサイルに揺れる島
石垣市が駐屯地の受け入れを表明したのは18年。配備されるミサイルは敵の着上陸を防ぐための「防御的な装備」と説明されていた。これが、他国にも届くとなれば、島が標的になりかねない。防衛省は長射程ミサイルをどこに置くかは「未定」と繰り返すが、石垣市議会は「到底容認できない」とする意見書を賛成多数で可決した。
島で生まれ育った宮良(みやら)麻奈美さん(30)は、東京の大学を卒業後、5年前に島に戻り、地元で働きながら、地域振興に取り組む。この間、同世代の若者らと、陸自配備計画への賛否を問う「住民投票を求める会」を立ち上げ、活動を続けてきた。
有権者の約4割の署名を集めたが、市議会や市は受け入れず、宮良さんたちは裁判に訴え、今も係争中だ。
仲間には、駐屯地に賛成の人も反対の人もいる。住民投票を求めるのは、賛否にかかわらず、市民が意思を示す場が必要だと考えるからだ。宮良さんはいう。「自衛隊の駐留もミサイル配備も、市民からすると、何が起きているのかよくわからず、意思表示もできないまま、市民がいないような形で進んでしまっている」
駐屯地受け入れに賛同していた人たちにも、不安や疑念を広げたのが、岸田政権が踏み切った敵基地攻撃能力の保有である。平和主義を掲げる憲法の下、日本の防衛の基本方針である「専守防衛」を空洞化させるもので、判断を誤れば、国際法違反の先制攻撃になりかねない。相手国からの攻撃を誘発する恐れもある。
■戦後の不文律どこへ
岸田首相は安保3文書の改定について、戦後の安保政策の歴史的転換だと胸をはったが、それに見合う国民的な議論はなされなかった。通常国会に入っても、「手の内は明かせない」などと、具体的な説明を避ける場面ばかりが目立つ。
そんななか、3文書に盛り込まれた方針の具体化が急ピッチで進んでいる。
安保関連予算「倍増」の初年度にあたる新年度予算は3月末に成立。防衛費は前年度から一気に1兆4千億円の大幅増となった。「借金で防衛費を賄わない」という戦後の不文律は破られ、護衛艦の建造費などに建設国債が充てられた。
政府の途上国援助(ODA)とは別に、「同志国」と認める途上国の軍に資機材の提供などを無償で行う政府安全保障能力強化支援(OSA)という新たな枠組みも創設された。
防衛装備品の輸出を後押しするなど、防衛産業への支援を強化する法案を国会に提出。武器輸出の緩和に向けた、自民、公明の与党協議も始まった。
野放図な軍拡につながらないよう、国債を防衛費には充てない。途上国への支援は、経済社会開発を目的とする。武器の輸出や技術の提供には厳格な歯止めをかける。
「平和国家」を支える規律が次々と骨抜きとなり、変質しかねない。しかも、それが、リスクを含めた情報開示と、異論にも向き合う丁寧な議論抜きに進んでいることは見過ごせない。
■合意形成の努力こそ
弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮。急速な軍拡を進め、力による一方的な現状変更もいとわない中国。そして、ロシアによるウクライナ侵略。
日本を取り巻く安保環境の厳しさを感じてか、敵基地攻撃能力の保有にも、防衛費の大幅増にも、賛同する国民は少なくない。だが、不安に乗じるかのように、政府が合意形成をおざなりにした先に何があるのか。
ウクライナ情勢を受け、欧州各国は安保政策の見直しを迫られた。日本と同じく、先の戦争に対する反省を戦後の国づくりの礎とするドイツは、紛争地に武器を送らないとしてきた原則を転換し、ウクライナへの武器供与に踏み切った。
ドイツ出身で仙台白百合女子大学で国際関係を教えるセバスティアン・マスローさん(40)は、ドイツ政府の対応は緊急措置として理解はできるとしつつ、幅広い合意をつくる時間がなかったと指摘する。
「国民の理解なしに進めれば、民主主義の弱体化を招く。合意形成がないと、支援疲れを起こして長続きしないし、極端な主張をする政治勢力の台頭を許す恐れもある。結果的にロシアの思うつぼになってしまう」
恐れるべきは「敵国」ばかりではない。政府が説明や議論を軽んじ、憲法が主権者と定める国民を置き去りにしたまま、国の大事な原則を次々と変えていく。真に恐れるべきは、民主主義の形骸化である。
(a) 国防は、国の所掌だ。愚か者。
☆
(b)①A【朝日社説】日本国憲法と死刑 今こそ意見を交わすとき
日本国憲法と死刑 今こそ意見を交わすときだ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15627875.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年5月4日 5時00分
list
1
写真・図版
支援者の前で話す袴田巌さん(右)と姉の秀子さん=2023年3月21日、静岡市葵区
[PR]
やっていない行為で逮捕され、死刑を宣告される。国家による、あってはならない人権侵害だが、1980年代には、死刑が確定していた4人が再審で無罪になっていた。
今年3月、袴田巌さんの再審開始が決まり、戦後5例目となる可能性が高まっている。
第2次大戦後、制定された日本国憲法は「すべて国民は、個人として尊重される」と掲げ、残虐な刑罰を禁じる。一方で死刑を想定すると読める規定ももつ。戦前からの死刑は残ったが、許容される刑なのかどうか、絶えず見直すべきだろう。
死刑の対象者が社会生活を送っている状況はまれだ。袴田さんから何を学ぶか、同じ時代を生きる私たちが問われている。
■冤罪そそぐ力も奪う
袴田さんは静岡地裁の再審開始決定に伴い、9年前に釈放された。姉秀子さんとの日々は穏やかだが、48年近くに及ぶ自由の拘束で精神を病み、コミュニケーションは難しい。
公判中、冤罪(えんざい)を訴え続け、手紙をたくさん書いていた袴田さんの変調は、80年に死刑が確定した後、進んでいった。
「隣の部屋の人が昨日、処刑された」「『お元気で』って言っていた」。面会にきた秀子さんにそう伝えた後、何年間もだれとの面会も拒んでいたこともある。名前で呼びかけた人には、本人であることを否定し、妄想の世界の言葉を重ねた。
死刑執行と向き合う恐怖と孤独が、自ら冤罪をそそぐ意思や能力も奪っていた。
袴田さんの再審請求は、秀子さんと弁護団が続けていたが、100人以上いる死刑確定者には家族や支援者とのつながりがとうに絶えた人も少なくない。
■現代にかなうのか
死刑制度は、誤判で執行されたら取り返しがつかないこと、国家が個人の生命を奪うことへの根源的な疑問など、さまざまな問題をもっている。絞首刑という方法には、死刑存置の立場からも批判がある。朝日新聞の社説は、廃止に向けた議論を始めることを呼びかけてきた。
罪を犯した人が刑に服し、自らの責任と厳粛に向き合う大切さはいうまでもない。犯罪被害者や遺族を孤立させず、支援や補償を手厚くしていくことも、併せて考えていく課題である。
一方、刑罰制度は処罰感情に任せるのではなく、罪に見合った刑をめぐり社会が重ねてきた合意に支えられるべきものだ。
その前提で、死刑の本質を見つめることから始めたい。
袴田さんの経験からわかるのは、死刑は命を奪うことにほかならないのに、執行までの日々の過酷さも事実上の刑となっていることだ。身体より先に心を殺す刑と指摘されるゆえんだ。
死刑が確定すると、心情の安定を理由に、他者との交流は厳しく制限される。一人部屋で過ごし、面会や手紙の相手も近親者らに限られる。
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」という憲法の規定に死刑が適合するか問われた裁判で、最高裁大法廷は1948年、合憲と判断した。憲法施行から10カ月後のことで、今日までの司法判断もそれに沿うものだ。
判決は裁判官11人の全員一致だったが、4人は補充意見で、社会の変化によっては死刑が排除されることもあるとし、将来の選択に道を開いていた。
それから75年。56年には議員提案の死刑廃止法案が国会で審議され、89年から3年4カ月は執行が途絶えた。2009年から死刑対象事件の裁判に市民が参加するなどいくつかの節目があったが、死刑存廃の議論を深めるには至らなかった。
その間、世界では死刑廃止の流れが加速し、世界の7割の国は死刑を行っていない。日本以外の先進国で唯一死刑を続けてきた米国も、2年前、連邦での死刑執行の停止を決めた。
■話し合いの土台を
死刑制度にかんする19年の政府の世論調査では8割が「死刑もやむをえない」と答えた。国会の場や、国連人権機関などから廃止を促されると、政府は「国民の多数の支持」を最大の論拠として反論してきた。
だが、政府は人々が死刑について意見を形成するために必要な情報を十分に提供してきたといえるだろうか。情報は法務省に集中しているが、刑場を報道機関に公開したのは民主党政権時代の1回だけだ。執行状況などの情報公開請求にはほぼ黒塗りの文書で応じるなど、後ろ向きな姿勢を貫いてきた。
死刑廃止を目指している日本弁護士連合会は昨年11月、死刑に代わる新たな最高刑として終身拘禁刑を創設する提言をまとめた。議論の土台になる。
対象者の処遇や執行に携わる公務員の考えにも耳を傾けたいが、発信の場はほとんどない。かつての死刑廃止法案の審議では執行を担った法務省幹部が公述人になり、個人の意見として死刑廃止を求めたこともある。
執行を一時停止し、知見を集め自由に意見を交わす。その機会を今こそ逃すべきではない。
(c) 死刑制度が厳然と存在する以上、死刑は執行されるのが当然である。大体、確定した死刑は半年以内に執行されるよう、法律で決まっているのであるから、現在停滞して居る百人以上に及ぶ確定死刑囚は、今この瞬間に全員死刑執行しても、何ら文句を言われる筋合いは、無い。これは憲法の問題ですら無く、単に、法律の問題だ。
☆
2.②【毎日社説】憲法と安全保障 平和希求のあり方探る時
憲法と安全保障 平和希求のあり方探る時
https://mainichi.jp/articles/20230503/ddm/005/070/040000c
朝刊政治面
毎日新聞 2023/5/3 東京朝刊 English version 1663文字
ロシアによるウクライナ侵攻が続き、東アジアの安全保障環境も厳しさを増す中、76回目の憲法記念日を迎えた。
日本国憲法は9条で戦争放棄と戦力不保持などをうたう。その憲法の平和主義と整合性を取りつつ、防衛力を整備する考え方が「専守防衛」の原則だ。
自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力を持つにとどめ、「盾」に徹する。日本に駐留する米軍が「矛」の役割を果たすことで成り立ってきた。
理想を掲げる9条に対して、日米安全保障条約は同盟のリアリズムに基づく。
「憲法と日米安保がお互いの緊張関係を保ち、一つの円にはならない。これこそが戦後日本の政治外交の選択肢である」
宏池会(岸田派)前会長の古賀誠・自民党元幹事長は、雑誌「世界」のインタビューで語った。
変容する専守防衛原則
かつて宏池会会長だった大平正芳元首相が唱えた「楕円(だえん)の哲学」を援用した。二つの軸が緊張した均衡関係にある方が、物事がうまく進むという考え方である。
憲法は、先の大戦の悲惨な体験を踏まえて生まれた。連合国軍総司令部(GHQ)占領下で制定されたが、平和を願う国民は歓迎した。だからこそ定着し、今日まで続いている。
根底には、1928年のパリ不戦条約から脈々と続く思想がある。第一次世界大戦の反省を受けて戦争放棄を宣言したものだ。
だが、国際情勢の変化に伴い、戦後日本を規定してきた楕円の二つの軸の関係は揺れ動いている。
自衛隊の存在は時代を経るごとに大きくなり、国際社会における日本の役割も拡大した。冷戦終結後には日米安保が再定義された。
第2次安倍晋三政権下では集団的自衛権の行使が可能となる安全保障関連法が施行され、自衛隊の米軍との一体化が進んでいる。
政府が昨年末に閣議決定した安全保障3文書の改定は、その流れの延長にある。「新時代リアリズム外交」を掲げる岸田文雄首相は、日米安保条約締結や安保法制などと並び、「日米同盟の強化にとって、歴史上最も重要な決定の一つ」だと位置づけた。
3文書には「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有が明記され、政府は防衛関連予算を2027年度までに国内総生産(GDP)比2%に倍増させる方針だ。戦後の安保政策の大転換にあたり、専守防衛のあり方が変容している。
米国は同盟国と協力して抑止力を高め、軍事大国化する中国に対抗する戦略を取っている。日本政府の防衛力強化は、それに呼応した動きだ。
安全保障上、相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力を各国は必要としている。それが国際政治の冷徹な現実だ。ただ、緊張緩和の努力を欠いたまま抑止力強化に走れば、際限のない軍拡競争を招く「安全保障のジレンマ」に陥る恐れがある。
新たな歯止めの議論を
中国の海洋進出や北朝鮮の核・ミサイル開発などを受け、防衛力整備に理解を示す世論は広がっている。一方で、平和を願う国民の思いは揺らいでいない。
戦後日本の指針となってきた9条の理想を忘れることなく、目の前の現実に対処するしなやかさが求められる。時代状況に合わせて専守防衛のあるべき姿を考える必要がある。
だが、首相は反撃能力と憲法の整合性を問われると「安保環境は大きく変化した」などと言うだけで、問題に向き合っていない。
専守防衛の観点から自衛隊は何ができ、何ができないのか。新たな歯止めが欠かせない。そのために重要な役割を担うのが国会だ。
防衛力の強化には裏付けとなる予算が必要となる。自衛隊の活動範囲や装備がなし崩し的に拡大しないよう、国会審議で野党は厳しく問いただし、政府は正面から答えなければならない。
外交努力も不可欠である。
日本外交の基軸は日米同盟だが、隣国の中国との関係は経済面などで死活的に重要だ。激化する米中対立に翻弄(ほんろう)されないよう、日本には楕円の知恵を生かした戦略が求められる。
力だけでは平和や安定を維持できない。緊張緩和に向けて地域の国々と対話を重ね、経済・文化の交流を深めることが肝要だ。平和を希求する重層的な取り組みに努めなければならない。
3.③【東京社説】憲法施行から76年 専守防衛は死んだのか
憲法施行から76年 専守防衛は死んだのか
https://www.tokyo-np.co.jp/article/247867?rct=editorial
2023年5月4日 07時42分
戦争放棄と戦力不保持を明記した日本国憲法九条は、先の大戦で日本国民だけでなく内外の人々に多大な犠牲を強いた反省から発した「不戦の誓い」です。
戦後日本は九条に基づく専守防衛を堅持し、平和国家として歩んできましたが、二十一世紀に入って、専守防衛を形骸化させる安全保障政策の転換が続きます。
憲法施行による不戦の誓いから七十六年。「専守防衛は死んだのか」との問いにはこう答えるほかありません。「死んではいないと信じたいが、瀕死(ひんし)の状態であることは認めざるを得ない」と。
専守防衛とは日本独特の用語です。二〇二二年版防衛白書は次のように説明しています。
「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則(のっと)った受動的な防衛戦略の姿勢をいう」
つまり国連憲章が認める自衛権のうち自国に関わる個別的自衛権しか行使しないというもので、この記述は長年一貫しています。
しかし、自公連立政権下で専守防衛を事実上、変質させる安保政策の転換が続いています。一つは安倍晋三政権が二〇一五年に成立を強行した安保関連法で、歴代内閣が憲法違反との政府解釈を堅持してきた「集団的自衛権の行使」を可能にしました。
もう一つが岸田文雄政権が昨年十二月に改定した国家安保戦略です。歴代内閣が「憲法の趣旨ではない」としてきた「敵基地攻撃能力の保有」を一転認める内容で、これまで国内総生産(GDP)比1%程度で推移してきた防衛費を関連予算と合わせて2%程度に倍増する方針も表明しました。
◆平和国家の歩みと矛盾
こうした安保政策転換が専守防衛を逸脱し、憲法と矛盾することは一見明白ですが、岸田首相=写真(左)、二二年十一月の国際観艦式で=は「非核三原則や専守防衛の堅持、平和国家としての歩みを変えるものではない」と述べています。これは詭弁(きべん)ではないのか。
まず、集団的自衛権を行使するということは、自国が攻撃されていないにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国への攻撃を自国への攻撃と認め、反撃することですから、「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使」する専守防衛とは、明らかに相いれません。
そもそも意味合いが異なる集団的自衛権を個別的自衛権とひっくるめて、憲法が認める「自衛権の行使」だと強弁することには、無理があります。
敵基地攻撃能力の保有も同様です。岸田政権は三文書の決定を受けて、長距離巡航ミサイルなど外国領域を直接攻撃できる装備の調達に着手しましたが、専守防衛で保持できるとされる「自衛のための必要最小限」の防衛力を超えるのは明白です。
戦後日本が歩んできた、他国に軍事的脅威を与えない「平和国家の歩み」からも逸脱します。
そして防衛費の倍増です。GDP比1%という目安は「軍事大国にならない」という平和国家として歩む宣言でもありました。
それを関連予算と合わせてではありますが、ロシアと対峙(たいじ)する北大西洋条約機構(NATO)並みの2%程度に倍増させるということは、国際社会には、平和国家の歩みを止めようとしているように映るでしょう。
こうした数々の例が挙げられても、専守防衛に変わりはないというのは、どういった根拠に基づくのか。岸田首相は明白に論拠を示して語らなければ、とても説得力はありません。
◆不断の努力で守る誓い
日本が再び戦火に巻き込まれれば、憲法で保障された自由や基本的人権は戦前戦中のように蔑(ないがし)ろにされます。日本が専守防衛を堅持し続けることこそが、基本的人権を守ることになるのです。
憲法には「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(九七条)であって、そうした自由や権利は「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(一二条)との記述があります。
戦争に突き進まず、自由や基本的人権を守るには、九条だけでなく、憲法条文に込められた先人たちの決意を読み取り、不断の努力を続ける必要があります。
それこそが不戦の誓いというバトンを受け継ぐ今を生きる私たちの使命ではないでしょうか。
(a) 憲法は、とっくの昔に「死んで」居る。自衛隊発足時点で、「現実との乖離」は致命的であった。
(b)③A【東京社説】憲法記念日に考える 「偶然」と「必然」の赤い糸
憲法記念日に考える 「偶然」と「必然」の赤い糸
https://www.tokyo-np.co.jp/article/247703?rct=editorial
2023年5月3日 07時50分
「忠」という言葉があります。江戸時代の武家社会では、主君に忠節を尽くすことが根本でした。
では、主君が暴君だったら?。暴君による暴虐や不正、理不尽な命令に対してまでも、家臣たちは服従すべきなのでしょうか。
実は「なりませぬ」と主君を諫(いさ)めることこそ、武士道での忠義の本質だったそうです。著書「主君『押込(おしこめ)』の構造」で知られる歴史学者の笠谷和比古(かずひこ)氏から、かつて聞いた話です。
◆主君押し込めの論理は
「手討ちや切腹になりかねないけれど、我が身の不利益をも顧みず、あえて主君の命に抗することが真の忠節です。逆にお家のためにならないことが分かっていながら、同調することは、許し難い不忠とされたのです」(笠谷氏)
でも、暴君とは家臣の命懸けの諫言(かんげん)にも耳を貸さず、権力を強行する存在です。その場合は?。
「『主君押し込め』です。諫言を阻却し、藩士や領民を苦しめるとしたら、家臣団は力を用いて藩主を交代させても構わないという考えでした。藩主を座敷牢(ざしきろう)に押し込め、隠居させたのです」
権力の暴走をどう防ぐか?。近代の欧米社会では「憲法の力」によって、権力を縛り、暴走させない?。そのような立憲主義の考え方をとりました。
歴史は偶然と必然の糸が絡み合って動いていくものです。
幕末のペリー提督の黒船来航は、日本側には「偶然」に見えたかもしれませんが、米国側にすれば「必然」です。大統領の親書を携え、開国と条約締結を求めにやって来たのですから…。
明治政府の重鎮・岩倉具視(ともみ)たちが一八七一(明治四)年から七三(同六)年にかけて欧米諸国を回ったのも歴史の必然です。文明の視察にとどまらず、社会を動かす中核的な原理を探す旅でした。
たどり着いたのが「憲法」でした。それゆえ一足先に帰国した重鎮の一人、木戸孝允(たかよし)は早々に憲法意見書をまとめています。
さらに伊藤博文が憲法調査のため英国やドイツなどに派遣され、著名な学者たちに学びました。伊藤の成果は後に、枢密院で述べた言葉に表れています。
<憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり>
個人は多くの自由と権利を持っていますが、権力はときにそれを奪ったりします。だから、権力を制限せねばならない。立憲主義の本質を見事にとらえています。
◆奇妙な出来事の共通点
憲法により権力の暴走を防ぐ?そんな仕組みです。さて現代の為政者たちは伊藤博文の理解をどれだけ身に付けているでしょうか。
近年、奇妙な出来事がいくつも起こりました。例えば内閣法制局や日銀、NHKなどのトップに首相のお友達を据えました。
独立機関は政府と対抗することも前提として、民主政はつくられています。憲法秩序の一形態として、権力の暴走を防ぐ装置が統治機構に埋め込まれているのです。
ところが、お友達人事が横行すれば、政府の暴走への歯止めとはなり得ません。検察庁法を解釈変更してまで、息のかかった高検検事長の定年延長を図ろうとしたこともありました。
日本学術会議は科学分野の「ご意見番」ですが、従来の政府見解を破って、首相が会員候補の任命拒否をした出来事もありました。
放送局は「表現の自由」や国民の「知る権利」を担う機関ですが、放送法を事実上、解釈変更した舞台裏も判明しました。政府は「けしからん番組は取り締まる」つもりだったようです。
さて、一連の出来事は「偶然」でしょうか。共通点はどれも独立機関です。つまり権力の暴走を防ぐ装置を権力自ら一つずつ破壊していることです。「なりませぬ」と諫言できる存在を消し去っているのです。民主政に仕組まれた歯止めがなくなれば、「暴君」が現れてしまいます。
権力自ら憲法秩序を破壊しているなら、それこそ権力の暴走です。そもそも権力者たちが一生懸命、憲法改正の旗を振っているのも何とも不思議な構図です。
伊藤博文が言い当てたように、憲法とは「権力の制限」に目的があるのですから…。自分たちに都合のいいように憲法を変えたいのではと勘繰られます。
◆「なりませぬ」の声を
憲法に基づく立憲政治、民主政治では常に「なりませぬ」の声が為政者の耳に届かなくてはならないはずです。われわれも主権者として、権力の横暴や、自由や権利の侵害には勇気をもって「ノー」の声を上げるべきなのです。
怠れば「暴君」の出現を許してしまいます。それも歴史が教える「必然」の姿です。
(①) ここまで来ると、ポエムだぞ。「社説がポエム」ってのは、褒め言葉ではない。寧ろ、悪罵に近いモノがあるぞ。
☆
4.④【沖縄タイムス社説】憲法記念日 平和の理念守る行動を
憲法記念日 平和の理念守る行動を
https://nordot.app/1026223936037634048?c=62479058578587648
2023/05/03
憲法施行から76年を迎えた。1972年5月15日に日本復帰した沖縄では、憲法が適用されてから、51回目の憲法記念日となる。
73年5月3日、復帰後初の記念日に、本紙は1面で「異民族支配の下で、県民が求めてきた平和憲法の理念はすでに空洞化している」と、憂慮する記事を掲載した。
沖縄への自衛隊配備、米軍の駐留、地主が反対しても強制的に米軍用地として使用する公用地暫定使用法などを理由に挙げている。
それから半世紀。空洞化が進むどころか、「憲法9条は死んだ」とさえ言われるようになった。
9条は1項で戦争放棄、2項で戦力不保持を定めるが、日本は解釈による「改憲」を繰り返してきた。
施行から7年目の54年には自衛力の保持や自衛権の行使は9条に違反しないと、自衛隊を発足させた。92年には自衛隊の海外派遣、2014年には条件付きで集団的自衛権の行使を容認した。
そして昨年12月の安保関連3文書で、敵基地攻撃能力を言い換えた「反撃能力」の保有を明確に打ち出した。
自衛隊が他国領域のミサイル基地などを攻撃する態勢を整える内容で、大幅な政策転換である。政府はそのための長射程ミサイルの沖縄への配備を否定していない。
海外で武力行使しない、専守防衛に徹するという辛うじて維持してきた平和憲法の中心部分が抜き取られた。
にもかかわらず、国民的な関心は高まらない。そこに危うさを感じる。
■ ■
憲法9条の源流は、第1次世界大戦後の国際協調の中で結ばれた1928年のパリ不戦条約である。戦争放棄をうたっている。
日本は条約に署名しながら満州事変の発端となった31年の柳条湖事件で、南満州鉄道の線路爆破を中国軍の仕業と見せかけ、「自衛のための戦争」に突き進んだ。戦火を広げ、その果てに多くの住民を巻き込んだ沖縄戦があった。
戦後日本の出発に当たり、不戦条約の理念に立ち返ったのが憲法9条である。人類、世界の2次にわたる大戦の反省が詰め込まれている。
自衛力や有事の備えといった軟らかい言葉を使っても、他国は軍備増強と捉える。
日本はまた、誤った道へ進もうというのであろうか。不戦条約や憲法9条の理念をほごにすることは許されない。
日本だからこそ、国際社会、アジアの平和秩序の構築に果たすべき役割がある。
■ ■
沖縄県は4月から地域外交室を設置し、「平和の緩衝地帯」になるための取り組みを始めた。南西諸島の防衛強化が進む中で、沖縄からの発信力を高めたい。
憂えてばかりも嘆いてばかりもいられない。憲法9条を守れば、戦争は起きない、平和を実現できるという考えはもはや幻想ではないか。
追求しなければ、平和を守れない。ノーと言い続けなければ、戦争はやってくる。
一人一人の声や行動で平和憲法を蘇生させ、米軍統治下の沖縄で県民が求めていた真の理念を取り戻したい。
(a) 正に、気違い。
☆
5.⑤【琉球新報社説】憲法施行76年 拙速な改憲論議はやめよ
憲法施行76年 拙速な改憲論議はやめよ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1704054.html
2023年5月3日 05:00
社説
mail_share
日本国憲法は施行から76年を迎えた。国会では「改憲勢力」が国会発議に必要な3分の2以上の議席を確保し、改憲論議を加速させている。しかし、国民の機運は盛り上がらない。何のための改正か、改正を急ぐ必要があるのか。世論は割れている。
共同通信が3月から4月にかけて実施した世論調査によると、多くの国民が改憲の必要性があるとしつつ、改憲の機運は高まっていないと感じている。国会での改憲論議を「急ぐ必要がある」が49%、「急ぐ必要はない」が48%で拮抗(きっこう)した。衆院憲法審査会の毎週開催が定着したが、機運上昇につながっていない。
人口減や少子高齢化、気候変動、安全保障環境の不安定化などさまざまな情勢が変化している。これらの問題に対応するため憲法改正が必要だというのが、「改憲勢力」の基本姿勢だ。ただ、最高法規である憲法を改正しなければ諸課題に対処できないのか疑問だ。拙速な改正ありきの論議は許されない。
衆参両院で国会発議に必要な議席を得たことを受け、岸田文雄首相は「できる限り早く発議に至る取り組みを進めていく」と述べ、自身の党総裁任期の来年9月までの改憲を目標に掲げている。
自身の総裁任期と憲法改正を絡ませるような姿勢を国民は疑問視するのではないか。乱暴に時期を区切り、改憲の手続きを急ぐことがあってはならない。
憲法改正を巡っては大規模災害や感染症のまん延などの緊急事態への対応、同性婚の是非、プライバシー権などさまざまな論点がある。憲法に対する国民の認識も多様化している。
今回の調査でも72%が改憲の必要性を感じていると答えている。「憲法の条文が時代に合わない」「新たな権利や義務、規定を盛り込む必要がある」などが改憲を支持する理由である。しかし、大規模災害や感染症などの諸課題に対処するためには本当に改憲しなければならないのか。国民の間で理解が進んだとは言い切れない。
改憲論議は常に9条を焦点としてきた。国会の「改憲勢力」はロシアのウクライナ侵攻などを挙げ、9条改正を訴える。自民党は「9条の2」を新設し、自衛隊明記を掲げている。
それに対し、公明は「戦力の不保持」(9条2項)の例外規定と拡大解釈される可能性を指摘し、反対を表明した。9条改正については連立与党の足並みはそろっていない。
いま一度確認したいのは戦争放棄を明記した憲法の平和主義の原点である。軍事力増強によって東アジアの不安定な安全保障環境に対処するよりも、憲法9条の精神にのっとった外交努力によって緊張緩和を追求することが日本のあるべき姿である。平和主義を貫くことが国際社会での名誉ある地位を占めることにつながる。
-
(a) それはつまり、日本国憲法発布から80年で、自衛隊発足から70年を経ているというのに、「護憲論者」は「真面に国家安全保障を論じることが出来ない」と言う、自白・自供だな。
「拙速な改憲論議」などと抜かすのは、実に「頭の悪い遅滞戦術」でしか無い。マラソン演説よりも牛歩戦術よりもセクハラ戦術よりも、頭も身体も使っていない分、お粗末でお手軽で中身が無くて実効も何もありはしない。
自衛隊の前身たる警察予備隊発足以来、「軍隊の記述が全く無い日本国憲法の下で、厳然として現実として”日本軍”が存在する。」事実・現実には変わりが無い。その現実に対して不可避である筈の「改憲議論」から現実逃避して(*1)「逃げ回り」、とうとう(イヤ、ハナっから、か。)「改憲議論から逃げ回ることしか出来なくなった/出来なくなっている。」のが、上掲社説群を掲げるアカ新聞共であり、日本憲法学会のセンセイガタであり、数多の日本憲法学者達であり、「護憲論者」共である。有り体に言って、知性とか言うモノが欠片も微塵も感じられない、奴原だ。
「拙速な憲法議論」とは、片腹痛い。遅過ぎるぐらいだ。
拙速でもナンでも良いから、世の「日本国憲法擁護論者」共は、サッサと、ハッキリと、明確に明白に、「日本国憲法には一切記述が無い自衛隊も、自衛隊によって維持されている日米安保体制も、"無い"状態で、我が国の主権、我が領土領空領海、我が国民の生命財産を、十分に十全に保全保障出来る、根拠・論拠・ロジック・理屈」を、示しやぁがれ。
それを示すことなく「憲法守れ!」と主張するのは、憲法学者や新聞記者のようなお気楽で無責任な立場ならば許容もされようが、責任ある言論人として、あるいはまともな政治家としては、許されるべきではないぞ。
社民党の「憲法9条が最大の抑止力」って爆笑モノのお題目ぐらいしかそんな根拠・論拠・ロジック・理屈を、示せない/示したことが無い/議論した形跡すら無い、らしいのが、現存する「日本国憲法擁護論者」共だ。
だか私(ZERO)は、「日本国憲法擁護論者」のことを、「憲法信者」とか「憲法教徒」とか、揶揄し、罵倒し、嘲笑しているのである。
- <注記>
- (*1) 「現実よりも理論・空論を優先して」という言い方も、出来そうではあるが、「現実逃避して」居ることには、何ら変わりは無い。「自衛隊は憲法違反だから、廃止すべきだ。」とか言う愚論暴論空論が罷り通り、罷り通り続けてきた、のである。