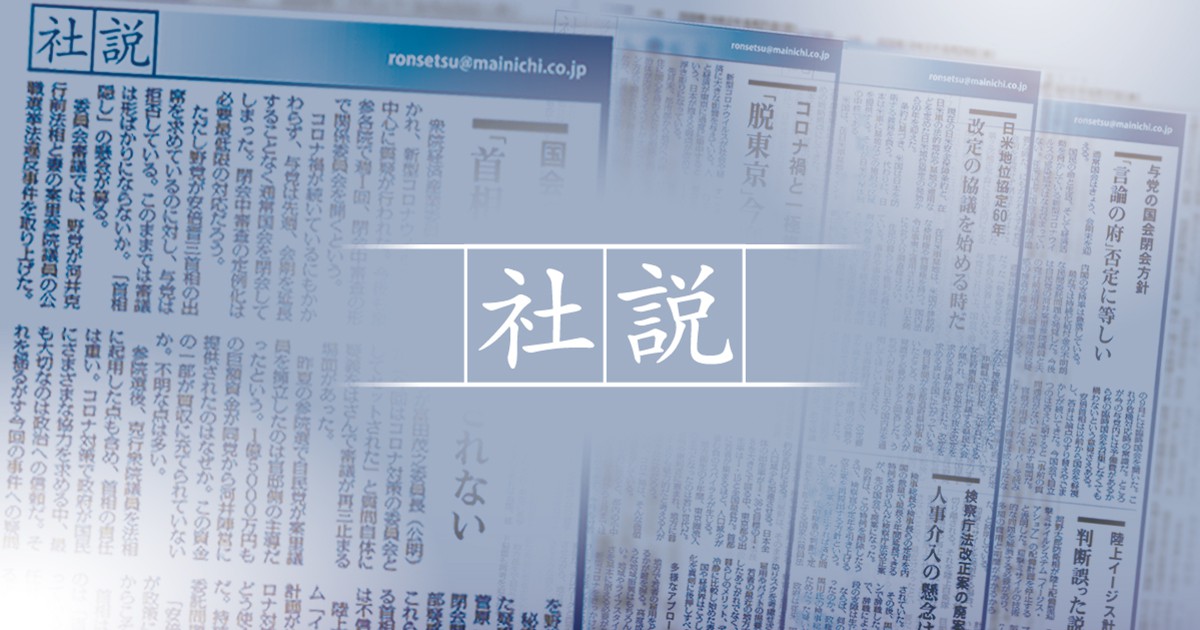-
蘇れ。「兵隊さんよ、ありがとう。」-スーダン邦人救出を受けての朝日、毎日、東京社説に、呆れる。
「劇的な成功」とか「電撃的な勝利」とか言うと大袈裟ではあろうが、戦乱の危機迫るスーダンから我が自衛隊機を以て邦人救出&脱出に成功した、と言うのは、「近年希に見る快挙」と言っても過言では無かろう。
無論、「戦乱が発生した国から邦人が脱出する/救出される」なんて事態は、「そうそうあって貰っては困る」事態ではあるが、左様な事態・状況下で、我等が自衛隊が有効に機能し、邦人救出/脱出に成功した、と言うことが「慶事である=目出度い」事に、変わりは無かろう。
かかる事態を受けて、アカ新聞各紙も社説で題材としている、の・だ・が・・・御前ら(矢っ張り)、根源的に「何か」が欠けてるンじゃぁ無いか?
人として、人間として、根源的に大切な「何か」が、よ。
①【朝日社説】スーダン退避 情勢安定に尽力継続を
②【毎日社説】スーダンから邦人退避 国際連携の重要さ示した
③【東京社説】スーダンの衝突 国際社会が停戦を促せ
☆
(1)①【朝日社説】スーダン退避 情勢安定に尽力継続を
スーダン退避 情勢安定に尽力継続を
https://www.asahi.com/articles/DA3S15620947.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年4月26日 5時00分
list
0
写真・図版
スーダンから退避し、ジブチの自衛隊拠点で健康チェックを受ける日本人家族ら=2023年4月24日、武石英史郎撮影
[PR]
アフリカ北東部のスーダンから、在留邦人らの大半が無事、国外に退避したことに安堵(あんど)した。国軍と準軍事組織の戦闘はなお続いており、日本はこの後も、国際社会と連携し、情勢の安定に向けて力を尽くさなければならない。
現地には、NGOや国際協力機構(JICA)、日本大使館の関係者とその家族ら約60人が滞在していた。うち45人は、自衛隊機で近隣のジブチに到着。他に計13人がフランスや国際赤十字の協力で国外に脱出した。岸田首相は、首都ハルツームからは希望者全員の「退避が完了」したと表明した。
一昨年、アフガニスタンでタリバンが首都を陥落させた際は、自衛隊機派遣の判断が遅れたとの批判があった。今回は、ジブチに自衛隊の拠点があったことも幸いし、輸送機を早期に派遣、待機させて、救出の機会をうかがうことができた。
「停戦」合意下でも、戦闘が収まらない厳しい環境のなか、自衛隊機が待つ東部のポートスーダンまで、邦人らをはるばる陸路で移送するのが難しい任務だったことは、想像に難くない。政府によると、韓国やアラブ首長国連邦(UAE)などの協力があったという。諸外国や国際機関との連携の重要性を改めて強く感じる。
まだ退避希望者が1人、スーダン南部に残っている。他に数人がそれぞれの事情で国内にとどまる。政府は大使館を一時閉鎖、ジブチに臨時事務所を開いたが、引き続き邦人の安全確保に万全を期してほしい。
退避の詳細はまだ明らかになっていない。今後の教訓をくみとるためにも、政府には国会報告などを通じた、できる限りの情報開示が求められる。
国連によれば、スーダンでの戦闘による死者は427人、負傷者は3700人以上に上る。周辺国に逃れる市民も増え、隣国のチャドには1万から2万人が流入したという。
グテーレス事務総長は、地域やそれを越えた破局的な惨事となる危険性を指摘。「国連はスーダンを去らない。平和で安全な将来への希望を支えるため関与する」と述べた。
米政府も仲介に動き、さらなる72時間の停戦で合意を取り付けたと発表した。確実に実現し、さらに恒久的な停戦に結びつけるためには、国際社会の一致した働きかけが欠かせない。
日本は国連安保理の非常任理事国で、主要7カ国(G7)の議長国でもある。首相はまた大型連休中に、エジプトやケニアなどアフリカ4カ国歴訪を予定している。あらゆる機会を生かし、和平に向けた国際的取り組みに指導力を発揮すべきだ。
(2)②【毎日社説】スーダンから邦人退避 国際連携の重要さ示した
スーダンから邦人退避 国際連携の重要さ示した
https://mainichi.jp/articles/20230426/ddm/005/070/103000c
注目の連載
オピニオン
朝刊政治面
毎日新聞 2023/4/26 東京朝刊 English version 854文字
内紛が激化しているアフリカ北東部スーダンから、在留邦人と配偶者ら58人が国外へ逃れた。健康状態に問題はないという。無事に退避できたことに安堵(あんど)する。
政府が派遣した自衛隊の輸送機が、そのうち45人をスーダン東部から近隣国ジブチへ運んだ。自衛隊法に基づく邦人輸送は6回目となる。このほか、フランスなどの支援を受けて13人が退避した。
現地で対立する正規軍と準軍事組織が数日間の停戦に合意し、欧米などが自国民らの脱出を急いでいた。日本政府による救出も大きな混乱なく進められた。
2021年にアフガニスタンへの自衛隊機の派遣が遅れた教訓が生かされた。当時、政府が意思決定に手間取り、邦人や現地職員らを迅速に救出できなかった。
その後、政府は現地の安全に関する派遣要件を緩和し、閣議決定なしで送ることができるよう法改正した。
改めて浮かび上がったのは、突発的な事態が発生した際、情報収集と救出作戦には国際的な連携が不可欠だということだ。
戦後日本は憲法9条に基づき、海外での武力行使を厳しく制約している。他国の紛争や戦争に関与しないようにするためだ。自衛隊の活動に一定の限界があることはやむを得ない。
そうであるからこそ、速やかに情報を集め、派遣の可否を含めて的確に判断する必要がある。
スーダンの邦人らは、危険な首都ハルツームから、空港のある他地域まで陸路で移動したという。岸田文雄首相は、移動などに協力したフランスや韓国、アラブ首長国連邦(UAE)、国連などに謝意を示した。
一時的な停戦が成立し、各国の人々が退避する時間を確保できたのも、国際社会がスーダン側に強く働きかけた結果だろう。
今後も日本として、平時から外交努力を重ねることが重要だ。それが紛争の防止や平和的解決だけでなく、在留邦人の安全に関わる事態への備えにもつながる。
スーダンの内紛が終わったわけではない。退避を望まなかった少数の邦人らもいるという。日本を含む国際社会は、地域の安定に向け、本格的な停戦を実現させる努力を尽くすべきだ。
(3)③【東京社説】スーダンの衝突 国際社会が停戦を促せ
スーダンの衝突 国際社会が停戦を促せ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/246343?rct=editorial
2023年4月26日 08時03分
アフリカ北東部スーダンで政府軍と準軍事組織との戦闘が続いている。国連によるとこれまでに市民を含む四百二十人が死亡。日本人を含む外国人の退避が進む。
今回の衝突は軍人同士の利権争いが本質であり、市民の流血を止めるため、国際社会は利害を超えて結束し、停戦実現を働きかけるべきだ。
スーダンでは二〇一九年、三十年続いたバシル独裁政権が民主化運動で倒され、この際、政府軍と準軍事組織「即応支援部隊(RSF)」も政権を見限った。
文民と軍の統治評議会が設けられたが、軍は二一年に文民勢力を排除。その後、軍は国際社会の圧力で民政移管に合意したが、軍の統合が課題となり、利権を失いかねないRSFが反発していた。
RSFは元民兵組織。二〇〇〇年代に反政府勢力ら四十万人以上が虐殺された西部ダルフール紛争では政府側の先兵を務めた。近年はイエメン内戦でサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)に傭兵(ようへい)を提供し、ロシアの民間軍事会社ワグネルとの関係も深い。
一方、政府軍も独自の企業体を抱え、特権集団を形成する。
ロシアは双方にパイプを持ち、アラブ諸国ではUAEがRSF側と関係が深く、エジプトは政府軍を支援するなど一様ではない。
まずは停戦に向け、これまで民政移管を促してきた国連やアフリカ連合などの介入が急がれる。
首都ハルツームでの戦闘では在留する外国人にも被害が及んだ。日本政府は自衛隊輸送機を東部ポートスーダンに派遣。友好国などの協力も得て邦人約六十人のほぼ全員が国外に退避できた。
自衛隊法では車両による「陸上輸送」も可能だが、より安全性の高い退避方法を選択したのは当然だ。残る邦人や他国の希望者の退避にも全力を挙げてほしい。
スーダンはリビア、チャド、エチオピアといった政情不安定な国々に接する。内戦は周辺諸国に波及しかねず、一帯に浸透する過激派「イスラム国」(IS)にも暗躍の機会を与えることになる。
内戦前から困窮していた市民の苦悩は計り知れない。国際社会は政府軍、RSF双方に停戦を強く働きかけねばならない。
日本は現在、国連安全保障理事会非常任理事国と先進七カ国(G7)議長国を務める。岸田文雄首相の指導力が問われる局面だ。
-
(4)先ず、「兵隊さんよ、ありがとう。」では、無いのかね?
「兵隊さんよ、ありがとう。」ってのは、戦前戦中を通じて人口に膾炙した「キャッチフレーズ」であり、国防・国家安全保障の大任を担う帝国陸海軍将兵に対する謝意を端的に表すフレーズ。「将兵=軍人に対する謝意」なモノだから、戦後は「滅多に使われなくなった(*1)」だけに、些か「レトロ感のある」フレーズだ。私(ZERO)が記憶しているところでは、ルパン三世劇場版アニメ「ルパンvs複製人間」に於いて、銭形警部(未だ、納谷悟朗の声だった・・・)が、大挙押し寄せてきた米軍を「ルパン逮捕のために応援に駆け付けてくれた」と勘違いし、「兵隊さんよ、ありがとう!」と手を振る、シーンがある。
ま、先述の通り、このフレーズにレトロ感がある上、銭形警部の勘違いもあり、このシーンのこの科白は、「ギャグ」というと言い過ぎだろうが、かなりコミカルなモノになっている。それだけ、「兵隊さんよ、ありがとう。」ってフレーズが「物珍しいモノ」である証左、でもあろう。(だから、「特別感」が、ある。)
軍隊も自衛隊も軍事知識も、「戦後平和教育(*2)」なる美名の下に、忌避し否定する風潮故に、「兵隊さんよ、ありがとう。」のフレーズは聴かなくなったし、言われなくなった、と言うのも、一面の史実/事実であろう。
だが、国の安全保障の大部分が軍事力に依存すると言う現実を直視するならば、その軍事力を担う軍人・自衛官には「相応の敬意と謝意」が表されて然るべきである。であるならば、「兵隊さんよ、ありがとう。」というフレーズは、「稀有である」ぐらいならば良いが、「死語としてはならない」し、「死語とすべきではない」だろう。
殊に、今次スーダン脱出/救出という「作戦」を美事に成功させたのだから、少なくとも「邦人脱出成功の功」に対して、礼の一言ぐらいはあるのが、「礼儀」と言うよりは、「人の道」であり、「常識」であろう。
だが、上掲朝日、毎日、東京各紙の社説には邦人救出した(と言って「言い過ぎ」ならば、「無事に邦人を脱出させた」)自衛隊に対する「感謝の言葉」は、ほぼ皆無。「各国との連携」が強調され、各国に対する謝意は表されているが、我が自衛隊に対しては「謝意の欠片も表されていない。」
「各国との連携」がどれだけ強く、深かろうが、我が自衛隊無くして、少なくとも今回のスーダン脱出/救出は、成立しないだろうに。
これが邦人脱出/救出に、一部なりとも失敗して、死傷者でも出ようモノならば、「岸田首相と自衛隊の責任追及」で非難囂々であったろう、と考えると、邦人救出に赴いた自衛隊も、それを命じた日本政府/岸田首相も、「誠にご苦労様」と皮肉でも何でも無く言いたくなるし、言うべきだろう。
であると言うのに、上掲アカ新聞社説と来たら、「未だ残っている邦人も脱出させろ。」だの「スーダンの武力衝突を止めさせろ。」だの、挙げ句の果ては「岸田首相はG7議長としての責務を果たして、スーダンを平和にしろ。」とまで、好き勝手なことを言うばかり。前述の通り「連携してくれた諸外国には礼を言う」が、「諸外国と連携した日本政府」にも、「その諸外国の連携を活かして、邦人救出に成功した自衛隊」にも、感謝の欠片も表明していないし・・・・恐らくは、「感謝の欠片も持っていない」。
「日本政府が邦人を救出するのは当たり前で、邦人救出を命じられた自衛隊は救出に成功して、当然。」ぐらいに思っていれば、未だ見つけモノかも知れない。「ちっ、失敗しやがらなかったか。残念。」ぐらいに思っている公算大、とすべきだろう。
無論これは、私(ZERO)の「推定/邪推」である。が、アカ新聞どもの「日頃の行い」、言説主張からすると、相当程度に確信を持って断言出来そうだ。
で、そんな、恐らくは「日本政府が邦人を救出するのは当たり前で、邦人救出を命じられた自衛隊は救出に成功して、当然。」ぐらいに思っている(ひょっとすると、「ちっ、失敗しやがらなかったか。残念。」とさえ、思っている)状態を、「人として、人間として、根源的な欠陥がある」と評するのは、先ず「常識の線」では、なかろうか。
- <注記>
- (*1) 実に妙な話だ。国防・国家安全保障の大任を軍人/自衛官が担うのには、戦前も戦中も戦後も、右も左も、軍国主義も共産主義も、関係ない、と言うのに、だ。
- (*2) 「戦後平和教育に対する一反例が、私(ZERO)自身である。」と言うことを認めるには、吝かでは無いが。