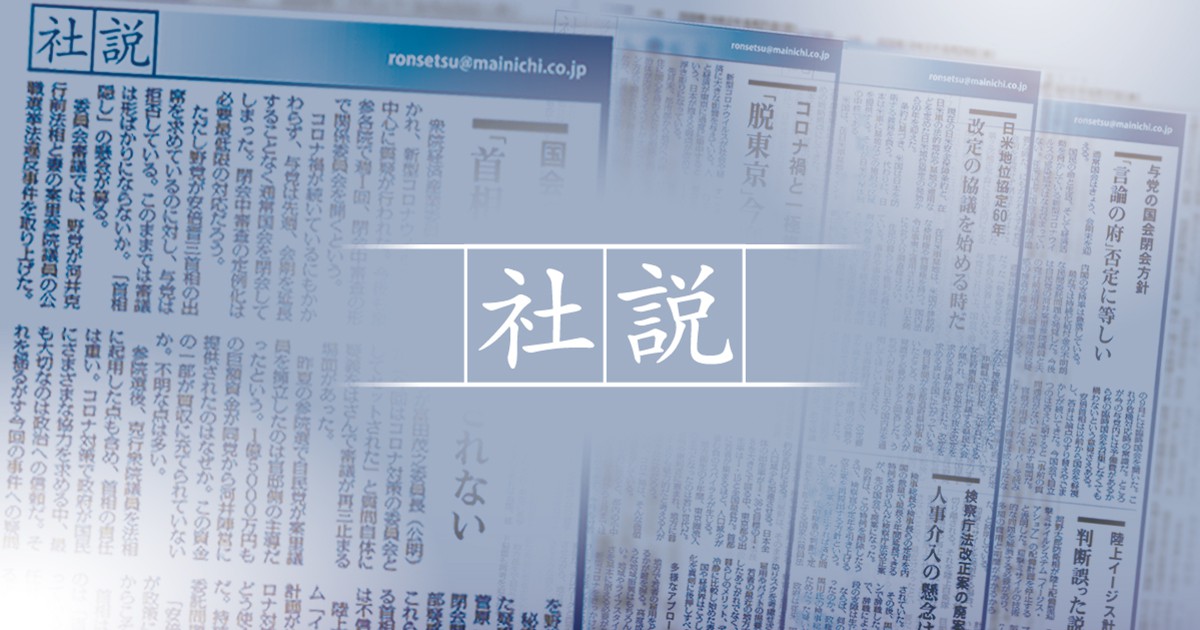-
防衛費、「規模ありき」だと、何が悪い?「1%」は「規模ありき」だった。-【朝日社説】首相2%指示 防衛費増 規模ありきだ 他
岸田首相が「防衛費の対GDP比率2%を指示したぁぁぁぁぁぁぁっ!!!」ってんで、アカ新聞どもが大騒ぎしている、らしい。まあ、下掲するアカ新聞ども社説を見れば/読めば、自ずと明らかな所、であるな。
いやぁ、安保法とか、機密保護法とか、チョイと前の、特に安倍晋三政権下での「アカ新聞ども大騒ぎ」が思い出されるねぇ。
って事は、「アカ新聞大騒ぎ」ってのは、ある種の「吉兆」と、考えたくなるな。だが、「吉兆となる」か「ならぬ」かは、岸田首相次第、ってところが、大きそうだ。
①【朝日社説】首相2%指示 防衛費増 規模ありきだ
②【毎日社説】防衛費2%の首相指示 やはり「数字ありき」だった
③【東京社説】防衛費2%指示 倍増ありき再考求める
☆
(1)①【朝日社説】首相2%指示 防衛費増 規模ありきだ
首相2%指示 防衛費増 規模ありきだ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15488752.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年11月30日 5時00分
防衛費に関する岸田首相の指示を受け、取材に応じる(左から)鈴木俊一財務相、浜田靖一防衛相=28日、首相官邸、瀬戸口翼撮影
[PR]
【1】 岸田首相が掲げる「防衛力の抜本的強化」は、内容、予算、財源をセットで決めるのではなかったのか。使途の具体的な説明がなく、財源の議論もこれからで、予算額だけ先に打ち上げるのでは、やはり「規模ありき」だったというほかない。
【2】 首相が、防衛費に関連経費を加えた安全保障関連予算を、2027年度に国内総生産(GDP)比2%とするよう、防衛・財務両大臣に指示した。
【3】 21年度の防衛費は補正を含めると6兆1千億円で、GDP比は1・09%。2%は約11兆円となり、防衛に資する研究開発や港湾などの公共インフラ整備の費用、海上保安庁予算や恩給費などを算入しても、兆円単位の大幅な増額になる。
【4】 2%はもともと、北大西洋条約機構(NATO)諸国の国防予算の目標だ。自民党は昨年の衆院選の公約に、この数値を「念頭」にした防衛力強化を掲げ、年末の安保3文書の改定に向けた今年5月の政府への提言にも盛り込んだ。
【5】 しかし、日本とNATO諸国では、安全保障環境も歴史的経緯も異なり、予算の仕組みも違う。社説はこれまで、着実な防衛力整備の必要性には理解を示しつつ、費用対効果を吟味し、真に必要な予算を積み上げるのが原則だと主張してきた。
【6】 この間、「3点セットで明らかにする」と、防衛力整備の水準への言及を避けてきた、首相の対応は不誠実だ。土壇場になって2%を追認したが、敵基地攻撃能力の保有について、まだ公式には結論が出ていないのに、長射程のミサイル導入を見込む予算の大幅増を決めるのは、順番が逆ではないか。
【7】 首相の指示は27年度時点の水準だけで、来年度から5年間に要する予算の総額は示されていない。一方で、他の歳出の見直しに最大限努力することを前提に、安定財源の確保が不可欠だとして、「歳出歳入両面での措置」を決めるとした。事実上、増税の検討を求めたものだ。
【8】 政府が設けた「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」も、先日の報告書に、「幅広い税目による負担が必要」と明記している。
【9】 自民党内からは「増税反対」「国債で対応しろ」の大合唱が聞こえる。1千兆円を超す国の借金を抱えながら、さらに野放図に将来世代にツケを回そうというのは無責任きわまる。
【10】 ただ、身の丈を超えた負担増で、国民生活を疲弊させるようなことがあってはならない。また、いかなる増税も、国民の幅広い理解と協力が大前提である。国民への説明を後回しにする今の政権の進め方で、納得が得られるかは疑問である。
(2)②【毎日社説】防衛費2%の首相指示 やはり「数字ありき」だった
防衛費2%の首相指示 やはり「数字ありき」だった
https://mainichi.jp/articles/20221130/ddm/005/070/088000c
朝刊政治面
毎日新聞 2022/11/30 東京朝刊 English version 830文字
【1】 やはり「数字ありき」だったと言うほかない。議論と説明を尽くしてこなかった岸田文雄首相の責任は重い。
【2】 首相は防衛、財務両省に対し、防衛費などの関連予算を2027年度に国内総生産(GDP)比で2%まで増やすよう指示した。
【3】 1976年に定められた「1%枠」は、80年代に撤廃された後も防衛費の目安となってきた。今年度当初予算は約5兆4000億円(0・96%)だ。2%なら倍増の約11兆円となる。
【4】 従来の防衛費に加え、安全保障関連の研究開発、インフラ整備、サイバー、国際協力などの経費も合算して達成するという。
【5】 だが、内容を詰め切らないまま規模を決めてしまうのは問題だ。
【6】 そもそもGDP比2%は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国の国防費目標である。自民党は、7月に死去した安倍晋三元首相を中心に、日本もならうべきだと要求してきた。
【7】 ただ、地理的条件などから、必要となる防衛力は異なるはずだ。単純な比較は成り立たない。
【8】 岸田首相はこれまで、あらかじめ数値目標を設けることを避け、「内容、予算、財源を一体で決める」「必要なものを積み上げる」と繰り返していた。ところが、年末の予算編成を控える今になって突然、前言を翻した。
【9】 予算規模ばかりが先行するのは本末転倒だ。個々の項目の金額が必要以上に膨張するなどの弊害が出かねない。
【10】 防衛省の来年度概算要求は過去最大の約5兆6000億円で、金額を示さない事項要求が多数に上っている。
【11】 5年後の「2%目標」を見据えて、予算を積むことが優先されれば、装備品の優先順位や費用対効果、コスト削減などの観点も抜け落ちる懸念が高まる。
【12】 しかし、そうした点が精査されたようには見受けられない。
【13】 憲法に基づき、軍事大国とはならず、専守防衛を堅持することが日本の基本方針だ。規模の論理が先走れば、それとの整合性もおろそかになりかねない。
【14】 予算の倍増は防衛政策の大転換に直結する。国民の理解を得る努力を欠いたまま、なし崩しに決めることは許されない。
(3)③【東京社説】防衛費2%指示 倍増ありき再考求める
防衛費2%指示 倍増ありき再考求める
https://www.tokyo-np.co.jp/article/216928?rct=editorial
2022年11月30日 06時48分
【1】 岸田文雄首相が、防衛費を関連予算と合わせて二〇二七年度に国内総生産(GDP)比2%に倍増させるよう関係閣僚に指示した。防衛力の抜本的強化のためとされるが、財源確保のための増税は避けられず、周辺情勢の安定に資するかも疑問だ。再考を求めたい。
【2】 首相は防衛費の在り方について「金額ありき」を否定し、内容、予算、財源を合わせて「具体的に国民の命を守るために何が必要なのかをしっかりと議論し、積み上げる」と繰り返してきた。
【3】 しかし、積み上げの議論が十分に行われたとは言い難い。
【4】 例えば、政府は中国や北朝鮮の軍備増強を踏まえ、他国の領域でミサイル発射を阻む敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に踏み切る方向だが、必要な装備や予算規模は具体的に示していない。
【5】 首相が自身の説明を翻して、防衛費増額の数値目標を設定したのは、与党自民党の要求をそのまま「丸のみ」したに等しい。
【6】 そもそも、日本の防衛費をGDP比「2%」とすることに、明確な根拠があるわけではない。
【7】 北大西洋条約機構(NATO)加盟国はGDP比2%を国防費の目標とするが、ロシアと地続きで相互に防衛義務を負う欧州各国と日本を同列に扱う必然性はない。
【8】 米国から防衛費の増額を求められた安倍晋三首相当時の自民党が打ち出した2%目標が独り歩きしているだけではないのか。
【9】 二二年度の防衛費は約五・四兆円でGDP比1%弱。2%に増やすには、仮に海上保安庁や研究開発、公共インフラ、サイバーなどを関連予算として合算しても、毎年五兆円以上が必要になる。
【10】 当面は国債発行や歳出改革で捻出するとしても、政府有識者会議は増税を提言している。自民党は直近の衆参両院選で増税を公約しておらず、国民理解のない「軍拡増税」など許されない。
【11】 日本が防衛費を倍増させれば、中国も軍事力拡充で対抗し、日本は際限なく防衛費を増やさざるを得なくなる。軍拡競争をあおり、地域の緊張を高める「安全保障のジレンマ」に陥りかねない。
【12】 戦後日本の平和国家としての歩みを踏み外しかねない防衛政策の大転換を、駆け込みで決めていいはずがない。国際情勢の変化に対応しつつ、国力に応じた抑制的な防衛力の整備に向けて国民的議論を重ねるべきである。
-
(4)抽出、防衛費が「2%の規模ありき」では悪い/いけない理由
例によって、丸数字は出典元となった社説の新聞社。【】はそのパラグラフ番号だ。
- <理由1> 「内容、予算、財源のセット」だった、筈だから。①【1】②【5】【8】【9】③【2】
- <理由2> 「2%」と言うのはNATOの国防予算目標で、日本はNATOとは安全保障環境も歴史的経緯も異なり、予算の仕組みも違うから。①【4】【5】②【6】【7】③【6】【7】
- <理由3> 費用対効果を吟味し、真に必要な予算を積み上げるのが原則だから。①【5】②【11】
- <理由4> 敵基地攻撃能力に結論が出ない内に、長射程ミサイル導入予算を決めたから。①【6】
- <理由5> 増税につながるから。①【7】【8】③【1】【10】
- <理由6> 国債を財源とするのは、将来にツケを回すことになるから。①【9】
- <理由7> 国民が納得しないだろうから。/国民理解の無い「軍拡増税」など許されないから。①【10】③【10】
- <理由8> 憲法に基づき、軍事大国とはならず、専守防衛を堅持することが日本の基本方針だから。②【14】③【12】
- <理由9> 防衛政策の大転換に直結するから。②【14】③【12】
- <理由10> 周辺情勢の安定に資するか疑問だから。/軍拡競争につながるから。③【1】【11】
- <理由11> 敵基地攻撃能力保有は決めたが、装備や予算は明示していないから。③【4】
- <理由12> 首相が与党自民党の要求を「丸呑み」したに等しいから。③【5】
-
(5)お前ら、国防や国家安全保障を、舐めてるだろう。
真っ先に上掲社説を掲げている、朝日、毎日、東京新聞各社に、言うべきだろうな。「お前ら、国防とか、国家の安全保障とか言うモノを、舐めてるだろう。」と。
国防とか、国家の安全保障と言うモノは、「戦争」と言う、国の存亡にも関わる一大事に直結しており、国防や国家安全保障上の失敗は、「国が滅びる」事さえあり得る「大事(おおごと)」である。孫子の昔から21世紀の今日に至るまで、「兵は凶事」なのである。
「”兵は凶事”ならばこそ、防衛論議は慎重に。」ってのは、一つのロジックであるが、一方で「兵は拙速。忌むべきは巧遅」とも言うのだから、なかなか「兵=国防・軍事」はタダでさえ厄介だ。それこそ、妙な先入観や思い込みや偏見を排した、真摯で真剣な議論と思考、考察が必要なのである。
だと言うのに・・・お前らが「我が国の防衛費が”GDP比2%の規模ありき”であってはならぬ」とする理由が、上掲<理由1>~<理由12>とは・・・「我が国の戦後”平和教育”の成果」を見る、思いだな。
あ、念のために言っておくが、私(ZERO)自身が「我が国の戦後”平和教育”」をしっかりキッチリ受けている。私(ZERO)自身が「我が国の戦後”平和教育”」の呪縛と頸木を免れ得たのは、幾つもの幸運のお陰もあるが、根源的なところは「健全なる自主自存した猜疑心」のお陰である。これが「無い」ないし「特定の対象(*1)に対しては無くなってしまう」と言うのは、ある種の「知性の欠如」だと思うぞ。
さて、気を取り直して、上記で抽出した「アカ新聞各紙社説が、我が国の防衛費を、”GDP比2%の、規模ありき”であってはならぬ、とする理由」を、見て行こうか。
- <注記>
- (*1) 「平和」とか「反核兵器」とか
-
1.<理由1> 「内容、予算、財源のセット」だった、筈だから。①【1】②【5】【8】【9】③【2】
端的に言って、この批判<理由1>は、「前言を翻した」って批判でしかない。そりゃ為政者にして我が国の最高権力者たる日本国首相が「前言を翻す」ってのは、一寸したことではあるが、「ままあること」でもあろう。アカ新聞ども(特に沖縄二紙)が大好きな鳩山由紀夫なんざぁ、「前言翻しまくり」で「翻さなかった前言なんて、あったかぁ?」状態ではないか?
ま、鳩山由紀夫は、鳩山由紀夫であるから、置くとしよう。
「前言を翻した」事よりも罪が重く責められるべきは、「方針が首尾一貫しない」事だろう。「”内容、予算、財源のセット”だった筈が、そうでは無くなったのだから、方針は首尾一貫していない。」と言うのが一つのロジックであることは認めるが、それは「方針」を、業と狭義に捉えている、様に思われる。謂わば、「言葉尻を捉えている」のでは、ないかな?
言い替えようか。岸田首相はある時点から、「防衛費2%」を言い出し、打ち出した。その当初に「内容、予算、財源のセット」と言ったのも事実だが、戦略・大筋・目的はどう考えても「防衛費2%」であって、「内容、予算、財源のセット」はその際の一手法であり、戦術・細部・手段であろう。
ならば、「内容、予算、財源のセットでは無くなった」のは、戦術変更ではあっても、戦略変更ではない。批判の対象たり得なくもないが、大した批判たり得ない。
言い替えるならば、「防衛費2%」と言い出し、打ち出した時点で「既に(或程度)規模ありき」だったのであり、「内容、予算、財源のセット」ってのは、謂わば些事だ。
それは、従来従前の、数十年間もの間我が国の防衛費を圧迫・矯正し続けてきた「防衛費1%枠」を想起すれば、自明とさえ思えるぞ。
-
2.<理由2> 「2%」と言うのはNATOの国防予算目標で、日本はNATOとは安全保障環境も歴史的経緯も異なり、予算の仕組みも違うから。①【4】【5】②【6】【7】③【6】【7】
<理由1>の解説で、ほぼ議論は尽きている様な気がするが、続けるとしよう。
しかし、この<理由2>もヒドいな。「NATOと日本は、違う。」ってのは、少なくとも一面の真理で、この点には私(ZERO)も同意出来るが、「NATOよりも我が国の方が安全だから、防衛費のGDP比率も低くて良い」なんて主張には、全く同意出来ない。
「脅威対象であるロシアとNATOは地続き」ってのは事実だが、大半のNATO諸国はロシアと国境を接していない。只今正にロシアに侵略されているウクライナをはじめとする東欧諸国(の一部)が緩衝国となり、「ロシアの脅威を和らげている。」。
緩衝国ったって、両大戦のベルギー(*1)を見れば明らかな通り、場合によっては「当てにならない」のだが、我が国と脅威対象国の間に「緩衝国がない」事は、NATO諸国よりも我が国の国防上の安全度を下げている。
我が国が「四面海もて囲まれし」島国であることは、我が国防上の利点たり得る。海を越えて兵力を送る渡洋侵攻は、「軍事的には最難事」で、現代戦でこれに成功した実績があるのは、米国、日本、ちぃとオマケして英国(*2)位なのも事実。
だが「軍事的に最難事」なのは、陸上兵力で渡洋侵攻する場合であり、航空機による空爆やミサイル攻撃には、海洋もさして役には立たない。
何よりも、NATO諸国は、「NATO諸国が寄って集ってロシア一国に対峙する」だけで良いのに対し、我が国の脅威対象国は、ロシアに加えて「今や世界第2位の経済力」の中国と、経済はショボいが核恫喝しまくりの北朝鮮と、三国を我が国は相手にしなければならない。しかも、同盟国は、米国、台湾、殆ど当てに出来ない韓国ぐらい。インドやオーストラリアは、一寸遠い。
即ち、「我が国の安全保障環境は、NATO諸国よりも、悪い。」のは、ほぼ自明である。それを、「ロシアと地続きのNATO諸国」と屁理屈付けて、「NATO諸国より我が国の方が安全だから、NATO諸国並みの防衛費2%は必要ない。」と言わんばかり(しかも、左様に明確に主張すらせず、暗示するばかり)なのは、詭弁であり、姑息である。
- <注記>
- (*1) 第1次大戦でも第2次大戦でも、ベルギーはドイツのフランスへの進撃路として蹂躙された。
- 地理的に不幸な位置にあるとは言え、同じ手を立て続けに二度も喰うなよな。
- (*2) フォークランド紛争を、渡洋侵攻と見なして、だ。「渡洋」であることは間違いないが、派遣した兵力がショボいんだよねぇ。まあ、目的は達したのだけど。
-
3.<理由3> 費用対効果を吟味し、真に必要な予算を積み上げるのが原則だから。①【5】②【11】
この<理由3>とされている「原則」は、凡そありとあらゆる予算について言えることであり、なればこそ「原則」たり得ている、と言えよう。それだけに「正統派」の「防衛費が『2%の規模ありき』では悪い/いけない理由」と言えそうであり、今回抽出した12の理由の中で『説得力のある点』では一二を争う、と言って良さそうだ。
だが、その「原則」がしばしば破られる、のも事実であり、現実である。而して、従来従前の我が国の防衛費が「費用対効果を吟味し、真に必要な予算を積み上げた」モノであったとは、到底言えまい。部隊現場の隊長が自腹でトイレットペーパーを買っているとか、『共食い整備』とか言う事例は、従来従前の防衛費が少なくともローカルには「真に必要な予算では無かった。不足していた。」事を意味するし、その元凶が従来従前の「防衛費1%枠」であり、「防衛費が、『1%の規模ありき』であった。」事を、相当に強く示唆している。
「艦対艦ミサイルの調達は、新造艦建造時に定数(普通の護衛艦は8発)にさえ足らない発数(6発)だけで、備蓄どころか定数搭載することも出来ない(*1)。」なんて、普通に考えれば「常軌を逸した」状態も「真に必要な防衛予算では無かった。不足していた。」証左であり、<理由3>の様な、ある意味「正論」を以て「防衛費を論じる」事は、到底出来ない。
従って、この<理由3>を以て「防衛費2%の規模ありき」に反対するのは、「我が国の防衛予算の実情を、全く顧みていない暴論」であり、「理想論」とか「書生論」とさえも、評しがたい、とすべきだろう。
- <注記>
- (*1) 退役した艦から下ろした発数だけは、「余剰」がある、のみ。
-
4.<理由4> 敵基地攻撃能力に結論が出ない内に、長射程ミサイル導入予算を決めたから。①【6】
-
<理由11> 敵基地攻撃能力保有は決めたが、装備や予算は明示していないから。③【4】
朝日新聞と東京新聞の「主張が異なる」のは、別に異とするには足らないが、上記朝日が掲げる<理由4>と東京新聞が掲げる<理由11>には、矛盾が在る。
<理由4>で朝日は、「敵基地攻撃能力の保有が決まらない内に、長射程ミサイル予算を決めるとはケシカラン!」と非難しているのに対し、<理由11>で東京新聞は、「装備や予算を明示しないで、敵基地攻撃能力保有を決めるとはケシカラン!」と非難している。「長射程ミサイル予算を決めた」ならば「装備や予算は、自ずと決まった」筈なのに、である・・・ああ、「長射程ミサイル予算を決めたが、装備や予算は明示していない」って可能性が、「論理上存在しうる」気はするが、一寸想像を絶する。そんな状態に「今現在の我が国がある」とは、到底信じ難い。
「敵基地攻撃能力保有を、決める/決めない」も、「長射程ミサイル予算を決める/決めない」も、日本政府の取りうるのは、どちらか一方しかない。「決める/決めない」を秘匿し、曖昧にすることは(一応)可能だろうが、そうだとしたら「日本政府が秘匿/曖昧にしている決定/未決定を、朝日も東京新聞も、断定した上で非難している」事になる。そりゃ、まあ、そんな状態では、「朝日と東京新聞の非難に、矛盾が生じる」のも無理はないが、両者の非難に「矛盾がある」という事実は、「政府が如何したって両紙は非難批判しただろう」事を、かなり強く示唆している(様に私(ZERO)には思われる)。
それ即ち、<理由4>と<理由11>は、イチャモンでしかなく、論じるに足らない、と言うことだ。
因みに現時点での私(ZERO)の認識は、「日本政府は、敵基地攻撃能力の保有を決定したが、長射程ミサイルの予算や数は、決めていない。」であり、非難としては東京新聞の<理由11>に「未だ理がある」とは思うのだが、「敵基地攻撃能力の保有を決めた瞬間に装備や数を明示する」ってのも相当無理があれば(*1)、「装備や数を明示しないことで、抑止力を高める」事もあり得るのだから、<理由11>は「そもそも事実誤認しているらしい<理由4>よりは、マシ」という、だけである。
- <注記>
- (*1) その為には、相当な事前検討が必要であり、そん事前検討が露見した日には、「敵基地攻撃能力を保有していないのに、敵基地攻撃能力を検討しているぅぅぅぅ!!」と東京新聞が騒いだことは、賭けても良いぐらいだ。
-
5.<理由5> 増税につながるから。①【7】【8】③【1】【10】
-
<理由6> 国債を財源とするのは、将来にツケを回すことになるから。①【9】
<理由5>と<理由6>は、何れも「金がないから」という「上位概念」に集約出来よう。下世話な話だが、「無い袖は振れない」って奴だ。
だが、頭を冷やして考えるが良いや。国が戦争に負けると言うことは、国が滅びると言うこと。「男は皆殺し。女は性奴隷。」ってのは、流石に「国際法違反」って事になったが(それだって、戦史からすればごく最近の話だ。)、類似した事象はロシアのウクライナ侵略でも発生している。「国が滅びる」とは、「国が戦争に負ける」とは、「男は皆殺し。女は性奴隷。」に準じた事象が、全国規模で生起する、と言うことだ。
大東亜戦争に於ける我が国の敗戦は、「血が流されなかった」と言う点では「理想に近い敗戦」だったのである(*1)。アレが「敗戦」だと思うと間違えるぞ(*2)。
かてて加えて、住民虐殺ったら、「支邦特産」でこそ無いものの、「大陸名物」ではあるという歴史的背景と、既に数十年にわたって実施されている「反日教育」を考えるならば、「中国に対する日本の敗戦」は、「通州事件が21世紀の今日に日本全国規模で拡大再生される」可能性さえ、考慮すべき対象であろう。
「敗戦」とは、実に、「恐ろしいモノ」なのである。
更には、仮に敗戦に至らず、対中/対露/対北朝鮮戦争に日本が勝利、したとしても・・・惹起された戦争による被害というのは官民/軍民を問わず、大小の程度の差はあるかも知れないモノの、「必ず、ある」と考えねばならない。「勝利の美酒」なんて表現もあるが、大抵の勝利には多少なりとも「苦み」はあるのであり、その「苦み」は大東亜戦争後80年もの間、相応の平和を享受してきた我が国には特に強烈であろう。
言い替えれば、「開戦に至らない」のが最善であり、「開戦して勝利」は、かなりギャップのある次点。「開戦して敗北」は、最悪。「百戦百勝は、善の善たる所に非ず。」とか、「戦わずして、勝つ」とかの、「孫子の教え」は、21世紀の我が国にも、有効有益である、と言うことだ。
で、「開戦に至らせない」抑止力として、「開戦に至った場合、勝利する(可能性を高める)」実行力として、「軍備の拡張」は重要重大である。それは、「金が無いから、やらない/止めよう」なんて言えるほど、呑気なモノでは無い、のである。
私(ZERO)ならば、断言するね。「我が国が経済的に滅んでしまうのは、困る。だが、『国が傾く』程度ならば、十分許容出来るから、軍備増強すべきである。それこそ正に、我等の代の、未来に対する責任である。」と。
「軍艦造れぇぇぇぇぇぇ!!」樺山資紀(と、される。)
- <注記>
- (*1) 「流されなかった血」以外の部分では、日本国憲法の押しつけだとか、戦前戦中暗黒史観の洗脳とか、相当に「ヒドい」部分も多々あるが。
- (*2) 「ソ連軍が攻めて来たら、赤旗と白旗を持って、威厳ある降伏をするのが良い。」って正真正銘掛け値無しの降伏主義者共(かつては、相応に居た)なんざぁ、「大東亜戦争の敗戦」が「普通の敗戦」と、勝手に思っているんだろうな。
- まあ、ロシアのウクライナ侵略でも、「ウクライナ軍が抵抗するから、戦争が長引く。」とか「西欧諸国が武器援助するから、市民が犠牲になる。」とか抜かすやつばらは相当いるから。似たような発想なのだろうよ。
-
6.<理由7> 国民が納得しないだろうから。/国民理解の無い「軍拡増税」など許されないから。①【10】③【10】
この<理由7>の言っているのは、「国民には、"防衛費2%"に納得して欲しくない。」と言う、①朝日及び③東京新聞の「期待」であり、「願望」であろう。だが、その「希望」/「願望」が裏切られ、世論調査か何かで「国民の圧倒的多数が、『防衛費2%』や『防衛費増のための増税』を許容している」って結果が出たとしても、朝日や東京新聞は納得も理解もしないだろう事は、賭けても良いぐらいだ。
言うなれば、この<理由7>は、「国民の名をかたってのイチャモン」だろうと、私(ZERO)は見ている。
而して、「防衛費2%に国民が納得しない。」ならば、「国民を説得する」だけの話。今現在「防衛費2%に国民が納得しない。」としても、大した問題ではない。政治・政策は、世論調査結果ではない。不人気だろうが、為すべき政治・政策は為すこと事こそ、政治家の仕事であり、責務だ。
言い替えるならば、朝日や東京新聞が、「防衛費2%に、国民が納得しない」事に期待し、賭けるのは勝手だが、「防衛費2%を、国民に納得させる」心算があれば、政府が「防衛費2%」を実施実行することに、何の問題も無い。その結果、支持率が下がろうが、次の選挙に大敗しようが、「防衛費2%」を実施実行は、出来る。
否、その程度のリスクを負うだけの価値が、「防衛費2%」には、ある、と言うべきだ。
-
7.<理由8> 憲法に基づき、軍事大国とはならず、専守防衛を堅持することが日本の基本方針だから。②【14】③【12】
-
<理由9> 防衛政策の大転換に直結するから。②【14】③【12】
<理由8>と<理由9>は、詰まるところ、「防衛政策の従来方針を変えるな。」と言う主張である。
が、「防衛政策の方針」も、「防衛政策」そのものも、政府の、内閣の所掌であり、その変更もまた然り。前内閣の方針や政策をそのまま踏襲するも、改変するも、大転換するも、覆すも、現政府=現内閣ならば可能であり、他の誰にも出来ないことである。
「憲法に基づき、軍事大国とならず、専守防衛を堅持すること」が、仮に「日本の基本方針であった」としても、それを更新し、変更し、大転換し、覆す権限が、現政府=現内閣にはあり、そうしたところで「国民投票にかける」必要も無い。ああ、憲法だけは「基づかねばならない」と言い得るが(・・・あ・の・憲法に、だがね。)、「専守防衛を止める」ぐらいは、造作も無いことだ。
言い替えるならば、現政府=現内閣には、「防衛政策の方針を変える」権限があるのだから、「防衛費2%の規模ありき」とする事への反対理由として、<理由8>と<理由9>は、「反対理由として不適切である。」
精々の所、「防衛費2%を規模ありきとするならば、防衛政策の方針変更を、明示明言すべきだ。」と、主張出来る程度である。
-
8.<理由10> 周辺情勢の安定に資するか疑問だから。/軍拡競争につながるから。③【1】【11】
ここまで来ると、「論外」の域に近づいてくる。「軍拡競争は、安全保障のジレンマだから、陥ってはならない。」とか、素面で平気で抜かす輩には事欠かないのだが・・・軍拡競争。結構ではないか。上等ではないか。軍拡競争にすら至らず、軍拡不戦敗になるより、余程マシだ。
大体、軍拡競争したからこそ、「冷戦」は成立し、究極的に西側自由主義陣営が「冷戦に勝利した」という冷厳たる事実があるというのに、「軍拡競争に陥ってはならない」って主張出来てしまう人の頭の構造は、一体どうなっているのか。私(ZERO)の様な「異教徒」は、正気を疑うばかりである。
軍拡競争、ひいては冷戦は、一方的に軍事的優位を取られる「軍拡競争の不戦敗」よりは安定しているし、我が国の利益である。
軍拡競争、上等である。
-
9.<理由12> 首相が与党自民党の要求を「丸呑み」したに等しいから。③【5】
さて、どん尻に控えしこの東京新聞が挙げた「アカ新聞社説が、我が国の防衛費を”GDP比2%の、規模ありき”であってはならぬ、とする理由」<理由12>が、実のところ「私(ZERO)が一番呆れた理由」である。
何しろ我が国では、議院内閣制であり、原則的に日本国首相は日本国会最大与党の党首(*1)である。現首相の岸田首相も例外では無く、最大与党・自民党の党首=総裁を兼任している。
で、最大与党の党首でもある日本国首相が、その党首を務める最大与党の要求を「丸呑み」したら、非難されるのかね?????「非難されるべき」としたら、議院内閣制の否定では、無いのかね????
「最大与党党首と、日本国首相とでは、立場が違う。」と言うことは、あり得る事だろう。「首相たるもの、党利党略よりも国益・国家戦略を優先すべきだ。」と言うのは、「その通り」と、私(ZERO)も同意しよう。だがそれならば、今回の「防衛費2%の総額ありき」が、どう「自民党の党利党略に沿っており、且つ、国益・国家戦略に反するか。」を、論証すべきであろう。
と、ここまで書いて、漸く気が付いた。私(ZERO)は「防衛費2%総額ありき」が、我が国益・我が国家戦略に沿うモノと思っている。なればこそ、自民党の党利党略に沿おうが反しようが、「知ったことではない」のである。「日本国首相が、自民党の要求を丸呑みにする」のも、「些事だ」と思えるのは、その為だ。
対して、上記<理由12>を掲げる③東京新聞は、前述の<理由11>の様な、私(ZERO)に言わせれば「実に奇妙なロジック」で、「防衛費2%総額ありき」が我が国益・我が国家戦略に反するモノ、と信じ込んでいる。だから、<理由12>「自民党の党利党略に(のみ)沿っているから」と「日本国首相が日本国会最大与党=自民党の要求を丸呑みしている」と、「非難・批判」出来てしまう、らしい。
なるほど、「思考の水平線を広げる」とは、こう言う事を言うのだな。矢っ張り異論・異説は「異端」と思えても、大切にしないといけないな。
「森羅万象、皆我が師(たり得る)。」、改めて、肝に銘じよう。
- <注記>
- (*1) 例外は、村山富市・社民党党首首相ぐらい、だろう。
-
10.「防衛費1%枠」は、「総額ありき」で、なし崩しに決めたろうが。
で、改めて想起願いたいんだが・・・我が国の防衛を長いこと呪縛し続けて来た「防衛費1%枠」なんてのは、「NATO諸国の国防予算基準」なんて参考値も無く、たぁだノリと雰囲気だけて決めつけやぁがって、そのまま「引きずられているだけ」だったろうが。それに対してアカ新聞どもは、「規模ありき」とも「金額ありき」とも言わず、寧ろそれに抵触しそうになると、大抵「大騒ぎ」して来やぁがった、ろうが。
そんなアカ新聞どもが、「防衛費2%に反対」なのは、判ったよ。だが、その反対理由が「規模ありきだから。」ってのは、全く説得力を持たないぞ。