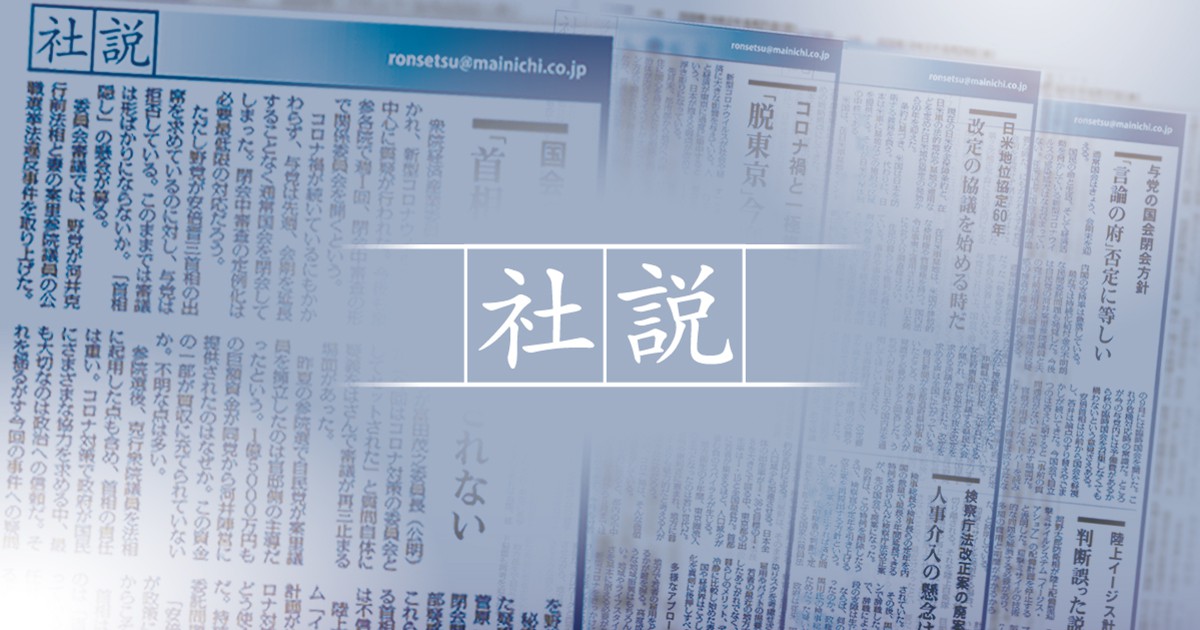-
手前ぇら、何か忘れてねぇか?-【朝日社説】日豪安保協力 地域の安定につなげよ &【毎日社説】日豪の安保共同宣言 関係いかし地域の安定を
日本の岸田首相とオーストラリアのアルバニージー首相が首脳会談し、新たな安全保障協力に関する共同宣言に署名した、そうである。
下掲するのは、かかる事態を受けての朝日新聞と毎日新聞の社説、な・の・だ・が・・・
☆
(1)【朝日社説】日豪安保協力 地域の安定につなげよ
日豪安保協力 地域の安定につなげよ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15455886.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年10月26日 5時00分
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
list
はてなブックマークでシェアする
0
メールでシェアする
印刷する
写真・図版
オーストラリア西部パースのキングスパークで22日、コアラを抱く岸田首相(右)とオーストラリアのアルバニージー首相=AP
[PR]
東・南シナ海から南太平洋まで、海洋進出を強める中国に対し、民主主義、人権、法の支配といった価値観を共有する両国が、協力して臨むのは当然だ。力による現状変更を許さないのと同時に、対話や信頼醸成にも共に取り組み、地域の平和と安定に資する連携にしなければならない。
岸田首相が先週末、豪州を訪れ、アルバニージー首相と会談し、新たな安全保障協力に関する共同宣言に署名した。07年に、当時の安倍、ハワード両首相が初の安保共同宣言に合意して以降、自衛隊と豪州軍が弾薬などを融通し合う「物品役務相互提供協定(ACSA)」や、共同訓練で相互訪問する際の手続きなどを定めた「円滑化協定」の締結など、両国はこの分野での協力を深めてきた。
今回の宣言は「今後10年の羅針盤」とされ、「緊急事態に関して、相互に協議し、対応措置を検討する」と明記、自衛隊と豪州軍の相互運用性の更なる強化などが盛り込まれた。岸田首相は会見で「特定の国や地域を念頭に置いたものではない」と述べたが、中国が視野にあることは疑いようがない。
ただ、中国と経済的な結びつきの強い国が多い東南アジア諸国連合(ASEAN)にしても、日米豪印4カ国による「QUAD(クアッド)」の枠組みに参加しつつも「非同盟」の伝統を持つインドにしても、多くの国が望むのは、中国との平和的な共存だろう。
台頭する中国に対し、日本は「自由で開かれたインド太平洋」を掲げ、日米同盟を基軸に、豪州や欧州諸国とも安保面での協力を強めてきた。軍事的な対抗措置が突出して、かえって緊張を高めたり、地域に分断をもたらしたりするようでは元も子もない。日豪両国には外交努力を含む、バランスのとれた取り組みが求められる。
多くの天然資源を輸入に頼る日本にとって、世界有数の資源大国、豪州との緊密な関係は欠かせない。ロシアによるウクライナ侵略や円安の影響で価格が高騰し、経済や暮らしを直撃している今はなおさらだ。両首脳がエネルギー分野でも協力を確認したことは歓迎できる。
日本が輸入する液化天然ガス(LNG)の4割弱、燃料用の石炭の7割弱が豪州からだ。LNGをめぐっては、見送られたとはいえ、豪州では一時、国内向けを確保するため、輸出規制が検討された。ロシア極東の開発事業「サハリン2」からの調達が途絶え、国内需給が逼迫(ひっぱく)するリスクを抱える日本としては、今後も、豪州が安定供給の国際的な役割を果たし続けるよう、働きかける必要がある。
(2)【毎日社説】日豪の安保共同宣言 関係いかし地域の安定を
日豪の安保共同宣言 関係生かし地域の安定を
https://mainichi.jp/articles/20221027/ddm/005/070/087000c
注目の連載
オピニオン
朝刊政治面
毎日新聞 2022/10/27 東京朝刊 English version 874文字
「準同盟」と言われる関係を深化させ、地域に平和と安定をもたらすことが重要だ。
日本とオーストラリアが安全保障共同宣言を15年ぶりに改定した。岸田文雄首相が先週、豪州西部パースを訪問し、アルバニージー首相との会談で署名した。
両国の主権や地域の安全保障上の利益に影響を及ぼし得る「緊急事態」には、「相互に協議し、対応措置を検討する」と安保協力の強化を打ち出した。
名指しはしていないが、念頭にあるのは、軍事的拡張を続け、経済的影響力を拡大する中国だ。
日豪はともに米国の同盟国で、自由と民主主義の価値観を共有する。法の支配の普及を目指す「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想を推進し、「QUAD(クアッド)」という日米豪印4カ国の協力を積み上げてきた。
2国間でも、安全保障面で関係強化が急ピッチで進む。海上自衛隊による豪軍艦艇の「武器等防護」の実施や、相手国の軍隊が活動する際の構成員の地位などを定める「円滑化協定」の署名だ。
中国による南・東シナ海での現状変更の試みや、南太平洋の島しょ国への影響力拡大は、地域の安全保障にとって懸念材料だ。台湾海峡を巡る緊張も高まっている。
豪州は中国への警戒感を強めている。2010年代後半には中国の情報機関による豪州への内政干渉疑惑があった。新型コロナウイルスの発生源の調査を巡って通商関係が冷え込んだ。
多国間ネットワークの形成は必要だ。ただし、中国に対抗するあまり、不安定化を招くことがあってはならない。中国との対話にも同時に力を注ぐことが不可欠だ。
安倍政権時代から日豪両国は、経済面でも、11カ国が参加する環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)を主導するなど協力を加速させてきた。
新安保宣言には、強靱(きょうじん)なサプライチェーンの構築など経済安全保障の促進も盛り込まれた。
日本は液化天然ガス(LNG)の4割、石炭の7割を豪州から輸入する。ウクライナ危機で、エネルギーの安定確保の重要性が増す中、協力強化は時宜にかなう。
岸田首相は、両国の強みを生かし合う関係を前進させるべきだ。
-
(3)所で、日豪安保協力が可能なのは、我が国に集団的自衛権の行使を(部分的ながら)認めた安保法があるお陰、なのだが。手前ぇら、何か言うのを忘れてないか?
国家同士の安保協力には、本来、集団的自衛権の相互行使が不可欠である。集団的自衛権の相互行使があればこそ、相互防衛の信用と信頼が成立し、広範囲渡る安保協力が実現する。これが片務的な一方のみの集団的自衛権行使では、安保協力が「成立する」事さえ希であろう。チョイと考えれば、常識的とも言えそうなことだ。
所が、その「常識的とも言えそうなこと」が全く通用しなかったのが、「安保法成立執行以前の我が国・日本」であった。なぁにしろ、憲法学者の先生方(*1)の大半はおろか、日本政府(歴代日本国首相の相当数(*2)含む)まで、「我が国は、(国の基本的国権としての)集団的自衛権を有する。が、日本国憲法が集団的自衛権の行使を禁じているから、我が国は集団的自衛権を行使できない。」と主張していいた、のだ。左様な主張が「大手を振って罷り通る」どころか、日本政府の公式公的見解でもあった、のだ。
これに対して、「故に我が国は、日本国憲法を即刻改憲し、基本的国権たる集団的自衛権を行使できるようにしなければならない。」と結論づけるならば、未だロジックが通るのだが、そうはならずに、「我が国に集団的自衛権の行使を禁じる日本国憲法は素晴らしい(=変えてはならない!)」だったのだから、思い出すだに呆れ果てるような状態だった。左様な「呆れ果てるような状態」だったが故に、「安保協力」とはほぼ自動的に「唯一の同盟国たる米国との安保協力」に限定されていた。
集団的自衛権を行使できないような欠陥国と同盟結ぼうなんて酔狂な国は、左様な状態に我が国をおいた責任の一端を担う(*3)米国ぐらいしか、なかったから、だ。
そんな、「一寸韓国を笑えないような、半気違い状態」だった日本を、些かなりとも「正気に戻した」のが、「我が国の集団的自衛権行使を(一部なりとも)認めた、安保法」である。ある意味「解釈改憲」であり、それ故に、日本新聞業界の左半分をはじめとする「安保法反対キャンペーン」には、凄まじいモノがあった。「日本が、戦争できる国になる!!!」って非難は、「それは、良い事どころか、当たり前だろう。」って点を除けば「真面な非難(*4)」な方で、やれ、「日本が戦争に巻き込まれる!(これもまあ、一面の事実だから、非難としてはマシな方。)」だの「徴兵制になる!(このロジックは、今以て謎だ。が「マイナンバーカードを保険証と一体化して事実上の義務化すると、徴兵制になる。」よりは、まぁだ結びつきそうだ。)」だの、実に凄まじかった。
アカ新聞ども大好きな瀬戸内寂徳という作家にして尼僧が、「私の生涯で、今ほど戦争の危険を感じたことは無い!」と断定断言してしまったのも、忘れがたい。この人は結構なお歳で、大東亜戦争終結時には二十歳前の、「物心つく」どころか「多感なお年頃」だった人。その瀬戸内寂徳が「大東亜戦争戦時下よりも、安保法案審議に、戦争の危険を感じた。」と明言しているのであり・・・余程のオッチョコチョイか間抜けか気違い、としか思えなかったので、良く覚えている。
閑話休題(それはさておき)
我が国がこのたびオーストラリアと「日豪安保協力」を実現できるのも、突き詰めれば「我が国もまた、オーストラリアと同様に、集団的自衛権を行使できるから。」である。言い替えれば、「日豪安保協力は、ある意味、安保法のお陰」なのである。章題にした通りだ。
で、だ。上掲社説で朝日も毎日も、日豪安保協力を、絶賛礼賛こそしていないが、肯定し、更なる期待をかけている、よなぁ。
手前ぇら、「日豪安保協力を肯定する」前に、「日豪安保協力を可能とした、安保法に対して、手ぇついて謝るべき」じゃぁ、ねぇのかよ。
- <注記>
- (*1) 以前から書いているが、日本の憲法学者は「(少なくとも)半分は気違いだ。」と私(ZERO)は思っている。
- (*2) その中には、第1次安倍政権時代の安倍首相(当時)を含む。
- (*3) 「一端を担う」ではあるが、「全責任を負う」訳では無い。「日本国に集団的自衛権の行使を認めない日本国憲法」を日本に強制したのは米国だが、そんな欠陥憲法を後生大事にして今に至るも隻言半句も改憲しない、出来ないのは、日本自身の責任である。
- (*4) 非難根拠たる「戦争できる国になる」と、「安保法」が論理的にチャンと結びついている、という意味で、「真面」である。
- 「そもそも、非難になっていない」って、致命的欠点があるが。