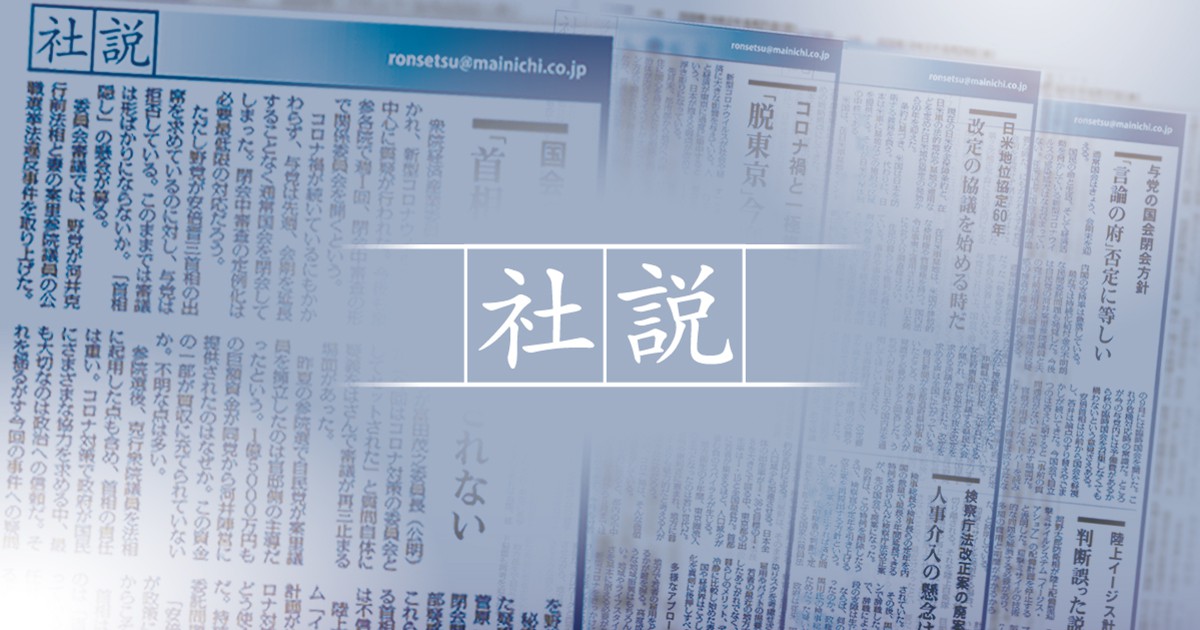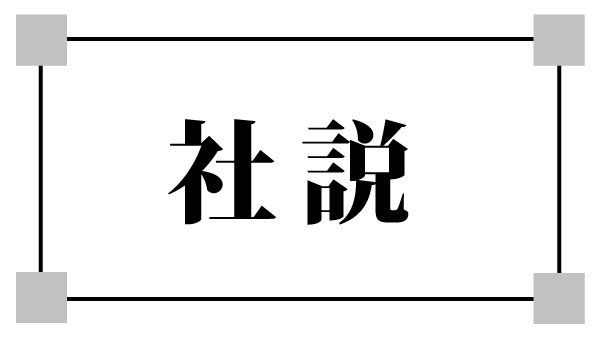-
中国弾道ミサイル5発、我が国の排他的経済水域EEZに着弾、に対する、朝日他社説
少なくとも、挑発。ヘタすりゃそのまま開戦と言うこともあ、ありうる事態である。中国軍弾道ミサイルが我が国のEEZ排他的経済水域に着弾した、と言う事態は、左様な異常事態である。
無論、EEZ排他的経済水域は、「我が国の領海」ではない。だが、我が国の領海に隣接した海域であり、なればこそ「排他的」経済水域と称されるのである。そこにミサイルを5発も着弾させるとは、「我が国の排他的経済水域を狙った」と言うこと。諄いようだが、立派な挑発。下手すれば開戦理由ともなり得る。
なればこそ、「少なくとも挑発」って認識は、大方のアカ新聞どもも「共有」し、我が国の相当な広範囲(何しろ、私(ZERO)のような「殆ど生まれながらの右翼」から、朝日新聞まで包含するのだから。)での共通認識であるようだ。
①【朝日社説】中国軍事演習 無責任な威嚇やめよ
②【毎日新聞】台湾情勢と日本 偶発的衝突避ける外交を
④【沖縄タイムス社説】[中国軍大規模演習]度が過ぎる「台湾包囲」
①【朝日社説】中国軍事演習 無責任な威嚇やめよ
中国軍事演習 無責任な威嚇をやめよ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15381008.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年8月7日 5時00分
4日、中国人民解放軍東部戦区が公表した同戦区ロケット軍部隊による台湾東沖の海上に向けた通常ミサイルの発射訓練の写真。撮影場所は不明=ロイター
[PR]
自らの意に沿わぬ言動に接すると、武力で威嚇し、外交の扉も閉ざす。こんなふるまいでは、平和発展を志向する大国とは誰も認められない。
中国が台湾周辺の区域で、大規模な軍事演習を続けている。ペロシ米下院議長の訪台に抗議し、「結託する米国と台湾を震え上がらせるものだ」と、中国国防省は公言している。
区域は台湾を囲み、まるで封鎖するかのようだ。艦船や戦闘機多数が参加し、複数の弾道ミサイルが発射された。うち5発が日本の排他的経済水域内に落下した。台湾本島上空を通過したものもあったという。
演習名目とはいえ、危険極まりない。地域の安全保障環境を揺るがす無謀な行為である。
日米など主要7カ国の外相は緊張悪化を懸念する共同声明を出した。これを中国外相は「紙くず」と呼び、予定された日中外相会談を取りやめた。米国に対しては、軍同士の協議や気候変動問題を含む多分野の対話を取りやめると発表した。
中国からすれば、事前の警告に耳を貸さなかった米台の側に非があり、日本も突き放すということのようだ。
しかし、議員外交をめぐる摩擦を理由にこれほどの軍事力を動員するのは、明白な過剰反応だ。異論があるからこそ対話で意見をぶつけ、打開を探るのが責任ある国家の態度である。
中国外務省は「台湾問題で日本は歴史的な罪を負っており、とやかく言う資格はない」とする。台湾の植民地支配という過去が日本にあるのは事実だが、自国と近隣を脅かす現状を座視できないのは当然だ。
中国メディアは大々的に軍事演習の様子を報じている。秋の党大会を前に、共産党政権は軍の動きを国威発揚に利用し、求心力を高めたいという内向きの狙いがあるのだろう。
だが、ゆがんだナショナリズムを増長させる恐れはないのか。国民感情が高まれば、逆に中国指導部が外交の幅を狭められはしないか。危うい動きと言うしかない。
日中関係は今年9月に国交正常化50周年の節目を迎える。
これに向け、両国は岸田首相と習近平(シーチンピン)国家主席の首脳協議を模索してきたが、その先行きも不透明になってしまった。日中関係の今後の行方を憂慮せざるをえない。
日本も米国も冷静な対応に努めるべき時だ。来日したペロシ氏と岸田首相は会談し、台湾海峡の平和と安定のための日米の連携を確認したという。
これ以上の情勢悪化は誰の利益にもならない。その現実を日米はくり返し中国側に説き、強く自制を促したい。
②【毎日新聞】台湾情勢と日本 偶発的衝突避ける外交を
台湾情勢と日本 偶発的衝突避ける外交を
https://mainichi.jp/articles/20220807/ddm/005/070/109000c
注目の連載
オピニオン
朝刊政治面
毎日新聞 2022/8/7 東京朝刊 English version 1633文字
台湾を巡る緊張が高まっている。偶発的な軍事衝突を避けるためにも、米中両国は対話の道を閉ざすべきではない。
ペロシ米下院議長の台湾訪問への対抗措置として、中国は台湾を取り囲む空海域で実弾射撃を含む軍事演習を続けている。
4日には弾道ミサイル11発を発射し、一部が台湾本島上空を飛び越えたという。沖縄県の波照間島に近い日本の排他的経済水域(EEZ)内にも5発が着弾した。前例のない事態である。
台湾では航空会社が一部の運航を取りやめた。与那国島の漁協は漁業者に対し、演習終了までの操業自粛を要請した。
ミサイル落下を受け、日本政府は中国に抗議し、演習の即時中止を要求した。岸田文雄首相は「日本国民の安全に関わる重大な問題だ」と懸念を表明した。
緊張高める中国の行動
国際社会の安定に責任を負う大国として、中国は地域の緊張を高めるような軍事的威圧をただちにやめるべきだ。
他国のEEZ内で演習を実施すること自体が国際法に違反するわけではない。しかし今回は、1996年に起きた台湾海峡危機の際を上回る演習規模である。
中国は台湾統一を、譲ることのできない「核心的利益」と位置付け、対外政策の基礎に据える。
世界第2位の経済大国であり、米国に迫るほどの軍事力を手にしている。今回、それを見せつけ、台湾問題への米国の介入を阻もうとの思惑がうかがえる。
ただし米中両国とも、これ以上事態をエスカレートさせることは避けたいのが本音だろう。
中国は演習計画を事前に公表し、船舶などの航行に注意を呼びかけた。演習を本格化したのはペロシ氏が台湾を離れてからだ。
バイデン米政権は、台湾の独立を支持しない「一つの中国」政策に変更はないと強調し、対話で事態を沈静化させたいとの考えを示した。予定していた大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験も延期した。
それでも、緊張状態が続けば、米中の偶発的な衝突が起きる危険性は否定できない。日本にも、地域を安定させるための外交戦略が求められる。
浮き彫りになったのは、米中対立が激化した場合、台湾から地理的に近い日本が巻き込まれるというリスクがあることだ。沖縄県・尖閣諸島を巡る対立にも波及しかねない。
日本の安全保障は日米同盟が基軸である。だが米国と違い、日本にとって中国は歴史的なつながりが深い隣国だ。経済面でも相互に依存しており、安定的な関係を築くことが欠かせない。
9月の日中国交正常化50年を控えて、両国とも関係改善に動き出そうとする矢先だった。
ところが今回の事態を受け、中国は、4日に予定されていた日中外相会談を突然キャンセルした。日本を含む主要7カ国(G7)の外相が共同声明で演習に懸念を表明したことを理由に挙げている。
対話探る努力を今こそ
しかし情勢が厳しさを増している時こそ、打開に向けた対話が必要となる。
松野博一官房長官は「わが国は中国との対話については、常にオープンだ」と述べ、日中関係を安定させる努力を続ける姿勢を示している。
岸田首相は、中国に「言うべきこと」を主張しつつ協力も模索する「リアリズム外交」を掲げる。
ただ、近年、日中間では首脳や閣僚同士の対話が停滞している。危機管理のために必要な防衛当局間のホットライン開設も実現していない。
米中は火種を抱えながらも、バイデン大統領と習近平国家主席が過去1年半で5度の対話を重ねている。対照的に、岸田首相は、昨秋の就任直後に習氏と電話による協議を1回行っただけだ。
岸田政権は防衛費の大幅な増額を検討している。今後、自民党内からの増額圧力が強まることが予想される。
防衛力の見直しは必要だが、周辺国との対話が不十分なまま、際限のない軍拡競争に陥れば、かえって地域の緊張を高める。
米中対立が続く中、求められるのは独自の対中戦略である。中国の強硬姿勢には毅然(きぜん)とした対応を取ると同時に、対話を通じて建設的な関係の構築を探る。したたかな外交を展開すべきだ。
④【沖縄タイムス社説】[中国軍大規模演習]度が過ぎる「台湾包囲」
[中国軍大規模演習]度が過ぎる「台湾包囲」
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1004124
2022年8月7日 06:50
強大な軍事力による、あまりにも露骨な威嚇である。
米国のペロシ下院議長の台湾訪問に対抗し、中国軍は4日から7日までの日程で、大規模な軍事演習を始めた。
台湾を取り囲むように6カ所の演習区域が設定されており、「台湾封鎖」を想定した演習だとみられている。
各演習エリアに中国本土から弾道ミサイルが発射され、その一部は台湾上空を通過した。日本の排他的経済水域(EEZ)にも5発が着弾した。
台湾の国防部によると、中国軍の航空機や艦船は頻繁に台湾海峡の中間線を越え、台湾側に進入した。
6日の演習では台湾本島を攻撃する模擬演習も実施された。
このような演習が実際に行われること自体、東アジアの安全保障環境が極めて危険な水準に達しつつあることを物語っている。
台湾に近い沖縄県にとっては、看過できない深刻な事態だ。実際、与那国町漁協は、旧盆前の書き入れ時に周辺海域への出漁自粛を余儀なくされた。
琉球海運の貨物船も、石垣島沖で停泊し、台湾到着を遅らせるなどの影響を受けた。
「台湾を孤立させない」というペロシ氏の強烈なメッセージは、中国による武力統一を警戒する台湾の人々を勇気づけたかもしれない。
その一方で、東アジアの軍事緊張を著しく高め、米中関係や日中関係を悪化させたことも確かだ。
台湾を巡る問題は、新たな局面に入ったというべきだろう。
■ ■
事態の展開が予測されていながら、ペロシ氏はなぜ、訪台を強行したのか。
米議会の空気を反映した行動だとしても、その理由がよく分からない。
同じ民主党に属していながらバイデン大統領との「すきま風」も表面化した。
米国の中には、台湾問題を巡ってこれまで堅持してきた「あいまい戦略」では中国を抑止できない、との声が広がりつつあるという。
強硬策には強硬策で対応するしかないとの空気が米側に広がれば、中国側は中間線を越えた軍事行動を常態化させ、軍事的な揺さぶりを強めるはずだ。
ロシアによるウクライナ侵攻で、「武力による威嚇」や「武力の行使」に踏み出す心理的な垣根が低くなってきているのではないか。
中国が台湾封鎖を想定した大規模な軍事演習を行ったのも、その表れなのではないか。そんな懸念が拭えない。
■ ■
1995~96年の台湾海峡危機の際は、軍事力に勝る米国が空母を派遣し、力を誇示することで中国軍を抑え込んだ。
あれから四半世紀あまり。中国の軍備増強は著しい。その自信が今回の対応にも表れている。
米国の凋落(ちょうらく)と中ロの接近、権威主義国家の台頭によって世界の混迷は深まるばかりである。
緊張緩和に向けた外交努力が今ほど必要な時はない。防衛力の強化だけでは、危機は回避できない。
-
朝日だけ「弾道ミサイルは落下」している。
毎日も、沖縄タイムスも、「着弾」と明記しているのに、朝日は「落下」で、事故か何かで「間違った落ちた」かの如き表記をしている。
1発や2発ではない。5発の着弾だ。「間違って落下」などでは無く、「我が国の排他的経済水域を、狙った」のであり、「着弾」か「命中」と、表記すべきであろう。
「着弾」と「落下」の違いこそあるものの、上掲アカ新聞各紙の主張は、大凡一致している。即ち、
(1) 対中対話継続・重視 特に、今秋の「日中国交回復50周年」に悪影響を与えるな。
(2) 日本の防衛費増額に対する婉曲的非難
これらに加えて、上掲沖縄タイムスでは、
(3) ペロシ米下院議長訪台への批判
が付け加えられている。詰まるところ、上記(2)も(3)も、中共にとっては誠に好都合な主張であり、上記(1)もある意味「中共にとって好都合な主張」である。
平たく言えば、「中共の我がEEZへの弾道ミサイル発射は、非難する」モノの、「対話は続けろ。防衛費増額は慎重に。」ってのが、上掲アカ新聞の主張。「対話継続」に「日中国交回復50周年」は必須では無かろう。寧ろそんなモノを「記念する」事こそ「誤ったメッセージを、中共へ送りかねない。」と考えるのが、普通・常識的であろうに。まあ、そこは、アカだから、ある意味「非常識なのは当たり前」で、「中共を非難しただけ、上出来」とさえ、言えるかも知れない。
と言うのも、「上には上が居る」というか、「下には下が居る」というか、イヤ、「左には、左が居る。」と言うのが、正しそうなのだが・・・
一方その日の東京新聞&琉球新報の社説は・・・
(1)③【東京社説】週のはじめに考える 謝ろう 誤ったのなら
③【東京社説】週のはじめに考える 謝ろう 誤ったのなら
週のはじめに考える 謝ろう 誤ったのなら
https://www.tokyo-np.co.jp/article/194427?rct=editorial
2022年8月7日 07時31分
六月に出た一冊の漫画が話題を呼んでいます。「刑務官が明かす死刑の秘密」(竹書房)。日本の拘置所で、実際に死刑の執行にも携わる刑務官に一之瀬はちさんが取材して描く、重い内容です。
死刑囚の首にロープの輪をかける動作と似ているため、自動車のハンドルを握れなくなり、心身を患った同僚など、想像もできない絞首刑の実情を伝えています。
刑務官がこうした過酷な任務に就けるのも「死刑判決は裁判所の厳密で間違いない判断による」という前提があればこそでしょう。
でも実際には、全く無実の人が死刑を宣告されるという驚くべき事態も起きています。例えば。
今から六十年前の一九六二年。名古屋高裁で、殺人事件の再審が始まりました。再審を求めたのは一三年に現在の名古屋市内で人を殺したとして、一審で死刑判決を受けた吉田石松さん。二審で無期懲役に減刑されても、吉田さんはひたすら無実を叫び続けました。
その声はフランスの文豪デュマの名作「巌窟王(モンテ・クリスト伯)」になぞらえて報じられ、真相究明の声が高まります。また吉田さんが罪をなすりつけられていたことも明らかになります。
◆死刑から完全無罪へ
六三年、名古屋高裁は吉田さんに完全な無罪を言い渡しました。吉田さんは何度も「バンザイ」と叫びましたが、逮捕から半世紀も後の名誉回復でした。
死刑と無罪。その恐ろしい差を考えると、つい言葉を失います。吉田さんの生涯をかけた訴えは、裁判所の判断も時には大きく誤るものだと、世に示したのでした。
ですが当時、この判決で司法が国民の信頼を失ったかといえば、それは少し違います。その理由は裁判長たちの言動にありました。
裁判長は、当時八十三歳になっていた吉田さんに「被告人と言うに忍びず吉田翁と呼ぼう」と語りかけ、「我々の先輩が翁に対して冒した過誤をひたすら陳謝する」と謝罪しました。さらには、陪席裁判官二人と頭を下げたのです。
この対応を、当時の新聞は特筆しました。また吉田さんの冤罪(えんざい)を報じてきた記者青山与平さんは、著書「真実は生きている」の中で閉廷後の傍聴席に「感動の拍手が起こった」と書いています。
以来六十年近く。この裁判長の潔い姿勢がしっかり受け継がれているかといえば、少し疑問です。
今年に入ってからも「名張毒ぶどう酒事件」「大崎事件」の再審請求が裁判所に退けられました。ともに確定判決には疑問があり、事実の再検討が必要ではないかと思われるケースですが、裁判所の「重い扉」は開かないままです。
ごく率直に言って、刑事裁判の「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則を司法が軽んじ、再審を拒む理由がよく分かりません。
人を裁く裁判官もまた人であるからには、誤りもあるでしょう。他者を裁く者こそは自らや先達の過ちにも敏感であり、改めるべき点は改めてほしい、と言いたい。もし誤ったのなら謝ろう、きっとその方が信頼されますよ、と。
こうしたことを書くのは、今の司法のあり方を批判するためだけではありません。私たちもまた、先人の過ちを素直に認められない心情を持つように思うからです。
その端的な例は近ごろ、戦前や戦時中の日本の侵略行為を否定し「日本は悪くない」と言い募り、逆に、過去の過ちを直視しようとする人たちを「自虐的」と責める風潮が強まっていることです。
自分の生きている国を立派だと思いたい気持ちは、本来は自然な感情でしょう。だからといって、この国の父祖が犯した過ちに目をつぶり、見過ごしていては、同じ失敗の道を歩みかねません。
さらに最近、日本の戦争などを巡る諸外国からの批判を「不当な反日攻撃」と見なして、積極的に反撃をしようとする「歴史戦」という考えも広まっています。先月亡くなった安倍晋三元首相もまたこの言葉を使った一人でした。
◆「歴史戦」への違和感
しかし、違和感が消えません。国際情勢が混迷する中で、日本も主張するべきことは主張するべきです。けれども日本が戦争をした結果、国民も諸外国の人も多くが傷つき、亡くなりました。そんな重い戦いの歴史を、新たな戦いの火種にするのは愚かなことです。
ウクライナへのロシアの蛮行を見るにつけ「戦い」という言葉がいつか、スポーツやゲームだけの用語になるよう祈ります。戦争で殺された人のためにも「歴史戦」などと言い立てるのは慎みたいと思う敗戦の月、八月です。
⑤【琉球新報社説】最低賃金中央審答申 賃上げ伴う経済好循環を
最低賃金中央審答申 賃上げ伴う経済好循環を
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1562427.html
2022年8月7日 05:00
社説
mail_share
厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」は、2022年度の最低賃金について全国平均31円引き上げ全国平均961円を目安額とする答申を決めた。ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響に伴う急激な物価高を重視した。
最低賃金は人を雇う際の一般的な金額ではなく、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するセーフティーネットである。新型コロナウイルス拡大による経済の落ち込みも加わって、深刻な経済情勢が続く中、過去最大の上げ幅となったことは一定の評価をしたい。
しかし物価は急激に上昇しても賃金が上がらない構造的問題は改善していない。官民が協力し合いながら、市場の力を効率的に使い、持続的な賃上げが伴う経済好循環をつくっていく必要がある。今回の賃上げはその一助となってほしいが、まだ課題山積だ。
日本の労働者の所得水準は、先進国の平均値より低い。経済協力開発機構(OECD)加盟国中22位で、1位の米国の6割に満たない。最低賃金を含む全体の賃上げが大きな課題となっている。
中央審では物価高の評価が焦点となった。直近の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は3カ月連続で2%超上昇し、生計費が家計を圧迫している窮状が浮き彫りになった。また、厚生労働省は従業員30人未満の企業の賃金上昇率が1・5%と、24年ぶりの高水準だったと明かし、最大増額幅とする流れとなった。
物価上昇を懸念する労働者側に対し、企業側も「去年とは状況が変わってきた」との認識で、2年連続据え置きを訴えてきた姿勢を一転、一定の増額を容認する構えだった。
ただ、資源・原材料の高騰を価格転嫁しにくい中小零細企業もあり、そのような企業にとって賃金上昇は厳しさを増すばかりだ。
政府は賃上げ政策に力を入れ、賃上げを実現した企業には最大40%の税控除を打ち出している。しかし原料高などコスト面で収益を圧迫された中小企業に賃上げの余裕があるか、不透明だ。しかも2年間の時限立法であり、将来も人件費を負担する企業にとって魅力的な制度かどうかを実態に照らして検証する必要がある。特に中小零細企業に対して、賃上げにつながるきめ細かな支援を実行してほしい。
一方の企業側には、物価を上げるに伴い、労働者への賃上げも担保することが求められる。人材に対して積極的に投資し、社員の生産性を長期にわたって高めることも重要だろう。このような経済合理性に基づく賃金アップにも取り組まねばならない。
今回の最低賃金引き上げで沖縄は30円の引き上げ目安通りなら850円となる。ただ県民所得全国最低水準で、産業の柱である観光はコロナ禍で非常に厳しい。非正規雇用の割合も全国で最も高い。こうした地域事情を踏まえた企業努力と政策が必要だ。
(
-
両紙とも、「中国軍弾道ミサイルの我が排他的経済水域への着弾」よりも重大関心事が「歴史戦」や「最低賃金」であった、らしい。
「地方紙なんてそんなモノ」って考え方もあるが、⑤琉球新報こそ「沖縄という、かなりマイナーな地方を、更に二分している片割れ(*1)である地方紙」でしか無いが、③東京新聞は「首都圏ではかなりマイナー」では在るモノの(それでも、首都圏ではある。)、日本第三の都市である(多分)名古屋圏では「独占状態」である中日新聞と同じ経営母体&紙面&社説であり、「地方紙だからと、軽視もし難い」地方紙である。
ま、弊ブログでもたびたび取り上げる通り、どちらも「朝日よりも左」であるだけで無く、「朝日以上に気違い」なんだけどね。上掲社説も、その「気違いぶり」の一端を示している、気がするぞ。
- <注記>
- (*1) でも、もう片割れの沖縄タイムスも、大差ないんだよなぁ。