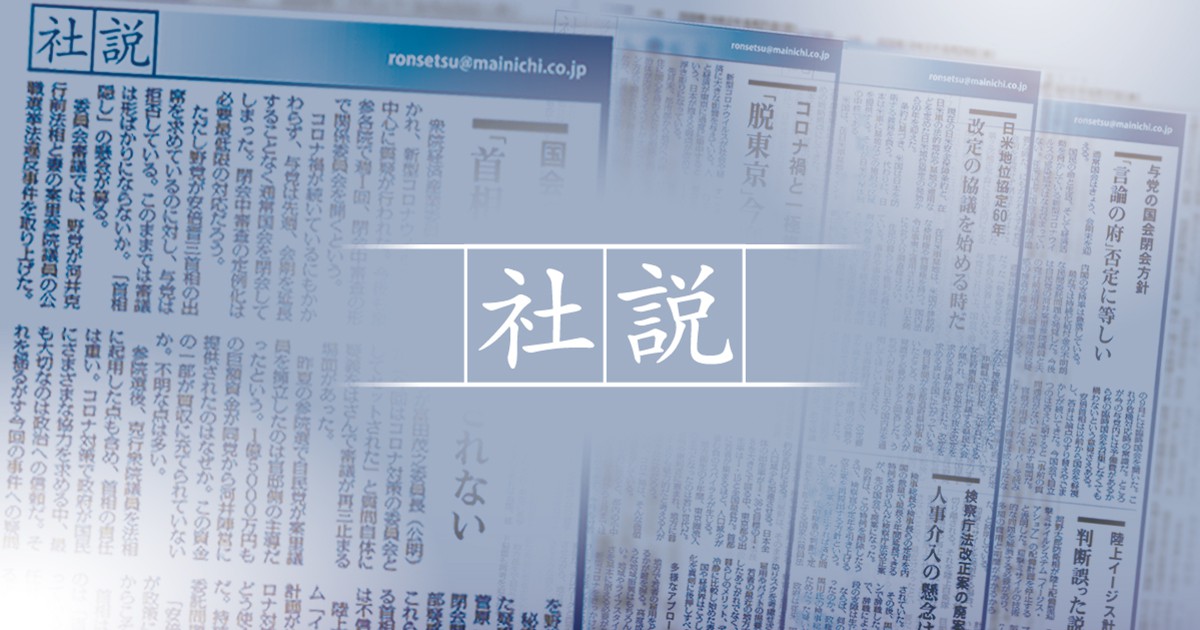-
不公平礼賛ー【毎日社説】増えぬ女性議員 まずは制度を作ることから
既に記事にもし、「東大合格者の男女比率」に喩えて、「結果平等は、不公平である https://ameblo.jp/zero21tiger/entry-12726687284.html」
事も述べた。斯様なことは「ほぼ常識」とさえ思えるのだが、先行記事で取り上げた朝日社説と言い(*1)、後掲する毎日社説と言い、「結果平等を要求し、結果平等を(ほぼ無条件に)"良いこと"と思える」のは、一体何故なんだろうねぇ。
「男女平等」とか「ジェンダーフリー」とか言うキャッチフレーズに、「目が眩む」のかねぇ。
「男が普通に妊娠・出産する世界(*2)」にでもならない限り、「ジェンダー」が「フリー」な、訳が無い、のになぁ。
- <注記>
- (*1) 「議員を男女同数に!」と訴えながら、女性候補が男性候補の二倍も居る共産党を絶賛しているのは、大笑いだったが。
- (*2) 或いは、「女が普通は妊娠・出産しない世界」。こちらの方が未だ実現性はありそうだが、イヤな世界だよな。
【毎日社説】増えぬ女性議員 まずは制度を作ることから
https://mainichi.jp/articles/20220308/ddm/005/070/111000c
朝刊政治面
毎日新聞 2022/3/8 東京朝刊 English version 843文字
2
【1】 きょうは「国際女性デー」だ。女性の権利を守り、社会参加を進めるために国連が定めた。米国で参政権を求めたデモが起源という。
【2】 しかし、日本の政治の現状は、その理念に遠く及ばない。政府が男女格差の是正を掲げても、遅々として進まない。
【3】 もはや、実効性のある制度を作るしかない。候補者や議席の一定数を女性に割り当てる「クオータ制」を導入すべきだ。
【4】 昨年の衆院選では、候補者に占める女性の割合が17・7%にとどまり、2017年の前回選挙から改善しなかった。
【5】 当選者は9・7%で前回を下回った。今年2月現在の各国議会のランキングで、日本は189カ国中166位と低迷している。
【6】 参院は女性議員の割合が23・1%だが、有権者の半数が女性であることを考えれば、まだ不十分だ。地方議員は14・5%に過ぎず、女性のいない議会も少なくない。
【7】 議員構成が偏ると、議論が硬直化しやすい。見過ごされてきた問題に光を当てるためにも、多様な視点が不可欠だ。
【8】 市民活動が盛んな神奈川県大磯町では、全国に先駆けて議会が男女半々の構成となった。審議が活発になり、情報公開も進んだ。
【9】 今夏には参院選がある。立憲民主党は「女性候補者5割を目指す」と掲げ、共産党も発表した候補者の過半数が女性である。
【10】 一方、与党の自民党や公明党の擁立状況は「男性優位」だ。候補者数の男女均等を目指す法律は、掛け声倒れになっている。
【11】 海外では、クオータ制が効果を上げている。118の国・地域で導入され、女性議員の割合が高まっている。
【12】 日本も比例代表の名簿を男女半々とするなど、具体的な議論を始める時だ。女性候補者の比率に応じて、政党交付金を配分する仕組みも検討する必要がある。
【13】 立候補しやすい環境の整備も欠かせない。同僚議員や有権者からのセクハラ、マタハラが横行している。根絶への対策が急務だ。
【14】 男女問わず、子育てや介護などと議員活動を両立できるようにすることも大切である。
【15】 社会の男女格差を解消していくためにも、政治が率先して動かなければならない。
-
そりゃ確実に「不公平」だぞ。
「女性議員の比率を上げること」が「絶対善」に思えてしまうんだから、思い込みって怖いねぇ。以て他山の石としよう。
あらためて、「東大合格者の男女比率」の喩えで、「結果平等」と「機会平等」を説明しておくと、
①「東大合格者数を、男女同数とする」のが「結果平等」
②「東大受験資格にも採点にも、男女の差をつけない」のが「機会平等」
現状は無論、上記②「機会平等」だ。東大入試には共通テストによる一次試験と、東大自身による二次試験による「二段階選抜」であるから、
③「東大一次試験合格者数を、男女同数とする」
って「第三案」が考えられるが、これは「一次試験に対する結果平等」であり、「結果平等の一種」と見なすべきだろう。
また、先行記事にした通り、上記①にせよ上記③にせよ、「結果平等」を求めた場合は、「合格基準の男女間格差」を生じることは、先ず間違いない。仮に「東大志望者数が男女同数」だったとしても、「全体の学力分布まで完全に一致する」なんて事は先ず無いから、「合格点が男女で異なる」ことになる。「合格基準の男女間格差」は、「結果平等」を求める以上必然であり、これを「公平だ」と感じられ、主張できる神経というのが、私(ZERO)の様な「異教徒」には、サッパリ判らない。上記②「機会平等」の方が、「合格基準は男女一律」なのだから、「遙かに公平」だ。
上掲毎日社説(や、先行記事にした朝日社説)が求めているのは、「女性議員の比率向上」で、その為に「選挙制度を変えろ」と主張している。約めて言えば、「女性議員比率向上のための選挙制度改革」である。
「改革」と言えば、聞こえは良いが、見ようによっては「男性議員差別の(現行法では)選挙制度違反」と言うことでもある。
その「女性議員比率向上のための選挙改革」の事例として、上掲毎日社説があげるのは、以下の三案。
(1) 諸外国のクオータ制【パラグラフ11】
(2) 比例代表の名簿を男女半々とする【パラグラフ12】
(3) 女性候補の比率に応じて、政党交付金を配分する【パラグラフ12】
上記(1)「クオータ制」ってのは色々あるらしいが、「女性限定議席数を定める」か、「候補の女性比率を定める」に大別されるらしい。上記(2)は後者の一例。前者は「女性枠当選者の決め方」が難しそうだな。全国区ならば「得票数の多い女性議員から順に当選」と出来そうだが、「地方区の当選者数の一部を女性指定」ってのは、かなり無理があろう。(まあ、後述の通り、「選挙制度を変えることで女性議員を増やす」というのは、それだけで必然的に「無理がある」のだが。)
上記(2)の「女性議員比率向上策」は、先ず確実に次は「比例代表の名簿順を男女交互にする(つまり、比例区当選者は強制的にほぼ男女同数となる)」、更に進んで(比例代表以外の当選者は男性が多いだろうから)「比例代表名簿は、女性候補を上位とする」って所まで、主張し始めそうだ。
上記(3)は、「女性候補が男性候補の二倍居る」共産党優遇になるだろうし、今後は(今度の参院選で半数を女性候補にするという)立憲民主党優遇にもなるだろう。また、各党が「女性候補を増やす動機付け」ともなるだろう。
だが、頭冷やして考えてみろや。それらは果たして、「公平」かぁ?
例えば上記(3)は、「金で政党を釣って女性候補を増やす」策である。「政党助成金ほしさに女性候補を増やす政党」は、「女性だと言うだけで候補に仕立て上げる」だろう事は、想像に難くない・・・と言うよりこの施策は、政党が左様な候補を仕立てることを期待し、以て「政党候補の女性比率を上げよう」としている。無論、私(ZERO)ならば、「政党助成金ほしさに祭り上げられた女性候補」に我が一票を投じる気にはならないが。世の多くが左様に考えれば「候補の女性比率は上がったが、議員の女性比率は(さして)上がらない」ことになるだろう。
いや、左様な上記(3)の「不発」で終われば、見つけモノかも知れない。
問題なのは、上記(3)が「成功」してしまい、「政党助成金ほしさに祭り上げられた女性候補」が当選し、議員となってしまった場合、なのでは無かろうか。「女性である」以外にさしたる利点が無い候補が、議員になってしまい、「議員の女性比率が上がる」事が、「良いこと」などと、何故断定できるのか、私(ZERO)の様な「異教徒」には、サッパリ判らない。
大体、上掲毎日社説の(タイトルにもある)「女性議員比率向上のために、選挙制度を変えろ。」という主張は、必然的に「男性差別の選挙制度」とならざるを得ない。その典型例が上記(2)の「発展型」である「女性上位比例代表名簿」であろう。
「女性上位比例代表名簿」は「極端な例」としても、議席数を当面さほど変えないならば、現行の議席の大半を占める男性議員が落選の憂き目に遭わなければ「女性議員比率の向上」なぞ、実現しない。従って「女性議員比率向上のための、選挙制度変更」は、不可避的必然的に「現職男性議員に対する逆風」である。
別に現職男性議員の肩を持つ心算は無いが、「女性議員比率向上」という結果平等を求めて「選挙制度を変える」ことは、「不公平に繋がりかねない」のであるし、現行選挙法では「基本的に選挙違反である/となる」事も、認識すべきだろう。
選挙制度や候補者選びなど「議員決定」には複雑なプロセスがあるから、「東大入試」という比較的単純なプロセスに比べると「結果平等」と「機会平等」の区別が難しかろうが、「結果平等の追求は、先ず確実に不公平となる」点には、変わりは無さそうだ。
その「不公平」を「甘受する」ってのは、一つの考え方だ。「クオーター制」とか言って「女性限定当選枠」と設けてしまうと言うのは、左様な「不公平を甘受してでも、女性議員数を確保することに、利点がある。」との判断ではあろう。
だが、その「不公平」を、「認識しない」ってのは、論外だぞ。