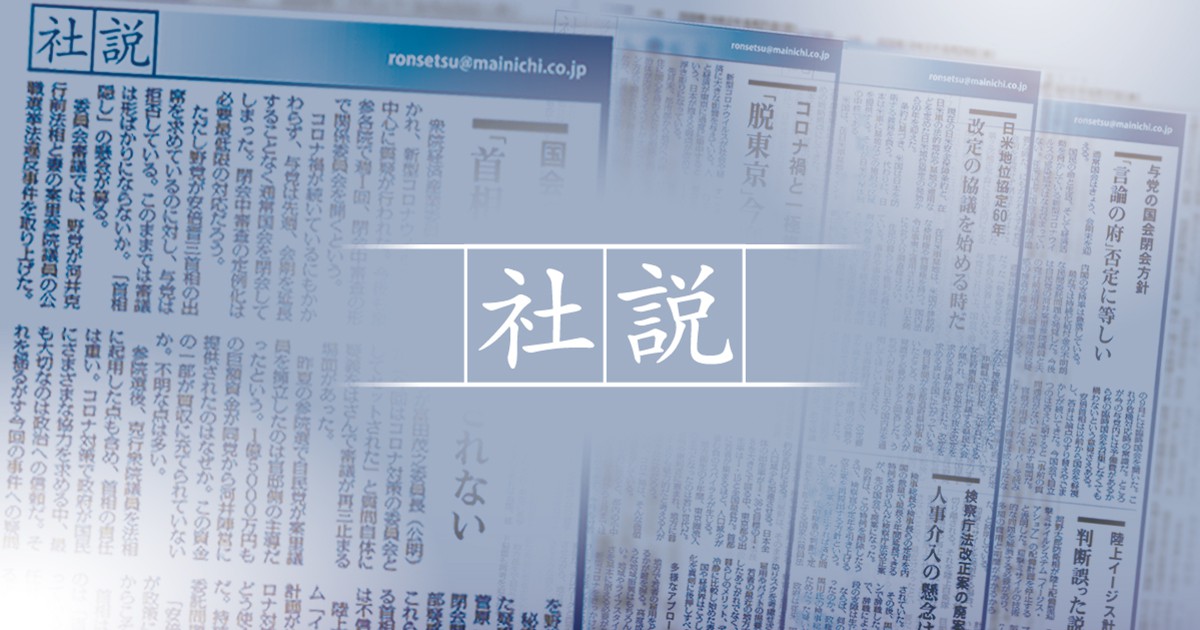-
珍しく賛同できる毎日社説。但し・・・ー【毎日社説】ウクライナ危機 日本は揺るぎない外交を
弊ブログを幾らか御覧になれば明らかであろうが、私(ZERO)は「右翼」であり、「殆ど生まれながらの右翼」と自認し、公言している。「世の中は、右翼も左翼も居るから面白いので、片方だけだったら(*1)、(少なくとも)つまらない(*2)。」と考えている。
「森羅万象皆我が師」を実践しようと心掛けているから(「実践できている」と断定断言する心算は、無い。所詮は神の身ならぬ不完全なる人の身だ。)、「大抵は私(ZERO)とは意見の異なるアカ新聞社説」を、タイトルぐらいは毎日目を通すようにしている。
その「心掛け」が、弊ブログ記事として結実することも、ままある。大抵は「アカ新聞がとなえる、私(ZERO)とは異なる意見を批判し攻撃する」形を取るが、中には「珍しく賛同できる主張である」ために弊ブログ記事とすることもある。「犬が人を噛んでもニュースにはならないが、人が犬を噛んだらニュースだ」ってのと同じ理屈で、「珍しい、稀有なこと」であるし、それ以上に「アカ新聞と雖も偶には”真面なことを言う”事がある」事例として記録し、自戒とするためでもある。
下掲する毎日社説は、タイトルにもした通り、「私(ZERO)が珍しく賛同できる(部分の多い)アカ新聞(=毎日新聞)社説」である。
ま、そこは「アカ新聞」であるから、タイトル後半で示唆した通り、「但し書き」が付いてしまう、のだが。
- <注記>
- (*1) 例え私(ZERO)と同様の「右翼ばかり」となっても。
- 況んや、「私(ZERO)と全く同意見の右翼ばかり」なんて状態は、「ゾッとする」な。
- (*2) 「つまらない」で済んだら、かなりのメッケモンなんだがな、そんな世界。
【毎日社説】ウクライナ危機 日本は揺るぎない外交を
ウクライナ危機 日本は揺るぎない外交を
https://mainichi.jp/articles/20220212/ddm/005/070/130000c
朝刊政治面
毎日新聞 2022/2/12 東京朝刊 English version 832文字
ウクライナ危機に日本はどう対処すべきか。軍事的な圧力で緊張を高めるロシアに揺るぎない姿勢を示しつつ、対話による解決を促す外交努力が重要だ。
予断を許さない状況が続く。フランスとドイツが仲介外交を展開しているが、打開の糸口は見えてこない。
米国とロシアの協議も難航し、米軍を急派したバイデン大統領は「ロシアの軍事侵攻への準備はできている」と強調する。
ロシアとウクライナはそれぞれ軍事演習を実施し、緊張は高まるばかりだ。大規模な武力衝突に至れば被害は計り知れない。外交努力を諦めてはならない。
国際秩序を大きく揺すぶるウクライナ危機は、日本にとっても対岸の火事ではない。
国会は「力による現状変更は断じて容認できない」と批判する決議を採択した。政府に「緊張状態の緩和と速やかな平和の実現に全力を尽くす」ことを求めている。
政府は輸入する液化天然ガス(LNG)の一部を欧州に融通する。欧州は天然ガス調達の約4割をロシアに依存する。ロシアが輸出を制限しても欧州が困らないよう支援するのが目的だ。米国の要請に応じた。
同盟国や友好国と連帯し、結束を示すことは、ロシアに再考を促すうえでも意義がある。
日本はロシアと北方領土問題で対立する一方、エネルギー分野では協力している。安定した関係が大事なことは言うまでもない。
だが、問われるべきは、独立国を武力で威嚇し、その主権と領土を侵害しようとするロシアの振る舞いにほかならない。
アジアに目を向ければ、中国が東シナ海や南シナ海での「力による勢力拡大」の動きを強め、周辺国の脅威となっている。
何より大切なのは、国際規範を順守し、法の支配を重んじることだ。こうした普遍的な理念をないがしろにするなら、どの国であれ看過できない。
譲れない原則を明確にしながら交渉を続け、妥協点を探ることが、戦争を回避する唯一の方法だ。
ウクライナとロシアが折り合える案をどう見いだすか。欧米の取り組みを後押しする外交努力を日本は尽くすべきだ。
-
「揺るぎない外交」には賛同できるが、「軍事力抜きの外交」は「軍事力を利用する外交」よりも、弱いのが道理と言うモノだ。
言い替えれば、「揺るぎない外交」の為には、「通常、軍事力の外交利用が不可欠」である。
世上良くある誤解、だと思うのだが、「外交力=平和的=善」「軍事力=戦争的=悪」という「善悪二元論」は、根源的に誤っている。
「砲艦外交」の一言で、その誤りは端的に指摘できよう。「砲艦外交」とは、「軍事を利用し、軍事的恫喝を利用して成果を狙う外交」である。幕末の黒船来航(*1)によって我が国の開国・開港・通商開始(*2)等の「外交的成果」を引き出したのは、「砲艦外交」の一例であり、我が国としては忘じがたい処である(筈だ)。
本質的に、外交力も軍事力も「国益追求の手段」であり、両者は相反的と言うよりは相補的な関係である。故に、「軍事力を利用した外交」たる「砲艦外交」が成り立つ。逆に「外交力を利用した軍事」というと、「自国の同盟国を増やし、敵国の同盟国を減らす」事が挙げられよう。
「外交力と軍事力の関係が、相補的であること」を縷々述べたのは、上掲毎日新聞社説及び毎日新聞自身が、その事を理解しているとは、想像しがたいから。「想像しがたい」根拠は、毎日新聞の「日頃の行い」であって、上掲毎日社説によるモノでは無い、がな。
更に言えば、軍事的恫喝ばかりが「軍事力の外交利用」ではない。部隊の派遣、駐屯。軍事援助や軍事顧問団の派遣(コレは、部隊派遣の一変形とも言い得る)等がある。これらの選択肢を「取らない/取れない」というのは、「外交上の不利」である。
これらの選択肢を「思いつきすらもしない」というのは、相当な大間抜けだ。まあ、毎日新聞がそんな「大間抜け」である公算は、高そうではあるが。
「部隊の派遣は海外派兵にになるから、憲法違反である!」とするならば、正にそれは、「我が国の外交的選択肢を憲法が制限している」と言うことであり、コレもまた「十分な改憲すべき理由」であろう。
- <注記>
- (*1) 黒船とは鋼製船であり、その相当部分は軍艦である。当時の軍艦と民間船との差違は、今日程には大きくなかったが。
- (*2) 当時欧米諸国が独占的に行っていた遠洋捕鯨の捕鯨船に対す薪水補給ってのも、開国・開港の一つの目的であったことも、忘れるべきでは無いな。通商条約と和親条約が相前後して結ばれたのは、この「捕鯨船に対する薪水補給」というのが、一つの理由である。
- 序でに、その欧米諸国の捕鯨が、鯨油のみを目的とした、実に無駄にして無惨な捕鯨であったことも、忘れるべきでは無いな。小説「白鯨」を読むと、其奴が良く判る。
- 「謝肉祭」などと称して「人間様だけは肉食して良い」とか考えて居るキリスト教徒共は、「鯨油にしか用が無い」モノだから、骨も肉も鯨の粗方をそのまま捨てている、のである。