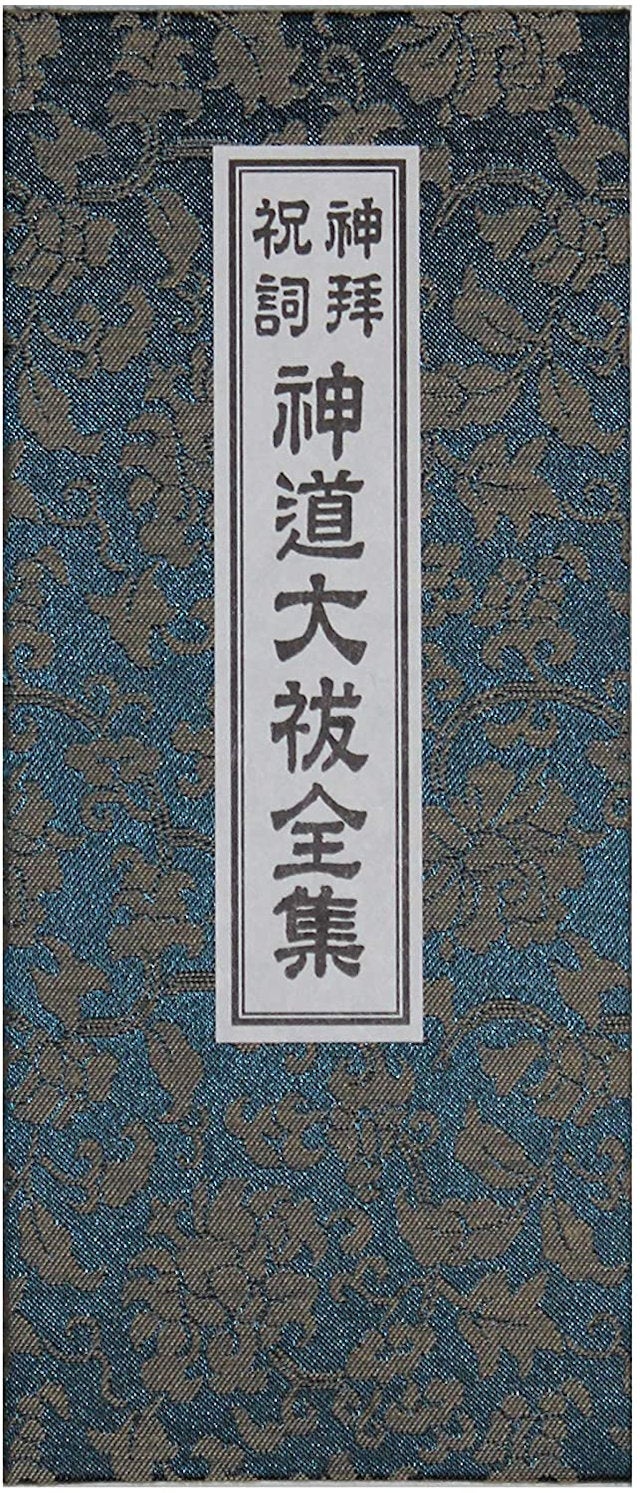大國神甲子祝詞
甲子の日に
読み上げる祝詞
また
大黒さまの神社で
読み上げます
大国主神さまの
名称の由来が
書かれています
地津主
大己貴神夫甲子
(くにつぬし
おおなむちのかみ
それきのえね)
とは
地上を造られた神様
大己貴神さまの縁日
甲子とは
氣(き)の榮(さかえ)る
根(ね)を云(いう)
気の栄える根をいう
根待(ねまち)は
普(あまね)く地(ち)を
祭事(まつること)ぞ
根待 とは
すべての大地を
神事することである
地(ち)は則(すなわち)
妻(つま)なれば
是(これ)を
祭(まつ)るを
寝交待(ねまち)と
云(いう)
大地とは、すなわち
妻を表し
大地である、妻を祀るとは
交わりという
然(しか)り
心善子孫
(こころよくしそん)を
授老(さづけおい)て
これによって
何事もなく、すんなりと、
子孫を賜るということは
大国神
(だいこくじん)の
徳(とく)に叶(かな)ふ
謹(つつし)み
謹(つつし)み
恐(かしこ)み
恐(かしこ)み
申(もお)す
大黒さまの徳に叶う
大変ありがたいことと
感謝申し上げます
古(いにし)へ
此国荒芒
(このくに
あらびたる)
の世(よ)
その昔
この国は、荒れていて
大変な世でした
磐根木根立草
(いはねきねたちくさ)
の
片葉(かたは)も
能強暴(よくあしかる)
の
時(とき)
岩や木や
草の葉の一葉までもが
同調して
暴れていました
天下(あめがした)を
經修治給
(つくりおさめたまう)
は
その荒れている騒乱の世を
治めたのは
国作大己貴神
(くにつくり
おおなむちのかみ)と
申(もお)す
国をつくられた
大己貴神と申した神様でした
武(たけ)く強(つよ)き
勢(いきお)ひ
在(ましませ)ば
大己貴神さまは
勇ましく、強く
勢いもある神様で
あられる
葦原(あしはら)の
醜男(しごお)と
申(もお)し
日本の
強くたくましい男と
申され
天(あま)の
廣戈(ひろほこ)を
振(ふりたて)て
邪鬼(あしきもの)を
撥平(はらいむけ)
天の廣矛を振り立てて
邪鬼を祓い除けて
語問
(こととい)し
木草(こくさ)の
類(たぐい)を
摧伏給
(くだきふせたまえ)ば
悪いことに同調していた
木や草などを
説き伏せれば
八千戈(やちほこ)の
神(かみ)の
申(もお)し
八千矛の神、と申され
諸(もろもろ)の
不和順神等
(まつろはぬ
かみたち)を
和順(まつろひ)
従わぬ、荒ぶる神々を
従わせ
国(くに)を
持給(もちたま)へば
国を平定させれば
大国主神
(おおくにぬしのかみ)と
申(もお)す
大国主神と、申す
此神(このかみ)の
住(すま)せ
給(たま)へる
宮(みや)は
この神様の住まわれている
宮殿は
千尋(ちひろ)の
拷縄(たぐなわ)を
以(もち)て
結(ゆい)て
百餘八十結
(ももあまりやそむす)
び
計り知れない数の
拷縄を結んで
当時、大きな建築物の縄張りをする場合、
一定間隔に結び目をつけた
長い縄を用いたと思われる。
ここでは、
高天原の天日栖宮に基づき、
その寸法を縄の結び目で表して
地上に送ったという。
この100結び、
80結び、60結びという、
数値の組み合わせが注目される。
これらの間には、
ピタゴラスの定理、
a2+b2=c2の関係が
成り立っている。
これらの数値は、
古代出雲大社の巨大神殿の
階段の、
高さ、底辺、斜面長を
表している可能性がある。
1尋は両手を広げた長さで、
1.5~1.8mだとされる。
仮に1結=1尋だとすれば
高さは90m~108mとなり、
出雲大社の言い伝え
「中古には16丈(約48m)、
上古には32丈(約96m)」
のうち、
上古の高さに一致する。
と、あります。
木柱(はしら)は
高(たか)く太(ふと)く
板(いた)は
廣(ひろ)く厚(あつ)く
木の柱は太くて、高さがあり
板は、幅が広くて、厚い
高橋浮橋
打橋鳥船百餘
(たかはしうきはし
うちはしとりふね
ももあま)り
八十縫(やそぬい)の
白楯有又祭祝
(しらだて
ありまたまつり)の
主(つか)さ
諸(もろもろ)の
司(つかさ)に
面備(してそなふ)れば
大物主神
(おおものぬしのかみ)
と申(もう)す
神光海原
(あやしきひかり
うなばら)に
照(てら)し
幸魂奇魂
(さちたま
くしきひたま)を
三諸山(みもろやま)に
鎮(しづ)め
給(たま)へば
三輪山は
古来から
「三諸山(みむろやま)」と呼ばれ、
「うま酒みむろの山」と
称されるは
「みむろ(実醪)」
すなわち
「酒のもと」の意味で、
酒の神様としての信仰からの
呼び名
大国玉
(おおくにたま)
の神(かみ)
と申(もお)し
治世顕露
(よをおさむる
あらは)の
事(こと)を
皇孫尊
(すめみまのみこと)に
依(よざ)し
奉(たてまつ)り
神事(かみこと)を
治(おさ)め給(たま)ふ
御身(おんみ)に
瑞(みつ)に
八坂瓊(やさかに)を
被寂然長隠給
(おきしづかに
ながくかくれ
たま)へば
顕国玉神
(うつくしに
たまのかみ)
と申(もお)す
顕見蒼生及畜
(うつくし
あおひとくさ
およびけもの)の
為(ため)に
其病(そのやまい)を
療(おさむ)る
方(さま)を
定(さだ)め
鳥獣昆虫
(とりけだもの
はうむし)の
災(わざはい)を
拂(はらわ)ん
為(ため)に
其禁厭
(そのまじない
やむ)る
法(のり)を
定(さだ)め給(たま)ふ
是以百姓今
(ここをもつて
おおんたから
いま)に
至(いたる)まで
皆恩賴
(みな
みめぐみのふゆ)を
蒙(かうむ)れりと
稱辭竟奉
(たたえごとを
えたてまつ)り
宇豆(うづ)の
廣前(ひろまえ)に
宇豆(うづ)の
御膳(みけ)
宇豆(うづ)の
御酒(みき)
宇豆(うづ)の
御幣(みてくら)を
朝日(あさひ)の
豊榮登
(とよさかのぼり)に
捧(ささげ)て
奉(たてまつ)る
平(たいら)けく
聞食(きこしめせ)と
申(もお)す
寶祚天壊
(あまつひつぎ
あめつち)と
究(きはま)り
無(な)く
百姓安穏
(おおみたから
やすくおだや)かに
某姓名等家
(なにがしらのいえ)の
自分の家を言います
内諸(うちもろもろ)の
災難(さいなん)なく
萬(よろづ)の
幸(さいわ)ひ
給(たま)へと
夜(よ)の守(まも)り
日(ひ)の守(まも)り
愚(おろか)なるを
猶(なお)も
恵(めぐ)み幸給
(さいはいたま)ひし
謹(つつし)み
謹(つつし)み
恐(かしこ)み
恐(かしこ)み
申事(もおすこと)の
洩落(もれおち)ん
事(こと)
神直日大直日
(かんなおび
おおなおび)に
見直(みなお)し
平(たいら)げく
安(やすら)げく
左男鹿(さかおしか)の
御耳(おんみみ)を
振立(ふりたて)て
聞(きこ)し食(めせ)と
申(もお)す