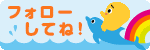僕は自分でも、そんな言葉が口に出るとは思わなかった。
「裕行さんって頭がいいのね。」
彼女のは優しく微笑んでくれた。
「ねぇ、私のこと、好き?」
彼女の声は頭の残像の囁きに埋もれてしまいそうなほど、小さなものだった。
「うん、好きだよ。」
「私の事愛してる?」
「愛しているよ。」
僕は彼女が闇の奥深くで小さくなっているところまで降りていくように、彼女の身体を優しく包んだ。
きっと、今まで泣いていたんだろう。何があったのかを聞く必要はない。今はただ、彼女を優しく包んであげよう。
彼女と僕は、そっと唇を重ね合い、静かに暗い闇の淵で愛を交わしながら、少しづつ二人は光を集め輝きだした。