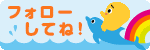すると美冬は急に微笑んで、こう付け加えた。
「でも、あなたといると、時が過ぎてゆくのが怖いくらいに、とても早く感じられるわ。」
僕は、その意味を探さずに視線を落として微笑んだ。
「もう少し眠らないか?なんだかまだ眠いよ。」
「うん、でも私は帰る。」
「えっ?帰るのかい?」
僕は慌てた。彼女が傷付いたまま帰ってしまうのが怖かった。
「もう少し側にいてくれないか?なんだかとっても寂しいんだ。」
彼女は少しだけ微笑んだ。
「そんな風に言ってくれると、なんだかとっても嬉しいわ。いいわよ、じゃ、何か飲み物持ってきてあげる。何が良い?」
「そうだな~ビールでも飲もうかな。」
「こんなに朝から飲むの?大丈夫?」
美冬のその言葉は、とても新鮮だった。僕をそんな風に心配してくれることは初めてのことだったからだ。けれど、少し寂しい気持ちになった。今まで知らずにいた彼女が、ようやくそこにいる。そして、その新しい彼女もまた別の悲しみを背負っているのだろう。
「平気だよ。レッドアイでも飲もうかな。」
「あの、ビールをトマトジュースで割ったやつね。」
「嫌いかい?」
「別に嫌いじゃないわ。でも、こんな朝早くから飲むと酔いそう・・・・・。」
「じゃあ、君は何か別のものを飲んだら?ジャスミン・ティーとかさ、あるよ。」
「じゃあ、私はジャスミン・ティーにする。」
彼女の心が少しづつほぐれてゆくようだった。