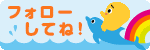「ねぇ、そんな話題、誰から聞いたんだい?」
「剛造さんから・・・・・。」
彼女の涙が、止め処なく流れ出した。
「誰かが、剛造さんに誰かが君のことを告げ口したんだ・・・。」
「告げ口じゃないわ!悪口よ!」
彼女は、まるで剛造に対しての怒りをぶつけるように、僕の言葉に、やつあたりし始めた。
「あぁ、・・・・・そうだね。」
僕がグッと我慢して彼女の幾筋かの涙を見つめた。
「でも、そんなつもり全くないんだよね?」
「うん、だって私、剛造さんのこと好きだし裏切るつもりなんてないわ。だから別れる決心までしていたのに・・・・・。」
僕には、その言葉が辛かった。僕が美冬を諦めようとしている気持ちに似ている。
多分、・・・いや、僕は彼女を諦めきれないのだろう。僕は、その話にジェラシーを覚えた。
でも、僕は気を取り直し、もう一度、確かめるように彼女に尋ねた。
「でも、剛造さんは、そんな話、どうでもいいと思っているんだろ?」
「だって・・・・・。何だか、彼女つくっちゃったみたいなんだもの・・・・・。」
「その事について何か聞いてみたの?」
「聞いたわ。」
「そしたら、なんて言ってたんだい?」
「誤解だって。そんな人いるはずないし、出来れば私と一緒に暮らしたいって・・・・・。」
「へぇ・・・・・。そうなんだ。」
僕はその言葉に愕然とした。