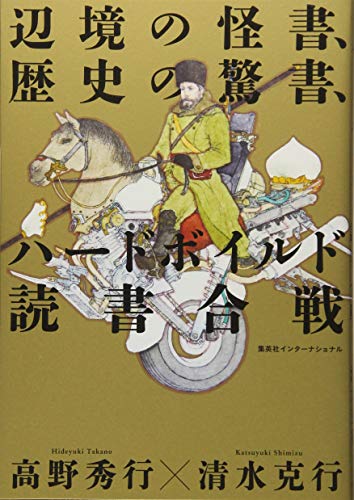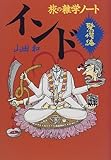ぬる目の風呂につかりながら文庫本を1時間ほどかけて読む。その時は長篇ミステリーや社会を切る新書は向かない。短いエッセイや短編小説やアンソロジー、そして紀行モノである。このスタイルの王様は東海林さだお先生であるのだが、記憶に留まりすぎない情報量の湯加減がキモである。
ある時出会ったのが「巨流アマゾンを遡れ」。今にして思えば文庫になったばかりの初版本であったが、当時はそんなことも知らずに読み終わったら捨ててしまう運命であった。
その時の印象は、「船の旅」に軽くトリップしようと思ったらいつのまにか一緒に人探しをして、森のなかで幻覚剤をやり、ついには雪山の頂上へ。あれ、アマゾンじゃない?そして、最後には旅の中で同行していた相棒の「鈴木」や「宮沢」と一緒に急に消えてしまう。あれ、ココがゴールだった?と聞こうにも目の前にいたはずの高野さんも一瞬で帰ってしまい、そこにいるのはアルパカだけ。狐につままれたような読後感なのだ。
本を閉じて風呂からでながら振り返ると、旅の間に出会った人々の楽天的でユーモアのある愛おしいこと!高野秀行の最大の魅力だと私が思うのは、アマゾンであれ、アフリカであれ、ゲリラやクンサー、ソマリの海賊まで、すべての人が「話せばわかる」楽しいヤツなのである。
当時の流行していた紀行エッセーでは「こんな凄い場所にいった」「アンダーグラウンドな人にあった」「こんな貧乏な旅をした」というもので、当たり前だけど人にできないことをしたからこそ読む価値があるように思えるわけである。でも、この「アマゾン」は、「凄いと思って行ってみたけど、みんないいヤツで合理的だった」というスタンスに貫かれていて、この世界に浸ると、アマゾン旅行も誰にでも出来るような気持ちになってしまう。市場で売られている水族館にある巨大なナマズやピラニアも、スーパーで出会った輸入魚くらいの感覚で「一口だけでいいから味見させて!」というご近所さん感覚。
まさに、実家の風呂というぬるい場所から、気軽にアマゾン奥地へサンダル一つで出掛けられるような錯覚を与えてしまう。実際、私も高野本の影響か「人間が食べているものは何でも食べる。人間が暮らせる場所は楽しく過ごせる」を心情とすることにしている。
この本は結局、手元に残ることはなく、数年後に買い直したのだ、改めてあとがきを読むと「あの巨大なアマゾンを一ヶ月かけて取材してガイドブックを書く」という依頼を受け書いたら、「旅行記におまけとして旅行情報がのっている」という本が出来上がり、編集部に“カツ丼を注文したらトンカツが出てきた、いや豚ショウガ定食が出てきた”という衝撃であったそうだ。
「ありえねー!!」本の成り立ちからしてさまよっている、これぞ、高野本の真骨頂!