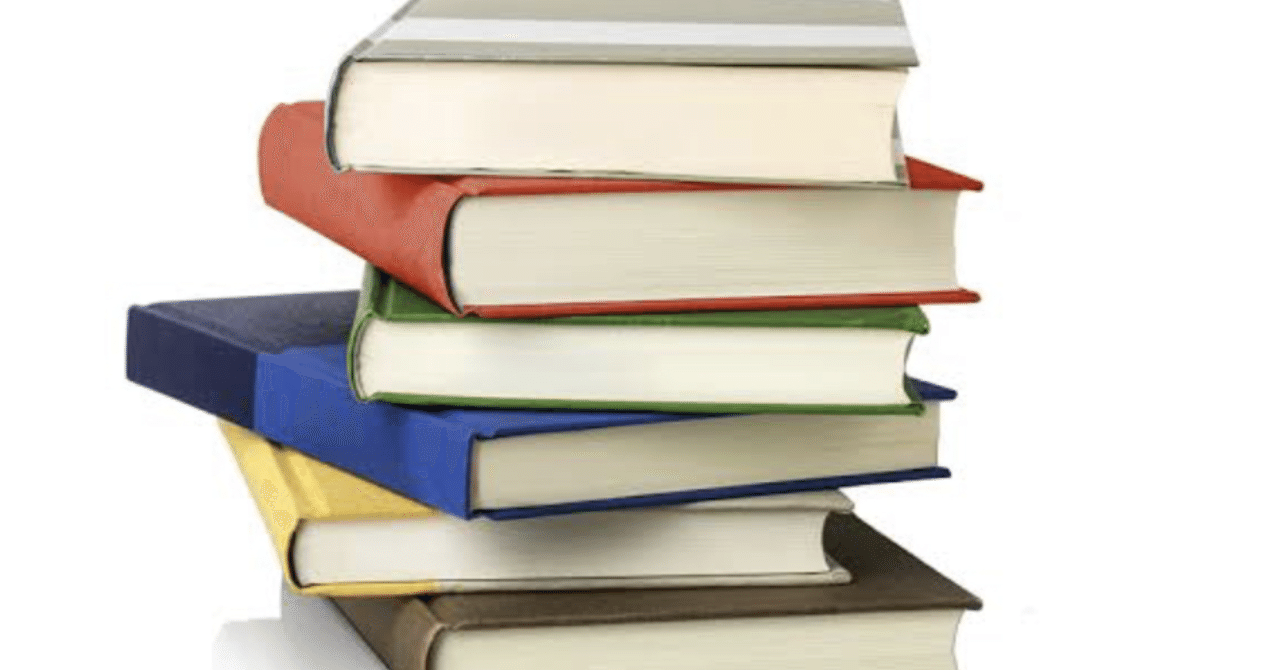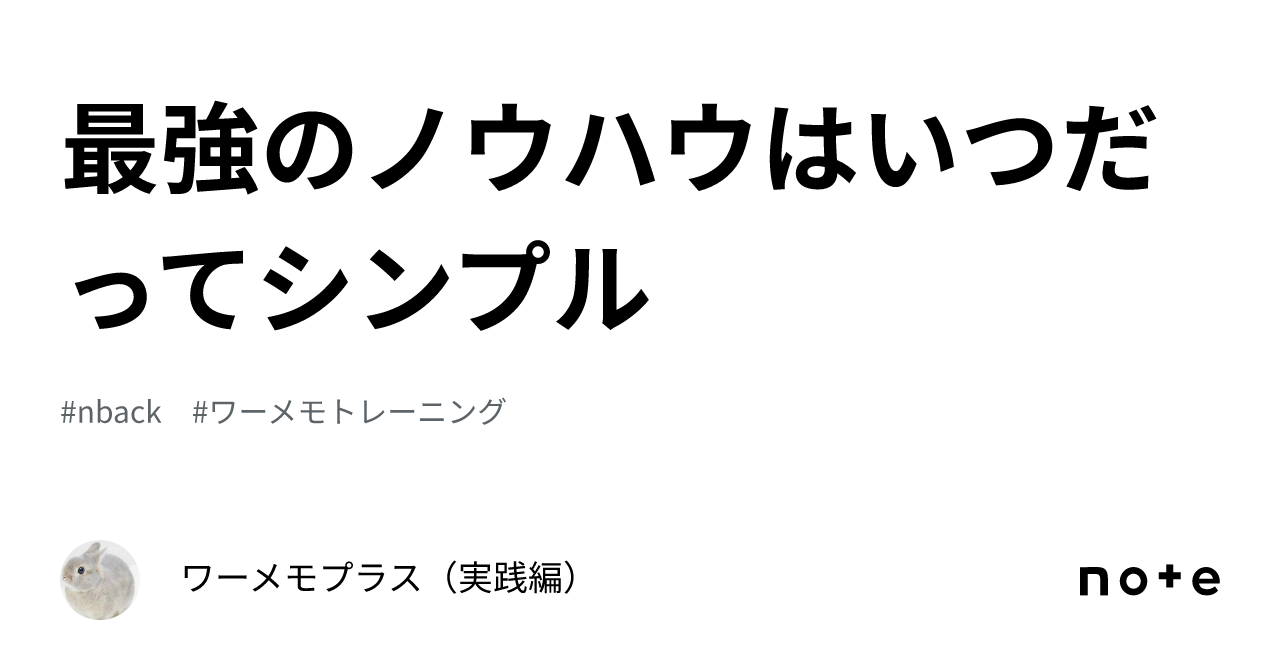参照note記事
- 前ページ
- 次ページ
2023年のワーキングメモリについての論文をわかりやすく要約解説していきます
今回は
「ワーキングメモリ容量に影響を与える要因に関するメタ分析研究」
研究者: Fika Tri Anggraini
発表年: 2023
の論文です
「Factors Affecting Working Memory Capacity: a Meta-Analysis Study」の研究では、私たちの短期記憶の力、つまり「ワーキングメモリ」がどんなことに影響を受けるのかを調べました。
この研究でわかったことは、ワーキングメモリは年齢や、どれだけよく眠れているか、運動をしているか、音楽を聴いているかなどの生活習慣によって変わるということです。
例えば、よく眠れている人や定期的に運動している人は、短期記憶の力が強い傾向にあります。つまり、毎日の生活の中で健康的な選択をすることが、私たちの記憶力をよくする手助けになるということです