
えほん講座 第2回は「子育て中のお母さんへの講座」。
盛岡市総合福祉センター 3F子供会研修室が会場でした。
じつは遅れて入ったのですが、みなさんが、前へ前へ、と声をかけてくれて、
前のほうの席でじっくりお話に入っていくことができました。
いのちのおくりもの-バラクランジャンのうた― こんどう なつみ 作 (リーブル)
うれし野こども図書室主催の高橋美知子さんの読み聞かせに、みんな引き込まれています。
茶色と太い描線はアフリカの大地そのもののようです。
心優しく、いつも唄をうたっているコロにはなかなか子どもが授からなかった。
ある夜、夢にバラクランジャン(大きなきれいな鳥)が現れ、そのお告げをきいて
コロは大きな樹と、大きな立派なヤギの皮で太鼓をつくる。
ヤギの命の実をバラクランジャンが咥えて、コロはひとつの命を宿す。
やがてコロのおなかはふくらみ、コロは元気な赤ん坊を生む。
最初の絵本がこれで、すっかりその世界に引き込まれてしまいました。
絵も文章も力強くシンプルで、なにかを伝えるバイブレーションをもっているようだ。
読み聞かせの後、
この絵本は子どもたちに、というより、きょうは、「子育て中のお母さんへ」ということだから、と
選びました、とコメントしたあと、
子どもたちが人生の中で出会う大人である私たち、というお話へ。
たった1冊の本とさっと溶け込み、子どもたちと一体化しなくてはならない、
という言葉の響きをうまくお伝えできないのが残念です。
高橋さんの言葉は、言葉の響きの力がつよいので…。
骨太でメッセージ性のつよい絵本のつぎは、こちら。
わたしはバレリーナ さく ぴーたー・しす やく 松田素子(BL出版)
サイズもそう大きくはなく、
「地味だけどよく描かれている本」とコメントして、
絵本のよみきかせがはじまりました。
そう、地味なんですが、その世界はカラフルでまるで自分が
バレリーナになって遊んでいるような感じなんですね。
絵本の展開も最初は中央の太い描線のレオタードの女の子が、
彩色のない、白い絵のままお話がはじまるのですが、
彼女が空想の中でバレエダンサーとして優美なドレスで踊ったり、
キャラクターダンサーとして楽しい変身をしたり、そのポーズのひとつひとつも
丁寧に描かれていて、
あれ~?地味だと思っていたけれど、この絵本は自由に遊べるなあと。
この絵本がすきで何度もかりていく女の子がいるそうです。
お姉ちゃんがいて、お姉ちゃんはこれね、私はこれね、と役をきめて
彼女はまだ小さいのにバレリーナになっているのです。絵本のなかで。
そのエピソードがすごく印象に残っています。
そんなふうに1冊の絵本をぎゅっと抱きしめるようにして繰り返しよんだ体験は
その子にとってどんなに豊かなものをもたらすだろう、と思って。
高橋さんから、なにを選んだらいいかわからないひとへ、ということで、
まずはブックリストの活用を、というお話がありました。
何冊ものブックリストを比較して、どれにも載っているような
絵本はまずまちがいない、ということ。
うれし野こども図書室でも『えほんの回転木馬』というブックリストがあって、
ほかのブックリストと重なる絵本も多いけれど、うれし野の個性で選んでいる
絵本も入っていますよ、と。
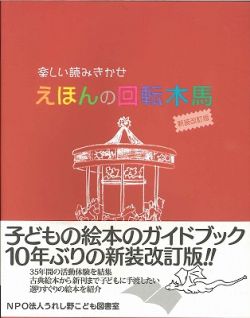
この講座ではたくさんの本と出会って本に教えられたことを
お話していますから、その中で腑に落ちたことがあれば、
と。

すばらしい季節 ターシャ・テューダー作
末盛千枝子訳 (すえもりブックス)
ターシャ・テューダー…私は彼女の庭のファンなのですが、
じつは絵本は絵が地味だ、と思っていてあまり入れないんです。
(その絵を描くためのエピソードや、ターシャが子ども時代からずっと、
昔風の服や暮らし方にあこがれていて、生活のために絵を描き、
球根のために絵を売り、そうしてあの素晴らしい庭と、子どもたちのために
心をつくした楽しいことを考えて一緒に行事を楽しむ、
そういうところにあこがれているんですが)
しかし、
どうしたことでしょう。
読み聞かせで耳でみたターシャの世界は、私の子どものころのいくつかの断片と
重なり合って、ほんとうにすばらしい季節の思い出が展開したではないですか。
(私のうまれた岩手県南部はそれほど田舎ではないですが、
田んぼにはいってタニシをとったりドジョウとったりイナゴをとったり、父の実家は隣の家まで2kmというほんとうの田舎なので、川で釣りをしたり、大きな農家だったので馬も牛もいたし、
夏の夕ぐれは山のほうに向かって自分の影がとてつもなく長く長く伸びるのが楽しかった。
ターシャの絵本の絵とはちがうエピソードばかりですが、
ターシャの絵本をよみきかせしてもらっている間に、体の記憶がよみがえってきたんですね。
高橋さんは子どもたちを育てている間、できるだけ自然にふれさせよう、海にいってサンダルに砂粒が入ってジャリジャリして気持ち悪かったり、そういう必ずしも快適なことばかりではない自然を体で体験させよう、と心がけていらしたそうです。
私はたぶん、高橋さんよりやや若いですが、育った環境はもうすこし昔の年代のひとに近いですし、そんな私なので、平成2桁生まれである息子にも、けっこう過酷な要求をしているかもしれません。
でも、今朝は水やりのあと、ふと、という感じで庭のラズベリーをもいでたべてましたけどね。
そのくらいのことでも、八百屋さんやスーパーで売っているものじゃないとたべられないんじゃないか、と思ってしまっている子どもには刺激になると思います。昔の子どもの私からしたら、それくらいとっとと気づけよ!もっといろいろ庭になってるぜ!と言いたいところはありますが、
この絵本についての言葉を記しておこうと思います。
ことばをようく聴いてください。
いつも耳と目と口と手で
季節のよろこびを探します。
体で自然を感じることが、なにかの役に立つと 信じていきたいです。
ラリー・デーン・ブリマー/ぶん ホセ・アルエゴ と アリアンヌ・デューイ/え
まさきるりこ/やく
この絵本は表紙カヴァーはちょっとポスター風で、ん?と思ったのですが、
本文は繊細な水彩画で、終わりのほうに大きな木からおおかみ一家を俯瞰した構図のページがあって、
特にその大きな楢の木がすばらしかった。
お兄ちゃんやお姉ちゃんに劣等感をもっている、すえっこのおおかみが、
どーんと構えたお父さんおおかみにはげまされ、
自分はいま小さいおおかみだから、できないことがある、
でもそれでいいんだ、と感じる、そんな絵本です。
まっすぐに転がれない、というすえっこおおかみに、
「それでいいのだ。
まっすぐにころがるのは 大きくなってからだ」
と何度も繰り返し語り掛けるおとうさんおおかみ。
お父さんおおかみは繰り返し、末っ子おおかみに低い太い、落ちついた声で語りかけます。。
実際に低く太い、落ちついた声でよんでいるのは高橋さんなのですが、
絵本と読み手の声がぴったり合っている、と思いました。
読んであげたいと思う本があって、その本に合わせた声を自分の中に探す作業が
あったと思うのですが、でも、完全につくられた声ではなく、
そのひとの個性の上におおかみの声が重ねられている感じで、演技ではないのでした。
子どもを育てている人には、
おおかみのお父さんの言葉のような気持ちを忘れないでほしい、
いまはできなくてもいいんだよ、それでいいのだ、と声掛けしてほしい、と。
オーパル・ウィットリー/原作 ジェイン・ボルタン/編
バーバラ・クーニー/絵 やぎたよしこ/訳
大草原の小さな家、を連想してしまったのですが、
これは1900年ごろ、5歳の女の子が書いた日記です。
原作オーパル・ウイットリーというのが、エプロンをして、
大きな木に腕をまわしている女の子の名前。
彼女はお父さんとお母さんは天国へ、そして彼女を引き取った「ママ」の
いいつける用事に追われて、あまり幸せな子ども時代を送っているとはいえません。
当時は全自動洗濯機もありませんから、洗濯と言うと一日仕事で、その日は学校を休ませられます。
彼女の慰めは、
牛のブラウニング(英国の詩人)、
リスのホラチウス(ローマの詩人)
カラスのホラセナ、
ブタのルーベンス
ネズミのメンデルスゾーン!
なんて洒落ていて、知的な女の子なんでしょう。
彼女の心をいちばんわかってくれるのは、大きな木のラファエル。
そして人間でも彼女をかわいがってくれる、優しい女の人があらわれます。
旦那さんから「大好きな人」と呼ばれている若い奥さんです。
彼女はオーパルのためにメンデルスゾーンの小さな布団を縫ってくれたりするのです。
別れが訪れます。
ラファエルが伐られてしまったのです。
そして彼女は「ママ」たちと一緒に製材所のある街へ引っ越すことになり、
なにかと気にかけてくれた「だいすきな人」とも、
友達だった目の見えない女の子とも、お別れです。
絵は最初、小さく控えめに描かれていたのですが、
次第に大きな、構成の大胆な絵になっていって、
オーパルの心が育っていることを絵からも感じていました。
100年も昔のひとりの小さな女の子の日記ですが、子どもは
こういうふうに自分が考えていることを言葉にすることはなかなか、
この年齢では難しくて、
ただ、この子のように心の中では大人よりはるかに様々なことを
哲学者のように考えたり、詩人のように感じたりしているのかもしれない。
そんなことを感じました。
この絵本の前に、「おやすみなさいフランシス」や「フランシスとジャムつきパン」のような、
子どものことをわかってくれる大人、
子どもに通じるように行動をとる大人、というお話がありました。
オーパルの「ママ」は冷たいひとでしたが、「大好きな人」がいてくれたおかげで
オーパルの心はどれだけ守られていたことでしょうか。
教訓のように、こういう大人になりましょう、ということを話されたのではなく、
私も大きな木がすきでね、と、ポッと言ったのがむしろ印象に残っています。なんででしょう。
(つづく)


