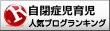こんにちは!
今日は「子供が青信号状態を保ったくれたら?」の続きで、まだ発語がない、または単語をいくつか言う、2.3.4語文くらいまで話せるお子さんに向けた提案です。
誘った遊びにお子さんが体を使って参加してくれて、例えばもっとくすぐって欲しいとか、手や足や体をぎゅーーーっとしてほしいとか(感覚統合の関係で自閉症スペクトラムの子供はかなり強くぎゅーっとされることを好む子が多いです)、もっと並べたいからブロックがほしいとか、もっとボールをコロコロ転がしてほしい、毛布の上に乗ったまま毛布を引きずり回してほしい(これ子供すごーく好きですが、お子さんの体重を考えてできるか考えてくださーい。私、けっこう大きい子にこれをやっちゃって、めっちゃノリノリで長ーいいこと遊んでくれたんですが、後で手指の関節痛になってしまいました!(笑))等々、子供が前のめりで遊びに参加してきてこちらにいろいろと要求するようになったら次のステップに移ります。
ここまで来て初めて、お子さんの目標としていることができるように お子さんの様子を見ながらお子さんのリードに任せて誘導していくことになります。
まず、今一緒に遊んでいる遊びに簡単な名前を付けます。例えばくすぐっているなら「こちょこちょ」とか、体をギューッとするなら「ぎゅー」とか、「コロコロ」とか。 そして、その名前を何度も言いながら遊びます。何回か遊びの名前を聞かせたら、一度ストップして、子供がその遊びの名前を言うのを待ちます。5−15秒待ってくださいね。
さて問題です。 ここで子供が赤信号状態に戻ったらどうしますか?
A: もう一度遊びに誘ってみる。
B: 残念だけど、もう一度一緒に同じことをする。
C: 嬉々として一緒に同じことをして絆を深める。
答えは
Cですねー。
5−15秒待っている間に子供が少しでも音を発したら「あ!今 こちょこちょ って言ってくれた! 言ってくれてありがとう!!! いくよ〜。 こちょこちょこちょ〜!!!!」 みたいに 大喜びでもう一度遊んでください。 そしてストップして待つのを繰り返します。
何かジェスチャーや表情でもっとやってほしいと訴えてくる場合は「こちょこちょ して欲しいんだね。教えてくれてありがとう!!」ともう一度遊んでください。 そしてまたストップして待つのを繰り返してください。
何も反応がない時も、「こちょこちょ するよ〜〜〜! こちょこちょこちょ〜!!!!」と楽しく遊び続けながら、ストップして待つことを繰り返します。
何度がやって、子供が 自分が何らかの要求をすると こちょこちょしてもらえる、というパターンが分かってきたところで、今度はストップして 子供が音を発したりジェスチャーをしてもっとやれと伝えてきたら、 「こちょこちょ って言って」と促してみます。また5−15秒待ちます。 そして 少しでも何か言ってくれたらまた大喜びで遊んでください。 何も言わなくても遊びを続けて、折を見てまたストップ 待つ 促す を繰り返してください。
子供がしっかりとパターンを認識して、コンスタントに「こちょこちょ」と要求してくれるようになったら(これは何日もかかるかもしれません)、今度はそこにもう一言加えられるように持っていきます。 例えばストップした後「どこをこちょこちょしてほしい?」と聞いて5−15秒待つ。答えがなかったら選択肢を提案する。「どこをこちょこちょして欲しい? おなか? 足? それとも床?」みたいな感じです。最後の選択肢はありえないようなものとか、子供の大好きな おしっこ とか おなら とか入れるとバカウケすることが多いです。(笑)答えがだいたい分かっていたら、答えるであろうことは最後の選択肢にしないほうがいいです。(例えば 多分 おなかって答えるな、と思う場合は「足?床?それともおなか?」と聞くのではなくて、「おなか?足? それとも床?」のように言います。そうすると、ただ単に最後に聞いた言葉をリピートするのではなくて、ちゃんと言われたことを聞いて考えないといけないからです。) 次は「おなか こちょこちょ って言って」と促すようにしていきます。 そうやって一語文から二語文「おなか こちょこちょ」へと誘導していきます。
その後は「どうやって こちょこちょして欲しい? たくさん? ちょっと? それともぐじゃぐじゃ?」、「誰のおなかをたくさん こちょこちょして欲しい? 〇〇くんの? ママの? それともおしり大魔神の?」、「誰に〇〇くんのおなかをたくさんこちょこちょして欲しい? パパ? ママ? それともおしり大魔神?」、といった感じです。「ママ、〇〇くんのおなかをたくさんこちょこちょして。」まで行けるように。
ちょっと気をつけたいのが、「もっと」とか「もう一回」という言葉です。これは便利な言葉なんですが、何でも「もっと」で片付けることができてしまうので、言葉が増えない可能性があります。 使っても大丈夫ですが、親御さんがお子さんの言葉を誘導するときには「もっと」という言葉はできるだけ避けてみてください。
次回は会話ができるお子さんへの接し方についてお話したいと思います。
読んでいただいてありがとうございます。
(