5月の洋書はこの本です。
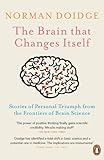 |
The Brain That Changes Itself: Stories of Perso...
1,171円
Amazon |
脳の可塑性について書かれた本。
以前は、localizationismと言って、脳の部分はそれぞれ特定の機能を司っていて、遺伝的にあらかじめ決められているものだという考え方が主流でした。
One function, one location.
1つの機能、1つの場所
その主張に反対したのが、神経学者 Bach-y-Rita氏です。
彼は脳の可塑性(plasticity)を主張。
脳の可塑性についての論文を発表しようとしましたが、6度にもわたり拒否されます。
彼の実験は、盲目の人が見えるようになる椅子の開発や、前庭神経下核のダメージを受けた患者の舌に電気刺激装置を設置することで、平衡感覚を保てるようになったことなどがあります。
彼の父親が脳梗塞で倒れ、体の半分が麻痺し、話すこともできなくなりました。
Paulの兄弟であるGeorgeの世話と訓練で、父親は日常生活を送ることができるようになります。
父の死後、解剖を行った結果、脳はダメージを受けたが、自らが再編成をしていたことが明らかになります。
これは、Paulの主張である脳の可塑性の強い証拠となりました。
彼以外にもたくさんの神経学者や研究者が実験や研究を行います。
そして後にやっと主張が認められることになります。
神経生物学者Carla Shatz氏は、一緒に発火したニューロンは結びつくようになり、脳の中で1つのマップを作るということを主張。
Fire together, wire together.
一緒に発火すると、つながる
小さい頃の脳は、大人の脳と比べて50%も多くのつながりがニューロンやシナプシスの間で起こっています。思春期になると、すでにそれまであまり使われなかったつながりは消されていきます。
大人になってからではなく、思春期にすでに消えていくのは驚きました。
教育でニューロンの枝の数を増やすことができます。
新しいスキルを適切な環境のもと練習すると、脳の中の神経細胞が変化します。
The brain is more like a living creature with an appetite, one that can grow and change itself with proper nourishment and exercise.
脳は欲求を持った生き物のようで、適切な栄養とエクササイズがあれば成長し変化することができる。
In order to keep the brain fit, we must learn something new, rather than simply replaying already-wasted skills.
脳を鍛えるためには、単純にすでに使い古されたスキルを何度も行うよりも、何か新しいことを学ばなければなりません。
脳の仕組み、脳の可塑性について書かれたこの本。
一見、難しそうですが、たくさんの実例が盛り込まれて、難しい概念も理解しやすくなっています。
自らの学習障害を乗り越え、学習障害のある子供たちのための施設を創設したBarbara Arrowsmith Young氏や、脳に大きな損傷を受けた後、通常のリハビリでは回復しなかったけど、ある訓練で日常生活が送れるようになった人など、たくさんの例が紹介されています。
言語学習や文化、子供の成長について興味深い点もいくつかあったので、それはまた別の記事で書きたいと思います。
この洋書は日本語の翻訳版も出版されています。
 |
脳は奇跡を起こす
1,944円
Amazon |
