前回、読もうと思った本はまだ読んでいない。
鬱関連の本は何冊か読んだが、記憶に新しい実近で読んだ自殺関連の本と絡めて、考えていこう。
あらすじとしては、
自殺した4人の幽霊が49日間で100人の自殺志願者を救うというものだ。
自殺する理由はあまり多くない。
・鬱
・借金
・無気力
・罪滅ぼし
・無力感
・寂しさ
・演技
・生活苦
・・・・・・など。
人の数だけ原因があるというほど多様ではないけれど、どれも当人にしてみればあきれるほど個人的な問題でしかない。
個人的だからこそ、誰にもいえない。
個人的だからそこ、伝えても理解されない。
個人的だからこそ、心を開けない。
そして、個人的だからこそ、自分で解決しなければならない。
そんな風に思っているように思えた。
この小説でもどかしいながらも良い設定だと思ったのは、幽霊側から干渉できるものはメガホンを使った声だけ。それもはっきりとその声が届くのではなく、その意味するところを数瞬考えさせるという程度。
扉をすり抜けられもしなければ、人間に触る事も出来ない。ものを動かすことも浮き上ることも出来ない。
だから、物理的に自殺しようとしている人間を助けることは出来ない。
首吊りを阻止したり、飛び降りを襟首つかんでやめさせたりは出来ない。
ただ、直接相手の心に自殺をやめるよう小さく働きかけるだけだ。
それは、誰かを思い出すことかもしれないし、
病院に行こうと思うことかもしれない。
挨拶することかもしれないし、
第三者を介入させることかも知れない。
この物語で、印象的だったのは、
自殺を止めないほうがいいのではないかという問答。
結論からすれば、それが使命だから。
なにより、『生きてこそ』といったところだろう。
生きてさえいればいい事あるさなどと楽観的な事は言えないが、あるかもしれないとは言える。
死ぬよりは良いと断言できる。
なんにでも寿命がある。
今日産まれた赤子だっていつかは死ぬ。
自然の摂理として終わりに向かって自分の意志とは関係なく
進まざるを得ない。
どうせいつか天寿を全うするのに死に急ぐ必要はあるのだろうか?
愛し合い、慈しみあった妻に先立たれる事だってあるだろう。
その際、その旦那はこの物語にもあったように喪失感から自殺を考えるかもしれない。
子も自立し、趣味も無く、どうせ老い先は短い。
ならば、と。
しかし、それでも『生きてこそ』だ。
物語では救助隊員たちが友人に様子を見に行かせ、その場を収める。
現実にはそううまくいかなくたって、何となく始めて味噌汁作りに挑戦し、湯通しのしなかった油揚のくどさに思わず苦笑してしうかもしれない。
あいつはどうやって味噌汁を作ってたんだろうななんてその日の晩にもう一度試して見るかもしれない。
いつか、妻の味噌汁に出会えるかもしれない。
この物語では失敗がない。
関わった自殺志望者すべての自殺を食い止めている。
全ての自殺は食い止められる。著者はそういいたいのかも知れない。
自殺する意志さえ確認できれば。
けれど、現実には自殺の意志を確認することは容易ではない。
だから、手持ちの肉親友人知人との人間関係をしっかりしたものに
しなければならない。
結局そこに行き着くのかなとも思う。
だからといっていまさら、積極的になれだとか、友人を作れだとか
そういうことを推奨しても仕方ない。
先日だって、自身の自殺をネットで実況中継した学生がいたらしい。
リアルタイムで観てたら嘘だと思う人、焦った人もいただろう。
そうすることでその人の中の足りない何かを埋めようとしたのだろう。
けれど、その何かは、自殺を実況中継しようとし、筋書きを決め、夢想した時、既に心の隙間は埋まっているのではないだろうか。
みんなが、親がこんな反応するなんて!如何に自分が大切かわかったでしょ??
と、それこそニヤリと笑っていたかもしれない。
本当はそこで満足してもいいはずだ。
怖くて死ねない、結局だらだらと生き続けるんだ。
そんな悪循環に陥っても生きてることだけで価値がある。生命とは存在そのもので、存在そのものに価値はある。
そんなんでいいじゃないかと思ってしまう。
が、
行動しなければ意味がないという思い込みで行動に移してしまう。
移してししまえば、当たり前だが死んでしまう。
それは意識的には本懐なのかもしれない。
が、やめるという選択肢があり、実際にやめることができるのであれば、本懐というのは一時の迷いなのではないだろうか。
自殺者は声をあげない。
だから、誰にも届かない。
が、その前に自殺を考えないものは、聞き耳を立てるべきなのかもしれない。
そんなにしょっちゅう周りの人間が自殺するわけではないだろう。
けれど、まさか、はいつでも起こりうる。
そのための対処を誰もが知っておいた方がいいと思う。
調べてみると、
自殺防止センターのようなものがある。
死にたくなったら、話を聞いてもらえる。それだけでも、心は静まるだろう。
まず、深呼吸し、死のうと思うその気持ちを真剣に伝えてから、次の手を考える。
それだけでも、夜の寂しく孤独で虚しい自分に優しくしてあげられるかもしれない。
生きて何がいいことがあるか?なんて誰もわからない。
気持ちの持ちようだし、実際その辛さすら未来では活力に変わるかもしれない。
http://www.befrienders-jpn.org/index.html
http://network.lifelink.or.jp/index.html
誰もがそんな考え方ができるとは思わないが、
明日は明日の風が吹くもんだと思う。
幽霊人命救助隊 (文春文庫)/文藝春秋
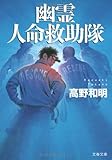
¥780
Amazon.co.jp
鬱関連の本は何冊か読んだが、記憶に新しい実近で読んだ自殺関連の本と絡めて、考えていこう。
あらすじとしては、
自殺した4人の幽霊が49日間で100人の自殺志願者を救うというものだ。
自殺する理由はあまり多くない。
・鬱
・借金
・無気力
・罪滅ぼし
・無力感
・寂しさ
・演技
・生活苦
・・・・・・など。
人の数だけ原因があるというほど多様ではないけれど、どれも当人にしてみればあきれるほど個人的な問題でしかない。
個人的だからこそ、誰にもいえない。
個人的だからそこ、伝えても理解されない。
個人的だからこそ、心を開けない。
そして、個人的だからこそ、自分で解決しなければならない。
そんな風に思っているように思えた。
この小説でもどかしいながらも良い設定だと思ったのは、幽霊側から干渉できるものはメガホンを使った声だけ。それもはっきりとその声が届くのではなく、その意味するところを数瞬考えさせるという程度。
扉をすり抜けられもしなければ、人間に触る事も出来ない。ものを動かすことも浮き上ることも出来ない。
だから、物理的に自殺しようとしている人間を助けることは出来ない。
首吊りを阻止したり、飛び降りを襟首つかんでやめさせたりは出来ない。
ただ、直接相手の心に自殺をやめるよう小さく働きかけるだけだ。
それは、誰かを思い出すことかもしれないし、
病院に行こうと思うことかもしれない。
挨拶することかもしれないし、
第三者を介入させることかも知れない。
この物語で、印象的だったのは、
自殺を止めないほうがいいのではないかという問答。
結論からすれば、それが使命だから。
なにより、『生きてこそ』といったところだろう。
生きてさえいればいい事あるさなどと楽観的な事は言えないが、あるかもしれないとは言える。
死ぬよりは良いと断言できる。
なんにでも寿命がある。
今日産まれた赤子だっていつかは死ぬ。
自然の摂理として終わりに向かって自分の意志とは関係なく
進まざるを得ない。
どうせいつか天寿を全うするのに死に急ぐ必要はあるのだろうか?
愛し合い、慈しみあった妻に先立たれる事だってあるだろう。
その際、その旦那はこの物語にもあったように喪失感から自殺を考えるかもしれない。
子も自立し、趣味も無く、どうせ老い先は短い。
ならば、と。
しかし、それでも『生きてこそ』だ。
物語では救助隊員たちが友人に様子を見に行かせ、その場を収める。
現実にはそううまくいかなくたって、何となく始めて味噌汁作りに挑戦し、湯通しのしなかった油揚のくどさに思わず苦笑してしうかもしれない。
あいつはどうやって味噌汁を作ってたんだろうななんてその日の晩にもう一度試して見るかもしれない。
いつか、妻の味噌汁に出会えるかもしれない。
この物語では失敗がない。
関わった自殺志望者すべての自殺を食い止めている。
全ての自殺は食い止められる。著者はそういいたいのかも知れない。
自殺する意志さえ確認できれば。
けれど、現実には自殺の意志を確認することは容易ではない。
だから、手持ちの肉親友人知人との人間関係をしっかりしたものに
しなければならない。
結局そこに行き着くのかなとも思う。
だからといっていまさら、積極的になれだとか、友人を作れだとか
そういうことを推奨しても仕方ない。
先日だって、自身の自殺をネットで実況中継した学生がいたらしい。
リアルタイムで観てたら嘘だと思う人、焦った人もいただろう。
そうすることでその人の中の足りない何かを埋めようとしたのだろう。
けれど、その何かは、自殺を実況中継しようとし、筋書きを決め、夢想した時、既に心の隙間は埋まっているのではないだろうか。
みんなが、親がこんな反応するなんて!如何に自分が大切かわかったでしょ??
と、それこそニヤリと笑っていたかもしれない。
本当はそこで満足してもいいはずだ。
怖くて死ねない、結局だらだらと生き続けるんだ。
そんな悪循環に陥っても生きてることだけで価値がある。生命とは存在そのもので、存在そのものに価値はある。
そんなんでいいじゃないかと思ってしまう。
が、
行動しなければ意味がないという思い込みで行動に移してしまう。
移してししまえば、当たり前だが死んでしまう。
それは意識的には本懐なのかもしれない。
が、やめるという選択肢があり、実際にやめることができるのであれば、本懐というのは一時の迷いなのではないだろうか。
自殺者は声をあげない。
だから、誰にも届かない。
が、その前に自殺を考えないものは、聞き耳を立てるべきなのかもしれない。
そんなにしょっちゅう周りの人間が自殺するわけではないだろう。
けれど、まさか、はいつでも起こりうる。
そのための対処を誰もが知っておいた方がいいと思う。
調べてみると、
自殺防止センターのようなものがある。
死にたくなったら、話を聞いてもらえる。それだけでも、心は静まるだろう。
まず、深呼吸し、死のうと思うその気持ちを真剣に伝えてから、次の手を考える。
それだけでも、夜の寂しく孤独で虚しい自分に優しくしてあげられるかもしれない。
生きて何がいいことがあるか?なんて誰もわからない。
気持ちの持ちようだし、実際その辛さすら未来では活力に変わるかもしれない。
http://www.befrienders-jpn.org/index.html
http://network.lifelink.or.jp/index.html
誰もがそんな考え方ができるとは思わないが、
明日は明日の風が吹くもんだと思う。
幽霊人命救助隊 (文春文庫)/文藝春秋
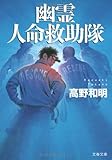
¥780
Amazon.co.jp