あとがきに書いてあったんですが、
元々この作品の題名は「走れ平太」だったそうです。
読み終えたあとでは、
盛り上がりに盛り上がるクライマックスの余韻を強く引いてしまい、
なんだかしっくりきませんでした。
読み終えて、二日がたった今、これを書き始めるや否や、
良いな、その題名もと思うようになりました。
その心境の変化はのめり込んでいた小説の世界の熱が冷めてきたからかもしれません。
けれど、それだけでもやはり、元々のタイトルは芳しく感じない。
やはり、主人公が良かったのだとしみじみ思います。
若さと元気が取り柄みたいな主人公は読んでいる最中それほど感情移入できたわけでも無く、むしろ、談合課に配属させるよう辞令を下してきた上司の冴え冴えとした立ち振る舞いに痺れてました。
けれど、ふと振り返ると平太の姿がやたらとくっきりと思い浮かびます。
それにしても、
談合とは凄まじい。
この本ではそれほど深くは掘り下げられてはいませんが、ここに書かれている事だけでも、ゾッとしてしまう反面、まぁ、、必要悪なのかな?とも思ってしまいます。
この仕事を取らないと、ノルマが達成できないではなくて、会社が潰れて、下請けが路頭に迷う。
その全責任を負って、公共入札に挑む。
と書くとなんだか余り面白そうに思えませんが、
本の厚さが気にならない程面白い。
ハゲタカが硬質な物語だとしたら、
これはソフトに描いた作品といえるのではないでしょうか。
確かにシビアな業界の話ではあるのですが、
描かれている人間からほとばしる殺気のようなものは
感じませんでした。
だからこそ読みやすいし、だからこそ平太なのかもしれません。
鉄の骨と言うと
私は鉄骨造を思い浮かべてしまい、
さらには冒頭で、描かれた生コン打ちの場面では
少しだけ、?マークが浮かびました。
まぁ、あまり現場は知らないので、
そういう事もあるのだろうな、と。
それにしても、
建築の業界と言うのは
細分化していくとどのくらいの業種があるのでしょうか?
大きく分ければ
設計事務所、施工会社、ゼネコンといった感じで、
細かく分けていくと、
下請け業者が多岐にわたるし、
その上、大きく分けた3者からもさらに枝分かれしていきます。
今も大きなクレーンが空へ腕を伸ばして、
また新しい高い建物が建って行きます。
その中で、空間として新鮮なものはどれだけあるかはわかりませんが、
指折り数えてみて、少ないと思うのはきっと
そういう空間が必要とされていないだけなのかもしれません。
高層マンションから見下ろす東京の夜景は恐らく
大きな感動をもたらしてくれるでしょう。
けれど、その感動を味わえるのはほんの一握りでしかありません。
公共の建築もお金をかけ過ぎれば文句を言われるし、
斬新なものを提案したところで、
想像できないものを受け入れてくれる人はそう多くありません。
だからと言って、そんな事じゃ建築業界は駄目だというのではなく、
今までのものと共存し
これから先全く違う価値観で触れる事の出来る建築と言うものを
提案出来たらいいそう切に願います。
そんな事を考えていたら手もとには
ずーーーーーーっと気になっていたあの本が。
ちょっと読むのに時間がかかりそうですが、
なんとか読み切って感想をつづってみます。
では、次回は
バックミンスターフラー『宇宙船地球号 操縦マニュアル』です。
鉄の骨 (講談社文庫)/講談社

¥880
Amazon.co.jp
宇宙船地球号操縦マニュアル (ちくま学芸文庫)/筑摩書房
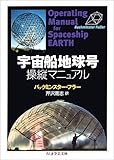
¥945
Amazon.co.jp
元々この作品の題名は「走れ平太」だったそうです。
読み終えたあとでは、
盛り上がりに盛り上がるクライマックスの余韻を強く引いてしまい、
なんだかしっくりきませんでした。
読み終えて、二日がたった今、これを書き始めるや否や、
良いな、その題名もと思うようになりました。
その心境の変化はのめり込んでいた小説の世界の熱が冷めてきたからかもしれません。
けれど、それだけでもやはり、元々のタイトルは芳しく感じない。
やはり、主人公が良かったのだとしみじみ思います。
若さと元気が取り柄みたいな主人公は読んでいる最中それほど感情移入できたわけでも無く、むしろ、談合課に配属させるよう辞令を下してきた上司の冴え冴えとした立ち振る舞いに痺れてました。
けれど、ふと振り返ると平太の姿がやたらとくっきりと思い浮かびます。
それにしても、
談合とは凄まじい。
この本ではそれほど深くは掘り下げられてはいませんが、ここに書かれている事だけでも、ゾッとしてしまう反面、まぁ、、必要悪なのかな?とも思ってしまいます。
この仕事を取らないと、ノルマが達成できないではなくて、会社が潰れて、下請けが路頭に迷う。
その全責任を負って、公共入札に挑む。
と書くとなんだか余り面白そうに思えませんが、
本の厚さが気にならない程面白い。
ハゲタカが硬質な物語だとしたら、
これはソフトに描いた作品といえるのではないでしょうか。
確かにシビアな業界の話ではあるのですが、
描かれている人間からほとばしる殺気のようなものは
感じませんでした。
だからこそ読みやすいし、だからこそ平太なのかもしれません。
鉄の骨と言うと
私は鉄骨造を思い浮かべてしまい、
さらには冒頭で、描かれた生コン打ちの場面では
少しだけ、?マークが浮かびました。
まぁ、あまり現場は知らないので、
そういう事もあるのだろうな、と。
それにしても、
建築の業界と言うのは
細分化していくとどのくらいの業種があるのでしょうか?
大きく分ければ
設計事務所、施工会社、ゼネコンといった感じで、
細かく分けていくと、
下請け業者が多岐にわたるし、
その上、大きく分けた3者からもさらに枝分かれしていきます。
今も大きなクレーンが空へ腕を伸ばして、
また新しい高い建物が建って行きます。
その中で、空間として新鮮なものはどれだけあるかはわかりませんが、
指折り数えてみて、少ないと思うのはきっと
そういう空間が必要とされていないだけなのかもしれません。
高層マンションから見下ろす東京の夜景は恐らく
大きな感動をもたらしてくれるでしょう。
けれど、その感動を味わえるのはほんの一握りでしかありません。
公共の建築もお金をかけ過ぎれば文句を言われるし、
斬新なものを提案したところで、
想像できないものを受け入れてくれる人はそう多くありません。
だからと言って、そんな事じゃ建築業界は駄目だというのではなく、
今までのものと共存し
これから先全く違う価値観で触れる事の出来る建築と言うものを
提案出来たらいいそう切に願います。
そんな事を考えていたら手もとには
ずーーーーーーっと気になっていたあの本が。
ちょっと読むのに時間がかかりそうですが、
なんとか読み切って感想をつづってみます。
では、次回は
バックミンスターフラー『宇宙船地球号 操縦マニュアル』です。
鉄の骨 (講談社文庫)/講談社

¥880
Amazon.co.jp
宇宙船地球号操縦マニュアル (ちくま学芸文庫)/筑摩書房
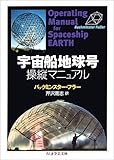
¥945
Amazon.co.jp