
人は知らないことがあると何をするか?
…検索する。
インターネットが完全に情報の主流になり、知りたい事はすぐに調べられる。
調べた結果についての信憑性については何とも言えない。
嘘ばかりとは思えないし、本当の事だけとも限らない。
そこを見極める方法はさらに検索していくしかない。
けれど、行き詰まる。
それは資料がないだけかもしれないし、ネット上にないだけかもしれない。さらに言えば、その検索ワード自体が虚構である可能性もある。
それはネットだけに言える事ではないけれど、その傾向が顕著である事は間違いないだろう。
主人公は自問する。勇気はあるか?と。
検索から監視された世界の外側をのぞく事は隠されているが故にリスクがある。そのリスクは想像もつかない。
真っ暗闇の中で歩き出す勇気はあるのか?と。
そして、踏み込んだ先にある事実と認められるものを手に入れる。
しかし…。
と物語は進む。
前作「魔王」を読んでいなくても、充分楽しめる作品だけど、読んでいればもう少し楽しめるといった程度。
たまたまかもしれないが、オーファーザーに続いてこの作品でも女性の影が色濃い。
主人公を食うほどに個性的だ。
その個性の出し方に最も伊坂幸太郎らしさを感じたのは私だけではないはずだ。
ふと、思い出した。
昔、人は言語でコミュニケーションを取れていると勘違いしていると思いついた時期があった。
私がAと言ったはずの言葉はBと介錯され、相手からのBは私にはAと聞こえる。
つまり、永遠に理解しあえないまま、会話はなりたち、違和感を覚える事もない。そこからはみ出そうとすることは私は私である事をやめなければならない。
事実とか現実と言われるものは、安易に使えるほどに自由度の高い単語ではないはずなのに、吐き捨てるくらい簡単に使われる。
本当にそれが事実なのか、現実なのか、そこから先に行こうとする人は稀だ。
今、こうして、書いている文章ももしかしたらノーベル賞ものの名文と思う人がいるかもしれない。
けれど、ほかの誰かには神経を逆なでする誹謗中傷かもしれない。
だから、こうして、文章を放る事,言葉として外側に出す事には覚悟がいる。
外側に出した時点から言葉は無形化する。その不安定な状態、誤解されうる意味を時には端的に、時には外堀を埋めるように焦点を絞っていかなければならない。
伝わらない、分からないと相手に言わせる事はコミュニケーションに於いて怠惰と言わざるを得ない。
つまり、それが慣習にしろ、誤解にしろ、今が成り立っていると言うのは殆ど奇跡だと言って良いのではないだろうか?
大きく、派手な物事はわかりやすく単純だ。
けれど、自己の内側が裏返るくらい内部から外へと向かう力は繊細で頼りない。
そして、その繊細さを繊細さたらしめているのは外部からの情報によるところが大きい。
今はまだ、選択する自由はある。
あるのだと思う。
情報を見極めるにはより多くの情報を取り込まなければならない。しかし、取り込んでいる間に横道に逸れるかもしれない。
横道にそれれば、信じてきた事が瓦解する出来事に出会うかもしれないし、出会わないかもしれない。
だからといって、情報を遮断することは容易ではない。
だから、調べる際には勇気がいる。
選択するには勇気がいる。
言葉にするにも勇気がいる。
…はずだ。
その為には信じるしかない。
何を?
自分を。
伴侶を。
そして、この物語にはヒントはないにしろ、最小の集合である家族を信じる事が一貫して描かれている。
不安定な世の中になった際、頼りになるのは国でも、政治家でも、会社でもない。
家族だ。
だから、解説とは解釈が変わるが私にとっての物語はやはり「魔王」で描かれた無防備な家族の繋がりであるのではないかと思う。
モダンタイムス(上) (講談社文庫)/伊坂 幸太郎

¥590
Amazon.co.jp
モダンタイムス(下) (講談社文庫)/伊坂 幸太郎
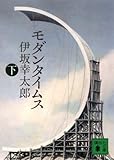
¥690
Amazon.co.jp