冒頭からこんなに泣かされたのは初めてだ。
自分でもここで泣くのか‼と驚きを隠せない。
なにせ、その日提供するメニューを眺めていただけで、泣けてきてしまうのだから。
物語は「アリババにネコババされた」所から始まり、声を失って…。
実家に戻って、食堂を開く。
手伝ってくれた熊さんに提供する料理人として始めての料理。
そのレシピに踊る料理名に主人公の愛を感じる。
愛と言ったが、ニュアンスを詰めれば「愛おしさ」がにじみ出ている、と言った方が良さそうだ。
出てくる料理が美味しそうな事は間違いないけれど、それよりも、食材の瑞々しさが食べる人の生命力に変わっていく様は予想を裏切らないありきたりな展開だったとしても、感動してしまう。
当然、今の時期だからというのもあるだろう。
そして、クライマックスでは豚の解体が描写される。
主人公は淡々と妹と言わしめたその豚を解体する。
今までの流れがメルヘンを内包しているとしたら、ここで描写されるのは厳然たる現実。
殺して食らう。
そこには幾ばくの感情の移入を許さない。許してしまえば言い訳をして、正当化して、上手にまとまってしまう。
けれど、命を食べるとはそもそも人間の感覚でいう「残酷」なだけ。
どんな言葉を並べても、菜食主義だろうが他の生命を自分の血肉としている事に変わりない。
だから、主人公の一行の感情の揺らぎで、充分伝わるものがあったのだろう。
包丁で人参を切る、採りたての赤カブを齧る、その動作にいちいち「愛おしさ」を感じてしまう。丁寧とも違うし感謝とも違う。大きな生命の流れを俯瞰する様な感覚だろうか。
喫茶店でこっそり目を腫らし、電車では鼻水を花粉のせいにした。
その涙の理由は生きているのではなく生かされている事実によるのではないかと思っている。
感動する物語かどうかはその人次第だろう。だから、これは人に勧めにくい物語。決して難解では無いし、深い物語でもない。でも、明らかに読み手を選ぶ物語だろう。
Amazonのレビューを見ると、酷評されたりもしているのがその証拠と言って良いのではないだろうか。けれど、大半は好みと本の良さを履き違えている様な気がする。
細部にとらわれすぎるとせっかくの物語がガラクタ以下になってしまう。
多分、この世には良書以外は無いと思う。適当な状態、その時その場所その状況と本は指示してくれるわけでは無い。だから、本に飛び込んでいかなきゃいけない。
読書の喜びはその世界にどっぷり浸れた時ではないだろうか。力のある作家ならその腕力で世界を一変させる。力の無い作家だとしても、こちらからそちらを推し量る事で世界を変える。
作家への不満はある意味自分の不満だと思って間違いない。
生理的にとか難しいとかリアリティが無いというのはそこが自分の限界なのだ。
さて、
主人公は物語のラストで、鳩を食べる。
ここでも、主人公は静かに命を食べる。人間らしく、女性らしく。けれど、ほとばしり始めた生命力は原初のそれを彷彿とさせる。
iPhoneからの投稿食堂かたつむり (ポプラ文庫)/小川 糸
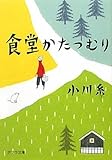
¥588
Amazon.co.jp
自分でもここで泣くのか‼と驚きを隠せない。
なにせ、その日提供するメニューを眺めていただけで、泣けてきてしまうのだから。
物語は「アリババにネコババされた」所から始まり、声を失って…。
実家に戻って、食堂を開く。
手伝ってくれた熊さんに提供する料理人として始めての料理。
そのレシピに踊る料理名に主人公の愛を感じる。
愛と言ったが、ニュアンスを詰めれば「愛おしさ」がにじみ出ている、と言った方が良さそうだ。
出てくる料理が美味しそうな事は間違いないけれど、それよりも、食材の瑞々しさが食べる人の生命力に変わっていく様は予想を裏切らないありきたりな展開だったとしても、感動してしまう。
当然、今の時期だからというのもあるだろう。
そして、クライマックスでは豚の解体が描写される。
主人公は淡々と妹と言わしめたその豚を解体する。
今までの流れがメルヘンを内包しているとしたら、ここで描写されるのは厳然たる現実。
殺して食らう。
そこには幾ばくの感情の移入を許さない。許してしまえば言い訳をして、正当化して、上手にまとまってしまう。
けれど、命を食べるとはそもそも人間の感覚でいう「残酷」なだけ。
どんな言葉を並べても、菜食主義だろうが他の生命を自分の血肉としている事に変わりない。
だから、主人公の一行の感情の揺らぎで、充分伝わるものがあったのだろう。
包丁で人参を切る、採りたての赤カブを齧る、その動作にいちいち「愛おしさ」を感じてしまう。丁寧とも違うし感謝とも違う。大きな生命の流れを俯瞰する様な感覚だろうか。
喫茶店でこっそり目を腫らし、電車では鼻水を花粉のせいにした。
その涙の理由は生きているのではなく生かされている事実によるのではないかと思っている。
感動する物語かどうかはその人次第だろう。だから、これは人に勧めにくい物語。決して難解では無いし、深い物語でもない。でも、明らかに読み手を選ぶ物語だろう。
Amazonのレビューを見ると、酷評されたりもしているのがその証拠と言って良いのではないだろうか。けれど、大半は好みと本の良さを履き違えている様な気がする。
細部にとらわれすぎるとせっかくの物語がガラクタ以下になってしまう。
多分、この世には良書以外は無いと思う。適当な状態、その時その場所その状況と本は指示してくれるわけでは無い。だから、本に飛び込んでいかなきゃいけない。
読書の喜びはその世界にどっぷり浸れた時ではないだろうか。力のある作家ならその腕力で世界を一変させる。力の無い作家だとしても、こちらからそちらを推し量る事で世界を変える。
作家への不満はある意味自分の不満だと思って間違いない。
生理的にとか難しいとかリアリティが無いというのはそこが自分の限界なのだ。
さて、
主人公は物語のラストで、鳩を食べる。
ここでも、主人公は静かに命を食べる。人間らしく、女性らしく。けれど、ほとばしり始めた生命力は原初のそれを彷彿とさせる。
iPhoneからの投稿食堂かたつむり (ポプラ文庫)/小川 糸
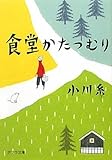
¥588
Amazon.co.jp