今日、読み終えました。
化学関連の本ですが、化学と関係ない人にもぜひ読んでほしい本です。
(そんな思いから、本記事のテーマは「科学」ではなく、「読書」です。)
大気を変える錬金術――ハーバー、ボッシュと化学の世紀/トーマス・ヘイガー
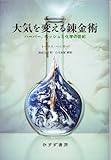
¥3,570
Amazon.co.jp
空気中の窒素からアンモニアを合成する技術を開発し、ともにノーベル賞を受賞したドイツの二人の科学者ハーバーとボッシュ。その技術開発の苦労、戦争に翻弄された二人の人生、そしてこの技術が人類に与えた意味、など、広い視野から記述されています。
ちょっと値段が高いので、図書館にでもあればいいですね。
空気中にいくらでもある窒素。窒素はまた、植物の生育に必要な元素でもある。
しかし、空気中の窒素を肥料として役立つ形に変換する(窒素固定)ことができるのは、マメ科の植物の根にいる根粒菌だけ。
19世紀から20世紀初頭の欧州で食料を生産するのに必須の肥料であった固定窒素は、遠く南米から運ばれるグアノ(鳥糞石)やチリ硝石だった。
空気中の窒素を人間の力でアンモニアにできれば、当時の予想通り南米の窒素肥料が枯渇しても、食料の生産が継続でき、人類を飢えから守ることができる。
これを実現したのが、ユダヤ人の科学者フリッツ・ハーバーと、当時は染料会社だったBASFの技術者カール・ボッシュであった。(ケミカルエンジニアとして私には、当時誰も実現したことのない高温・高圧のプロセスを開発する話はたいへんに興味深いものでしたが、この本全体の中でさほどのウェイトは占めていません。)
こうして苦労の末、アンモニアが世界で初めて工業的に製造できるようになった頃、戦争が二人の人生を翻弄する。
ハーバーは、キリスト教に改宗。既に一流の科学者として尊敬されていた第一次世界大戦時には、祖国ドイツに忠誠を尽くそうと、ドイツ軍のために毒ガス兵器を開発。
その陰で、自身ももともと優秀な科学者であった妻クララは、孤独感からうつ病を患い、ついに自殺。
その後、ユダヤ人ハーバーはナチスの台頭とともに居場所を失い、英国に脱出するも、失意のうちに1934年にスイスで死亡した。
一方のボッシュは、BASFの社長に登りつめた。アンモニアは肥料になる一方で、爆薬の原料にもなるため、第一次世界大戦ではおおいに増産。
戦後は、苦労して石炭から合成ガソリンを製造する技術を開発したが、結局これも第二次世界大戦のヒトラーの軍隊の燃料として使用された。
自分の開発した技術が結果的にヒトラーの戦争を実現可能にしてしまったことに悩み、さらにヒトラーに従わない危険人物として会社の重要役職からもはずされたボッシュはうつ状態に陥り、やはり失意のうちに1940年に亡くなった。
現在、世界の何百という工場で、ハーバー・ボッシュ法により年間1億トン以上のアンモニアが製造されている。これらの目につかない巨大産業がなければ、20億人から30億人が飢え死にすると言われているそうだ。
私たちが、飢餓や栄養不良ではなく肥満に悩んでいるのは、実は、優秀なドイツ人科学者のハーバーとボッシュのおかげです。
さて、
この本に出てくる、アンモニアの第二工場として1927年に稼働開始したロイナ(Leuna)工場。
実は、昨年、仕事で訪問した工場でした!
こんな歴史があったとは、知らなかったーーー。
一通り自動車で見学させてもらったけど、内陸にとてつもない巨大石油コンビナートがあるもんだなぁ、と漠然と思ってただけでした。
この本を読んでからだったら、もっともっと感慨深かったはず。
残念!