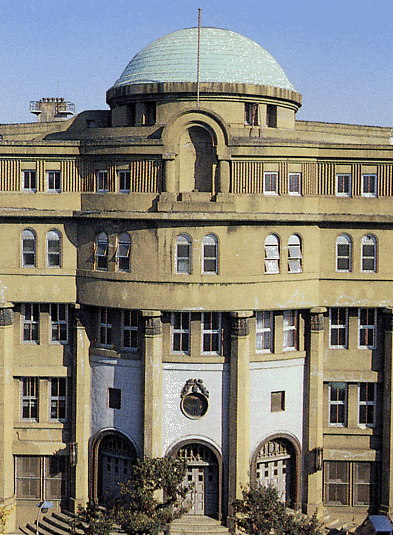第1章 神田神保町と秋葉原
1986年(昭和61年)2月11日〜13日
部屋は10人くらいのタコ部屋で2段ベッドが5つばかり置いてあったか。勉強机もないし、消灯時間も決まっている。夜中にいびきをかく者もいる。そんな環境だった。ここを拠点として各大学の試験に行くのだった。みな各々の受験のために地方から出てきていた。
僕の滞在予定は、2月11日から21日までの10日間だ。
風呂、トイレ、食堂は共同。食事は冷凍品の焼き直し。それでも日頃あまり口にしない鶏肉のソテーだのトンカツだの、あまりうまくはなかったが量はあった。
混んでいる食堂で順番を待つ間、コンクリート打ちっぱなしの渡り廊下の踏み板簀子の上で、一緒に下見に行くことになった彼が
「東大合格者のうち、毎年なんにんか抜けるやろ、あれは毎年うけているんだ」
などと話してきた。
「どうしてそんなことをするの?」
「東大を受けるのが趣味の人がいるんだ」
と彼は説明する。
「なんねんもなんねんも受け続けて、今年は数学が難しかったとか、全問できたとか言っているんだ」
自分には、東大の「と」の字も縁がないのに、毎年そこを受け続けて試験の難易を報告している人がいるとは、世の中広いものだと思った。
「そういう人が毎年なんにんかいるから、大学は数人多めに合格者を出しているけどね」
ずいぶん暇なことをする人もいるもんだ、とその時は思った。けれど確かに、5年くらいかけて丹念に勉強すれば東大くらい御せるようになり、受験が学問の基礎を通り越してゲーム感覚になる感覚は解らないでもない。受験中毒になる。受験がクセになる。何かをひたすら繰り返す無限じごくみたいになって苦しみが喜びとなる。赤本を見ながら叡智の賢者になれる。
そんな外道の境地もないことはない。
「東大を受けるの?」
と僕は聞いた。
「いや、受けない」
とだけ彼は答えた。
「駿台予備校が駿河台大学とかいう大学を作くろうとしている」
と彼は言った。ーーその時点では駿台予備校なる予備校があることさえ知らなかった。
「そこから司法試験の合格者を多数出す計画なんだけど」
まったく知らなかった受験業界事情を教えてくれた。
「日本一の大学にするつもりらしいが、大学の偏差値は短期間ではひっくり返らないだろうな」
「いくら駿台予備校が東大に合格者を多く出すからといって、新設の大学が格をあげるのはそう簡単にはいかないだろう」
ふむふむ、と僕は聞いた。彼の予言は見事に当たった。それから10年経っても20年経っても駿河台大学は日本一にならず、40年経った現在では自前の予備校の出す偏差値では枠外に押し出されそうな勢いだ。
ご飯を盛ったり、鯖の焼いた切り身を皿に入れたり、味噌汁をついだりしてテーブルにつくと彼はまた、初耳のこんなことも言った。
「私大の入試の採点は、パートのおばちゃんがやっているんだよね」
え?! と思ったと同時に、ゾッとした。
「短大出の主婦がアルバイトでやっている」
ならば、答『案』なんか、ないではないか。短大出の女性が採点しやすいように、模範解答を予想してそれに近い答えを書いてやらなければならない。『答案』を介して学者と対話するなど、幻想だった。
国立のようにひと学科10人とか25人とか工学部でもせいぜい40人の50人のの採点とちがい、受験者何千人、何万人にもなる私立大学の採点はパッと見て丸かバツか、部分点などないのに違いない。採点ミスやら計算まちがいやらなんでもありなのだろう。決して平等でも公平でもない世界なのだ。僕はそんなあやふやであいまいでイイ加減な社会の縮図みたいな受験に心血を注いできたんだなと思った。
次の日(12日)だったか一緒に下見に行った。
彼が駿台予備校に通っていたかどうかは知らない。名前はお互い言わなかったので彼のことを『駿台の彼』と呼ぶことにしよう。
この施設は農大の近くだったので、志望が似た受験生が多く含まれていた。駿台の彼も同じ私立大学の同じ学部を受験するのだが、非常にスマートで優秀だったので、おそらく滑り止めで、国立の農学部が第1志望だったのではないか。彼には方言がなかった。九州でも関西でもない。ここに泊まって下見に行くくらいだから、関東でもないのだろう。北海道か? 詳しくは知らない。ただお互い、農大と明大を受けるという共通点があっただけだ。
世田谷にある東京農大の木造校舎は古く、教室の窓枠には年季が入っており伝統を感じさせた。とても好い大学だと思った。
明大は、農学部のある生田キャンパスには行かなかった。試験は神田の駿河台校舎で実施されるからだ。
周囲に立て看板が並んでいて、気合の入った大学だと思った。
入り口の所まで行って確認し終わると、
「ついでに、モスバーガー1号店に行かないか?」
と誘われた。
この当時、九州にはモスバーガーは出店しておらず珍しかった。内面を樹脂コートされた包み紙にはみ出すほどの玉ねぎとトマトのみじん切りのたっぷりのソースとジューシーなパテはとても美味しかった。また食べたいと思った。
だんだん都内の交通に慣れてきた。明治大学は神田駿河台にあり、神田神保町の古本屋街があったので楽しみだった。初めていく東京で、ぜひともここを探索したいと思った。僕はこの時を皮切りに、大学時代にも社会人になって出張した時も、必ずここに立ち寄り古本を大量に買い込んだ。
板橋のモスバーガーに行った帰りに別れ、僕だけ神田に舞い戻り古本屋街をめぐった。次の日(13日)だったか僕は確か、秋葉原にも行ったと思う。秋葉原は神田と目と鼻の先にあった。古本屋街には非常に魅かれるものがあった。ずらっと並んだ本を見ると、僕は胸がときめいた。
京大周辺にも古本屋はあるが、神保町にはかなわない。熊本にも大学周辺の『デラシネ書房』と上通り何軒かあった。毎日の書店散歩が日課だったが、ちょっと不服だった。そのご、東京に出張がある度に休みを取って街をめぐった。たくさんあるけれど目当ての書物や資料はあまりなかった。唯一、裏路地にある専門店(ヤマノヰ本店)をみつけて、そこで何十万円分か購入した。


秋葉原には日大の下見(16日)をしたあとにもう一度寄ったのではなかったか。古い日本の街並みが残っていたし、コンピューターやオーディオに興味があったからだ。
秋葉原駅
ラジオパーツ 昌平坂
SONY ウオークマン Apple マッキントッシュ
ナカミチ ドラゴン JBLスピーカー4344
初めての東京はすべてが真新しくて、などと、決してお上りさん気分で浮ついていたわけではなかった。けれども、勉強時間はトータルでどれだけあったろう? あまりおぼえていない。東京での10日間で何時間くらいやっただろうか? 勉強は食堂のテーブルでやった。時間は、・・・。一応、食堂なのであまり長時間はできなかった。部屋のベッドではノートを見返すくらいしかできなくて。

それでも受験に来る前に詰め込むだけ詰め込んでいたから、そうそう学力は落ちていなかったはずだ。英語の毎日の日課だった逐語訳がやれなかったのは痛かったとしても、生物に至っては次の模擬試験、すなわちこの年の5月半ばまで3ヶ月ほどノー勉でも95点を2回取ったほどだったから。特に14日と15日あった農大の試験ではブランクは3日、ほぼベストの状態で臨んだと言える。
ところで東京での10日間に多少の寄り道はした。早い、うまい、安い、とテレビで宣伝していたのを観ていただけで九州にはまだ店舗がなく一度食べてみたいと思っていたら見つけた。たしか僕はこれを都合3回は食べた。
御茶ノ水あたりの通りだったと思う。(JR御茶ノ水駅前の明大通り界隈ではなかったか)よみうりランドでは朝と夜に食事がついていたが昼はどうしてもどこかで取ることになり、下見に出かけたついでに食べることになった。名前だけ知っていてまだ九州にはなかった吉野家。
どこもかしこも人であふれていたが、青年がたくさんいる通りで、まさに東京の学生街といった感じだった。近辺には、明治大学だけでなく日大や専修大学、順天堂大、東京医科歯科大などがひしめいている。(中央大学はこの時より10年前に多摩に移転したらしい)ガロの『学生街の喫茶店』はこのあたりのことを歌っているようだ。


歩道から階段が2段あってガラスの扉の向こうは3段目になっているちょっと小高い店内には前面のカウンター席しかなかった。おずおずと着席してさりげなく周囲をうかがう。
ーーどうやって頼むのかなあ?
と思いながら先人たちを観察した。
なみ、たま!
と声を出す。なみ、たま! また聴こえる。なるほど、そうやって頼むのか、どうやら並盛りに生卵を追加しているらしい。見ていると、皆カウンターに置いてある紅ショウガを箸でどんぶりに移動している。みな紅ショウガをこのくらいこづんでから箸で崩しにかかるのだ。
よく観ていると、まず若者は箸で牛丼の中央にくぼみを作り7味唐辛子を振りかける。しっかりかき混ぜた生卵を流し込むとさらに醤油ダレをかけ、肉ごとぐちゃぐちゃに混ぜ合わせる。その上に鬼のように紅ショウガを積み上げるのだ。まるでいちごのカキ氷だ。
食べているのも学生なら、店員も学生なのだろう。最小の値段で腹一杯食べるための作法なのだ。
おそるおそる僕も並玉を注文した。やってきた丼を見つめながら同じようにしようかと思ったが、さすがにいきなりのトーテンポールは憚られた。
控えめに生姜を乗せて食べた。うまかった。並盛り350円に卵で430円だかそこらになったと思う。ど田舎出身でど貧乏人の子倅の僕にはちょっぴり高いように感じられた。
2回目3回目と足を運ぶ内に大胆になり、紅ショウガの量が増えていった。3回目は大盛りを頼んでみたが皆が頑強に並盛りを注文しているわけがわかった。並盛りに大盛りの紅ショウガ、これが学生の胃袋を満たす最適なレシピなのだ。
第2章 いよいよ、本番
東京農業大学 昭和61年 2月14日(金曜日)農学科 15日(土曜日)農芸化学科
駿台の彼と二人で行った。
木造平屋の校舎は古く、年季が入っていた。長い教室は外との段差がなかったようにおぼえている。そこに小学校にあるような古くてちいさな机と椅子が並べてあって、明治や大正の奥ゆかしさを醸し出している。
開始までの空き時間に校庭に立っていた。受験生がたくさんいて、ところどころに受験生のかたまりや輪ができていた。駿台の彼と二人で庭いると一人の受験生と思われる男子が歩み寄り、話しかけてきた。短ラン、ボンタンに赤いシャツ。なかなかキマった格好だ。
群馬だったか茨城だったか、その辺りの農業高校の生徒だと名乗った。そして、
「俺もう、合格は決まっているんだよね」
「あとはいくら寄付金を払うかだけなんだ」
ちょっと照れくさそうに言った。僕の文脈にいきなり入り込んできた違和感。すでに合格の決まったやつが試験を受ける? どういうことだ、訳が解らない。戸惑っていると尚も彼は言う。
「ここに来ているやつの多くは、推薦で決まっている」
吸っていたタバコの殻を投げ捨てながら。だから「余裕」なのだと。
「試験で何点取るかで、寄付金の額が決まるんだよね」

この時、僕は彼の言うことの意味がまったく解らなかった。駿台の彼も、何も言わなかった。
しかしそれにしても、こんなことが偶然に起きてくるものなのか? すでに推薦で合格が決まった者が自分から寄ってきて、自分がこれから何をするのか打ち明ける。短ラン赤シャツが寄ってきて言ったのは偶然か、それとも宇宙の作用か。
試験前に彼の言ったことが僕にどんな心理的作用を及ぼしたのか!
ほとんど影響はなかったろうと思う。けれども、ずっと心に引っかかっていた。40年ほど。
試験が始まる。
初めて見る問題形式だ。3教科とも20問くらいあり、多くが選択問題で四角い升に記号か番号を書き入れる。1問5点の100点満点か、などと思いながら試験に取り組んだ。
昼休みを挟んであったように思う。駿台の彼も国語で受験していた。生物系の人は、数学より語学の得意な人がいる傾向にあるのと、
「国語で平均点くらいはおさえておきたい」
という考えからだ。
国語の試験が終わったあと彼が
「しょげんはどう書いた?」
と聞いてきた。
「諸言」
と答えると、
「糸へんの方だよ」
「たくさんという意味じゃなくて、始まりの方だから」
と言った。試験中に迷った僕は『諸島』を思い出し書いたのだったが、彼の言うのが正しい。1問は確実に落とした。漢字一つ間違えたくらいどうってことない、と思った。が、他の問題も簡単だった割には手応えがなく、英語国語生物の各問のどれも自信をもって正解とは思えない、不思議な感じがした。まだ、あとひと学科ある。木漏れ日の構内を歩きながら、伝統ある静かな佇まいに惹かれながらも、どっちにしてもこの大学には来る気がない。受かっても入学しない。そう思っていた。決意に近かった。
ーーおそらく菅原道真は僕の本心を知っていたのにちがいない。どんなに表面では「絶対合格」などと気張って見せていても。
無理やりに受けさせられている屈辱感があった。怒り、悲しみ、恨み、そんな感情が奥底で渦巻いていたのを抑えつけている自分があった。
しかしそれにしても、駿台の彼はとてもインテリジェントでスマートな受験生だったのではないだろうか。どこが第1志望だとは明かしてくれなかったが、ひとつひとつ丁寧に言葉の意味を理解している、小学生の時から真摯に勉強に向きあってきたのにちがいない。どこか旧帝大の農学部や生物学科の受験予定なのではないか。きっと明治や農大は併願というか万一の時の備えに受けていたのだろう。
ここまでが彼と行動を共にした受験だった。日大は受けないとのことだった。彼はその日のうちに宿を引き払った。おそらく、明治受験には宿泊地を替えるのだろう。なるべくなら、こんなタコ部屋でなく、個室のホテルに泊まって最後の勉強をするのが賢明だから。
日本大学 農獣医学部 農芸化学科 2月17日(月曜日)
その日は晴れ渡っていた。日大には一人で行った。(受験場が、現在の湘南藤沢だったかどうかは憶えていないが。できたばかりの真新しいビルだった。『三軒茶屋』という地名が記憶に残っているが定かでない)
学科試験が終わった。基本問題程度。これに勉強要った? 肩透かしを食らうほど簡単な問題だった。しかもマークシート。合格ラインは3教科平均で80点にはなるだろう。僕は少なくとも270点/300点満点は取れているだろうと思った。あとで確認したら240点/300点満点が合格最低点となっていた。
さて、帰ろうかと席を立った時、館内放送が入った。
なんと、ガッデム先生の指導教授された面接試験があるのだった。
聞いてないよ!

といったところだ。赤本は買わなかったし、旺文社の付録か何かに『農獣医学部は面接』と小さく書いてあったが、獣医学部だけだと思っていたのだった。ここは受かっても絶対に来ないし、第一、面接試験など試験でない、と僕は勝手に思っていたのだった。しかし実施されるのなら、ついでだから受けてから帰るか、と思った。
いくつもある入り口の前にずらっと並んだ受験生。

会場に何列も用意された面接、何十人も後ろに並ぶ、その列がいくつもあった。
入り口の中に入った。そこにも列がある。十間くらいの横長い部屋に長机が5つばかり置いてあり、そこに面接官がおのおの2人ずつ腰掛けている。その前にも受験生の列があり自分の順番を待つ。学生服の生徒、私服の生徒、さまざまだった。
待っている間、周囲を見ていると、右や左でハキハキ受け答えする受験者たち、礼や腰掛け方に気を配る姿。

ここに受かるためにそんなにヘコヘコしなくちゃならないもんかね、とずいぶん落ちた視力で眺めていた。
なんだか、ああいのはしかつめらしくて嫌だなあと思ったし、この大学をなめていたので、生徒たちの態度が嘘くさく思えた。
僕の番になった。見えない目でぼぉっと試験管をながめ、特にお辞儀をするでもなく、ぞんざいな態度で着席した。
そしてガッデム先生に教えられた通りに、二人いた試験官の眉のあたりを見て受け答えした。四十代くらいの面接官だった。ちょっと浅黒い右側の面接官はとても良い人に見えた。優しさと知性のある。どことなく親近感を覚えた。

この人がもし教授なら、是非とも教えを請いたいと思う魅力がにじみ出ていた。
けれども僕はひどくぞんざいな態度で着席し、
ぶれいな振る舞いで受け答えし、傲然とした口調で物を言った。
しかも目も見ずに。
アゴをあげ窓の外でも眺めるようにして、ずいぶん横柄な素振りを続ける僕に試験官が放った核心的なこの質問にだけ、僕は真顔で反応し、初めて相手の目を直視した。
「他にどこを受けていますか?」
「明治大学の農学部農学科と東京農大の農学科と農芸化学です」
こと細かく答えた。試験官はちょっとうなづいたあとに続けてこう聞いた。
「もし、そこにも受かったら、どうしますか? この大学に来ますか」
それに対して僕はスラスラと答えた。
「そうですか」
と応じた試験官が僕のエントリーシートにどんな評価をつけたかは知らない。僕は、妙なことを聞くものだなと思いながら退席した。挨拶も、お辞儀もせずに。
これに関して、僕はまったく反省しない。むしろ、眼のある試験管に当たって本当によかったと思っている。
問 傍線部に「僕はスラスラと答えた」とありますが、受験者の僕はどんなことを答えたと推測されますか、答えなさい。なお、解答は指定の解答欄に記すこと。(15点)

ここには受かっても来ない。高い模擬試験だったなあ、と思いながらビルを後にした。さて、残るは本命の明治大学だ。
明治大学 農学部 農学科 昭和61年 2月21日(金曜日)
千代田区神田駿河台キャンパス
指定された講義室に入った。歴史を感じさせる重厚なドーム型の教室だった。きっとあの駿台の彼も来ていてどこかの教室にいることだろう。
英語は90分の150点満点、国語と生物は(数学・化学・生物・国語の中から)120分で2教科取り組むことになっていて、各100点。合計350点満点の試験だ。たしか、午前10:30から英語が90分行なわれ、昼の休憩を取って午後1:00から3:00まで120分だったと思う。試験時刻については記憶が不確かだが、終わったのは九州よりも日暮れの早い東京であったけれども、まだ明るい時刻だった。
僕は着席して試験開始を待った。この瞬間は、ガッデが的に銃を構え、引き金に指をかけのと同時だ。的は広く、しかもかなりの至近距離、弾は的の中心を撃ち抜くのは確実だ。
射的の中心と銃口までの間は2センチというところか、あとは引き金を引き、弾が正常に発射されさえすれば、それでいい。
ゴクリ・・・
ガッデム汚腹は喉を動かし、唾を呑む。
2年間の努力が報われようとしている瞬間だった。あとは弾がまっすぐに飛んで的を射抜いてくれればいい。いくらなんでも当たるだろう。いや。外しようがない。
合格確実の偏差値を5も上回っているのだ。ほとんど至近距離からの的撃ち状態だ。ど真ん中を撃ち抜くための鉄砲の銃口と的の距離は2センチ、いや1センチもない。引き金を引きさえすればど真ん中を撃ち抜くことは必至である。
試験監督者が教室に入ってきて一番前の席から冊子を配り始めた。皆に行き渡り、しばらく待った。
試験開始の合図がかけられた。みな一斉に問題に取り掛かった。僕も冊子を開き問題を確認した。
この瞬間、ガッデム先生の拳銃が火を噴いた。
薬きょうが弾け飛び、弾丸は激しく撃ち出されたのだった。
これでおまんまが食いつなげる‼︎
ガッデは自分に言い聞かせるようにそうつぶやいた。
万全だ。
撃ち出された弾丸は回転しながら銃身を進み、銃口を離れた。10ミリ、9ミリ、8ミリ、弾は的のど真ん中に向かって近づいていく。
第3章 帰路
試験が終わるちょうどその頃、こちらは九州にいるガッデ。時計を眺める。
おわったな・・・
これで俺は、有名私大合格に導いた、名教師だ。と、キメ顔の最終確認をする。

俺の名声とボーナスは確定した。ドキドキしながら合格発表を待つ1週間がガッデム先生に始まった。
午後3時台、陽は傾きなんとなく暮れかかっていたがまだ十分明るかった。ちょっとためらったけれども、一応、駿河台キャンパスで販売していた電報を頼んだ。500円だったと思う。そしてその足ですぐ僕は神保町の書店街に行った。いくらか古書店を巡ったあと、たぶん、ジュンク堂だったと思う、まだ九州にはない巨大な新刊書店、そこで地元周辺の書店には売っていなかった参考書と問題集を2冊ばかり買い込み、バス停に行った。
日が落ちていた。暗くなりかけている中を行き交うバスの行き先表示板が緑色に灯っているのが印象的だ。
僕は東京駅行きのバスに乗り込んだのだった。
その日の夜中に自宅に帰り着いた僕はそのまま机に向かって数学を始めた。玄関を入り、廊下を歩き、戸を開け、カバンを下ろすとそのままだ、そのまま机につき買ったばかりの問題集を解き始めた。
両親はすでに就寝していた。
10日ぶりに帰ってきた我が家は静かだった。
つづきはseesaaブログにて。