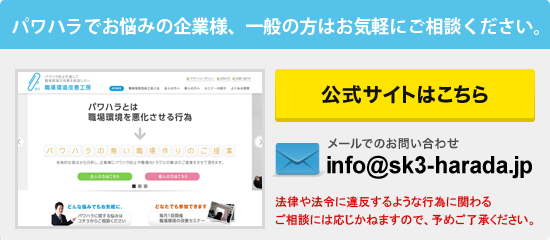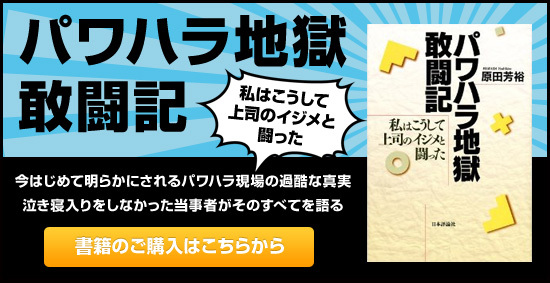愛情を表現能力が高い人がキャリアを重ねていく・・・・
https://ameblo.jp/syokuba-kankyou-kaizen-k/entry-12304097946.html
ということは、以前、このブログでお伝えしました。
ですが、ただ、これを見ても、
「安易に褒めたり認めたりしたら、仕事がゆるくなってしまう・・」
「部下が言うこと聞かなくなってしまう・・・・」
などと納得できない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

確かに、ただ褒めたり、認めたりするだけでは、効果は薄いです。
愛情表現に厳しさと現状分析の妙味が加わって、成果の出るマネジメントが出来、キャリアを重ねることができます。
実際に、部下に良い顔をして、表面だけで認めたり褒めたりしている上司が統括する部署は、業績が上がりません。部署の雰囲気が弛緩し、目標に向かって進もうという気概がなくなるからです。緩さゆえのパワー不足が生じてしまいます。
厳しさがあって、組織は前へ進みます。そして、現状分析は、無駄なロスを無くします。
現状分析なき愛情表現は、単なるおせっかいであり、部下や同僚は適切に業務をこなすヒントも材料も失うことが多いので、非効率化していきます。
また、厳しさが伴わない「認める 褒める」は、ルーズな風土を生みだします。
ですが、それ以上に恐ろしいのは、厳しさも現状分析も伴わない愛情表現は「ひとりよがり」であり、部下や同僚の支持を失うということです。
そして・・・・・
「自分はこれだけ、みんなのこと考えてるのに、どうして分かってくれないんだ!」と思い込み、挙句の果てには、無視したり、関わろうとすることを意図的に避けようとし、自分に都合よく反応してくれる人間だけを重宝してしまうということが起こる!のです。
つまり、キャリア形成に一番必要なコミュニケーション能力は、ややもすると、ハラスメントをしやすい性質に転化する可能性を高く潜めていることも覚えていただければと思います。