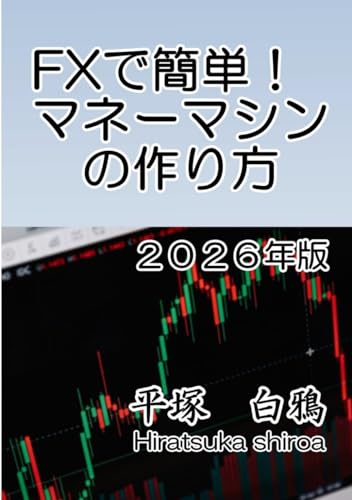アンチエイジングの話が長くなって。
しろあです。
その間にいろんな映像作品も見ていたので、遅ればせながらレビューしていこうと思います。
今回はNetflix版の『今際の国のアリス』シーズン3。
シーズン1、2で物語としては綺麗に完結しているので
続編はいらないくらいでしたが、人気だったのでしょうね。
調べてみるとオリジナルストーリーとのこと。
アリスとウサギ、その他一部のプレイヤーは現実世界に帰ってきたわけですが。
今際の国で何やらたくらむ人がいて、
その人の罠にかかりアリスとウサギは再び今際の国でゲームをすることになります。
何かしらの理由で先にウサギが今際の国に行くのですが、
それを助けるためにアリスも追ってその世界に。
今際の国で以前と同じようにデスゲームをするのですが、
アリスとウサギは平行して別ルートでゲームを進めておりなかなか出会えない。
なかなかこの構図が面白いし、主要キャラクターの立ち位置の設定もうまく、
ウサギを助けながらゲームをクリアしていくキャラは、アリスにとって敵であったり。
強敵が仲間になってともに戦うことになったり。
前作同様、主人公側のキャラたちもどこで脱落していくかはまったく読めないし、
それぞれの散り方もなかなかカッコよかったり。
細かいところは抜きにして作品自体の設定、構図、ストーリー展開は十分面白い楽しめるものでした。
ただ、残念なところはいくつかあります。
ゲームの性質上、運の要素が強いものもあるのに、主人公はするりとクリアする。
こういうのはよくないよね。
主人公がゲームをクリアするのはいいんだけど、そのクリアの理由が ”運が良かったから” というのじゃ納得いかない。
今際の国のアリスなら、頭脳戦で勝利していって欲しいところ。
また、頭脳戦で頑張ってるゲームもあるんだけど、
ゲームルールの盲点をついたり、相手の裏をかく心理戦がやや足りなかったり、
結局運要素が強かったりと、魅力的なゲームであるものの、物足りないゲーム展開もしばしば。
そして一番大切な黒幕の理由がなんかよくわからない。
理由だけじゃない、なんで黒幕には今際の国と現実世界を自由にコントロールするよう力を持っているのかもわからない。
こういうゲームは黒幕だから、主人公だから万能だとかすべてが許されるとか、ワイルドカード的な状態にしちゃうとやっぱり面白くなくなってしまう。
特にこの手の作品は、限定的な力で弱点を持つくらいじゃないと面白くない。
その限られた条件の中でいかに知恵を絞り機転を利かして戦っていくか。
それを見るから面白いんだよね。シーズン1、2にはそれがあった。
ということでちょっと残念な部分もあったけど、それを考えても十分に楽しめる作品でした。
さて。
今際の国のアリスといえばデスゲーム。
シーズン1,2で見たことのあるゲームを今回もいくつか使っています。
それだけではなく、新たなゲームも追加。
ひとつはゾンビゲーム(正式名は覚えてない)。
ゲームスタート時、多数の一般人と、少数のゾンビに分かれる。
本人以外、誰が人かゾンビかは不明。
一定時間ごとにそれぞれのプレイヤーがカードゲームでバトルをします。
そのバトルによって人のままか、ゾンビになるか、
ワクチンを使って人に戻るか?! と変化していきます。
数ターン繰り返し、ゲーム終了時点で人とゾンビのどっちが多いかで勝敗が決まるわけです。
……なんか知ってるな。
予想通り、だいたい思った通りのストーリー展開。
こ、これはどこかで似たゲームを見たことがあるからだ!
——2026年4月からアニメ化が決まった『ライアーゲーム』。
TVerでは年末12月にドラマ版を期間限定公開してました。
久々にみて、めっちゃ面白い! と興奮してたんですが、ふと思い出したんですよ。
あ、「パンデミックゲーム」だ。
ゾンビゲームと『ライアーゲーム』に登場する「パンデミックゲーム」はほぼ同じ性格のゲームでした。
シーズン3のラストゲームは未来ゲーム(やっぱり正式名は覚えてないし、調べる気もない)。
主人公たちは上から見ると縦数列、横数列で区切られた四角い部屋の中央に閉じ込められます。
主人公たちはポイントをもってゲームに臨みます。
1ターンごとに部屋を選んで移動します。
ただ扉を選択するのは考えどころで、部屋の壁には自分たちの未来の姿が映ってます。
便宜上 上、下、右、左 と部屋に壁があるとすると、それぞれの壁に自分の違う4つの未来が映るのです。
ゲームマスターは言います。「その未来は本当に起こる未来だ。それを選択するかどうかはお前ら次第だ」
嘘くさいですが、そんなことを言われると幸せな未来を選びたいですよね。
また、扉によって開けるために必要なポイントが違います。
だからどの扉を開くのか、自分の残りポイント数を考えながら選ぶ必要も出てくるのです。
ゴールはどこかの部屋にあり、そこから脱出するのが目的です。
……なんか台無しなルールだなぁ。
主人公たち数人が一緒にゲームを進めるのでもっと細かいルールもあるんだけど割愛。
残念なのはルール聞いた時点で「未来、関係ないやん。ただどこかにあるゴールを総当たりで探すだけやん」と気づいちゃうとこです。
しっかりところがどうして! ラストゲームだったこともあり結構しっかり作られてて、
頭脳プレイというより、人間の情緒にうったえかけるゲーム展開でなかなか面白かったです。
部屋によりトラップがあるところなんかは映画『Cube』っぽくていい。
まぁ不満もあるけど楽しめた。
と、思ってたんですよね。
——今、LINEマンガで『嘘喰い』という作品を読んでるんですけど、
それに「迷宮(ラビリンス)ゲーム」が出てきました。
ん、こ、これか!! どうやら未来ゲームもアイディアぱくってきてたようです。
ルールは全然違うんだけど、マス目状の部屋に閉じ込められてゴールを目指すのは一緒。
しかし『嘘喰い』の方はルールや部屋の構造などをしっかりと利用した頭脳戦。
ある部分、プレイヤーそれぞれの特殊能力バトル(スタンドや超能力じゃないよ)となっており、
逆転につぐ逆転で展開の面白さも素晴らしい。
ただ、あまりにも難解過ぎて内容を完全に把握するのは相当時間をかけ何回も読み返す必要があるでしょう。
そういう意味でも奥深く面白い。
是非シーズン3が面白かった方は、『ライアーゲーム』と『嘘喰い』も併せて読むことをお勧めします。
私が気づいたのはこの2ゲームだけど、
他のオリジナルもきっと原案があるんだろうな。