Vol.17 「子育てのシンクロディスティニー①」
「封建的」な教育とは、教師からの一方的な学習項目の説明と、それを子どもに繰り返し反復練習させる、画一的なマス教育ということを指しているのでしょうか?
漢字ドリルや計算ドリルがこれに当たると思いますが、漢字や計算は反復練習が必要なので、それは「封建的」であっても続けていくべきだと思います。
(もちろん、子ども1人1人の学習レベルに合わせての進行が望ましいですが。)
問題は、教育がドリル的な学習で終わってしまうことであり、学習項目を発展させたり膨らませたり、自分の意見や友達の意見を交換して発表したりする機会や教室を出て学習する機会が極端に少ないことでしょう。
私は、特に学校のシステムからはみ出していたような、跳びぬけて優秀でもなく、落ちこぼれているわけでもない、平凡といえば平凡な「平均的な」子どもだったと思います。
学校の宿題や課題に対してはまじめにこなしていく子どもで、「国語の本読み5回」の宿題が出れば、ちゃんと5回読んでいました。
小学校高学年になってくると、授業のプリントなどはちゃんとするけれど、それ以外のときはとなりの席の子とおしゃべりばかりしていました。
小学校の授業はそれほど面白いわけではなかったけれど、そんな退屈でもなかったように思います。
今でも印象に残っている授業があります。
それは理科の授業でした。
教科書の順に進むのではなく、先生がある項目についてQA形式で説明していくものでした。
はじめに、「液体は固体になると、体積が①大きくなるのか②小さくなるのか③変わらないのか?」と質問して、①~③で手を挙げさせ、それに対して「どうしてそう思うのか?」と尋ねる形式の授業でした。
私は、ほとんどの質問に対して、「私は①だと思う。なぜなら、~~~だから。」と手を挙げて発言していたのを覚えています。
また、家で寝転がりながらたまたま理科の教科書を眺めていると、「オリオン座を夜7時と9時と時間を変えて見てみよう。」とあったので、7時頃に外に出てみると、想像していたよりも大きいオリオン座が空に見えて、感動して興奮したのを今でも覚えています。
そして9時頃にまた外に出てみるとオリオン座がさっきよりも上の位置に動いているのを見て、また一人で感激していました。
理科が好きだったのかもしれません。
私が今から頑張ってチル大を本気で実践しても、娘が学校のシステムからはみ出してしまう程優秀な子どもなるとは今のところ思えません。
娘が保育所でプラネタリウムに行けば、星や星座に関する絵本を見せたりして、チル大のネットワーク教育をするようにしています。
娘が来年度から小学校に上がったら、学校で習っていることをネットワーク教育したいなあと考えています。
「子どもの能力を最大限に伸ばす教育をすることがお母さんの役割」なので、私が子どもにやってやりたいと思うことはできる限りやっていきたいです。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
テレビで、「かぼちゃは水に浮くのか沈むのか?きゅうりはどうか?」というのをしていたので、娘に「浮力」について教えたくて、本を探してみました。
「うくことしずむこと」
簡単に解説していましたが、娘にはまだ難しいようでした。

「おもいの?かるいの? 物理の絵本」
これは物理を絵本で説明している本で、娘も楽しく見ていました。
ただ、浮力の説明は難しいのか一部分しか説明されていませんでした。
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
「小学生のキッチンでびっくり実験66」
ここにのっていた水と油の実験をしてみました。
水と油は比重が違うから分離するんですね。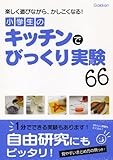
- ¥945
- Amazon.co.jp
「新しい教養のための理科 基礎編」
もともと中学受験用のテキストとのことでしたが、理科に関する「なぜ?どうして?」がすぐに探せます。
子どもが小学校高学年ぐらいでないと、自読は難しいでしょう。
ちょうど昨日読んでいた絵本に子どもがお母さんのおなかにいる絵があったので、「個体発生は系統発生を繰り返す」が図解で載っていたので、娘に説明してみました。
セキツイ動物の分類を説明したくて、いろいろ探していたのですが、やっとこの本に説明を見つけました。
ただ、全体的に説明書きの量は少ないので、子ども用の本も引き続き探しています。

- ¥2,100
- Amazon.co.jp
にほんブログ村