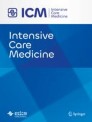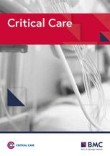こんにちは!ひよっこ救急医です🐣
みなさん、救急関連の論文は定期的にcheckしていますか?私はいくつかの雑誌を、数日に1回更新されていないか追い続けています。勿論、全部読む時間はないので、タイトルから気になった論文と、review articleを中心に読んでいます。
今回は私が読んでいる雑誌を中心に、皆さんにおすすめの雑誌や各雑誌に対するイメージをご紹介します!
(個人的な好みでおすすめ度を星3段階で表しています)
Annals of Emergency Medicine
おすすめ度:⭐⭐⭐
ACEP(米国救急医学会)が監修する雑誌。救急関連の雑誌の中では、Resuscitationと並んでトップクラスのインパクトファクターを誇る。ACEPからの臨床指針もよく載るので必見。重症管理だけでなく、小児・産婦やマイナーエマージェンシーなど、ER診療全般で勉強になる論文が多い。
Resuscitation
おすすめ度:⭐⭐
https://www.resuscitationjournal.com/
前述のように救急領域ではトップクラスのインパクトファクターを誇る。名前の通り、ECPR等の心肺蘇生に関する論文などに少し偏っているイメージ。
The American Journal of Emergency Medicine
おすすめ度:⭐⭐⭐
https://www.sciencedirect.com/journal/the-american-journal-of-emergency-medicine
Annals of Emergency Medicineと似た雰囲気を感じる。ER診療一般について、偏りなく論文をあつかっており、ER医としてはとても勉強になる。
The Journal of Emergency Medicine
おすすめ度:⭐
AAEM(American Academy of Emergency Medicine)関連の雑誌。神経ブロックやマイナーな箇所のPOCUSなど、少しニッチなところまで書いてある印象。ER医向け。
Internal of Emergency Medicine
イタリア内科学会の雑誌。一般内科のことも多く書いてあるが、意外とマイナーエマージェンシーのreviewもある。論文内に画像が多めで分かりやすい。
Emergency Medicine Clinics of North America
おすすめ度:⭐⭐
https://www.sciencedirect.com/journal/emergency-medicine-clinics-of-north-america
年間4回ほど、「Hematologic and Oncologic Emergencies」「Geriatric Emergency Medicine」などと、カテゴリーを決めてReview articleを一気に出してくる。各分野について、深すぎずにまとまっている。Reviewなので最新の知見というよりは、基礎的なことを固めていくのに有用。抄読会にもおすすめ。
Critical Care Medicine
おすすめ度:⭐⭐
https://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx
SCCM(米国集中治療学会)のJournal。必見。
Intensive Care Medicine
欧州集中治療医学会のJournal。上記Critical Care Medineとともにcheckしている。Visual Abstract的なのが目につきやすい。
Chest Critical Care
おすすめ度:⭐⭐⭐
更新頻度は少な目だが、初療~集中治療のことまで扱っている。秀逸なreviewも多く、すごく参考にしている雑誌の一つ。
Chestの関連雑誌なので、呼吸器疾患や循環管理、術後管理などが特に面白い。
Critical Care
Critical Care Medicineと名前がややこしい(笑)
Visual abstractがかっこいい。ひよっこ救急医のcheck頻度は他の雑誌より少し落ちる。
Burns and Trauma
おすすめ度:⭐
https://academic.oup.com/burnstrauma
かなり有名な雑誌。名前の通り、熱傷や創傷処置に関する論文が多い。
論文の内容は少しニッチな印象がある。
Circulation
おすすめ度:⭐⭐
https://www.ahajournals.org/journal/circ
AHAの誇る循環器雑誌。ACLSなどもそうですが、循環器と救急は切っても切れないのでcheckしている。脳卒中や高血圧などについてのガイドラインや論文もここに載るので、優先度高めに読んでいる。更新頻度も多い。
NEJM
https://www.nejm.org/browse/nejm-article-category/review?date=past5Years
誰もが知る雑誌。救急関連に過ぎず、さすがにここに出る論文はある程度把握しておいたが方がよさそう。
JAMA
おすすめ度:⭐⭐⭐
https://jamanetwork.com/journals/jama
いわずもがな、こちらも誰もが知っている。Review articleが非常にまとまっている。ガイドラインとしてここに載ることも多い。ひよっこ救急医はJAMAのreviewは半分以上読んでいます。
BMJ/State of the art review
4大誌の1つ。BMJには救急医学として集まったカテゴリーがない。各分野の最近の治療についてまとめられたreviewが載るので、基礎的というより、新しいことに関するreviewを知ることができる。更新頻度が少なく、救急に全く関係ないことも載っている。
まとめ
どうでしたか?皆さんもcheckしている雑誌はあったでしょうか?🤔
もし、これから救急の論文をこれから読んでみたいけど、何から読んでよいか分からないという、若手がいたら参考になると嬉しいです!また、皆さんのおすすめの雑誌も教えてくださいね✏️