熊谷まどか監督が自身の介護体験を元にした映画「話す犬を、放す」
急増している〈認知症〉にはいくつかのパターンがあり、そのひとつが幻視や幻覚を見るレビー小体型認知症。母親がレビー小体型認知症と診断された若手女性監督の熊谷まどかが自身の体験をベースに脚本・監督した長編デビュー作。上映時間84分。11日公開。 演技を教えながら芝居を続ける売れない女優の下村レイコ(つみきみほ)にかつての劇団仲間で人気俳優になった三田大輔(眞島秀和)から映画出演の話が舞い込む。舞い上がるレイコだが、レビー小体型認知症を発症している母、ユキエ(田島令子)が気になる。出産間もない女性監督の山本(木乃江祐希)と三田は、レイコに介護と芝居の両立をすすめるが……。

介護報酬の不正請求や法令違反で、介護保険法に基づき指定取り消しなどの処分を受けた施設や事業所が、2015年度に計227カ所と過去最多になったことが、厚生労働省の集計で分かった。
このうち報酬の不正請求で自治体が返還を求めた事業所は144カ所、返還請求額は計約5億5500万円だった。
処分の内訳は、介護保険のサービス提供ができなくなる指定取り消しは119カ所。新規利用者の受け入れを認めないなど事業の停止処分が108カ所だった。
指定取り消しの理由は不正請求が最も多く、「書類提出命令に従わない、または虚偽の報告をした」「設置・運営基準に従って運営できない」が続いた。サービス種別ではヘルパーを派遣する訪問介護が最も多かった。

今後、高齢化が急速に進むと見られるベトナムで、日本の最新の介護用品などを集めた大規模な展示会が、首都ハノイで初めて開かれました。
この展示会は、ベトナムで日本の介護用品やサービスを紹介しようと、JETRO=日本貿易振興機構が4日から2日間の日程で、首都ハノイで初めて開いたものです。
会場となった日系の大型商業施設には、最新の介護ベッドや車いすを紹介するコーナーなど、50を超えるブースが設けられ、訪れた人たちは実際に車いすに乗ったり、介護ベッドの使い方を熱心に尋ねたりしていました。
車いすに乗ってみた女性は「とても操作が簡単で、方向を変えるのも容易だったので、お年寄りでも使いやすいと思います」と話していました。
ベトナムでは現在9000万を超える人口の半数近くが30歳以下の若者ですが、2020年に65歳以上の高齢者が全体の7%を超える高齢化社会になったあと、日本を上回る速さで高齢化が進むと見られています。
このため、JETROでは今後、ベトナムで日本の介護用品などの需要が高まることが見込まれるとして、大規模な展示会などを通じたPRを強化していくことにしています。

近くのコンビニが介護の拠点に-。介護相談を受け付けたり、介護用品の販売に重点を置いたりするコンビニの設置が各地で進んでいる。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」を念頭に、全都道府県で事業展開を目指す企業もある。
高齢者への日替わり弁当宅配サービスなどを手掛けるコンビニが登場する中、ローソンは介護を必要とする人とその家族に照準を合わせた店舗「ケアローソン」を15年4月に開設。現在9店舗ある。相談窓口、ケア用品売り場の他、高齢者らの交流の場を併設し、「介護関連のニーズにワンストップで応える」(同社担当者)戦略を描く。25年の全国出店に向け、17年度末までに都市部を中心に30店舗に拡大する方針だ。
埼玉県川口市内の1号店。表看板に書かれた「介護相談」の大きな文字がひときわ目立つ。通常の店舗に比べ10平方メートルほど広い店内一角には、介護の専門職が朝から夕方まで常駐。ケアの悩みや介護保険制度に関する疑問など、幅広く相談に応じている。必要があれば近隣の介護事業者への橋渡し役も担う。同社広報室は「行政窓口を訪ねづらい人もいる。コンビニ内という日常生活の延長線に窓口があれば、相談のきっかけになる」と敷居の低さをメリットに挙げる。
店内には、通常の店舗で扱う食料品や日用品に加え、介護用おむつや歯茎でつぶせる柔らかさのレトルト食品などがずらりと並ぶ。飲料用の棚は開き戸をなくし、車いすの利用者が通行しやすいよう配慮。お年寄りの使い勝手を考え、買い物用カートはかごやハンドルの位置が低い。
健康器具を備えた交流スペースでは、筋力測定などのイベントを定期的に実施。「毎朝ここに立ち寄ってみんなとお話。顔見知りの人もできた」と参加者の井上千江子さん(74)。相談窓口勤務の介護福祉士高橋綾子さん(39)は「ここは自宅と介護施設の中間的な役割を担う場所。リハビリの一歩手前の段階ですね」と説明する。
同社は、地域に根ざしたコンビニであれば、顧客が店員や介護専門職と顔の見える関係を築くことができ、地域の見守り機能強化にも一定の効果があるとみる。店舗展開に際しては、ケア関連の業務を受け持つ介護事業者と連携。
厚労省は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療や介護、住まいなどを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の整備を進めている。同省幹部は、コンビニの介護拠点化を地域包括ケアの一翼を担う動きとして注目している。

以下は小説と呼ぶ種類のものではないかも知れない。さうかと云つて、何と呼ぶべきかは自分も亦不案内である。自分は唯、四五年前の自分とその周囲とを、出来る丈こだはらずに、ありのまま書いて見た。従つて自分、或は自分たちの生活やその心もちに興味のない読者には、面白くあるまいと云ふ懸念けねんもある。が、この懸念はそれを押しつめて行けば、結局どの小説も同じ事だから、そこに意を安んじて、発表する事にした。序ついでながらありのままと云つても、事実の配列は必しもありのままではない。唯事実そのものだけが、大抵ありのままだと云ふ事をつけ加へて置く。
一
十一月の或晴れた朝である。久しぶりに窮屈な制服を着て、学校へ行つたら、正門前でやはり制服を着た成瀬に遇あつた。こつちで「やあ」と云ふと、向うでも「やあ」と云つた。一しよに角帽を並べて、法文科の古い煉瓦造れんぐわづくりの中へはいつたら、玄関の掲示場の前に、又和服の松岡がゐた。我々はもう一度「やあ」と云つた。
立ちながら三人で、近々出さうとしてゐる同人雑誌『新思潮』の話をした。それから松岡がこの間、珍しく学校へ出て来て、西洋哲学史か何かの教室へはいつたが、何時いつまで待つても、先生は勿論学生も来る容子ようすがない。妙だと思つて、外へ出て小使に尋きいて見たら、休日だつたと云ふ話をした。彼は電車へ乗る心算つもりで、十銭持つて歩きながら、途中で気が変つて、煙草屋へはいると、平然として「往復を一つ」と云つた人間だからこんな事は家常茶飯である。その中うちに、傴僂せむしのやうな小使が朝の時間を知らせる鐘を振つて、大急ぎで玄関を通りすぎた。
朝の時間はもう故人になつたロオレンス先生のマクベスの講義である。松岡と分れて、成瀬と二階の教室へ行くと、もう大ぜい学生が集つて、ノオトを読み合せたり、むだ話をしたりしてゐた。我々も隅の方の机に就いて、新思潮へ書かうとしてゐる我々の小説の話をした。我々の頭の上の壁には、禁煙と云ふ札が貼つてあつた。が、我々は話しながら、ポケツトから敷島を出して吸ひ始めた。勿論我々の外の学生も、平気で煙草をふかしてゐた。すると急にロオレンス先生が、鞄をかかへて、はいつて来た。自分は敷島を一本完全に吸つてしまつて、殻も窓からすてた後だつたから、更に恐れる所なく、ノオトを開いた。しかし成瀬はまだ煙草を啣くはへてゐたから、すぐにそれを下へ捨てると、慌あわてて靴で踏み消した。幸さいはひ、ロオレンス先生は我々の机の間から立昇る、縷々るるとした一条の煙に気がつかなかつた。だから出席簿をつけてしまふと、早速毎時いつもの通り講義にとりかかつた。
講義のつまらない事は、当時定評があつた。が、その朝は殊につまらなかつた。始からのべつ幕なしに、梗概かうがいばかり聴かされる。それも一々 Act 1, Scene 2 と云ふ調子で、一くさりづつやるのだから、その退屈さは人間以上だつた。自分は以前はかう云ふ時に、よく何の因果で大学へなんぞはいつたんだらうと思ひ思ひした。が、今ではそんな事も考へない程、この非凡な講義を聴く可く余儀なくされた運命に、すつかり黙従し切つてゐた。だからその時間も、機械的にペンを動かして、帝劇の筋書の英訳のやうなものを根気よく筆記した。が、その中に教室に通つてゐるステイイムの加減で、だんだん眠くなつて来た。そこで勿論、眠る事にした。
うとうとして、ノオトに一頁ばかりブランクが出来た時分、ロオレンス先生が、何だか異様な声を出したので、眼がさめた。始めはちよいと居睡りが見つかつて、叱られたかと思つたが、見ると先生は、マクベスの本をふり廻しながら、得意になつて、門番の声色こわいろを使つてゐる。自分もあの門番の類だなと思つたら、急に可笑をかしくなつて、すつかり眠気がさめてしまつた。隣では成瀬がノオトをとりながら、時々自分の方を見て、くすくす独りで笑つてゐた。それから又、二三頁ノオトをよごしたらやつと時間の鐘が鳴つた。さうして自分たちは、ロオレンス先生の後から、ぞろぞろ教室の外の廊下へ溢れ出した。
廊下へ出て、黄いろい葉を垂らした庭の樹木を見下してゐると、豊田実君が来て、「ちよいとノオトを見せてくれ給へ」と云つた。それからノオトを開けて見せると、豊田君の見たがつてゐる所は、丁度自分の居眠りをした所だつたので、流石さすがに少し恐縮した。豊田君は「ぢやようござんす」と云つて、悠然と向うへ行つてしまつた。悠然と云ふのは、決して好い加減な形容ぢやない。実際君は何時でも、悠然と歩いてゐた。豊田君は今どこで何をしてゐるか、判然とした事は承知しないが、ロオレンス先生に好意を持ち、若しくはロオレンス先生が好意を持つた学生の中で、我々――と云つて悪るければ、少くとも自分が、常に或程度の親しみを感じてゐた、たつた一人の人間である。自分はこれを書いてゐる今でも、君の悠然とした歩き方を思ひ出すと、もう一度君と大学の廊下に立つて、平凡な時候の挨拶でも交換したいやうな気がしないでもない。
その中に又、鐘が鳴つて、我々は二人とも下の教室へ行く事になつた。今度は藤岡勝二博士の言語学の講義である。外の連中は皆先へ行つて、ちやんと前の方へ席をとつて置くが、なまけ者の我々は、何時でも後からはいつて行つて、一番隅の机を占領した。その朝もやはりかう云ふ伝でんで、愈いよいよ鐘が鳴る間際まぎはまで、見晴しの好い二階の廊下に※(「彳+詆のつくり」、第3水準1-84-31)徊ていくわいしてゐたのである。藤岡博士の言語学の講義は、その朗々たる音吐とグロテスクな諧謔かいぎやくとを聞くだけでも、存在の権利のあるものだつた。尤もつとも自分の如く、生来言語学的な頭脳に乏しい人間にとつては、それだけで存在の権利があつたと云ひ直しても別に差支へはない。だから今日も、ノオトをとつたりやめたりしながら、半分はさう云ふ興味で、マツクス・ミユラアがどうとかしたとか云ふ講義を面白がつて聴いてゐた。すると自分の前の席に、髪の毛の長い学生が坐つてゐて、その人の髪の毛が、時々自分のノオトの上を、掃くやうにさらさら通りすぎた。自分は相手が名前も知らない人の事だから、どう云ふ了見で、あんな長髪を蓄へてゐるのだか、つい今日に至るまで問ひ質ただす機会を失つてしまつたが、兎に角それが彼自身の美的要求には合してゐても、他人の実際的要求と矛盾し得る事を発見したのは、正にこの言語学の講義を聞いてゐた時間である。しかし幸さいはひ、その講義を聴かうと云ふ、自分の実際的要求がそれ程痛切でなかつたから、髪の毛が邪魔になつた所だけは、ノオトをとらずに捨てて置いた。その中には邪魔にならない所でも、ノオトの代りに画を描く事にした。処が向うに坐つてゐる、何とか云ふ恐しくハイカラな学生の横顔を、半分がた描いた処で運悪く鐘が鳴つた。講義の終を知らせると同時に、午ひるになつた事を知らせる鐘である。
我々は一しよに大学前の一白舎いつぱくしやの二階へ行つて、曹達水ソオダすゐに二十銭の弁当を食つた。食ひながらいろんな事を弁じ合つた。自分と成瀬との間には、可也かなり懸隔かけへだてのない友情が通つてゐた。その上その頃は思想の上でも、一致する点が少くなかつた。殊に二人とも、偶然同時に「ジアン・クリストフ」を読み出して、同時にそれに感服してゐた。だからかう云ふ時になると、毎日のやうに顔を合せてゐる癖に、やはり話がはずみ勝ちだつた。すると二人のゐる所へ、給仕の谷がやつて来て、相場の話をし始めた。それも「まかり間違つたら、これになる覚悟でなくつちや駄目ですね」と、手を後へまはして見せたのだから盛である。成瀬は「莫迦ばかだな」と云つて、取合はなかつたが、当時「財布」と云ふ小説を考へてゐた自分は、さまざまな意味で面白かつたから、食事をしまふまで谷の相手になつた。さうして妙な相場の熟語を、十ばかり一度に教へられた。
午後は講義がなかつたから、一白舎を出ると二人で、近所の宮裏に下宿してゐる久米の所へ遊びに行つた。久米は我々以上のなまけ者だから、大抵は教室へも出ずに、下宿で小説や芝居を書いてゐたのである。行つて見ると、やはり机の側に置炬燵おきごたつを据ゑて、「カラマゾフ兄弟」か何か読んでゐた。あたれと云ふから、我々もその置炬燵へはいつたら、掛蒲団の脂臭あぶらくさい匂にほひが、火臭い匂と一しよに鼻を打つた。久米は今、彼の幼年時代に自殺した阿父おとうさんの事を、短篇にして書いてゐると云つた。小説はこれが処女作同様だから、見当がつかなくて困るとも云つた。が、相不変あひかはらず元気の好ささうな顔をして、余り困つてゐるらしい容子ようすもなかつた。その後で「君はどうした」と訊くから、「やつと『鼻』を半分ばかり書いた」と答へた。成瀬も今年の夏、日本アルプスへ行つた時の話を書きかけてゐると云ふ事だつた。それから三人で、久米の拵へた珈琲コオヒイを飲みながら、創作上の話を長い間した。久米は文壇的閲歴の上から云つて、ずつと我々より先輩だつた。と同時に又表現上の手腕から云つても、やはり我々に比べると、一日の長がある事は事実だつた。特に自分はこの点で、久米が三幕物や一幕物を容易にしかも短い時間で、書き上げる技倆に驚嘆してゐた。だから我々の中で久米だけは、彼自身の占めてゐる、或は占めんとする、文壇的地位に相当な自信を持つてゐた。さうしてその自信が又一方では、絶えず眼高手低の歎を抱いてゐる我々に、我々自身の自信を呼び起す力としても働いてゐた。実際自分の如きは、もし久米と友人でなかつたら、即すなはち彼の煽動せんどうによつて、人工的にインスピレエシヨンを製造する機会がなかつたなら、生涯一介の読書子たるに満足して、小説なぞは書かなかつたかも知れない。さう云ふ次第だから創作上の話になると――と云ふより文壇に関係した話になると、勢いきほひ何時も我々の中では、久米が牛耳ぎうじを執る形があつた。その日も彼が音頭とりで、大分議論を上下したが、何かの関係で田山花袋氏が度々問題に上つたやうに記憶する。
今になつて公平に考へれば、自然主義運動があれ丈だけ大きな波動を文壇に与へたのも、全く一つは田山氏の人格の力が然らしめたのに相違ない。その限りに於て田山氏は、氏の「妻」や「田舎教師」が如何いかに退屈であるにしても、乃至ないし又氏の平面描写論が如何に幼稚であるにしても、確に我々後輩の敬意――とまで行かなければ、少くとも興味位は惹ひくに足る人物だつた。が、遺憾ながら当時の我々は、まだこの情熱に富んだ氏の人格を、評価するだけの雅量に乏しかつた。だから我々は氏の小説を一貫して、月光と性慾とを除いては、何ものも発見する事は出来なかつた。と同時に氏の感想や評論も、その怪しげな ※(グレーブアクセント付きA小文字) la Huysmans の入信生活を聞かされる度に、先まづ Durtal と田山花袋氏との滑稽な対照を思ひ出させて、徒いたづらに我々の冷笑を買ふばかりだつた。では我々は氏を目して、全然ハムバツグとしてゐたかと云ふと必しも亦さうぢやない。成程小説家としての氏や思想家としての氏は、更に本質的なものだとは思はなかつたが、それらに先立つて我々は、紀行文家としての田山氏を認めてゐた。Sentimental landscape-painter――これが当時の自分が、田山氏へ冠らせてゐた渾名あだなだつた。実際氏は、小説や評論を書く合ひ間に、根気よく紀行文を書いてゐた。いや少し誇張して云へば、小説の多くも紀行文で、その中に Venus Libentina の信者たる男女なんによを点出したものに過ぎなかつた。さうしてその紀行文を書いてゐる時の氏は、自由で、快活で、正直で、如何にも青い艸くさを得た驢馬ろばのやうに、純真無垢な所があつた。従つてそれだけの領域では、田山氏はユニイクだと云はうが何だらうが差支へない。が、氏を自然主義の小説家たり、且かつ思想家たる文壇の泰斗たいとと考へる事は、今よりも更に出来憎かつた。遠慮のない所を云ふと、自然主義運動に於ける氏の功績の如きも、「何しろ時代が時代だつたからね」なぞと軽蔑けいべつしてゐたものである。
大体こんなやうな気焔をあげてから、又成瀬と二人で、久米の下宿を出た。出た時分には、短い冬の日脚が、もう往来へ長い影を落してゐた。我々は我々のよく知つてゐる、しかも常になつかしい興奮を感じながら、本郷三丁目の角まで歩いて行つて、それから別々の電車へ乗つた。
二
三四日たつた、これも好い天気の日の事である。自分は午前の講義に出席してから、成瀬と二人で久米の下宿へ行つて、そこで一しよに昼飯を食つた。久米は京都の菊池が、今朝送つてよこしたと云ふ戯曲の原稿を見せた。それは「坂田藤十郎の恋」と云ふ、徳川時代の名高い役者を主人公にした一幕物だつた。読めと云ふから読んで見ると、テエマが面白いのにも関らず、無暗に友染縮緬いうぜんちりめんのやうな台辞せりふが多くつて、どうも永井荷風氏や谷崎潤一郎氏の糟粕さうはくを嘗なめてゐるやうな観があつた。だから自分は言下ごんかに悪作だとけなしつけた。成瀬も読んで見て、やはり同感は出来ないと云つた。久米も我々の批評を聞いて、「僕も感服出来ないんだ。一体に少し高等学校情調がありすぎるよ」と、同意を表した。それから久米が我々一同を代表して、菊池の所へその意味の批評を、手紙で書いてやる事にした。そこへ幸ひ松岡も遊びに来た。松岡は我々三人が英文科に籍を置いてゐるのにも関らず、独り哲学科へはいつてゐた。が、勿論我々と同じやうに、創作もする心算つもりだつた。彼は我々の中で、一番久米と親しかつた。一しきりは二人で、同じ家に下宿してゐた事もあつた。それは砲兵工廠の裏にある、職工服を造る家だつた。実生活上のロマンテイケルだつた久米は、今にあの青い職工服を着て、アトリエのやうな書斎へ西洋机を据ゑて、その書斎を久米正雄工房と名づけたいなどと云ふ、途方もない夢をよく見てゐた。自分は彼等をその下宿に訪問すると、毎時いつもかう云ふ久米の夢を思ひ出したものだつた。が、松岡はその時分から、余り職工服とは縁のない思想なり心もちなりを持つてゐるらしかつた。まだ感傷癖こそ脱しなかつたが、彼の中には宗教の匂のするものが、もうふんだんに磅※(「石+薄」、第3水準1-89-18)ばうはくしてゐた。彼はその東洋とも西洋ともつかないイエルサレムの建設をもくろみながらキエルケガアドを愛読したり、怪しげな水彩画を描いて見たりした。当時彼の描いた水彩画の一つにさかさまにした方が遙はるかに画らしくなるもののあつたのは、今でもよく覚えてゐる。その後松岡は久米が宮裏へ移ると共に、本郷五丁目へ下宿を移した。さうして今でもそこにゐて、釈迦伝しやかでんから材料を取つた三幕物の戯曲を書いてゐた。
我々四人は、又久米の手製の珈琲コオヒイを啜りながら、煙草の煙の濛々もうもうとたなびく中で、盛にいろんな問題をしやべり合つた。その頃は丁度武者小路実篤氏が、将まさにパルナスの頂上へ立たうとしてゐる頃だつた。従つて我々の間でも、屡しばしば氏の作品やその主張が話題に上つた。我々は大抵、武者小路氏が文壇の天窓を開け放つて、爽さわやかな空気を入れた事を愉快に感じてゐるものだつた。恐らくこの愉快は、氏の踵くびすに接して来た我々の時代、或は我々以後の時代の青年のみが、特に痛感した心もちだらう。だから我々以前と我々以後とでは、文壇及それ以外の鑑賞家の氏に対する評価の大小に、径庭けいていがあつたのは已むを得ない。それは丁度我々以前と我々以後とで、田山花袋氏に対する評価が、相違するのと同じ事である。(唯、その相違の程度が、武者小路氏と田山氏とで、どちらが真に近いかは疑問である。念の為に断つて置くが、自分が同じ事だと云ふのは、程度まで含んでゐる心算つもりぢやない。)が、当時の我々も、武者小路氏に文壇のメシヤを見はしなかつた。作家としての氏を見る眼と、思想家としての氏を見る眼と――この二つの間には、又自らな相違があつた。作家としての武者小路氏は、作品の完成を期する上に、余りに性急な憾うらみがあつた。形式と内容との不即不離な関係は、屡しばしば氏自身が「雑感」の中で書いてゐるのにも関らず、忍耐よりも興奮に依頼した氏は、屡実際の創作の上では、この微妙な関係を等閑に附して顧みなかつた。だから氏が従来冷眼に見てゐた形式は、「その妹」以後一作毎に、徐々として氏に謀叛を始めた。さうして氏の脚本からは、次第にその秀抜な戯曲的要素が失はれて、(全くとは云はない。一部の批評家が戯曲でないやうに云ふ「或青年の夢」でさへ、一齣一齣いつせついつせつの上で云へばやはり戯曲的に力強い表現を得た個所がある。)氏自身のみを語る役割が、己自身を語る性格の代りに続々としてそこへはいつて来た。しかもそこに語られた思想なり感情なりは、必然性に乏しい戯曲的な表現を借りてゐるだけ、それだけ一層氏の「雑感」に書かれたものより稀薄だつた。「或家庭」の昔から氏の作品に親しんでゐた我々は、その頃の――「その妹」の以後のかう云ふ氏の傾向には、慊あきたらない所が多かつた。が、それと同時に、又氏の「雑感」の多くの中には、我々の中に燃えてゐた理想主義の火を吹いて、一時に光焔を放たしめるだけの大風のやうな雄々しい力が潜んでゐる事も事実だつた。往々にして一部の批評家は、氏の「雑感」を支持すべき論理の欠陥を指摘する。が、論理を待つて確められたもののみが、真理である事を認めるには、余りに我々は人間的な素質を多量に持ちすぎてゐる。いや、何よりもその人間的な素質の前に真面目であれと云ふ、それこそ氏の闡明せんめいした、大いなる真理の一つだつた。久しく自然主義の淤泥おでいにまみれて、本来の面目を失してゐた人道ユウマニテエが、あのエマヲのクリストの如く「日昃かたぶきて暮に及んだ」文壇に再ふたたび姿を現した時、如何に我々は氏と共に、「われらが心熱もえし」事を感じたらう。現に自分の如く世間からは、氏と全然反対の傾向にある作家の一人に数へられてゐる人間でさへ、今日も猶なほ氏の「雑感」を読み返すと、常に昔の澎湃はうはいとした興奮が、一種のなつかしさと共に還つて来る。我々は――少くとも自分は氏によつて、「驢馬の子に乗り爾なんぢに来る」人道ユウマニテエを迎へる為に、「その衣を途みちに布しき或は樹の枝を伐りて途に布く」先例を示して貰つたのである。
散々話をした後で、我々は皆一しよに、久米の下宿を出た。それから本郷三丁目で成瀬と松岡とに別れた。久米と自分とは電車で銀座へ行つて、カツフエ・ライオンで少し早い晩飯をすませてから、ちよいと歌舞伎座の立見へはいつた。はいると新狂言の二番目もので、筋は勿論外題げだいさへ、更に不案内なものだつた。舞台には悪く納つた茶室があつて、造花の白梅が所々に、貝殻細工のやうな花を綴つてゐた。さうしてその茶室の縁側で、今の中車ちゆうしやの侍が、歌右衛門の娘を口説いてゐた。東京の下町に育ちながら、更に江戸趣味なるものに興味のない自分は、芝居に対しても同様に、滅多にドラマテイツク・イリユウジヨンは起す事が出来ない程、冷淡に出来上つた人間だつた。(或は冷淡にならされた人間かも知れない。芝居を見る事は二歳位の頃から、よく家のものと一しよに見た。)だから芝居より役者の芸が、役者の芸よりも土間桟敷の見物が、余程自分には面白かつた。その時も自分の隣にゐた、どこかの御店者おたなものらしい、鳥打帽をかぶつた男が、甘栗を食ひながら、熱心に舞台を見てゐる方が、天下の名優よりも興味があつた。この男は熱心に舞台を見てゐると云つたが、同時に又甘栗もやはり熱心に食つてゐた。それが懐へ手を入れたかと思ふと、甘栗を一つつまみ出して、割るが早いか口へ入れる、口へ入れたと思ふと、又懐へ手を入れて、つまみ出すが早いか割つて食ふ。しかもその間中、眼は終始一貫して、寸分も舞台を離れない。自分はこの視覚と味覚との敏捷びんせふな使ひ分けに感心して、暫くはその男の横顔ばかり眺めてゐたが、とうとうしまひに彼自身はどちらを真剣にやつてゐる心算つもりだか、尋きいて見たいやうな気がして来た。するとその時、自分の側で、久米がいきなり「橘屋あ」と、無鉄砲に大きな声を出した。自分はびつくりして、思はず眼を舞台の方へやつた。見ると成程、女をたらすより外には何等の能もなささうな羽左衛門の若侍が、従容しようようとして庭伝ひに歩いて来る所だつた。が、隣の御店者おたなものは、久米の「橘屋」も耳にはいらないやうに、依然として甘栗を食ひながら、食ひつくやうな眼で舞台を眺めてゐる。自分も今度はその滑稽さが、笑ふには余りに真剣すぎるやうな気がして来た。さうして又そこに小説めいた心もちも感じられた。しかし舞台の上の芝居は、折角その「橘屋」が御出でになつても、池田輝方氏の画以上に俗悪だつた。自分はとうとう一幕が待ち切れなくつて、舞台が廻つたのを潮に、久米をひつぱつて外へ出た。
星月夜の往来へ出てから「あんな声を出して、莫迦ばかだな」と云つたが、久米は「何、あれだつて中々好い声だよ」と自慢して容易にその愚を認めなかつた。今でもあの時の事を考へると、彼はカツフエ・ライオンで飲んだウイスキイに祟たたられてゐたものとしか思はれない。
三
「一体大学の純文学科などと云ふものは、頗すこぶる怪しげな代物しろものだよ。ああやつて、国漢英仏独の文学科があるけれども、あれは皆何をやつてゐるんだと思ふ? 実は何をやつてゐるか、僕にもはつきりとはわからないんだ。成程研究してゐるものは、各国の文学に違ひなからう。さうしてその文学なるものは、まあ芸術の一部門とか何とか云へるにや違ひない。しかしその文学を研究する学問だね、あれは一体学問だらうか。(或は独立した学問だらうかと云つても好いが。)もし学問とすれば、――むづかしく云へば Wissenschaft として成立するのに必要な条件を具へるとすればだね。さうすれば美学と同じものになつちまふぢやないか。いや、美学ばかりぢやない。文学史なんぞは、始から史学と同じものだらうと思ふんだ。そりや成程今純文学科でやつてゐる講義にや、美学や史学と縁のないものだつて、沢山ある。が、その沢山あるものは、義理にも学問だとは思はれないぢやないか。あれはまあよく云へば先生の感想を述べたもので、悪く云へば出たらめだからね。だから僕は大学の純文学科なんぞは、廃止しちまつた方がほんたうだと思ふんだ。文学概論や何かは美学と一しよにする。文学史は史学へ片づけてしまふ。さうしてあとに残つた講義は、要するに出たらめだから、大学外へ駆逐しちまふんだ。出たらめだからと云つて悪るければ、余りに高尚で、大学のやうな学問の研究を目的にする所には、不釣合だと云つても好い。これは確に目下の急務だよ。さもないと同じ出たらめでも、新聞や雑誌へ出た評論より、大学でやる講義の方が、上等のやうな誤解を天下に与へ易いからね。それも実は新聞や雑誌へ出る方は、世間を相手にしてゐるんだが、大学でやる方は学生だけを相手にしてゐるんだから、それだけ馬脚が露あらはれずにすんでゐるんだらう。その安全なる出たらめが、一層箔をつけてゐるのは、どう考へたつて不公平だ。実際僕なんぞは無責任に、図書館の本を読まう位な了見で、大学にはいつてゐるんだから好いが、真面目に研究心でも起したら、一体どうすれば文学の研究になるんだか、途方にくれちまふのに違ひない。それや市河三喜さんのやうに言語学的に英文学を研究するんなら、立派に徹底してゐると思ふんだ。けれどもさうすると、シエクスピイアだらうが、ミルトンだらうが、詩でも芝居でもなくなつて、唯の英語の行列だからね。それぢや僕はやる気もないし、やつたつて到底ものにはなりさうもないだらう。勿論出たらめで満足してゐりや好いが、それなら御苦労にも大学へはいらずともの事だ。又美学なり史学なりの立ち場から、研究しようと云ふんなら、外の科へ籍を置いた方がどの位気が利いてゐるかわからない。かう考へて来ると、純文学科のレエゾン・デエトルは、まあ精々便宜的位な所だね。が、いくら便宜でも、有害の方が多くつちや、勿論ないのに劣つてゐると云ふもんだ。劣つてゐる以上は、廃止した方が正当だよ。――何、あれは中学の教師を養成する為に必要だ? 僕は皮肉を云つてゐるんぢやない。これでも大真面目な議論なんだ。中学の教師を養成するんなら、ちやんと高等師範と云ふものがある。高等師範を廃止しろなんと云ふのは、それこそ冠履顛倒くわんりてんたうだ。その理窟で行つても廃止さるべきものは大学の純文学科の方で、高等師範は一日も早くあれを合併してしまふが好い。」
その頃の或日、古本屋ばかり並んでゐる神田通りを歩きながら、自分は成瀬をつかまへて、こんな議論をふつかけた事がある。
四
十一月もそろそろ末にならうとしてゐる或晩、成瀬と二人で帝劇のフイル・ハアモニイ会を聞きに行つた。行つたら、向うで我々と同じく制服を着た久米に遇つた。その頃自分は、我々の中で一番音楽通だつた。と云ふのは自分が一番音楽通だつた程、それ程我々は音楽に縁が遠い人間だつたのである。が、その自分も無暗に音楽会を聞いて歩いただけで、鑑賞は元より、了解する事も頗すこぶる怪しかつた。先まづ一番よくわかるものは、リストに止めをさしてゐた。何時か帝国ホテルで、あのペツツオルド夫人と云ふお婆さんが、リストの der heilige Antonius schreitend auf den Wellen(だと思ふ。ちがつたら御免なさい。)を弾いた時も、そのピアノの音の一つ一つは、寸刻も流動して止らない、しかも不思議に鮮あざやかな画面を、ありありと眼の前へ浮ばせてくれた。その画面の中には、どこを見ても、際限なく波が動いてゐた。それからその波の上には、一足毎に波紋を作る人間の足が動いてゐた。最後にその波と足との上に、煌々くわうくわうたる光があつて、それが風の中の太陽のやうに、眩まばゆく空中で動いてゐた。この明い幻を息もつかずに眺めてゐた自分は、演奏が終つて拍手の声が起つた時に、音楽の波動が消えてしまつた、空虚な周囲の寂しさがしみじみ情なく感じられた。が、こんな事は前にも云つた通り、リストが精々行きどまりで、ベエトオフエンなどと云ふ代物は、好いと思へば好いやうだし、悪いと思へば悪いやうだし、更に見当がつかなかつた。だからフイル・ハアモニイ会を聞くと云つても、一向芸術家らしくない、怪しげな耳をそば立てて、楽器の森から吹いて来るオオケストラの風の音を、漫然と聞いてゐたのである。
当夜は閑院宮殿下も御臨場になつたので、帝劇のボックスや我々のゐるオオケストラ・ストオルには、模様を着た奥さんや御嬢さんが大分方々に並んでゐた。現に自分の隣なぞにも、白粉おしろいをつけた骨と皮ばかりの老夫人が、金の指環をはめて金の時計の鎖を下げて、金の帯留の金物をして、その上にもまだ慊あきたらず、歯にも一面に金を入れて、(これは欠伸あくびをした時に見えたのである。)端然として控へてゐた。が、前に歌舞伎座の立見をした時とは異なつて、今夜は見物の紳士淑女より、シオパンやシユウベルトの方が面白かつたから、それ以上自分はこの白粉と金とに埋つてゐる老夫人に、注意を払はなかつた。尤もつとも彼女自身は、自分に輪をかけた、デイスイリユウジヨンそれ自身のやうな豪傑だつたと見えて、舞台の上で指揮杖バトンを振つてゐる山田耕作氏には目もくれず、頻しきりに周囲ばかりを見廻してゐた。
その中に山田夫人の独唱か何かで、途中の休憩時間になると、我々は三人揃つて、二階の喫煙室へ出かけて行つた。するとそこの入口に、黒い背広の下へ赤いチヨツキを着た、背の低い人が佇んで、袴羽織の連れと一しよに金口の煙草を吸つてゐた。久米はその人の姿を見ると、我々の耳へ口をつけるやうにして、「谷崎潤一郎だぜ」と教へてくれた。自分と成瀬とはその人の前を通りながら、この有名な耽美主義の作家の顔を、偸ぬすむやうにそつと見た。それは動物的な口と、精神的な眼とが、互に我がを張り合つてゐるやうな、特色のある顔だつた。我々は喫煙室の長椅子に腰を下して、一箱の敷島を吸ひ合ひながら、谷崎潤一郎論を少しやつた。当時谷崎氏は、在来氏が開拓して来た、妖気靉靆えうきあいたいたる耽美主義の畠に、「お艶殺し」の如き、「神童」の如き、或は又「お才と巳之助」の如き、文字通り底気味の悪いFleurs du Mal を育ててゐた。が、その斑猫はんめうのやうな色をした、美しい悪の花は、氏の傾倒してゐるポオやボオドレエルと、同じ荘厳な腐敗の香を放ちながら、或一点では彼等のそれと、全く趣おもむきが違つてゐた。彼等の病的な耽美主義は、その背景に恐る可き冷酷な心を控へてゐる。彼等はこのごろた石のやうな心を抱いた因果に、嫌でも道徳を捨てなければならなかつた。嫌でも神を捨てなければならなかつた。さうして又嫌でも恋愛を捨てなければならなかつた。が、彼等はデカダンスの古沼に身を沈めながら、それでも猶なほこの仕末に了へない心と――une vieille gabare sans m※(サーカムフレックスアクセント付きA小文字)ts sur une mer monstrueuse et sans bords の心と睨み合つてゐなければならなかつた。だから彼等の耽美主義は、この心に劫おびやかされた彼等の魂のどん底から、やむを得ずとび立つた蛾の一群ひとむれだつた。従つて彼等の作品には、常に Ah ! Seigneur, donnezmoi la force et le courage/ De contempler mon coeur et mon corps sans d※(アキュートアクセント付きE小文字)go※(サーカムフレックスアクセント付きU小文字)t ! と云ふせつぱつまつた嘆声が、瘴気しやうきの如く纏綿てんめんしてゐた。我々が彼等の耽美主義から、厳粛な感激を浴びせられるのは、実にこの「地獄のドン・ジユアン」のやうな冷酷な心の苦しみを見せつけられるからである。しかし谷崎氏の耽美主義には、この動きのとれない息苦しさの代りに、余りに享楽的な余裕があり過ぎた。氏は罪悪の夜光虫が明滅する海の上を、まるでエル・ドラドでも探して行くやうな意気込みで、悠々と船を進めて行つた。その点が氏は我々に、氏の寧むしろ軽蔑するゴオテイエを髣髴はうふつさせる所以ゆゑんだつた。ゴオテイエの病的傾向は、ボオドレエルのそれとひとしく世紀末の色彩は帯びてゐても、云はば活力に満ちた病的傾向だつた。更に洒落しやれて形容すれば、宝石の重みを苦にしてゐる、肥満したサルタンの病的傾向だつた。だから彼には谷崎氏と共に、ポオやボオドレエルに共通する切迫した感じが欠けてゐた。が、その代りに感覚的な美を叙述する事にかけては、滾々こんこんとして百里の波を飜ひるがへす河のやうな、驚く可き雄弁を備へてゐた。(最近広津和郎氏が谷崎氏を評して、余り健康なのを憾うらみとすると云つたのは、この活力に満ちた病的傾向を指摘したものだらうと思ふ。が、如何に活力に溢れてゐても、脂肪過多症の患者が存在し得る限り、やはり氏のそれは病的傾向に相違ない。)さうして此の耽美主義に慊あきたらなかつた我々も、流石さすがにその非凡な力を認めない訳に行かなかつたのは、この滔々たうたうたる氏の雄弁である。氏はありとあらゆる日本語や漢語を浚さらひ出して、ありとあらゆる感覚的な美を(或は醜を)、「刺青」以後の氏の作品に螺鈿らでんの如く鏤ちりばめて行つた。しかもその氏の Les Emaux et Cam※(アキュートアクセント付きE小文字)es は、朗々たるリズムの糸で始から終まで、見事にずつと貫かれてゐた。自分は今日でも猶、氏の作品を読む機会があると、一字一句の意味よりも、寧むしろその流れて尽きない文章のリズムから、半ば生理的な快感を感じる事が度々ある。ここに至るとその頃も、氏はやはり今の如く、比類ない語ことばの織物師だつた。たとひ氏は暗澹たる文壇の空に、「恐怖の星」はともさなかつたにしても、氏の培つちかつた斑猫色はんめういろの花の下には、時ならない日本の魔女のサバトが開かれたのである。――
やがて又演奏の始まりを知らせる相図のベルと共に、我々は谷崎潤一郎論を切り上げて、下の我々の席へ帰つた。帰る途中で久米が、「一体君は音楽がわかるのかい」と云ふから、「隣の金と骨と皮と白粉とよりはわかりさうだ」と答へた。それから又その老夫人の隣へ腰を下して、シヨルツ氏のピアノを聞いた。確たしか、シオパンのノクテユルヌとか何とか云ふものだつたと思ふ。シモンズと云ふ男は、子供の時にシオパンの葬式の行進曲を聞いて、ちやんとわかつたと広告して居るが、自分はシヨルツ氏の器用に動く指を眺めながら、年齢の差を勘定に入れないでも、この点ではシモンズに到底及ばないと観念した。そのあとは何があつたか、もう今は覚えてゐない。が、会が終つて外へ出たら、車寄のまはりに馬車や自働車が、通りぬけられない程沢山並んでゐた。さうしてその中の一つの自働車には、あの金と白粉との老夫人が毛皮に顔を埋めながら、乗らうとしてゐる所だつた。我々は外套の襟を立てて、その間をやつと風の寒い往来へ出た。ふと見ると、我々の前には、警視庁の殺風景な建物が、黒く空を衝ついて聳えてゐた。自分は歩きながら、何だかそこに警視庁のある事が不安になつた。で、思はず「妙だな」と云つたら、成瀬が「何が?」と聞き咎とがめた。自分はいやとか何とか云つて、好い加減に返事を胡麻化した。その時はもう我々の左右を、馬車や自働車が盛んに通りすぎてゐた。
五
フイル・ハアモニイ会へ行つたあくる日、午前の大塚博士の講義(題目はリツケルトの哲学だつた。これが自分が聞いた中では最も啓発される所の多かつた講義である)をすませた後で、又成瀬と凩こがらしの吹く中を、わざわざ一白舎へ二十銭の弁当を食ひに行つたら、彼が突然自分に、「君は昨夜僕等の後にゐた女の人を知つてゐるかい。」と尋ねた。「知らない。知つてゐるのは隣の金と皮と骨と白粉とだけだ。」「金と皮と――何だい、それは。」「何でも好い。兎に角、後にゐた女の人ぢやない事は確だ。さうして君は又その女の人に惚れでもしたのかい。」「惚れる所か、僕も知らなかつたんだ。」「何だ、つまらない。そんな人間なら、ゐたつてゐなくたつて、同じ事ぢやないか。」「所がね。家に帰つたらムツタアが後の女の人を見たかと云ふんだ。つまりその人が僕の細君の候補者だつたんださうだね。」「ぢや見合ひか。」「見合ひ程まだ進歩したものぢやないんだらう。」「だつて見たかつて云へば、見合ひぢやないか。君のムツタアも亦、迂遠うゑんだな。見せる心算つもりなら、前へ坐らせりや好いのに。後にゐるものが見える位なら、こんな二十銭の弁当なんぞ食つてゐやしない。」成瀬は親孝行な男だから、自分がかう云ふと、ちよいと妙な顔をした。が、すぐに又、「しかし向うの女の人を本位にして云へば、僕等が前にゐた事になるんだからな。」「成程、あすこぢや両方で向ひ合つてゐようと思つたら、どつちか一方が舞台へ上らなくつちやならない訳だ。――訳だが、それで君は何つて返事をしたんだい。」「見なかつたつて云つたあね。実際見なかつたんだから仕方がないぢやないか。」「さう今になつて、僕に欝憤を洩したつて駄目だよ。だが惜しい事をしたな。一体あれは音楽会だつたから、いけないんだ。芝居なら僕が頼まれなくつたつて、帝劇中の見物をのこらず物色をしてやるんだのに。」――成瀬と自分とはこんな話をしながら、大笑ひに笑ひ合つた。
その日は午後には、独逸語の時間があつた。が、当時我々はアイアムビツクに出席するとか何とか云つて、成瀬が出れば自分が休み、自分が出れば成瀬が休んでゐた。さうして一つ教科書に代る代る二人で仮名をつけて、試験前には一しよにその教科書を読んで間に合せてゐた。丁度その午後の独逸語は成瀬が出席する番に当つてゐたから、自分は食事をしまふと、成瀬に教科書を引き渡して、独りで一白舎の外へ出た。
出ると外は凩こがらしが、砂煙を往来の空に捲まき上げてゐた。黄いろい並木の銀杏いてふの落葉も、その中でくるくる舞ひながら、大学前の古本屋の店の奥まで吹かれて行つた。自分はふと松岡を訪ねて見ようと云ふ気になつた。松岡は自分と(恐らくは大抵な人と)違つて大風の吹く日が一番落着いて好いと称してゐた。だからその日などは殊に落着いてゐるだらうと思つて、何度も帽子を飛ばせさうにしながら、やつと本郷五丁目の彼の下宿まで辿りつくと、下宿のお婆さんが入口で、「松岡さんはまだ御休みになつていらつしやいますが」と、気の毒さうな顔をして云つた。「まだ寝てゐる? 恐ろしく寝坊だな。」「いえ、昨夜徹夜なすつて、ついさつきまで起きていらしつたんですがね、今し方寝るからつて、床へおはいりになつたんでございますよ。」「ぢやまだ眼がさめてゐるかも知れない。兎に角ちよいと上つて見ませう。寝てゐればすぐに下りて来ます。」自分は松岡のゐる二階へ、足音を偸ぬすみながら、そつと上つた。上つてとつつきの襖ふすまをあけると、二三枚戸を立てた、うす暗い部屋のまん中に、松岡の床がとつてあつた。枕元には怪しげな一閑張いつかんばりの机があつて、その上には原稿用紙が乱雑に重なり合つてゐた。と思ふと机の下には、古新聞を敷いた上に、夥おびただしい南京豆の皮が、杉形すぎなりに高く盛り上つてゐた。自分はすぐに松岡が書くと云つてゐる、三幕物の戯曲の事を思ひ出した。「やつてゐるな」――-ふだんならかう云つて、自分はその机の前へ坐りながら、出来ただけの原稿を読ませて貰ふ所だつた。が、生憎あいにくその声に応ずべき松岡は、髭ののびた顔を括くくり枕まくらの上にのせて、死んだやうに寝入つてゐた。勿論自分は折角徹夜の疲を癒してゐる彼を、起さうなどと云ふ考へはなかつた。しかし又この儘帰つてしまふのも、何となく残り惜しかつた。そこで自分は彼の枕元に坐りながら、机の上の原稿を、暫しばらくあつちこつち読んで見た。その間も凩はこの二階を揺ぶつてしつきりなく通りすぎた。が、松岡は依然として、静な寝息ばかり洩してゐた。自分はやがて、かうしてゐても仕方がないと思つたから、物足りない腰をやつと上げて、静に枕元を離れようとした。その時ふと松岡の顔を見ると、彼は眠りながら睫毛まつげの間へ、涙を一ぱいためてゐた。いや、さう云へば頬の上にも、涙の流れた痕あとが残つてゐた。自分はこの思ひもよらない松岡の顔に気がつくと、さつきの「やつてゐるな」と云ふ元気の好い心もちは、一時にどこかへ消えてしまつた。さうしてその代りに、自分も夜通し苦しんで、原稿でもせつせと書いたやうな、やり切れない心細さが、俄にはかに胸へこみ上げて来た。「莫迦ばかな奴だな。寝ながら泣く程苦しい仕事なんぞをするなよ。体でも毀こはしたら、どうするんだ。」――自分はその心細さの中で、かう松岡を叱りたかつた。が、叱りたいその裏では、やつぱり「よくそれ程苦しんだな」と、内証で褒めてやりたかつた。さう思つたら、自分まで、何時いつの間にか涙ぐんでゐた。
それから又足音を偸ぬすんで、梯子段はしごだんを下りて来ると、下宿の御婆さんが心配さうに、「御休みなすつていらつしやいますか」と尋きいた。自分は「よく寝てゐます」とぶつきらぼうな返事をして、泣顔を見られるのが嫌だつたから、※(「勹<夕」、第3水準1-14-76)々そうそう凩の往来へ出た。往来は相不変あひかはらず、砂煙が空へ舞ひ上つてゐた。さうしてその空で、凄すさまじく何か唸るものがあつた。気になつたから上を見ると、唯、小さな太陽が、白く天心に動いてゐた。自分はアスフアルトの往来に立つた儘、どつちへ行かうかなと考へた。
齋藤孝のイッキによめる! 小学生のための芥川龍之介/講談社

¥1,080
Amazon.co.jp
古写本こしやほんの伝ふる所によれば、うるがんは織田信長おだのぶながの前で、自分が京都の町で見た悪魔の容子ようすを物語つた。それは人間の顔と蝙蝠かうもりの翼と山羊やぎの脚とを備へた、奇怪な小さい動物である。うるがんはこの悪魔が、或は塔の九輪くりんの上に手を拍うつて踊り、或は四よつ足門あしもんの屋根の下に日の光を恐れて蹲うづくまる恐しい姿を度々たびたび見た。いやそればかりではない。或時は山の法師はふしの背にしがみつき、或時は内うちの女房にようばうの髪にぶら下つてゐるのを見たと云ふ。
しかしそれらの悪魔の中で、最も我々に興味のあるものは、なにがしの姫君ひめぎみの輿こしの上に、あぐらをかいてゐたと云ふそれであらう。古写本こしやほんの作者は、この悪魔の話なるものをうるがんの諷諭ふうゆだと解してゐる。――信長が或時、その姫君に懸想けさうして、たつて自分の意に従はせようとした。が、姫君も姫君の双親ふたおやも、信長の望に応ずる事を喜ばない。そこでうるがんは姫君の為に、言を悪魔に藉かりて、信長の暴を諫いさめたのであらうと云ふのである。この解釈の当否は、元より今日こんにちに至つては、いづれとも決する事が容易でない。と同時に又我々にとつては、寧むしろいづれにせよ差支さしつかへのない問題である。
うるがんは或日の夕ゆふべ、南蛮寺なんばんじの門前で、その姫君の輿こしの上に、一匹の悪魔が坐つてゐるのを見た。が、この悪魔は外ほかのそれとは違つて、玉のやうに美しい顔を持つてゐる。しかもこまねいた両手と云ひ、うなだれた頭かしらと云ひ、恰あたかも何事かに深く思ひ悩んでゐるらしい。
うるがんは姫君の身を気づかつた。双親ふたおやと共に熱心な天主教てんしゆけうの信者である姫君が、悪魔に魅入みいられてゐると云ふ事は、唯事ただごとではないと思つたのである。そこでこの伴天連ばてれんは、輿こしの側へ近づくと、忽たちまち尊い十字架くるすの力によつて難なく悪魔を捕へてしまつた。さうしてそれを南蛮寺の内陣ないじんへ、襟がみをつかみながらつれて来た。
内陣には御主おんあるじ耶蘇ヤソ基督キリストの画像ぐわざうの前に、蝋燭らふそくの火が煤くすぶりながらともつてゐる。うるがんはその前に悪魔をひき据ゑて、何故なぜそれが姫君の輿の上に乗つてゐたか、厳しく仔細しさいを問ひただした。
「私わたくしはあの姫君ひめぎみを堕落させようと思ひました。が、それと同時に、堕落させたくないとも思ひました。あの清らかな魂たましひを見たものは、どうしてそれを地獄の火に穢けがす気がするでせう。私はその魂をいやが上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。が、さうと思へば思ふ程、愈いよいよ堕落させたいと云ふ心もちもして来ます。その二つの心もちの間あひだに迷ひながら、私はあの輿の上で、しみじみ私たちの運命を考へて居りました。もしさうでなかつたとしたら、あなたの影を見るより先に、恐らく地の底へでも姿を消して、かう云ふ憂うき目に遇あふ事は逃のがれてゐた事でせう。私たちは何時いつでもさうなのです。堕落させたくないもの程、益ますます堕落させたいのです。これ程不思議な悲しさが又と外ほかにありませうか。私はこの悲しさを味あじはふ度に、昔見た天国の朗ほがらかな光と、今見てゐる地獄のくら暗とが、私の小さな胸の中で一つになつてゐるやうな気がします。どうかさう云ふ私を憐んで下さい。私は寂しくつて仕方がありません。」
――- 美しい顔をした悪魔は、かう云つて、涙を流した。 ――
――- 古写本こしやほんの伝説は、この悪魔のなり行きを詳つまびらかにしてゐない。が、それは我々に何なんの関かかはりがあらう。我々はこれを読んだ時に、唯かう呼びかけたいやうな心もちを感じさへすれば好いいのである。 ――
うるがんよ。悪魔と共に我々を憐んでくれ。我々にも亦また、それと同じやうな悲しさがある。
(大正七年六月)
ザ・龍之介大活字版 [ 芥川龍之介 ]

¥2,052
楽天
支那シナの上海シャンハイの或ある町です。昼でも薄暗い或家の二階に、人相の悪い印度インド人の婆さんが一人、商人らしい一人の亜米利加アメリカ人と何か頻しきりに話し合っていました。
「実は今度もお婆さんに、占いを頼みに来たのだがね、――」
亜米利加人はそう言いながら、新しい巻煙草まきたばこへ火をつけました。
「占いですか? 占いは当分見ないことにしましたよ」
婆さんは嘲あざけるように、じろりと相手の顔を見ました。
「この頃は折角見て上げても、御礼さえ碌ろくにしない人が、多くなって来ましたからね」
「そりゃ勿論もちろん御礼をするよ」
亜米利加人は惜しげもなく、三百弗ドルの小切手を一枚、婆さんの前へ投げてやりました。
「差当りこれだけ取って置くさ。もしお婆さんの占いが当れば、その時は別に御礼をするから、――」
婆さんは三百弗の小切手を見ると、急に愛想あいそがよくなりました。
「こんなに沢山頂いては、反かえって御気の毒ですね。――そうして一体又あなたは、何を占ってくれろとおっしゃるんです?」
「私わたしが見て貰もらいたいのは、――」
亜米利加人は煙草を啣くわえたなり、狡猾こうかつそうな微笑を浮べました。
「一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんとわかっていれば、我々商人は忽たちまちの内に、大金儲おおがねもうけが出来るからね」
「じゃ明日あしたいらっしゃい。それまでに占って置いて上げますから」
「そうか。じゃ間違いのないように、――」
印度人の婆さんは、得意そうに胸を反そらせました。
「私の占いは五十年来、一度も外はずれたことはないのですよ。何しろ私のはアグニの神が、御自身御告げをなさるのですからね」
亜米利加人が帰ってしまうと、婆さんは次の間まの戸口へ行って、
「恵蓮えれん。恵蓮」と呼び立てました。
その声に応じて出て来たのは、美しい支那人の女の子です。が、何か苦労でもあるのか、この女の子の下しもぶくれの頬ほおは、まるで蝋ろうのような色をしていました。
「何を愚図々々ぐずぐずしているんだえ? ほんとうにお前位、ずうずうしい女はありゃしないよ。きっと又台所で居睡いねむりか何かしていたんだろう?」
恵蓮はいくら叱しかられても、じっと俯向うつむいたまま黙っていました。
「よくお聞きよ。今夜は久しぶりにアグニの神へ、御伺いを立てるんだからね、そのつもりでいるんだよ」
女の子はまっ黒な婆さんの顔へ、悲しそうな眼を挙あげました。
「今夜ですか?」
「今夜の十二時。好いいかえ? 忘れちゃいけないよ」
印度人の婆さんは、脅おどすように指を挙げました。
「又お前がこの間のように、私に世話ばかり焼かせると、今度こそお前の命はないよ。お前なんぞは殺そうと思えば、雛ひよっ仔この頸くびを絞めるより――」
こう言いかけた婆さんは、急に顔をしかめました。ふと相手に気がついて見ると、恵蓮はいつか窓際まどぎわに行って、丁度明いていた硝子ガラス窓から、寂しい往来を眺ながめているのです。
「何を見ているんだえ?」
恵蓮は愈いよいよ色を失って、もう一度婆さんの顔を見上げました。
「よし、よし、そう私を莫迦ばかにするんなら、まだお前は痛い目に会い足りないんだろう」
婆さんは眼を怒いからせながら、そこにあった箒ほうきをふり上げました。
丁度その途端です。誰か外へ来たと見えて、戸を叩たたく音が、突然荒々しく聞え始めました。
二
その日のかれこれ同じ時刻に、この家の外を通りかかった、年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか、二階の窓から顔を出した支那人の女の子を一目見ると、しばらくは呆気あっけにとられたように、ぼんやり立ちすくんでしまいました。
そこへ又通りかかったのは、年をとった支那人の人力車夫です。
「おい。おい。あの二階に誰が住んでいるか、お前は知っていないかね?」
日本人はその人力車夫へ、いきなりこう問いかけました。支那人は楫棒かじぼうを握ったまま、高い二階を見上げましたが、「あすこですか? あすこには、何とかいう印度人の婆さんが住んでいます」と、気味悪そうに返事をすると、匆々そうそう行きそうにするのです。
「まあ、待ってくれ。そうしてその婆さんは、何を商売にしているんだ?」
「占い者しゃです。が、この近所の噂うわさじゃ、何でも魔法さえ使うそうです。まあ、命が大事だったら、あの婆さんの所なぞへは行かない方が好よいようですよ」
支那人の車夫が行ってしまってから、日本人は腕を組んで、何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へはいって行きました。すると突然聞えて来たのは、婆さんの罵ののしる声に交った、支那人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、一股ひとまたに二三段ずつ、薄暗い梯子はしごを駈かけ上りました。そうして婆さんの部屋の戸を力一ぱい叩き出しました。
戸は直ぐに開きました。が、日本人が中へはいって見ると、そこには印度人の婆さんがたった一人立っているばかり、もう支那人の女の子は、次の間へでも隠れたのか、影も形も見当りません。
「何か御用ですか?」
婆さんはさも疑わしそうに、じろじろ相手の顔を見ました。
「お前さんは占い者だろう?」
日本人は腕を組んだまま、婆さんの顔を睨にらみ返しました。
「そうです」
「じゃ私の用なぞは、聞かなくてもわかっているじゃないか? 私も一つお前さんの占いを見て貰いにやって来たんだ」
「何を見て上げるんですえ?」
婆さんは益ますます疑わしそうに、日本人の容子ようすを窺うかがっていました。
「私の主人の御嬢さんが、去年の春行方ゆくえ知れずになった。それを一つ見て貰いたいんだが、――」
日本人は一句一句、力を入れて言うのです。
「私の主人は香港ホンコンの日本領事だ。御嬢さんの名は妙子たえこさんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが――どうだね? その御嬢さんはどこにいらっしゃる」
遠藤はこう言いながら、上衣うわぎの隠しに手を入れると、一挺ちょうのピストルを引き出しました。
「この近所にいらっしゃりはしないか? 香港の警察署の調べた所じゃ、御嬢さんを攫さらったのは、印度人らしいということだったが、――隠し立てをすると為ためにならんぞ」
しかし印度人の婆さんは、少しも怖こわがる気色けしきが見えません。見えないどころか唇くちびるには、反って人を莫迦にしたような微笑さえ浮べているのです。
「お前さんは何を言うんだえ? 私はそんな御嬢さんなんぞは、顔を見たこともありゃしないよ」
「嘘うそをつけ。今その窓から外を見ていたのは、確たしかに御嬢さんの妙子さんだ」
遠藤は片手にピストルを握ったまま、片手に次の間の戸口を指さしました。
「それでもまだ剛情を張るんなら、あすこにいる支那人をつれて来い」
「あれは私の貰い子だよ」
婆さんはやはり嘲るように、にやにや独ひとり笑っているのです。
「貰い子か貰い子でないか、一目見りゃわかることだ。貴様がつれて来なければ、おれがあすこへ行って見る」
遠藤が次の間へ踏みこもうとすると、咄嗟とっさに印度人の婆さんは、その戸口に立ち塞ふさがりました。
「ここは私の家うちだよ。見ず知らずのお前さんなんぞに、奥へはいられてたまるものか」
「退どけ。退かないと射殺うちころすぞ」
遠藤はピストルを挙げました。いや、挙げようとしたのです。が、その拍子に婆さんが、鴉からすの啼なくような声を立てたかと思うと、まるで電気に打たれたように、ピストルは手から落ちてしまいました。これには勇み立った遠藤も、さすがに胆きもをひしがれたのでしょう、ちょいとの間は不思議そうに、あたりを見廻していましたが、忽ち又勇気をとり直すと、
「魔法使め」と罵ののしりながら、虎とらのように婆さんへ飛びかかりました。
が、婆さんもさるものです。ひらりと身を躱かわすが早いか、そこにあった箒ほうきをとって、又掴つかみかかろうとする遠藤の顔へ、床ゆかの上の五味ごみを掃きかけました。すると、その五味が皆火花になって、眼といわず、口といわず、ばらばらと遠藤の顔へ焼きつくのです。
遠藤はとうとうたまり兼ねて、火花の旋風つむじかぜに追われながら、転ころげるように外へ逃げ出しました。
三
その夜よの十二時に近い時分、遠藤は独り婆さんの家の前にたたずみながら、二階の硝子窓に映る火影ほかげを口惜くやしそうに見つめていました。
「折角御嬢さんの在ありかをつきとめながら、とり戻すことが出来ないのは残念だな。一そ警察へ訴えようか? いや、いや、支那の警察が手ぬるいことは、香港でもう懲り懲りしている。万一今度も逃げられたら、又探すのが一苦労だ。といってあの魔法使には、ピストルさえ役に立たないし、――」
遠藤がそんなことを考えていると、突然高い二階の窓から、ひらひら落ちて来た紙切れがあります。
「おや、紙切れが落ちて来たが、――もしや御嬢さんの手紙じゃないか?」
こう呟つぶやいた遠藤は、その紙切れを、拾い上げながらそっと隠した懐中電燈を出して、まん円まるな光に照らして見ました。すると果して紙切れの上には、妙子が書いたのに違いない、消えそうな鉛筆の跡があります。
「遠藤サン。コノ家うちノオ婆サンハ、恐シイ魔法使デス。時々真夜中ニ私わたくしノ体ヘ、『アグニ』トイウ印度ノ神ヲ乗リ移ラセマス。私ハソノ神ガ乗リ移ッテイル間中、死ンダヨウニナッテイルノデス。デスカラドンナ事ガ起ルカ知リマセンガ、何デモオ婆サンノ話デハ、『アグニ』ノ神ガ私ノ口ヲ借リテ、イロイロ予言ヲスルノダソウデス。今夜モ十二時ニハオ婆サンガ又『アグニ』ノ神ヲ乗リ移ラセマス。イツモダト私ハ知ラズ知ラズ、気ガ遠クナッテシマウノデスガ、今夜ハソウナラナイ内ニ、ワザト魔法ニカカッタ真似まねヲシマス。ソウシテ私ヲオ父様ノ所ヘ返サナイト『アグニ』ノ神ガオ婆サンノ命ヲトルト言ッテヤリマス。オ婆サンハ何ヨリモ『アグニ』ノ神ガ怖こわイノデスカラ、ソレヲ聞ケバキット私ヲ返スダロウト思イマス。ドウカ明日あしたノ朝モウ一度、オ婆サンノ所ヘ来テ下サイ。コノ計略ノ外ほかニハオ婆サンノ手カラ、逃ゲ出スミチハアリマセン。サヨウナラ」
遠藤は手紙を読み終ると、懐中時計を出して見ました。時計は十二時五分前です。
「もうそろそろ時刻になるな、相手はあんな魔法使だし、御嬢さんはまだ子供だから、余程運が好くないと、――」
遠藤の言葉が終らない内に、もう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった二階の窓は、急にまっ暗になってしまいました。と同時に不思議な香こうの匂においが、町の敷石にも滲しみる程、どこからか静しずかに漂って来ました。
四
その時あの印度人の婆さんは、ランプを消した二階の部屋の机に、魔法の書物を拡ひろげながら、頻しきりに呪文じゅもんを唱えていました。書物は香炉の火の光に、暗い中でも文字だけは、ぼんやり浮き上らせているのです。
婆さんの前には心配そうな恵蓮が、――いや、支那服を着せられた妙子が、じっと椅子に坐っていました。さっき窓から落した手紙は、無事に遠藤さんの手へはいったであろうか? あの時往来にいた人影は、確に遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったであろうか?――そう思うと妙子は、いても立ってもいられないような気がして来ます。しかし今うっかりそんな気けぶりが、婆さんの眼にでも止まったが最後、この恐しい魔法使いの家から、逃げ出そうという計略は、すぐに見破られてしまうでしょう。ですから妙子は一生懸命に、震える両手を組み合せながら、かねてたくんで置いた通り、アグニの神が乗り移ったように、見せかける時の近づくのを今か今かと待っていました。
婆さんは呪文を唱えてしまうと、今度は妙子をめぐりながら、いろいろな手ぶりをし始めました。或時は前へ立ったまま、両手を左右に挙げて見せたり、又或時は後へ来て、まるで眼かくしでもするように、そっと妙子の額の上へ手をかざしたりするのです。もしこの時部屋の外から、誰か婆さんの容子を見ていたとすれば、それはきっと大きな蝙蝠こうもりか何かが、蒼白あおじろい香炉の火の光の中に、飛びまわってでもいるように見えたでしょう。
その内に妙子はいつものように、だんだん睡気ねむけがきざして来ました。が、ここで睡ってしまっては、折角の計略にかけることも、出来なくなってしまう道理です。そうしてこれが出来なければ、勿論二度とお父さんの所へも、帰れなくなるのに違いありません。
「日本の神々様、どうか私わたしが睡らないように、御守りなすって下さいまし。その代り私はもう一度、たとい一目でもお父さんの御顔を見ることが出来たなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかお婆さんを欺だませるように、御力を御貸し下さいまし」
妙子は何度も心の中に、熱心に祈りを続けました。しかし睡気はおいおいと、強くなって来るばかりです。と同時に妙子の耳には、丁度銅鑼どらでも鳴らすような、得体の知れない音楽の声が、かすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が、空から降りて来る時に、きっと聞える声なのです。
もうこうなってはいくら我慢しても、睡らずにいることは出来ません。現に目の前の香炉の火や、印度人の婆さんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるように、見る見る消え失うせてしまうのです。
「アグニの神、アグニの神、どうか私わたしの申すことを御聞き入れ下さいまし」
やがてあの魔法使いが、床の上にひれ伏したまま、嗄しわがれた声を挙げた時には、妙子は椅子に坐りながら、殆ほとんど生死も知らないように、いつかもうぐっすり寝入っていました。
五
妙子は勿論婆さんも、この魔法を使う所は、誰の眼にも触れないと、思っていたのに違いありません。しかし実際は部屋の外に、もう一人戸の鍵穴かぎあなから、覗のぞいている男があったのです。それは一体誰でしょうか?――言うまでもなく、書生の遠藤です。
遠藤は妙子の手紙を見てから、一時は往来に立ったなり、夜明けを待とうかとも思いました。が、お嬢さんの身の上を思うと、どうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう盗人ぬすびとのように、そっと家の中へ忍びこむと、早速この二階の戸口へ来て、さっきから透き見をしていたのです。
しかし透き見をすると言っても、何しろ鍵穴を覗くのですから、蒼白い香炉の火の光を浴びた、死人のような妙子の顔が、やっと正面に見えるだけです。その外ほかは机も、魔法の書物も、床にひれ伏した婆さんの姿も、まるで遠藤の眼にははいりません。しかし嗄しわがれた婆さんの声は、手にとるようにはっきり聞えました。
「アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことを御聞き入れ下さいまし」
婆さんがこう言ったと思うと、息もしないように坐っていた妙子は、やはり眼をつぶったまま、突然口を利きき始めました。しかもその声がどうしても、妙子のような少女とは思われない、荒々しい男の声なのです。
「いや、おれはお前の願いなぞは聞かない。お前はおれの言いつけに背そむいて、いつも悪事ばかり働いて来た。おれはもう今夜限り、お前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている」
婆さんは呆気あっけにとられたのでしょう。暫くは何とも答えずに、喘あえぐような声ばかり立てていました。が、妙子は婆さんに頓着とんじゃくせず、おごそかに話し続けるのです。
「お前は憐あわれな父親の手から、この女の子を盗んで来た。もし命が惜しかったら、明日あすとも言わず今夜の内に、早速この女の子を返すが好よい」
遠藤は鍵穴に眼を当てたまま、婆さんの答を待っていました。すると婆さんは驚きでもするかと思いの外ほか、憎々しい笑い声を洩もらしながら、急に妙子の前へ突っ立ちました。
「人を莫迦ばかにするのも、好いい加減におし。お前は私を何だと思っているのだえ。私はまだお前に欺される程、耄碌もうろくはしていない心算つもりだよ。早速お前を父親へ返せ――警察の御役人じゃあるまいし、アグニの神がそんなことを御言いつけになってたまるものか」
婆さんはどこからとり出したか、眼をつぶった妙子の顔の先へ、一挺のナイフを突きつけました。
「さあ、正直に白状おし。お前は勿体もったいなくもアグニの神の、声色こわいろを使っているのだろう」
さっきから容子を窺っていても、妙子が実際睡っていることは、勿論遠藤にはわかりません。ですから遠藤はこれを見ると、さては計略が露顕したかと思わず胸を躍おどらせました。が、妙子は相変らず目蓋まぶた一つ動かさず、嘲笑あざわらうように答えるのです。
「お前も死に時が近づいたな。おれの声がお前には人間の声に聞えるのか。おれの声は低くとも、天上に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか。わからなければ、勝手にするが好いい。おれは唯ただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、それともおれの言いつけに背くか――」
婆さんはちょいとためらったようです。が、忽ち勇気をとり直すと、片手にナイフを握りながら、片手に妙子の襟髪えりがみを掴つかんで、ずるずる手もとへ引き寄せました。
「この阿魔あまめ。まだ剛情を張る気だな。よし、よし、それなら約束通り、一思いに命をとってやるぞ」
婆さんはナイフを振り上げました。もう一分間遅れても、妙子の命はなくなります。遠藤は咄嗟とっさに身を起すと、錠のかかった入口の戸を無理無体に明けようとしました。が、戸は容易に破れません。いくら押しても、叩いても、手の皮が摺すり剥むけるばかりです。
六
その内に部屋の中からは、誰かのわっと叫ぶ声が、突然暗やみに響きました。それから人が床の上へ、倒れる音も聞えたようです。遠藤は殆ど気違いのように、妙子の名前を呼びかけながら、全身の力を肩に集めて、何度も入口の戸へぶつかりました。
板の裂ける音、錠のはね飛ぶ音、――戸はとうとう破れました。しかし肝腎かんじんの部屋の中は、まだ香炉に蒼白い火がめらめら燃えているばかり、人気ひとけのないようにしんとしています。
遠藤はその光を便りに、怯おず怯ずあたりを見廻しました。
するとすぐに眼にはいったのは、やはりじっと椅子にかけた、死人のような妙子です。それが何故なぜか遠藤には、頭かしらに毫光ごこうでもかかっているように、厳おごそかな感じを起させました。
「御嬢さん、御嬢さん」
遠藤は椅子へ行くと、妙子の耳もとへ口をつけて、一生懸命に叫び立てました。が、妙子は眼をつぶったなり、何とも口を開きません。
「御嬢さん。しっかりおしなさい。遠藤です」
妙子はやっと夢がさめたように、かすかな眼を開きました。
「遠藤さん?」
「そうです。遠藤です。もう大丈夫ですから、御安心なさい。さあ、早く逃げましょう」
妙子はまだ夢現ゆめうつつのように、弱々しい声を出しました。
「計略は駄目だったわ。つい私が眠ってしまったものだから、――堪忍かんにんして頂戴よ」
「計略が露顕したのは、あなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神の憑かかった真似まねをやり了おおせたじゃありませんか?――そんなことはどうでも好いいことです。さあ、早く御逃げなさい」
遠藤はもどかしそうに、椅子から妙子を抱き起しました。
「あら、嘘うそ。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか、知りはしないわ」
妙子は遠藤の胸に凭もたれながら、呟つぶやくようにこう言いました。
「計略は駄目だったわ。とても私は逃げられなくってよ」
「そんなことがあるものですか。私と一しょにいらっしゃい。今度しくじったら大変です」
「だってお婆さんがいるでしょう?」
「お婆さん?」
遠藤はもう一度、部屋の中を見廻しました。机の上にはさっきの通り、魔法の書物が開いてある、――その下へ仰向あおむきに倒れているのは、あの印度人の婆さんです。婆さんは意外にも自分の胸へ、自分のナイフを突き立てたまま、血だまりの中に死んでいました。
「お婆さんはどうして?」
「死んでいます」
妙子は遠藤を見上げながら、美しい眉をひそめました。
「私、ちっとも知らなかったわ。お婆さんは遠藤さんが――あなたが殺してしまったの?」
遠藤は婆さんの屍骸しがいから、妙子の顔へ眼をやりました。今夜の計略が失敗したことが、――しかしその為に婆さんも死ねば、妙子も無事に取り返せたことが、――運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にもわかったのは、この瞬間だったのです。
「私が殺したのじゃありません。あの婆さんを殺したのは今夜ここへ来たアグニの神です」
遠藤は妙子を抱かかえたまま、おごそかにこう囁ささやきました。
齋藤孝のイッキによめる! 小学生のための芥川龍之介/講談社

¥1,080
Amazon.co.jp
やはらかく深紫の天鵞絨ビロウドをなづる心地か春の暮れゆく
いそいそと燕もまへりあたゝかく郵便馬車をぬらす春雨
ほの赤く岐阜提灯もともりけり「二つ巴」の春の夕ぐれ(明治座三月狂言)
戯奴ジヨーカーの紅き上衣に埃の香かすかにしみて春はくれにけり
なやましく春は暮れゆく踊り子の金紗の裾に春は暮れゆく
春漏の水のひゞきかあるはまた舞姫のうつとほき鼓か(京都旅情)
片恋のわが世さみしくヒヤシンスうすむらさきににほひそめけり
恋すればうら若ければかばかりに薔薇さうびの香にもなみだするらむ
麦畑の萌黄天鵞絨芥子けしの花五月の空にそよ風のふく
五月来ぬわすれな草もわが恋も今しほのかににほひづるらむ
刈麦のにほひに雲もうす黄なる野薔薇のかげの夏の日の恋
うかれ女のうすき恋よりかきつばたうす紫に匂ひそめけむ
桐 (To Signorina Y. Y.)
君をみていくとせかへしかくてまた桐の花さく日とはなりける
君とふとかよひなれにしあけくれをいくたびふみし落椿ぞも
広重のふるき版画のてざはりもわすれがたかり君とみればか
いつとなくいとけなき日のかなしみをわれにおしへし桐の花はも
病室のまどにかひたる紅き鳥しきりになきて君おもはする
夕さればあたごホテルも灯ともしぬわがかなしみをめざまさむとて
草いろの帷とばりのかげに灯ともしてなみだする子よ何をおもへる
くすり香もつめたくしむは病室の窓にさきたる※(「さんずい+自」、第3水準1-86-66)芙藍サフランの花
青チヨオク ADIEU と壁にかきすてゝ出でゆきし子のゆくゑしらずも
その日さりて消息もなくなりにたる風騒ふうそうの子をとがめたまひそ
いととほき花桐の香のそことなくおとづれくるをいかにせましや
(四・九・一四)
薔薇
すがれたる薔薇さうびをまきておくるこそふさはしからむ恋の逮夜は
香料をふりそゝぎたるふし床より恋の柩にしくものはなし
にほひよき絹の小枕クツサン薔薇色の羽ねぶとんもてきづかれし墓
夜あくれば行路の人となりぬべきわれらぞさはな泣きそ女よ
其夜より娼婦の如くなまめける人となりしをいとふのみかは
わが足に膏あぶらそゝがむ人もがなそを黒髪にぬぐふ子もがな(寺院にて三首)
ほのぐらきわがたましひの黄昏をかすかにともる黄蝋もあり
うなだれて白夜の市をあゆむ時聖金曜の鐘のなる時
ほのかなる麝香じやかうの風のわれにふく紅燈集の中の国より
かりそめの涙なれどもよりそひて泣けばぞ恋のごとくかなしき
うす黄なる寝台の幕のものうくもゆらげるまゝに秋は来にけむ
薔薇よさはにほひな出でそあかつきの薄らあかりに泣く女あり
(九・六・一四)
客中恋
初夏の都大路の夕あかりふたゝび君とゆくよしもがな
海は今青き※(「目+匡」、第3水準1-88-81)をしばたゝき静に夜を待てるならじか
君が家の緋の房長き燈籠も今かほのかに灯しするらむ
都こそかゝる夕はしのばるれ愛宕ほてるも灯をやともすと
黒船のとほき灯にさへ若人は涙落しぬ恋の如くに
幾山河さすらふよりもかなしきは都大路をひとり行くこと
憂しや恋ろまんちつくの少年は日ねもすひとり涙流すも
かなしみは君がしめたる其宵の印度更紗いんどさらさの帯よりや来し
二日月君が小指の爪よりもほのかにさすはあはれなるかな
何をかもさは歎くらむ旅人よ蜜柑畑の棚によりつゝ
ともしびも雨にぬれたる甃石しきいしも君送る夜はあはれふかゝり
ときすてし絽の夏帯の水あさぎなまめくまゝに夏や往にけむ
若人 (旋頭歌)
うら若き都人こそかなしかりけれ。失ひし夢を求むと市まちを歩める。
橡マロニエの花もひそかにさけるならじか。夢未多かりし日を思ひ出でよと。
たはれ女のうつゝ無げにも青みたる眼か。かはたれの空に生まるゝ二日の月か。
しのびかに黒髪の子の泣く音きこゆる。初恋のありとも見えぬ薄ら明りに。
さばかりにおもはゆげにもいらへ給ひそ。緋の房の長き団扇にかくれ給ひそ。
なつかしき人形町の二日月はも。若う人の涙を誘ふ二日月はも。
いとせめて泣くべく人を恋ひもこそすれ。黄蝋の涙おとすと燃ゆる如くに。
湯沸器サモワルの湯気もほのかにもの思ふらし。我友の西鶴めきし恋語りより。(Kに)
ほゝけたる花ふり落す大川楊おほかはやなぎ。水にしも恋やするらむ大川楊。
香油よりつめたき雨にひたもぬれつゝ。たそがれの銀座通をゆくは誰が子ぞ。
恋すてふ戯れすなる若き道化は。かりそめの涙おとすを常とするかも。
何時となく恋もものうくなりにけらしな。移り香の(憂しや)つめたくなりまさる如。
砂上遅日
うつゝなきまひるのうみは砂のむた雲母きらゝのごとくまばゆくもあるか
八百日ゆく遠の渚は銀泥ぎんでいの水ぬるませて日にかゞやくも
きらゝかにこゝだ身動みぢろぐいさゝ波砂に消けなむとするいさゝ波
いさゝ波生あれも出でねと高天たかあめゆ光はちゞにふれり光は
光輪くわうりんは空にきはなしその空の下につどへる蜑あま少女はも
むらがれる海女あまらことごと恥なしと空はもだしてかゞやけるかも
うつそみの女人眠るとまかゞよふ巨海こかいは息をひそむらむかも
荘厳しやうごんの光の下にまどろめる女人の乳こそくろみたりしか
いさゝ波かゞよふきはみはろばろと弘法麦の葉は照りゆらぎ
きらゝ雲むかぶすきはみはろばろと弘法麦の葉は照りゆらぎ
雲の影おつるすなはちふかぶかと弘法麦は青みふすかも
雲の影さかるすなはちはろばろと弘法麦の葉は照りゆらぎ
羅生門・鼻 (新潮文庫)/新潮社

¥400
Amazon.co.jp
信子は女子大学にゐた時から、才媛さいゑんの名声を担になつてゐた。彼女が早晩作家として文壇に打つて出る事は、殆ほとんど誰も疑はなかつた。中には彼女が在学中、既に三百何枚かの自叙伝体小説を書き上げたなどと吹聴ふいちやうして歩くものもあつた。が、学校を卒業して見ると、まだ女学校も出てゐない妹の照子と彼女とを抱へて、後家ごけを立て通して来た母の手前も、さうは我儘わがままを云はれない、複雑な事情もないではなかつた。そこで彼女は創作を始める前に、まづ世間の習慣通り、縁談からきめてかかるべく余儀なくされた。
彼女には俊吉しゆんきちと云ふ従兄いとこがあつた。彼は当時まだ大学の文科に籍を置いてゐたが、やはり将来は作家仲間に身を投ずる意志があるらしかつた。信子はこの従兄の大学生と、昔から親しく往来してゐた。それが互に文学と云ふ共通の話題が出来てからは、愈いよいよ親しみが増したやうであつた。唯、彼は信子と違つて、当世流行のトルストイズムなどには一向敬意を表さなかつた。さうして始終フランス仕込みの皮肉や警句ばかり並べてゐた。かう云ふ俊吉の冷笑的な態度は、時々万事真面目な信子を怒らせてしまふ事があつた。が、彼女は怒りながらも俊吉の皮肉や警句の中に、何か軽蔑けいべつ出来ないものを感じない訳には行かなかつた。
だから彼女は在学中も、彼と一しよに展覧会や音楽会へ行く事が稀ではなかつた。尤もつとも大抵そんな時には、妹の照子も同伴いつしよであつた。彼等三人は行きも返りも、気兼ねなく笑つたり話したりした。が、妹の照子だけは、時々話の圏外へ置きざりにされる事もあつた。それでも照子は子供らしく、飾窓の中のパラソルや絹のシヨオルを覗き歩いて、格別閑却された事を不平に思つてもゐないらしかつた。信子はしかしそれに気がつくと、必かならず話頭を転換して、すぐに又元の通り妹にも口をきかせようとした。その癖まづ照子を忘れるものは、何時いつも信子自身であつた。俊吉はすべてに無頓着なのか、不相変あひかはらず気の利いた冗談じようだんばかり投げつけながら、目まぐるしい往来の人通りの中を、大股にゆつくり歩いて行つた。……
信子と従兄との間がらは、勿論誰の眼に見ても、来るべき彼等の結婚を予想させるのに十分であつた。同窓たちは彼女の未来をてんでに羨んだり妬ねたんだりした。殊に俊吉を知らないものは、(滑稽と云ふより外はないが、)一層これが甚はなはだしかつた。信子も亦一方では彼等の推測を打ち消しながら、他方ではその確な事をそれとなく故意に仄ほのめかせたりした。従つて同窓たちの頭の中には、彼等が学校を出るまでの間に、何時か彼女と俊吉との姿が、恰あたかも新婦新郎の写真の如く、一しよにはつきり焼きつけられてゐた。
所が学校を卒業すると、信子は彼等の予期に反して、大阪の或商事会社へ近頃勤務する事になつた、高商出身の青年と、突然結婚してしまつた。さうして式後二三日してから、新夫と一しよに勤め先きの大阪へ向けて立つてしまつた。その時中央停車場へ見送りに行つたものの話によると、信子は何時いつもと変りなく、晴れ晴れした微笑を浮べながら、ともすれば涙を落し勝ちな妹の照子をいろいろと慰めてゐたと云ふ事であつた。
同窓たちは皆不思議がつた。その不思議がる心の中には、妙に嬉しい感情と、前とは全然違つた意味で妬ましい感情とが交つてゐた。或者は彼女を信頼して、すべてを母親の意志に帰した。又或ものは彼女を疑つて、心がはりがしたとも云ひふらした。が、それらの解釈が結局想像に過ぎない事は、彼等自身さへ知らない訳ではなかつた。彼女はなぜ俊吉と結婚しなかつたか? 彼等はその後暫くの間、よるとさはると重大らしく、必かならずこの疑問を話題にした。さうして彼是かれこれ二月ばかり経つと――全く信子を忘れてしまつた。勿論彼女が書く筈だつた長篇小説の噂なぞも。
信子はその間に大阪の郊外へ、幸福なるべき新家庭をつくつた。彼等の家はその界隈かいわいでも最も閑静な松林にあつた。松脂まつやにの匂と日の光と、――それが何時でも夫の留守は、二階建の新しい借家の中に、活いき活きした沈黙を領してゐた。信子はさう云ふ寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと、きつと針箱の引出しを開けては、その底に畳んでしまつてある桃色の書簡箋をひろげて見た、書簡箋の上にはこんな事が、細々とペンで書いてあつた。
「――もう今日かぎり御姉様と御一しよにゐる事が出来ないと思ふと、これを書いてゐる間でさへ、止め度なく涙が溢れて来ます。御姉様。どうか、どうか私を御赦おゆるし下さい。照子は勿体ない御姉様の犠牲の前に、何と申し上げて好いかもわからずに居ります。
「御姉様は私の為に、今度の御縁談を御きめになりました。さうではないと仰有おつしやつても、私にはよくわかつて居ります。何時ぞや御一しよに帝劇を見物した晩、御姉様は私に俊さんは好きかと御尋おききになりました。それから又好きならば、御姉様がきつと骨を折るから、俊さんの所へ行けとも仰有いました。あの時もう御姉様は、私が俊さんに差上げる筈の手紙を読んでいらしつたのでせう。あの手紙がなくなつた時、ほんたうに私は御姉様を御恨おうらめしく思ひました。(御免遊ばせ。この事だけでも私はどの位申し訳がないかわかりません。)ですからその晩も私には、御姉様の親切な御言葉も、皮肉のやうな気さへ致しました。私が怒つて御返事らしい御返事も碌ろくに致さなかつた事は、もちろん御忘れになりもなさりますまい。けれどもあれから二三日経つて、御姉様の御縁談が急にきまつてしまつた時、私はそれこそ死んででも、御詫び[#「御詫び」は底本では「御詑び」]をしようかと思ひました。御姉様も俊さんが御好きなのでございますもの。(御隠しになつてはいや。私はよく存じて居りましてよ。)私の事さへ御かまひにならなければ、きつと御自分が俊さんの所へいらしつたのに違ひございません。それでも御姉様は私に、俊さんなぞは思つてゐないと、何度も繰返して仰有いました。さうしてとうとう心にもない御結婚をなすつて御しまひになりました。私の大事な御姉様。私が今日鶏を抱いて来て、大阪へいらつしやる御姉様に、御挨拶をなさいと申した事をまだ覚えていらしつて?
私は飼つてゐる鶏にも、私と一しよに御姉様へ御詫び[#「御詫び」は底本では「御詑び」]を申して貰ひたかつたの。さうしたら、何にも御存知ない御母様まで御泣きになりましたのね。
「御姉様。もう明日は大阪へいらしつて御しまひなさるでせう。けれどもどうか何時までも、御姉様の照子を見捨てずに頂戴、照子は毎朝鶏に餌をやりながら、御姉様の事を思ひ出して、誰にも知れず泣いてゐます。……」
信子はこの少女らしい手紙を読む毎に、必かならず涙が滲にじんで来た。殊に中央停車場から汽車に乗らうとする間際、そつとこの手紙を彼女に渡した照子の姿を思ひ出すと、何とも云はれずにいぢらしかつた。が、彼女の結婚は果して妹の想像通り、全然犠牲的なそれであらうか。さう疑を挾む事は、涙の後の彼女の心へ、重苦しい気持ちを拡げ勝ちであつた。信子はこの重苦しさを避ける為に、大抵はぢつと快い感傷の中に浸つてゐた。そのうちに外の松林へ一面に当つた日の光が、だんだん黄ばんだ暮方の色に変つて行くのを眺めながら。
二
結婚後彼是かれこれ三月ばかりは、あらゆる新婚の夫婦の如く、彼等も亦幸福な日を送つた。
夫は何処どこか女性的な、口数を利きかない人物であつた。それが毎日会社から帰つて来ると、必晩飯後の何時間かは、信子と一しよに過す事にしてゐた。信子は編物の針を動かしながら、近頃世間に騒がれてゐる小説や戯曲の話などもした。その話の中には時によると、基督教キリストけうの匂のする女子大学趣味の人生観が織りこまれてゐる事もあつた。夫は晩酌の頬を赤らめた儘、読みかけた夕刊を膝へのせて、珍しさうに耳を傾けてゐた。が、彼自身の意見らしいものは、一言も加へた事がなかつた。
彼等は又殆ほとんど日曜毎に、大阪やその近郊の遊覧地へ気散じな一日を暮しに行つた。信子は汽車電車へ乗る度に、何処でも飲食する事を憚はばからない関西人が皆卑しく見えた。それだけおとなしい夫の態度が、格段に上品なのを嬉しく感じた。実際身綺麗な夫の姿は、そう云ふ人中に交つてゐると、帽子からも、背広からも、或は又赤皮の編上げからも、化粧石鹸の匂に似た、一種清新な雰囲気ふんゐきを放散させてゐるやうであつた。殊に夏の休暇中、舞子まひこまで足を延した時には、同じ茶屋に来合せた夫の同僚たちに比べて見て、一層誇りがましいやうな心もちがせずにはゐられなかつた。が、夫はその下卑げびた同僚たちに、存外親しみを持つてゐるらしかつた。
その内に信子は長い間、捨ててあつた創作を思ひ出した。そこで夫の留守の内だけ、一二時間づつ机に向ふ事にした。夫はその話を聞くと、「愈いよいよ女流作家になるかね。」と云つて、やさしい口もとに薄笑ひを見せた。しかし机には向ふにしても、思ひの外ペンは進まなかつた。彼女はぼんやり頬杖をついて、炎天の松林の蝉の声に、我知れず耳を傾けてゐる彼女自身を見出し勝ちであつた。
所が残暑が初秋へ振り変らうとする時分、夫は或日会社の出がけに、汗じみた襟を取変へようとした。が、生憎あいにく襟は一本残らず洗濯屋の手に渡つてゐた。夫は日頃身綺麗なだけに、不快らしく顔を曇らせた。さうしてズボン吊を掛けながら、「小説ばかり書いてゐちや困る。」と何時になく厭味を云つた。信子は黙つて眼を伏せて、上衣の埃を払つてゐた。
それから二三日過ぎた或夜、夫は夕刊に出てゐた食糧問題から、月々の経費をもう少し軽減出来ないものかと云ひ出した。「お前だつて何時までも女学生ぢやあるまいし。」――そんな事も口へ出した。信子は気のない返事をしながら、夫の襟飾の絽刺ろざしをしてゐた。すると夫は意外な位執拗に、「その襟飾にしてもさ、買ふ方が反かへつて安くつくぢやないか。」と、やはりねちねちした調子で云つた。彼女は猶更なほさら口が利けなくなつた。夫もしまひには白けた顔をして、つまらなさうに商売向きの雑誌か何かばかり読んでゐた。が、寝室の電燈を消してから、信子は夫に背を向けた儘、「もう小説なんぞ書きません。」と、囁くやうな声で云つた。夫はそれでも黙つてゐた。暫くして彼女は、同じ言葉を前よりもかすかに繰返した。それから間もなく泣く声が洩れた。夫は二言三言彼女を叱つた。その後でも彼女の啜泣すすりなきは、まだ絶え絶えに聞えてゐた。が、信子は何時の間にか、しつかりと夫にすがつてゐた。……
翌日彼等は又元の通り、仲の好い夫婦に返つてゐた。
と思ふと今度は十二時過ぎても、まだ夫が会社から帰つて来ない晩があつた。しかも漸やうやく帰つて来ると、雨外套あまぐわいたうも一人では脱げない程、酒臭い匂を呼吸してゐた。信子は眉をひそめながら、甲斐甲斐かひがひしく夫に着換へさせた。夫はそれにも関らず、まはらない舌で皮肉さへ云つた。「今夜は僕が帰らなかつたから、余つ程小説が捗取はかどつたらう。」――さう云ふ言葉が、何度となく女のやうな口から出た。彼女はその晩床にはいると、思はず涙がほろほろ落ちた。こんな処を照子が見たら、どんなに一しよに泣いてくれるであらう。照子。照子。私が便りに思ふのは、たつたお前一人ぎりだ。――信子は度々心の中でかう妹に呼びかけながら、夫の酒臭い寝息に苦しまされて、殆ほとんど夜中まんじりともせずに、寝返りばかり打つてゐた。
が、それも亦翌日になると、自然と仲直りが出来上つてゐた。
そんな事が何度か繰返される内に、だんだん秋が深くなつて来た。信子は何時か机に向つて、ペンを執る事が稀になつた。その時にはもう夫の方も、前程彼女の文学談を珍しがらないやうになつてゐた。彼等は夜毎に長火鉢を隔てて、瑣末さまつな家庭の経済の話に時間を殺す事を覚え出した。その上又かう云ふ話題は、少くとも晩酌後の夫にとつて、最も興味があるらしかつた。それでも信子は気の毒さうに、時々夫の顔色を窺うかがつて見る事があつた。が、彼は何も知らず、近頃延した髭を噛みながら、何時もより余程快活に、「これで子供でも出来て見ると――」なぞと、考へ考へ話してゐた。
するとその頃から月々の雑誌に、従兄いとこの名前が見えるやうになつた。信子は結婚後忘れたやうに、俊吉との文通を絶つてゐた。唯、彼の動静は、――大学の文科を卒業したとか、同人雑誌を始めたとか云ふ事は、妹から手紙で知るだけであつた。又それ以上彼の事を知りたいと云ふ気も起さなかつた。が、彼の小説が雑誌に載つてゐるのを見ると、懐しさは昔と同じであつた。彼女はその頁をはぐりながら、何度も独り微笑を洩らした。俊吉はやはり小説の中でも、冷笑と諧謔かいぎやくとの二つの武器を宮本武蔵のやうに使つてゐた。彼女にはしかし気のせゐか、その軽快な皮肉の後うしろに、何か今までの従兄にはない、寂しさうな捨鉢すてばちの調子が潜んでゐるやうに思はれた。と同時にさう思ふ事が、後めたいやうな気もしないではなかつた。
信子はそれ以来夫に対して、一層優しく振舞ふやうになつた。夫は夜寒の長火鉢の向うに、何時も晴れ晴れと微笑してゐる彼女の顔を見出した。その顔は以前より若々しく、化粧をしてゐるのが常であつた。彼女は針仕事の店を拡げながら、彼等が東京で式を挙げた当時の記憶なぞも話したりした。夫にはその記憶の細かいのが、意外でもあり、嬉しさうでもあつた。「お前はよくそんな事まで覚えてゐるね。」――夫にかう調戯からかはれると、信子は必かならず無言の儘、眼にだけ媚こびのある返事を見せた。が、何故それ程忘れずにゐるか、彼女自身も心の内では、不思議に思ふ事が度々あつた。
それから程なく、母の手紙が、信子に妹の結納ゆひなふが済んだと云ふ事を報じて来た。その手紙の中には又、俊吉が照子を迎へる為に、山の手の或郊外へ新居を設けた事もつけ加へてあつた。彼女は早速母と妹とへ、長い祝ひの手紙を書いた。「何分当方は無人故、式には不本意ながら参りかね候へども……」そんな文句を書いてゐる内に、(彼女には何故かわからなかつたが、)筆の渋る事も再三あつた。すると彼女は眼を挙げて、必かならず外の松林を眺めた。松は初冬の空の下に、簇々そうそうと蒼黒く茂つてゐた。
その晩信子と夫とは、照子の結婚を話題にした。夫は何時もの薄笑ひを浮べながら、彼女が妹の口真似をするのを、面白さうに聞いてゐた。が、彼女には何となく、彼女自身に照子の事を話してゐるやうな心もちがした。「どれ、寝るかな。」――二三時間の後、夫は柔やはらかな髭を撫でながら、大儀さうに長火鉢の前を離れた。信子はまだ妹へ祝つてやる品を決し兼ねて、火箸で灰文字を書いてゐたが、この時急に顔を挙げて、「でも妙なものね、私にも弟が一人出来るのだと思ふと。」と云つた。「当り前ぢやないか、妹もゐるんだから。」――彼女は夫にかう云はれても、考深い眼つきをした儘、何とも返事をしなかつた。
照子と俊吉とは、師走しはすの中旬に式を挙げた。当日は午ひる少し前から、ちらちら白い物が落ち始めた。信子は独り午の食事をすませた後、何時までもその時の魚の匂が、口について離れなかつた。「東京も雪が降つてゐるかしら。」――こんな事を考へながら、信子はぢつとうす暗い茶の間の長火鉢にもたれてゐた。雪が愈いよいよ烈しくなつた。が、口中の生臭さは、やはり執念しふねく消えなかつた。……
三
信子はその翌年の秋、社命を帯びた夫と一しよに、久しぶりで東京の土を踏んだ。が、短い日限内に、果すべき用向きの多かつた夫は、唯彼女の母親の所へ、来き※(「勹<夕」、第3水準1-14-76)々そうそう顔を出した時の外は、殆一日も彼女をつれて、外出する機会を見出さなかつた。彼女はそこで妹夫婦の郊外の新居を尋ねる時も、新開地じみた電車の終点から、たつた一人俥くるまに揺られて行つた。
彼等の家は、町並が葱畑ねぎばたけに移る近くにあつた。しかし隣近所には、いづれも借家らしい新築が、せせこましく軒を並べてゐた。のき打ちの門、要かなめもちの垣、それから竿に干した洗濯物、――すべてがどの家も変りはなかつた。この平凡な住居すまひの容子ようすは、多少信子を失望させた。
が、彼女が案内を求めた時、声に応じて出て来たのは、意外にも従兄の方であつた。俊吉は以前と同じやうに、この珍客の顔を見ると、「やあ。」と快活な声を挙げた。彼女は彼が何時の間にか、いが栗頭でなくなつたのを見た。「暫らく。」「さあ、御上り。生憎あいにく僕一人だが。」「照子は? 留守?」「使に行つた。女中も。」――信子は妙に恥しさを感じながら、派手な裏のついた上衣コオトをそつと玄関の隅に脱いだ。
俊吉は彼女を書斎兼客間の八畳へ坐らせた。座敷の中には何処を見ても、本ばかり乱雑に積んであつた。殊に午後の日の当つた障子際の、小さな紫檀したんの机のまはりには、新聞雑誌や原稿用紙が、手のつけやうもない程散らかつてゐた。その中に若い細君の存在を語つてゐるものは、唯床の間の壁に立てかけた、新しい一面の琴だけであつた。信子はかう云ふ周囲から、暫らく物珍しい眼を離さなかつた。
「来ることは手紙で知つてゐたけれど、今日来ようとは思はなかつた。」――俊吉は巻煙草へ火をつけると、さすがに懐しさうな眼つきをした。「どうです、大阪の御生活は?」「俊さんこそ如何いかが? 幸福?」――-信子も亦二言三言話す内に、やはり昔のやうな懐しさが、よみ返つて来るのを意識した。文通さへ碌にしなかつた、彼是かれこれ二年越しの気まづい記憶は、思つたより彼女を煩わづらはさなかつた。
彼等は一つ火鉢に手をかざしながら、いろいろな事を話し合つた。俊吉の小説だの、共通な知人の噂だの、東京と大阪との比較だの、話題はいくら話しても、尽きない位沢山あつた。が、二人とも云ひ合せたやうに、全然暮し向きの問題には触れなかつた。それが信子には一層従兄と、話してゐると云ふ感じを強くさせた。
時々はしかし沈黙が、二人の間に来る事もあつた。その度に彼女は微笑した儘、眼を火鉢の灰に落した。其処そこには待つとは云へない程、かすかに何かを待つ心もちがあつた。すると故意か偶然か、俊吉はすぐに話題を見つけて、何時もその心もちを打ち破つた。彼女は次第に従兄の顔を窺うかがはずにはゐられなくなつた。が、彼は平然と巻煙草の煙を呼吸しながら、格別不自然な表情を装つてゐる気色けしきも見えなかつた。
その内に照子が帰つて来た。彼女は姉の顔を見ると、手をとり合はないばかりに嬉しがつた。信子も唇は笑ひながら、眼には何時かもう涙があつた。二人は暫くは俊吉も忘れて、去年以来の生活を互に尋ねたり尋ねられたりしてゐた。殊に照子は活き活きと、血の色を頬に透かせながら、今でも飼つてゐる鶏の事まで、話して聞かせる事を忘れなかつた。俊吉は巻煙草を啣くはへた儘、満足さうに二人を眺めて、不相変あひかはらずにやにや笑つてゐた。
其処へ女中も帰つて来た。俊吉はその女中の手から、何枚かの端書はがきを受取ると、早速側の机へ向つて、せつせとペンを動かし始めた。照子は女中も留守だつた事が、意外らしい気色を見せた。「ぢや御姉様がいらしつた時は、誰も家にゐなかつたの。」「ええ、俊さんだけ。」――信子はかう答へる事が、平気を強しひるやうな心もちがした。すると俊吉が向うを向いたなり、
「旦那様に感謝しろ。その茶も僕が入れたんだ。」と云つた。照子は姉と眼を見合せて、悪戯いたづらさうにくすりと笑つた。が、夫にはわざとらしく、何とも返事をしなかつた。
間もなく信子は、妹夫婦と一しよに、晩飯の食卓を囲むことになつた。照子の説明する所によると、膳に上つた玉子は皆、家の鶏が産んだものであつた。俊吉は信子に葡萄酒をすすめながら、「人間の生活は掠奪りやくだつで持つてゐるんだね。小はこの玉子から」――なぞと社会主義じみた理窟を並べたりした。その癖此処にゐる三人の中で、一番玉子に愛着のあるのは俊吉自身に違ひなかつた。照子はそれが可笑をかしいと云つて、子供のやうな笑ひ声を立てた。信子はかう云ふ食卓の空気にも、遠い松林の中にある、寂しい茶の間の暮方を思ひ出さずにゐられなかつた。
話は食後の果物を荒した後も尽きなかつた。微酔を帯びた俊吉は、夜長の電燈の下にあぐらをかいて、盛に彼一流の詭弁きべんを弄した。その談論風発が、もう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある眼つきをして、「私も小説を書き出さうかしら。」と云つた。すると従兄は返事をする代りに、グウルモンの警句を抛はふりつけた。それは「ミユウズたちは女だから、彼等を自由に虜とりこにするものは、男だけだ。」と云ふ言葉であつた。信子と照子とは同盟して、グウルモンの権威を認めなかつた。「ぢや女でなけりや、音楽家になれなくつて? アポロは男ぢやありませんか。」――照子は真面目にこんな事まで云つた。
その暇に夜が更けた。信子はとうとう泊る事になつた。
寝る前に俊吉は、縁側の雨戸を一枚開けて、寝間着の儘狭い庭へ下りた。それから誰を呼ぶともなく「ちよいと出て御覧。好い月だから。」と声をかけた。信子は独り彼の後から、沓脱くつぬぎの庭下駄へ足を下した。足袋を脱いだ彼女の足には、冷たい露の感じがあつた。
月は庭の隅にある、痩せがれた檜ひのきの梢こずゑにあつた。従兄はその檜の下に立つて、うす明い夜空を眺めてゐた。「大へん草が生えてゐるのね。」――信子は荒れた庭を気味悪さうに、怯おづ怯づ彼のゐる方へ歩み寄つた。が、彼はやはり空を見ながら、「十三夜かな。」と呟つぶやいただけであつた。
暫く沈黙が続いた後、俊吉は静に眼を返して、「鶏小屋とりごやへ行つて見ようか。」と云つた。信子は黙つて頷うなづいた。鶏小屋は丁度檜とは反対の庭の隅にあつた。二人は肩を並べながら、ゆつくり其処まで歩いて行つた。しかし蓆囲むしろがこひの内には、唯鶏の匂のする、朧おぼろげな光と影ばかりがあつた。俊吉はその小屋を覗いて見て、殆ほとんど独り言かと思ふやうに、「寝てゐる。」と彼女に囁ささやいた。「玉子を人に取られた鶏が。」――信子は草の中に佇たたずんだ儘、さう考へずにはゐられなかつた。……
二人が庭から返つて来ると、照子は夫の机の前に、ぼんやり電燈を眺めてゐた。青い横ばひがたつた一つ、笠に這つてゐる電燈を。
四
翌朝俊吉は一張羅の背広を着て、食後※(「勹<夕」、第3水準1-14-76)々そうそう玄関へ行つた。何でも亡友の一周忌の墓参をするのだとか云ふ事であつた。「好いかい。待つてゐるんだぜ。午頃ひるごろまでにやきつと帰つて来るから。」――彼は外套をひつかけながら、かう信子に念を押した。が、彼女は華奢きやしやな手に彼の中折なかをれを持つた儘、黙つて微笑したばかりであつた。
照子は夫を送り出すと、姉を長火鉢の向うに招じて、まめまめしく茶をすすめなどした。隣の奥さんの話、訪問記者の話、それから俊吉と見に行つた或外国の歌劇団の話、――その外愉快なるべき話題が、彼女にはまだいろいろあるらしかつた。が、信子の心は沈んでゐた。彼女はふと気がつくと、何時も好い加減な返事ばかりしてゐる彼女自身が其処にあつた。それがとうとうしまひには、照子の眼にさへ止るやうになつた。妹は心配さうに彼女の顔を覗きこんで、「どうして?」と尋ねてくれたりした。しかし信子にもどうしたのだか、はつきりした事はわからなかつた。
柱時計が十時を打つた時、信子は懶ものうさうな眼を挙げて、「俊さんは中々帰りさうもないわね。」と云つた。照子も姉の言葉につれて、ちよいと時計を仰いだが、これは存外冷淡に、「まだ――」とだけしか答へなかつた。信子にはその言葉の中に、夫の愛に飽き足りてゐる新妻の心があるやうな気がした。さう思ふと愈いよいよ彼女の気もちは、憂欝に傾かずにはゐられなかつた。
「照さんは幸福ね。」――信子は頤あごを半襟に埋めながら、冗談のやうにかう云つた。が、自然と其処へ忍びこんだ、真面目な羨望せんばうの調子だけは、どうする事も出来なかつた。照子はしかし無邪気らしく、やはり活き活きと微笑しながら、「覚えていらつしやい。」と睨にらむ真似をした。それからすぐに又「御姉様だつて幸福の癖に。」と、甘えるやうにつけ加へた。その言葉がぴしりと信子を打つた。
彼女は心もち※(「目+匡」、第3水準1-88-81)まぶたを上げて、「さう思つて?」と問ひ返した。問ひ返して、すぐに後悔した。照子は一瞬間妙な顔をして、姉と眼を見合せた。その顔にも亦また蔽ひ難い後悔の心が動いてゐた。信子は強ひて微笑した。――「さう思はれるだけでも幸福ね。」
二人の間には沈黙が来た。彼等は柱時計の時を刻む下に、長火鉢の鉄瓶がたぎる音を聞くともなく聞き澄ませてゐた。
「でも御兄様は御優しくはなくつて?」――やがて照子は小さな声で、恐る恐るかう尋ねた。その声の中には明かに、気の毒さうな響が籠つてゐた、が、この場合信子の心は、何よりも憐憫れんびんを反撥はんぱつした。彼女は新聞を膝の上へのせて、それに眼を落したなり、わざと何とも答へなかつた。新聞には大阪と同じやうに、米価問題が掲げてあつた。
その内に静な茶の間の中には、かすかに人の泣くけはひが聞え出した。信子は新聞から眼を離して、袂を顔に当てた妹を長火鉢の向うに見出した。「泣かなくつたつて好いのよ。」――照子は姉にさう慰められても、容易に泣き止まうとはしなかつた。信子は残酷な喜びを感じながら、暫くは妹の震へる肩へ無言の視線を注いでゐた。それから女中の耳を憚はばかるやうに、照子の方へ顔をやりながら、「悪るかつたら、私があやまるわ。私は照さんさへ幸福なら、何より難有ありがたいと思つてゐるの。ほんたうよ。俊さんが照さんを愛してゐてくれれば――」と、低い声で云ひ続けた。云ひ続ける内に、彼女の声も、彼女自身の言葉に動かされて、だんだん感傷的になり始めた。すると突然照子は袖を落して、涙に濡れてゐる顔を挙げた。彼女の眼の中には、意外な事に、悲しみも怒りも見えなかつた。が、唯、抑へ切れない嫉妬の情が、燃えるやうに瞳を火照ほてらせてゐた。「ぢや御姉様は――御姉様は何故昨夜も――」照子は皆まで云はない内に、又顔を袖に埋めて、発作的に烈しく泣き始めた。……
二三時間の後、信子は電車の終点に急ぐべく、幌俥ほろぐるまの上に揺られてゐた。彼女の眼にはひる外の世界は、前部の幌を切りぬいた、四角なセルロイドの窓だけであつた。其処には場末らしい家々と色づいた雑木の梢とが、徐おもむろにしかも絶え間なく、後へ後へと流れて行つた。もしその中に一つでも動かないものがあれば、それは薄雲を漂はせた、冷やかな秋の空だけであつた。
彼女の心は静かであつた。が、その静かさを支配するものは、寂しい諦めに外ならなかつた。照子の発作が終つた後、和解は新しい涙と共に、容易たやすく二人を元の通り仲の好い姉妹に返してゐた。しかし事実は事実として、今でも信子の心を離れなかつた。彼女は従兄の帰りも待たずこの俥上に身を託した時、既に妹とは永久に他人になつたやうな心もちが、意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせてゐたのであつた。――
信子はふと眼を挙げた。その時セルロイドの窓の中には、ごみごみした町を歩いて来る、杖を抱へた従兄の姿が見えた。彼女の心は動揺した。俥を止めようか。それともこの儘行き違はうか。彼女は動悸どうきを抑へながら、暫くは唯幌の下に、空むなしい逡巡を重ねてゐた。が、俊吉と彼女との距離は、見る見る内に近くなつて来た。彼は薄日の光を浴びて、水溜りの多い往来にゆつくりと靴を運んでゐた。
「俊さん。」――さう云ふ声が一瞬間、信子の唇から洩れようとした。実際俊吉はその時もう、彼女の俥のすぐ側に、見慣れた姿を現してゐた。が、彼女は又ためらつた。その暇に何も知らない彼は、とうとうこの幌俥とすれ違つた。薄濁つた空、疎まばらな屋並、高い木々の黄ばんだ梢、――後には不相変あひかはらず人通りの少い場末の町があるばかりであつた。
「秋――」
信子はうすら寒い幌の下に、全身で寂しさを感じながら、しみじみかう思はずにゐられなかつた。
羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 外十八篇 (文春文庫―現代日本文学館)/文藝春秋

¥605
Amazon.co.jp
中学へ入学前から徳富蘆花氏の「自然と人生」や樗牛の「平家雑感」や小島烏水氏の「日本山水論」を愛読した。同時に、夏目さんの「猫」や鏡花氏の「風流線」や緑雨の「あられ酒」を愛読した。だから人の事は笑へない。僕にも「文章倶楽部」の「青年文士録」の中にあるやうな「トルストイ、坪内士行、大町桂月」時代があつた。
中学を卒業してから色んな本を読んだけれども、特に愛読した本といふものはないが、概して云ふと、ワイルドとかゴーチエとかいふやうな絢爛けんらんとした小説が好きであつた。それは僕の気質からも来てゐるであらうけれども、一つは慥たしかに日本の自然主義的な小説に厭きた反動であらうと思ふ。ところが、高等学校を卒業する前後から、どういふものか趣味や物の見方に大きな曲折が起つて、前に言つたワイルドとかゴーチエとかといふ作家のものがひどくいやになつた。ストリンドベルクなどに傾倒したのはこの頃である。その時分の僕の心持からいふと、ミケエロ・アンヂエロ風な力を持つてゐない芸術はすべて瓦礫のやうに感じられた。これは当時読んだ「ジヤンクリストフ」などの影響であつたらうと思ふ。
さういふ心持が大学を卒業する後までも続いたが、段々燃えるやうな力の崇拝もうすらいで、一年前から静かな力のある書物に最も心を惹かれるやうになつてゐる。但、静かなと言つてもたゞ静かだけでも力のないものには余り興味がない。スタンダールやメリメエや日本物で西鶴などの小説はこの点で今の僕には面白くもあり、又ためにもなる本である。
序ながら附け加へておくが、此間「ジヤンクリストフ」を出して読んで見たが、昔ほど感興が乗らなかつた。あの時分の本はだめなのかと思つたが、「アンナカレニナ」を出して二三章読んで見たら、これは昔のやうに有難い気がした。
芥川龍之介全集〈1〉 (ちくま文庫)/筑摩書房
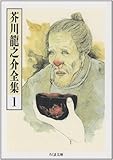
¥864
Amazon.co.jp
