※ 記事の更新がないときは、過去記事、もしくは、右下のツイッターに科学ニュースなどを載せていますので、そちらをお楽しみください。
そろそろ、夏休みも終わりそうですね
お子さんの宿題は終わりましたでしょうか?
私が勤める大学では今週から授業が
始まっています
他の学部はまだなのですが。。
さてさて、
以前、
子どもからの質問攻撃について
シリーズで書きました
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (1)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (2)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (3)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (4)』
これらのエントリーに対して
読者の方から嬉しいコメントを
いただきましたので
ご紹介いたします
##### 引用ここから #####
ブログ読ませていただきました。
中1の娘がいるのですが、5年生の頃
から些細な身の回りのことに「なぜ?」
「どうして?」と疑問をぶつけてくる
ようになりました。まるで幼い子ども
のようです。
物理とか自然現象とか理科分野に
つながることが多いです。
たとえば、車に乗っていてカーブで
後部座席の荷物が動くのはなぜか?
とか、廊下にできたドアの影が自分が
前に行くと短くなるはなぜか?とか。
私も一生懸命一緒に考えたり説明したり
しようとがんばっているのですが、
なかなか納得してもらえず、
気分的に参り気味でした。
わからないことがモヤモヤして本人に
とってものすごく苦痛らしいのです。
そんな時、「子どもの素朴な疑問から
逃げていませんか」を読んで、
勇気をいただきました。
じっくり腰をすえて向き合ってみようと
思えました。本当に煮詰まっていたので
一言お礼が言いたくて・・・
どうもありがとうございました。
##### 引用ここまで #####
こんなコメントをいただけると
私も書いてよかったと心から思います
ありがとうございました
なぜ?どうして?という質問攻撃は
一般的には小さい頃が多いようですが、
小学校高学年や中学生になってからが
頻繁だった、という話も聞きます
学校や塾で単純に覚えるばかりで、
どうしてなのか?という理屈を
教えてもらえない場合に、
頭の中で整理がつかず
落ち着かないのでしょう
断片的な知識を詰め込むことに
自然と違和感を覚える反応の現れ
とも言えます
よい反応ですので、お喜びください
単純に覚えないといけないことも
沢山ありますが、
ふと立ち止まって考えることも大事です
単純に覚えるよりも、理屈がわかると
世の中や自然とより関わりが深くなり
生きている実感にもつながると思います
小学校高学年や、中学校は多感な時期で
普段から対応も難しいですよね
お子さんが質問を通して意思疎通を
図ろうとされているのかもしれません
ここで突き放すと、
いろいろ積み重なって
関係がこじれてくる可能性もあります
まあ、突き放して、こじれるのも
お互いによい経験はあるのですが
とりあえず、
聞かれたときの対応を考えてみましょう
まず、目を見て聞くこと
これだけでも、
子どもは安心感が得られます
小さいお子さんでしたら
目線の高さを合わせるといいですね
もちろん、忙しいときは
「少し後にして」というのもアリです
待つことも身に付けて欲しいですし、
親の事情も理解してもらわないと
次に、一緒に考えましょう
ここで大事なのは、すぐに正解を
言ってしまわないこと
正解を知っていても、です
正解云々よりも、まず、
お子さんが自分なりに考えたことを
聞いてみましょう
それに基づいて話を拡げて
違っていたら、お子さんも自分で
気付けるようになります
とにかく、
知っているから分かる
というより、
考えるてみようと思う気持ちが大事です
知らなかったり、
考えても分からなかったりする場合は
「知らない」とか「分からない」で
プツっと終わらせず、
共通の宿題にして残しておきましょう
後にヒントが得られて
「そう言えば、前に分からなかった
あのことだけど、、」とか話かけると、
前のことを覚えてくれていたんだ
とも思ってくれて共感してもらえますし
分かることも増えて一石二鳥ですね
子どもから質問を受けると
正解を言わないといけないという
気持ちになるかもしれません
でも、
親が必ず正解を言わないといけないか
と言うと、そうではないと思います
前にも書きましたが、
ここで親のプライドは要りません
子どもと考え方のやり取りをしたり、
親の学ぶ姿勢を見せたりすることに
意味があります
お子さんの質問攻撃にお疲れの皆様、
上記のような感じで対処されてみては
いかがでしょうか?
そして、
分からないことがありましたら
私にもお裾分けください
一緒に考えさせていただけたら
私も嬉しいですので
(おしまい)
文:生塩研一
お読みいただきまして、ありがとうございました。
リクエストやコメントもお待ちしています。お気軽にどうぞ~!
対応できない場合はごめんなさい。。
このブログはランキングに参加しています。
私の順位を知りたい方、応援してくださる方は、
下のバナーをクリック
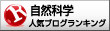
自然科学 ブログランキングへ

にほんブログ村
Facebook の「いいね!」も嬉しいです!
Twitterもやってます

そろそろ、夏休みも終わりそうですね
お子さんの宿題は終わりましたでしょうか?
私が勤める大学では今週から授業が
始まっています
他の学部はまだなのですが。。
さてさて、
以前、
子どもからの質問攻撃について
シリーズで書きました
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (1)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (2)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (3)』
拙ブログ『子どもの素朴な質問から逃げてませんか? (4)』
これらのエントリーに対して
読者の方から嬉しいコメントを
いただきましたので
ご紹介いたします
##### 引用ここから #####
ブログ読ませていただきました。
中1の娘がいるのですが、5年生の頃
から些細な身の回りのことに「なぜ?」
「どうして?」と疑問をぶつけてくる
ようになりました。まるで幼い子ども
のようです。
物理とか自然現象とか理科分野に
つながることが多いです。
たとえば、車に乗っていてカーブで
後部座席の荷物が動くのはなぜか?
とか、廊下にできたドアの影が自分が
前に行くと短くなるはなぜか?とか。
私も一生懸命一緒に考えたり説明したり
しようとがんばっているのですが、
なかなか納得してもらえず、
気分的に参り気味でした。
わからないことがモヤモヤして本人に
とってものすごく苦痛らしいのです。
そんな時、「子どもの素朴な疑問から
逃げていませんか」を読んで、
勇気をいただきました。
じっくり腰をすえて向き合ってみようと
思えました。本当に煮詰まっていたので
一言お礼が言いたくて・・・
どうもありがとうございました。
##### 引用ここまで #####
こんなコメントをいただけると
私も書いてよかったと心から思います
ありがとうございました
なぜ?どうして?という質問攻撃は
一般的には小さい頃が多いようですが、
小学校高学年や中学生になってからが
頻繁だった、という話も聞きます
学校や塾で単純に覚えるばかりで、
どうしてなのか?という理屈を
教えてもらえない場合に、
頭の中で整理がつかず
落ち着かないのでしょう
断片的な知識を詰め込むことに
自然と違和感を覚える反応の現れ
とも言えます
よい反応ですので、お喜びください
単純に覚えないといけないことも
沢山ありますが、
ふと立ち止まって考えることも大事です
単純に覚えるよりも、理屈がわかると
世の中や自然とより関わりが深くなり
生きている実感にもつながると思います
小学校高学年や、中学校は多感な時期で
普段から対応も難しいですよね
お子さんが質問を通して意思疎通を
図ろうとされているのかもしれません
ここで突き放すと、
いろいろ積み重なって
関係がこじれてくる可能性もあります
まあ、突き放して、こじれるのも
お互いによい経験はあるのですが
とりあえず、
聞かれたときの対応を考えてみましょう
まず、目を見て聞くこと
これだけでも、
子どもは安心感が得られます
小さいお子さんでしたら
目線の高さを合わせるといいですね
もちろん、忙しいときは
「少し後にして」というのもアリです
待つことも身に付けて欲しいですし、
親の事情も理解してもらわないと
次に、一緒に考えましょう
ここで大事なのは、すぐに正解を
言ってしまわないこと
正解を知っていても、です
正解云々よりも、まず、
お子さんが自分なりに考えたことを
聞いてみましょう
それに基づいて話を拡げて
違っていたら、お子さんも自分で
気付けるようになります
とにかく、
知っているから分かる
というより、
考えるてみようと思う気持ちが大事です
知らなかったり、
考えても分からなかったりする場合は
「知らない」とか「分からない」で
プツっと終わらせず、
共通の宿題にして残しておきましょう
後にヒントが得られて
「そう言えば、前に分からなかった
あのことだけど、、」とか話かけると、
前のことを覚えてくれていたんだ
とも思ってくれて共感してもらえますし
分かることも増えて一石二鳥ですね
子どもから質問を受けると
正解を言わないといけないという
気持ちになるかもしれません
でも、
親が必ず正解を言わないといけないか
と言うと、そうではないと思います
前にも書きましたが、
ここで親のプライドは要りません
子どもと考え方のやり取りをしたり、
親の学ぶ姿勢を見せたりすることに
意味があります
お子さんの質問攻撃にお疲れの皆様、
上記のような感じで対処されてみては
いかがでしょうか?
そして、
分からないことがありましたら
私にもお裾分けください
一緒に考えさせていただけたら
私も嬉しいですので
(おしまい)
文:生塩研一
お読みいただきまして、ありがとうございました。
リクエストやコメントもお待ちしています。お気軽にどうぞ~!
対応できない場合はごめんなさい。。
このブログはランキングに参加しています。
私の順位を知りたい方、応援してくださる方は、
下のバナーをクリック

自然科学 ブログランキングへ
にほんブログ村
Facebook の「いいね!」も嬉しいです!
Twitterもやってます
