応援していただける方!
↓ のクリックをお願いします!
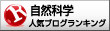
自然科学 ブログランキングへ

にほんブログ村
先日、原子を一個一個を並べて
コマ撮りした動画を紹介しました↓
「世界最小のコマ撮り動画 by IBM」
あの動画、
光学顕微鏡で撮ったわけではありません
というか、光学顕微鏡では見えません
光学顕微鏡で拡大して見るには
限界があるのです
あ、光学顕微鏡というのは、
小学校のときに、花粉やミジンコを
拡大して見た、普通の顕微鏡のことです
今から、約300年前のこと
レーウェンフック(1632-1723)は
自作の顕微鏡で微生物や精子を発見し
生物学に多大な影響を与えました

Wikiより
レーウェンフックの顕微鏡の
最高倍率は、約300倍
現代の技術では何倍でしょうか?
約2,000倍です
あれ? あまり進んでない?
いえ、
原理的にこれ以上拡大できないのです
視力が落ちると
眼鏡やコンタクトを使いますね
視力が落ちていなくても
肉眼の限界を超えたものを見るときは
顕微鏡や望遠鏡を使います
どちらもレンズを利用します
どれくらいよく見えるかは、
倍率や分解能で表します
倍率と分解能は同じように聞こえますが
実は違います
倍率とは、
実物よりもどれだけ拡大されるか
を示す比率のことです
拡大されたらよいので、
ぼやけていても構いません
クッキリ見える状態というのは
分解能が充分に得られているときです
では、
分解能とは、どういう意味でしょうか
それは
小さい2点を区別できる最小距離のこと
ヒトの視力検査も分解能で調べています
Cの字の空いた向きを指で示す、あれ
空いているのが見えるかどうかという
分解能をみるのです
ちなみに、
このCの字は、ランドルト環といいます
また、分解能は視覚だけではなく、
重さなどにも使われ、一般的に、
区別できる最小単位のことです
当たり前ですが、
光学顕微鏡では、光を使います
光は空間の電場と磁場が変化することで
伝えられる電磁波の仲間です。
電磁波には、電波、X線、γ線
などがあります
先日のガリレオで出てきた
マイクロ波も電磁波の仲間です
光には波の性質があり、色の違いは、
その波の山と山の間隔である「波長」
の違いによります
下図のλが波長です

Wikiより
結論から言いますと、
この「波長」が分解能を決めています
どうしてでしょうか?
(続く)
お読みいただきまして、ありがとうございました。
私を応援していただける方は、すぐ下のリンクのクリック願います! いずれも、同時に自然科学系ブログのランキングが開いて、他のおもしろい科学系ブログにアクセスもできます。
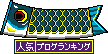
人気ブログランキングへ

にほんブログ村
↓ のクリックをお願いします!
自然科学 ブログランキングへ
にほんブログ村
先日、原子を一個一個を並べて
コマ撮りした動画を紹介しました↓
「世界最小のコマ撮り動画 by IBM」
あの動画、
光学顕微鏡で撮ったわけではありません
というか、光学顕微鏡では見えません
光学顕微鏡で拡大して見るには
限界があるのです
あ、光学顕微鏡というのは、
小学校のときに、花粉やミジンコを
拡大して見た、普通の顕微鏡のことです
今から、約300年前のこと
レーウェンフック(1632-1723)は
自作の顕微鏡で微生物や精子を発見し
生物学に多大な影響を与えました

Wikiより
レーウェンフックの顕微鏡の
最高倍率は、約300倍
現代の技術では何倍でしょうか?
約2,000倍です
あれ? あまり進んでない?
いえ、
原理的にこれ以上拡大できないのです
視力が落ちると
眼鏡やコンタクトを使いますね
視力が落ちていなくても
肉眼の限界を超えたものを見るときは
顕微鏡や望遠鏡を使います
どちらもレンズを利用します
どれくらいよく見えるかは、
倍率や分解能で表します
倍率と分解能は同じように聞こえますが
実は違います
倍率とは、
実物よりもどれだけ拡大されるか
を示す比率のことです
拡大されたらよいので、
ぼやけていても構いません
クッキリ見える状態というのは
分解能が充分に得られているときです
では、
分解能とは、どういう意味でしょうか
それは
小さい2点を区別できる最小距離のこと
ヒトの視力検査も分解能で調べています
Cの字の空いた向きを指で示す、あれ
空いているのが見えるかどうかという
分解能をみるのです
ちなみに、
このCの字は、ランドルト環といいます
また、分解能は視覚だけではなく、
重さなどにも使われ、一般的に、
区別できる最小単位のことです
当たり前ですが、
光学顕微鏡では、光を使います
光は空間の電場と磁場が変化することで
伝えられる電磁波の仲間です。
電磁波には、電波、X線、γ線
などがあります
先日のガリレオで出てきた
マイクロ波も電磁波の仲間です
光には波の性質があり、色の違いは、
その波の山と山の間隔である「波長」
の違いによります
下図のλが波長です

Wikiより
結論から言いますと、
この「波長」が分解能を決めています
どうしてでしょうか?
(続く)
お読みいただきまして、ありがとうございました。
私を応援していただける方は、すぐ下のリンクのクリック願います! いずれも、同時に自然科学系ブログのランキングが開いて、他のおもしろい科学系ブログにアクセスもできます。
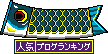
人気ブログランキングへ
にほんブログ村