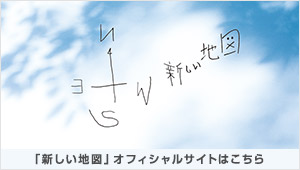至上の愛
秘密のトンネルの向こうにある扉・・
魔法
まだ昼だというのに夜のように暗いロンドン。間もなくクリスマスだというのに
商店の軒先や、集会禁止令のあおりを受けた音楽ホールは静まり返っていた。
公園広場にあるスピーカーズコーナーでさえも、自由に演説ができないらしい・・
ベルリンの目がいつも光ってるからな、
いや、欧州中がベルリンを見てるが正解か・・
聞いたか、反ドイツ主義の頭取が惨殺されたらしいぞ・・
英国王室も今じゃ、ドイツ製の軍靴に踏みつけられたも同然だ・・
町の人々は、新聞に載らぬ情報や世論工作を恐怖の目と耳で探り合った。
だが、この息苦しいご時世にありながらも、浮き立つ気持ちは押さえきれないのか、
どこからともなく子供達のクリスマスソングが聞こえてくる。そんな薄暗い路地を
一人の紳士が渡ってきた。名はクロードという。クロードは路地の並びにある屋敷の
玄関階段を駆け上がった、するとまるで見計らったかのように玄関ドアが開いた。
「やあ、スミス氏の具合はどうだい?」
「お変わりありません。ウナお嬢様が
お戻りになられたら、何よりの薬になりますわ」
屋敷の中から顔を出した若い女中は、外套とステッキを預かると、
コーヒーか紅茶かのどちらかを尋ね、客人を主が待つ書斎へと案内した。
「呼び立ててすまなかったね、クロード。
ようやくこれが、アードレーから届いたんだよ」
「では、さっそく拝見いたしましょう」
「ああ、頼む。すまないが座らせてもらうよ」
暖炉のそばのひじ掛け付き椅子に、ヨロリ座り込む屋敷の主スミス氏。
彼は健康というものを長く失っていた。命燃え尽きる前の使命感だけが、
病の床に臥せる彼を生かしている・・そんな厳しい病状にあるのだ。
「おや、この封筒は国際交換局を通ってませんな、軍の検閲印も
ないです。誰かが秘密裏に、英国内へと持ち込んでくれたのでしょう」
「ロンバート街にある、とある商社から使いが来て、合衆国から薬品の
預かり物があると、直接屋敷に届けてくれたんだよ、まる医者の往診姿で」
スミス氏は周囲に気を配ると、低い声で言った。書斎の執務机の上には、
それらしい薬品袋の他に、アードレー家の鷲の紋章が透かし彫りされた
数枚からなる上質紙の証書や、蝋押し封筒があった。それらを見やりながら
「上手くカムフラージュしたもんだ・・」とニヤリ笑うクロード。屋敷の主スミス氏が
首を長くして待っていたのは、娘に贈与した財産などを記した、アードレー発行の
銀行信用状であった。
「これであの子が何時アメリカに渡っても、暮らしに困ることはないでしょう」
「ああ、スイス銀もドイツに嗅ぎつけられてるからね、アメリカへ
隠すのが一番安全だ、アードレー家にある秘密の扉の向こう側にね。
それに、ウナの母親はアメリカ人だ、あの子も今ならまだ国籍を選べる・・」
「さようですな」
クロードは、スミス氏の言葉にうなずくと、彼の愛娘ウナ・クールスの
身元と財産や株券を保証したアードレー発行の銀行信用状を満足げに眺めた。
そこには、半月前の日付と総長アルバートの直筆サインもあった。
「それにしても、スミス氏があのウィリアム・A・アードレーと
面識があるとは思いませんでしたよ、古くからの友人だとか?」
「ウィリアムとは、大学時代に知り合ったんだ。ただ彼がAの一族アードレー家の
大総長だということは、かなり後になって知った。彼とウナの父親と私はクラブも
一緒で、いつも三人で楽しいことを考えていたよ、アードレー家の別宅があちこち
あったから汽車旅行にもよく行った。あの頃はみんな若かった、ウナの父親もね」
スミス氏は、ウナの父親と言った後、暖炉のマントルピースの上に
誇らし気に置かれている、古ぼけた銀のチャンピオンカップを見やった。
その横には、紺ジャケットにニッカポッカをはいた若かりし日の三人の姿が
映った小さな写真が飾ってあった。
「スコットランド式、綱引きクラブでしたっけ?」
「ああ、大学対抗試合では負けなしだった。ケンフォード大学の学生街を
はしごして三人で朝まで騒いでは酔いつぶれたもんだ。ウナにあいつの
武勇伝を披露してやると喜ぶんだよ」
スミス氏は古い友人のことを語り始めると懐かしそうに笑ったが、
同時に地獄の苦しみを詰め込んだような、沈痛な顔にもなった
「あなたは、立派にやり遂げましたよ、彼女の父親もそう思ってくれてるはずです」
「ああ、ウナもそう言ってくれる」
スミス氏は、バラ色に灯ったランプを見つめながら呟いた。
そう、彼はウナの本当の父親ではない、古い友人が残した愛娘の後見人だ。
スミス氏とウナの父親は、ミナスジェライスの鉱山で共同事業を展開していたが、
二人そろってブラジル特有の風土病にかかり、事業は一時破産に追い込まれた。
幸いスミス氏は病から回復したが、ウナの父親はそれが元で死んでしまったのだ。
スミス氏は孤児のウナを探し出し、彼女の後継人となった。彼女の父親が残した
鉱山はその後莫大な財産をもたらした。やがてウナは、イギリス国内の未婚女性
長者番付で上位に名を上げるまでになっていた。
「英国貴族の子息孫連合の公爵家跡取りから、かなり
しつこく求婚されたそうだ、ウナは相手にしとらんかったがな」
スミス氏は、その時のウナの口ぶりを思い出し
ちょっと笑いながら言った。
「まあどこのお貴族様も、金の工面に必死ですからね。今は国民の目も
厳しいですし、昔のようにはいきますまい。多くは、先の戦争での借金さえ
返せてないふところ事情を抱えてます、甘い汁を吸えたのは過去の話です」
「そういう君だって、名門の生まれじゃないか」
「たかが三男です、何の恩恵もありませんよ。まあ、
長兄を支えるべくの教育だけは、受けさせてもらえましたがね」
クロードは、アメリカから送られてきた書類や目録やらを丹念に
見やりながら皮肉交じりに言った。それと同時に、これからする話を、
どうこの男に伝えようかタイミングを計っていた。決して悪い話ではない、
塞ぎ虫にとりつかれたこの男が喜ぶような、とっておきの話なのだ。
「ところでウナは、アメリカ行きを少しも考えてくれないのですか?」
「去年の今頃から説得はしてるんだが、先日アルザスのブックフェアで
500冊近い本を買ってきて、この本、全部読み終わったらアメリカ行きの
ことを考えますと、宣言してたよ」
「ハハハ、頑固なあの子らしいやり方ですなぁ、しかし、ちょっと
不思議なことが起こってるんですよ、昔あの子がよく言っていた、
妖精やら魔法の力が働いてるのかもしれないんです、聞きたいですか?」
「ふむ、きみにしてはやけにもったいぶるね。ウナを
説得できる魔法があるなら、ぜひとも頼りたいもんだよ」
やや風変わりなウナを心配してか、頭を抱え心底弱り顔のスミス氏に
クロードは咳払いし「実はですね・・」と、前置きをした。クロードの本業は
弁護士である、父親と死に別れ孤児となったウナを探し当てたのもこの男だった。
一呼吸置くとクロードは、暖炉の上に置かれた古い写真をじっと見やった。そして
ゆっくりと話し始めた。
「私がチューターをしている生徒に、アメリカから来た社会人学生の
男がいるんです、彼の身分はとある家の若き主に仕える執事でしてね、名を
スチュワートといいます。彼の経歴がまた面白くて、元ホテルマンなんです。
実はその執事の仕えてる家というのがアードレー家でして、その若き主人が
スコットランドの大学にいるんですよ。私はまだ会ったことはないのですが、
話によれば経済を学びに来てるそうです」
話を聞かされたスミス氏は、一瞬魔法にかかったかのように口がきけなかった。
だが、落ち込み窪んでいた目が、いきいきとするのに大して時間はかからなかった。
「な、なんと・・まさか、あのウィリアムの息子なのか?こんな魔法は
想像してなかった。ぜひ会ってみたいものだな、名前は何というんだね?」
「はい、ウィリアム・ベンジャミン・アードレーといいます、アードレー家の
長男です。彼は旅好きらしく、休暇の度に欧州中を歩き回ってるそうですよ。
こんな不穏漂うご時世に変わり者でと、その執事は大変嘆いておりましたがね」
「おお変わり者同志、ウナと気が合いそうじゃないか!」
クロードの話を聞くなり、スミス氏は目を輝かせ声色を明るく変えた。
ウナの将来の憂いや長い間の病で塞ぎ気味だった心が、不思議な興味に
かられていた。なにより、旧友の息子をこの目で見てみたいのもある
「これはおぜん立てをしなければならない!そうだ、歓迎パーティを開こう。
大体ウナは、あれだけの器量良しにもかかわらず、本ばっかり読んでまるで
年頃の娘らしさがないのだ。放っておけば週末の夜だということも忘れて本を
読み耽ってるありさまだ!しかし、どうやって若い男女を引き合わせようか・・」
楽しかった学生時代を思い出してか、出会いを画策するスミス氏。
ウナのために金を惜しまぬスミス氏は、頭の中で様々なことを計画し始めた。
「お節介かとも思いましたが、こちらでの新年会に二人を招待
してあります。ところでスミス氏、招待客の顔ぶれは毎年のように私に
任せてくださいますね?もちろん、ウナのエスコートとダンスの相手も」
「もちろんだ、きみほど頭の回る優秀な弁護士はいないだろう、クロード。
その頭脳でウィリアムの息子とウナが、自然と近くなる手を考えくれたまえ!」
「では、我が家の娘たちを参謀に加えるとしましょうか」
得意げにひげを撫でながら、意味ありげに笑うクロード。彼にはウナより
少し年上の娘が二人いる。それゆえにスミス氏の心情もよくわかる。
言葉にはしないがこの弁護士も、近い将来、ウナがひとりぼっちに
なってしまうことを、心底心配しているのだ。
「急いではいけませんよ、最初が肝心です。まずは、趣味や価値観や
共通点ですかなぁ。旅好き、本好き、年は近いがやや変わり者の二人・・」
「そうだアメリカに電話をつないでくれ、シカゴは今何時だね?」
スミス氏の心はとても浮き立ったていた。襲い来る病のため、もう何年も
心躍る気持ちになれなかった。ベットの上で寝てるだけでも辛い毎日に、
突然楽しい魔法が現れたのだ。
「新しいドレスを仕立ててやりたいが、時間がない。
クロードの娘さんたちなら、デパートの服屋も詳しいかね?」
「娘達の話によれば、あのデパートの仕立屋は
デザイナーが変わってから、格段と良くなったそうですよ」
中年男二人が、ドレスの話、流行りのレストランの話、デートはどこに
すればいいのかを真剣に話し合っている中、水薬とお茶のお代わりを
運んできた若い女中は、屋敷の主スミス氏の明るい顔色に驚いていた。
遠いシカゴまでを巻き込んでの、作為的な出会い劇の幕開け。
どんな舞台が用意されているのか、主役の二人はまだ知る由もない。
元ホテルマンの嘆き・・
「どう、ご報告すれば・・」元ホテルマン、スチュワートは
そう嘆くと、書きあがらぬ白紙の報告書を前に頭を掻きむしった。
そして目の前のベンジャミンを恨めしげな眼で見上げ、また嘆く・・
「ああ、ベンジャミン坊ちゃまが大変なことになってしまった!
大学で何を学ばれたら、そんな風貌になってしまったのだろうか!」
「口を開けば嫌味節ばかりだね、スチュワート、
ちょっと遊び心で、ひげをのばしてみただけじゃないか」
「その小汚いお着物や、破れた靴もでございます・・よろしいですか、
坊ちゃま。こんなご時世です、不信を招くような行いは慎んでいただきたく」
「そう見えるかもしれないが、服も靴も汚くないぞ!」
ベンジャミンはケロリとした顔で悪びれずに言う。とにかく、エジンバラの駅を
発ってからというもの、ベンとスチュワートはこのやり取りを繰り返してるのだ。
「隣の個室にいるイタリア人老夫婦が、特製コーヒー淹れるからって
誘ってくれたんだ、ちょっと行ってくるよ。それからギャレーで急病人が
出たらしいから、俺夕方から芋の皮むきと皿洗い手伝ってくるからな!」
「いけません、ベンジャミン坊ちゃま!」
小言を鬱陶しそうに聞くベンジャミンと、くどくど説教するスチュワート。
不意に個室のドアをノックする音が聞こえて、汽車の乗務員が顔を出した。
爆弾低気圧の影響で、ロンドン到着が大幅に遅れる旨を伝えに来たのだ。
「聞いただろ、そういうことだ。汽車は進まないし暇なんだから、いいじゃないか」
「コーヒーでも紅茶でも、私がお淹れしますので話を聞いて下さい!
やはりその服装は感心致しません、それに坊ちゃまはアードレー家の
ご長男でございます、皿洗を手伝うだなんて、ご両親が知ったらどんなに」
「うちの両親は、そんなの気にしねぇよ」
「ああ、ベンジャミン坊ちゃまが大変な不良になってしまわれた!」
スチュワートはまたまた大袈裟に嘆いて見せた。せめて服装だけでもと更に懇願する。
大学生活で、確実になにかをこじらせつつあるベンジャミン。その変わり果てた服装と
風貌から、停車駅ごとにある軍の乗客検札で政治犯、脱獄犯、賞金稼ぎに賞金首にと
度々間違われるのだ。とはいえ、大学生であり身元も確かだ。背広にネクタイを締めた
執事も連れてるので誤解はすぐに解けるのだが、軍人がスチュワートに小声で「執事の
仕事も大変ですなぁ・・」と、労わりの言葉さえかけてくれるありさまで、向ける視線は、
多少の同情さえ混ざっていた。
「客車をウロウロしてるジャーマン・シェパード、あいつら利口だよな。軍人に
犬の名を聞いたら気軽に教えてくれて雄が”世界の終わり”で雌が世界の始まり”って
名前なんだって。少し撫でさせてもらった。久しぶりに大型犬触ったから、嬉しかったよ」
シカゴの自宅で飼っていた大きな犬たちを思い出してか、嬉しそうなベン。
話を聞いていたスチュワートは、みるみる青ざめていった。
「ジャーマン・シェパードですと!あれは訓練された軍用犬なのですよ。
お願いですからベンジャミン坊ちゃま、なんでもかんでも手懐けないで下さい!」
「犬の方から鼻を鳴らしてきたんだよ」
小言にも相変わらず飄々としているベンと、またまた頭を抱える執事スチュワート。
それから三時間、さてさてどこで油を売っているのか、いまだ芋の皮むきから
戻らぬベンジャミン・・
「若者にはよくあること、はしかみたいなもので時が解決するだろう」
スチュワートは優雅に紅茶をのみながら、ため息まじりに呟いた。
縁あってアードレー家の上級使用人となったスチュワートは、幼き主人の英国留学に伴い
執事兼世話係となったわけである。出逢った頃はまだあどけなさが残る少年だったのだが、
今じゃ小汚い大学生になり果ててしまった若き主人の姿に、本来なら心痛で病んでしまう
所なのだろうが、この執事、あのラガン家の元使用人であり悪名高き「ニール&イライザ」で
鍛えられているのか、実のところ、まだまだ余裕で平常心を保ててるらしい・・
つづく
色々入りきらなかったので持越し。次号はベンとウナの出会いに
双子次男の大学生活と、書けたらジルの入隊までかな?
その他にもテリィが金髪ロングのヅラ被ったり、腋毛伸ばしたり・・
バートさんが大学時代に綱引きクラブネタは二次設定です。
子供の頃、なぜかそう思ったんですよね、ああこの人ここで
綱引きの練習してたんだな、って。このコマの左側見て・・
こちらはDの意志
 |
テンプル騎士団 (講談社学術文庫)
864円
Amazon |
 |
十字軍騎士団 (講談社学術文庫)
1,134円
Amazon |
ルフィはDの一族
 |
ONE PIECE 88 (ジャンプコミックス)
150円
Amazon |
ユナ・D・海渡
 |
カードキャプターさくら クリアカード編(4) (KCデラックス なかよし)
463円
Amazon |
 |
水晶の夜 (新鋭書下ろし作品)
Amazon |
平成最後の魔法少女?アニメのエンディングいいね!
 |
魔法少女☆俺 コミック 1-2巻セット
1,468円
Amazon |
セーラークルーじゃなくてウナね。
 |
【第2類医薬品】新ウナコーワクール 30mL
260円
Amazon |
最近CMよく見るね
 |
ラバッツァ クオリタ・オロ VP (粉) 250g
907円
Amazon |
はしかといえばスージー
 |
キャンディ・キャンディ 全6巻文庫セット
Amazon |
お気づきでしょうがウナの元ネタとして。次号から本格的に登場予定
 |
世界名作劇場/小公女セーラ (世界名作劇場ジュニア・ノベルシリーズ)
950円
Amazon |