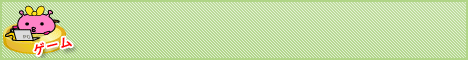私:ところで、自分で自分の性格とか、キャラを表現すると、どんなかんじ?
ま:楽しい人。明るいと思うよ。よく言われるし。
エネルギッシュとか、パワフルな陽性の気が流れてるとか、言われた事もあるしね。
私:激しく同意。気、ねー。詩的な表現でいいね。でも、そこまでの表現をしなくとも、たいていの人は麻里子さんの事を、明るいとか、天真爛漫とか言うだろうね。でも、そういうキャラって、アクターの仕事全般に向いてそうで、いいんじゃない?
ま:うーん、善し悪しだね。わたしの場合、キャラが濃いのよね。個性が強いというか、キャラクター俳優という感じで、限定した役しか回ってこない、という欠点はある。
ファッションだって、いつも、こんな風に、中性的でしょ。
私:濃いキャラとは思わないけど。でも、ファッションはいつもパンツルックで、マニッシュだよね。スカートにパンプスとか、想像できないや。
ま:失礼ねー。そんなかっこしたこともあんだから。
私:ごめん、ごめん。
ま:キャラに関しては、日本で演劇の教授に言われた事あるんだよ。わたしの演技って、動きが大きくて、マンガチックで、力強くて、かならずしも、演じてるキャラクターにマッチしているとは言えない、とか。動きとか、強さみたいな上っ面な事だけじゃなく、もっとこう、中身のある演技をすべき、とかね。
私:難しーねー。演技に人間的な深みをもっと、ということなんだろうか。
ま:うん。でも、それに関して、ニューヨークで、対照的な助言をもらった。さっき言った、パラレルイグジットの主催するワークショップで、ある日、授業で使うから、二つの対比したコスチュームを持ってこいって言われたのよ。
わたしは、ごく普通のトレンチコートと、ミリタリー調のかちっとしたジャケットをもっていったわけ。
そしたら、授業で、二つの衣装をとっかえひっかえで自分で着て、一人二役の演技を即興でやる、という趣向だった。もちろん、言葉はなし。
私は、普通のトレンチをつかって、おばあさんを、ミリタリージャケットの時は兵士という設定にした。
私:これもんで演技したのね。(片手をピッとのばして、顔のサイドにあて、敬礼のジェスチャー)
ま:そう。(麻里子さんも敬礼を返す。)で、普通のトレンチを着たときは、おばあさんだから、弱々しー仕草をした。
ストーリーは、二人がエンパイアステイトビルディングで出会うんだけど、いろいろあった後、兵士は実は、長く会ってなかったおばあさんの息子だということがわかる。
おばあさんは、それを知ったとたん、喜びのあまり、空にぴゅーん、と飛び上がる。それがラスト。
ワークショップの後で、以前、日本の教授から言われたアドバイスを紹介しながら、二人の先生、ジョエルとマークに聞いてみた。動きが大きすぎただろうか、とか、ストーリーが伝わったろうか、とか。
そしたら、二人は、確かに動きは大きいけれど、そこがエネルギッシュで、麻里子のスタイルが確立されていて、よかったと、とってもほめてくれた。麻里子の個性だ、と。
もし人間性とか出したかったら、一番最後、おばあさんが飛び上がったとき、一瞬後ろを振り返り、息子に小さく手を振る動作をいれると、もっと良かったかも。そんなちょっとしたことで、演技はより感動的になるからね、とアドバイスしてくれた。
わたしは号泣したくなるほどうれしかったよ。
私:わかるなー。素晴らしい先生だよね。麻里子さんのことを認めて、受け入れてくれて、その上での実践的アドバイスですもんね。
ところで、今回の舞台は麻里子さん以外、スタッフ全員ネイティブだったんでしょ?とまどいとか、やりにくいこととかあった?
ま:アメリカ人の集団の中に一人だけサムライ、という気持ちだったね。
私:戦闘モードだったの? 気合い入ってたんだね。
ま:うん。まあ、一番残念だったのは言葉の壁かな。
私:わかるよ。英語はきりがないものね。
ま:わたしは、日本語だと、マシンガントークのように、いっぱいしゃべるの。今回、英語で、ちゃんとコミュニーケーションはかるためにしゃべったけど、母国語でしゃべるような感じにはいかない。どうしても、日本語でしゃべる時に比べると、言葉少なになる。
もっと、しゃべってたら、もっとわたしの素の性格がわかってもらえて、もっと、深いコミュニケーションができたろーなー、と思うね。
私:そうだね。それから、日米の演劇の仕事の仕方の違いとか感じた?
ま:リハーサルのときとか、無駄な時間がなくて、すごいと思った。終わったらすぐ、みんなして、あっさり、さーっと帰っちゃうんだけど、稽古のときはプロフェッショナルにすごく集中してる。
私:それから、聞いた話だけど、アメリカでは、俳優のユニオンもちゃんとあって、長時間拘束されないようにもなってるんだってね。休憩時間など、規定があって、俳優が守られていると聞くよ。
ま:その辺も日本と大きく違うね。いちがいには言えないけど、国や企業がいろんな形で、演劇に関わっていて、芸術を育てて行こう、という姿勢がもっとあるように思うよ。
私:日本にもあるんだろうけど、まだ数的に少ないのかもね。
ま:日本だと、よっぽどメジャーな劇団とか、売れてる俳優で無い限り、自分らでチケット売ったり、稽古でも長い時間拘束されたり、きついアルバイトしながら演劇活動したり。
私:こっちでも、それはあるみたいよ。昔、私のルームメートでアメリカ人の女の子がいたけど、演劇しながらウェイトレスで生活たててたし。
ま:そうなんだけど、演劇教育の裾野が広くて、演劇専攻や演劇プログラムのあるカレッジがたくさんあるの。
私:日本では珍しい感覚よね。
ま:今日、ここに来る前に教えて来たBMCCだって、演劇クラスがあるんだもの。だから、俳優達がそういう機関で教える道がもっと開けてる。実際、今回の舞台のスタッフの何人かはそういうプロフェッサーもやりつつ、演劇やってる。
私:話変わるけど、フィジカルコメディーには女性がまだ少ないような気がする。まりこさん、パイオニアになれるんじゃ。
ま:なりたいね。女性が少ないのはアメリカだけじゃなくてね、シルクドソレイユも、そうだよ。(Cirque de Soleil :フランス語で、太陽のサーカス、の意。1984年、カナダで設立。)
シルクドソレイユのフィジカルコメディーはすごいんだけど、女性はまだ少ししかいない。
アメリカでは、リングリングサーカスが、クラウンの登竜門でね、実は2009年のオーディションに受かったんだ。欠員がなくて、まだお呼びがかかってないけど、最近、連絡したらちゃんと覚えててくれたよ。
私:すごいね。いい流れに乗ってる感じ。
シルクドソレイユの女性クラウン達。
<ここでインタビュー終了して、記念に麻里子さんの写真を撮る事になった。ホールフーズの一角でポーズをきめる麻里子さん、はじめてのデジカメで緊張しまくりの私>
私:はい、準備いい? いきますよー。ぱしゃ!
ま:ちょっと見せて、さっき体が動いてたよ、あ、やっぱりぶれてるじゃん。とり直し。
私:ごめんごめん、ではもう一度。
<何度も同じ失敗と同じ問答をくりかえす私>
ま:あれ、また、今度は脚がきれてるじゃない、もう、おねいさん、しっかりしてよー。
私:デジカメってサルでも撮れると思ってたけど、私、これじゃサル以下かしらー。
ま:そーかもよー。
<日本的な ”そんな事無いわよー” 的、慰め言葉を期待していたのに、あっさり図星の返答に、プチ落ち込みする私。なんだかんだやってる間に、店の人らしき黒人のおじさんがやってきて、>
おじさん:ちょいと、お嬢さん達、うちはもう閉店するんだかんね。それから、店のポリシーで写真撮影は禁じているんだよ。
私:すみませーん。
<すると、それを聞いていたお客の白人のおばさまが、急におじさんに食ってかかる。”このへんでは、どこでもみんなが好きなとこで写真とってるわよ、写真をとる権利があるのよ” とか言ってしばらくぶつぶつ不服申し立てしたのち、ディクレッシェンドして、ついにモノローグになってどっかに去ってしまった。ちょっとクレイジーな感じだ。>
と、まあ変な落ちがつきました。そして、図らずも、わたしは”天然スラップスティック”であることが判明。
麻里子さんによると、スラップスティックにはいろんな”型”があって、単純な事をしようと何度もトライするんだけど、失敗を重ねて、できない、というのもその一つ。わたしは、デジカメでそれをやってたわけだ。。。。
最後に、麻里子さんのモノローグ:
PHYSICALな演技は、PHYSICAL COMEDYは万国共通だと思うのです。
ダンス、音楽など、特別な「言語」を必要としないものに関しては誰もがダイレクトに共有出来るものだと思うのです。絵もそうかもだけど。だから、挑戦のしがいがあるってもんで。
今回のRabbit Islandのpre-showはまさに自分の今の専門分野、軽くタップもしたし。5分程度でしたがかなり自分のやりたいことをやらせて頂きました。
今回の役所は直接な役者ではなくても、あのような参加の仕方は充分演技であって、かなりやりがいがありました。
全てに興味を持つ事は大事な事であって。親に「何目指してるの!?」って言われちゃうけど。「エンターテイナー!」で生きたいのはホントのところなんです。
でも、自分の「得意分野」ってのはハッキリわかってた方がいいと思う。
今は、「コメディー」まっしぐらですが。右に出る者はいない!ってとこまでとことん突き詰めて行きたいです。
で、全ての表現において、「演技」「表現」の「幅」を広げて行きたいです。
Rabbit Islandはホントに素敵な出会いでした。
このように、新たな違う作品に出会う事で自分の引き出しが増えていくのが楽しいから辞められないんでしょう。
岩佐麻里子