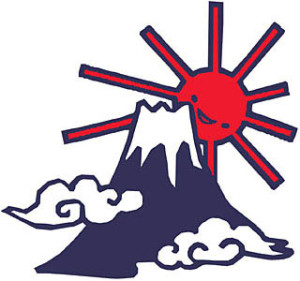というわけで、最近はペットも飼主も高齢化している現状で、タイトルのようなニーズが高まりつつあります。
というわけで、最近はペットも飼主も高齢化している現状で、タイトルのようなニーズが高まりつつあります。巷ではペット信託など新しいトピックもありますが、今回は「負担付死因贈与契約」についてご紹介したいと思います。
死因贈与契約とは、贈与者(飼主)の死亡によって財産処分の効力が生じる、贈与契約の一種です。民法上は、死因贈与は遺贈に関する規定に従うという旨を定めており(民法554条)、遺贈ととても似ています。
しかし、死因贈与が遺贈と違う点は、遺贈が遺言という単独行為(一人でする行為)であるのに対し、死因贈与は贈与者(飼主)と受贈者二人で行う契約である、というところです。すなわち、遺贈の場合は、贈られた側が放棄することができるのに対し、死因贈与の場合は受贈者は勝手に破棄することはできません。
しかし逆に、遺贈の場合は遺言なので飼主は後日自由に撤回することができますが、死因贈与の場合は契約なので一方的に契約を破棄することはできない、と考えられそうですが、判例は死因贈与契約後も贈与者(飼主)はいつでも取消すことができるとしています。
この、死因贈与契約を「ペットの世話をする」という負担付にして、かつ契約書を公正証書にしておくのです。
死因贈与契約は、書面ではない口頭によるものでも有効ですが、書面によらないと履行が終わるまでは撤回が自由にできてしまうので、例えば飼主が撤回することは考えられなくても、その相続人が(飼主の意思に反して)撤回してしまうことは十分考えられるので、この点が心配ならやはり契約書の形で、更に公正証書にしておくのが手堅いと思います。
また、相続人との関係で言うと、契約の中で受贈者でも第三者でもいいので執行者を決めておくと、円滑な履行が確保できると思います。死因贈与については、遺言執行者の規定も準用されるので、一般的に利害が対立する相続人との無用のトラブルを避けるためにも、執行者の規定を契約の中に盛り込んでおくとよいでしょう。
執行者が指定してあれば、相続人に代わって手続を履行することができますので、例えば狂犬病予防法上の犬の登録や世話をする上で必要な手続などを行うことができ、円滑に進むことができるのではないかと思います。
なお、「負担付死因贈与契約公正証書」を作成する上で、ペットの特定や希望する世話の仕方などの内容を忘れずに記載するようにしましょう。特に、世話をするに当たり必要な費用はどうするのか、費用として飼主の財産の一部(預金など)を一緒に贈与する場合は、明記しておかないとトラブルの種になりかねません。また、相続人や周りの知人などとの関係で、ペットの世話の仕方、例えば散歩の頻度、餌の種類、小屋・籠・ケージなどの飼育環境などは、実際によくトラブル事例として耳にしますので、両者で予め細かく決めておくことが望ましいと思います。
ご参考にしてください。