表現の勉強をしようと思って読んだ本の3冊目、山田ズーニーさんの「あなたの話はなぜ『通じない』のか」についての自分なりのまとめを書く。
この本は前回読んだ「伝わる・揺さぶる!文章を書く」よりもコミュニケーションのエッセンスを抽出した本となっている。そのエッセンスは私が改めて整理すると、以下の二つのようになる。
1.コミュニケーションは「問い」の立て方が重要
2.コミュニケーションが成立するためには、自分の「メディア力」が鍵
1.「問い」の立て方
どのような問題意識を持って文章を書いたり発言をするか意識することは、効果的かつ広がりをもったコミュニケーションを可能にする。普段の何気ない会話にしても、例えば「今日のお昼」という話題に対し、「内食か外食か」「日本食、中華、洋食のいずれか」「たくさん食べたいか少しでいいか」「早く食べたいかゆっくり食べたいか」・・・という問いを繰り返し、それぞれ「なぜか」という答えを与えることで最終的な「意見」として「外食でパスタが食べたい」ということになる。(これが要するに論理・ロジックである。)
効果的なコミュニケーションを取るためには、話す時も聞く時も「意見」をはっきりさせ、その意見への鍵となる「問い」を見つけることで、問いに対する相手の考え方や根本思想に語りかけることができ、お互いがハッピーになることができるだろう。
2.自分の「メディア力」を高める
いかに論理的に話しても、周囲の自分に対する「メディア力」がなければ意見を聞いてもらえる可能性は低い。本の中で上げられていたわかりやすいメディア力の違いの例として、NHKと東スポの違いがある。(どっちがメディア力が高いかは一目瞭然だろう。)
では、自分のメディア力を高めるにはどうしたらよいか。私は、一貫性の開示による信頼の獲得であると解釈した。一貫性とは、自分や企業がどのような歴史を辿り、そして今どのような問題意識を持って活動しているのかを一貫させることである。また、言っていることもコロコロ変えず、軸に基づいていることを示す必要がある。これにより言っている内容に信頼感を持たせることができる。
また、意外におろそかになりがちなのが、やっていることの開示である。これは特に身近にいる人とのコミュニケーションの問題である。「上司は自分のことを何も分かっていない」と考えてしまうのは、自分がやっていること・考えていることを見ていると思っているからであって、実際は他人が何を考えていて何を行っているか完全に見ている人はなかなかいないだろう。自分がやっていることを理解してもらうためには、自分の考えややっていることを頻繁に開示し、一貫性に関する理解を深めてもらうことが有効な手段となるだろう。
あなたの話はなぜ「通じない」のか (ちくま文庫)/筑摩書房
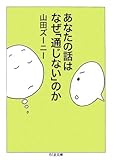
¥546
Amazon.co.jp
この本は前回読んだ「伝わる・揺さぶる!文章を書く」よりもコミュニケーションのエッセンスを抽出した本となっている。そのエッセンスは私が改めて整理すると、以下の二つのようになる。
1.コミュニケーションは「問い」の立て方が重要
2.コミュニケーションが成立するためには、自分の「メディア力」が鍵
1.「問い」の立て方
どのような問題意識を持って文章を書いたり発言をするか意識することは、効果的かつ広がりをもったコミュニケーションを可能にする。普段の何気ない会話にしても、例えば「今日のお昼」という話題に対し、「内食か外食か」「日本食、中華、洋食のいずれか」「たくさん食べたいか少しでいいか」「早く食べたいかゆっくり食べたいか」・・・という問いを繰り返し、それぞれ「なぜか」という答えを与えることで最終的な「意見」として「外食でパスタが食べたい」ということになる。(これが要するに論理・ロジックである。)
効果的なコミュニケーションを取るためには、話す時も聞く時も「意見」をはっきりさせ、その意見への鍵となる「問い」を見つけることで、問いに対する相手の考え方や根本思想に語りかけることができ、お互いがハッピーになることができるだろう。
2.自分の「メディア力」を高める
いかに論理的に話しても、周囲の自分に対する「メディア力」がなければ意見を聞いてもらえる可能性は低い。本の中で上げられていたわかりやすいメディア力の違いの例として、NHKと東スポの違いがある。(どっちがメディア力が高いかは一目瞭然だろう。)
では、自分のメディア力を高めるにはどうしたらよいか。私は、一貫性の開示による信頼の獲得であると解釈した。一貫性とは、自分や企業がどのような歴史を辿り、そして今どのような問題意識を持って活動しているのかを一貫させることである。また、言っていることもコロコロ変えず、軸に基づいていることを示す必要がある。これにより言っている内容に信頼感を持たせることができる。
また、意外におろそかになりがちなのが、やっていることの開示である。これは特に身近にいる人とのコミュニケーションの問題である。「上司は自分のことを何も分かっていない」と考えてしまうのは、自分がやっていること・考えていることを見ていると思っているからであって、実際は他人が何を考えていて何を行っているか完全に見ている人はなかなかいないだろう。自分がやっていることを理解してもらうためには、自分の考えややっていることを頻繁に開示し、一貫性に関する理解を深めてもらうことが有効な手段となるだろう。
あなたの話はなぜ「通じない」のか (ちくま文庫)/筑摩書房
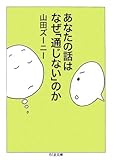
¥546
Amazon.co.jp