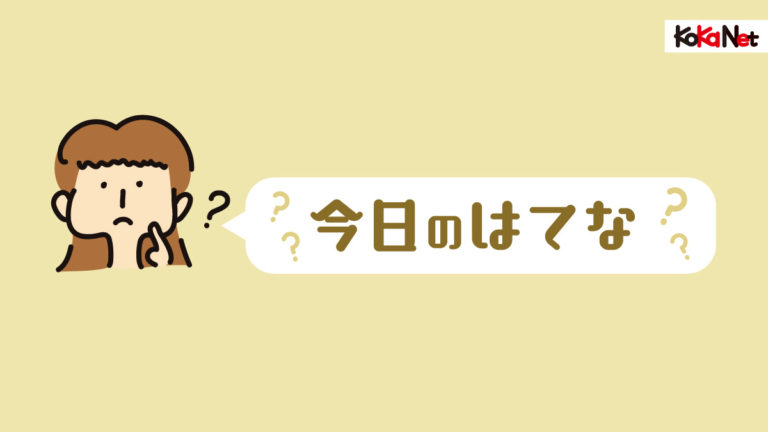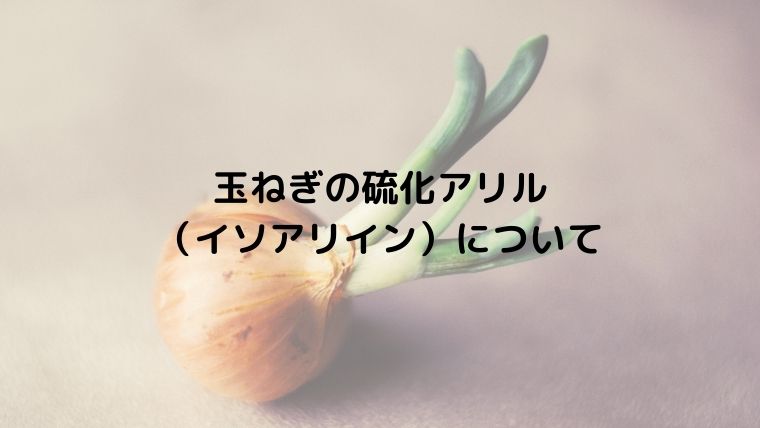多くの薬は動物ではなく植物から作られています。
では、なぜ植物から作られる薬が多いのでしょうか。それは動物は動けるが、植物は動くことが出来ないという違いが大きく関わってきます。
今回は植物が身を守るための生存戦略について考え、それがどのように人間に働く薬につながるのかを見ていきましょう!
[目次]
・どうして植物は薬を作るのか
・植物が自分の身を守るための3つの化学成分
-(1)病原体に打ち勝つための化学成分
-(2)病原菌に打ち勝つための化学成分
-(3)他の植物の生長を邪魔するための化学成分
・植物の化学成分を人間が使える理由は?
・まとめ
どうして植物は薬を作るのか
まず、なぜ植物は薬を作るのでしょうか。そのことは、前述したように「動物は動けるが、植物は動けない」というのが根端にあります。動物は動くことができるため、獲物を狩って食べたり、生えている草を食べに行ったりでき、敵に襲われてもその足で逃げることもできます。このように、動物は動くことで生きるための行動を起こすことができます。一方で、植物は動くことができないため、動くことを利用しない生存戦略を取る必要があります。つまり、動物が動いてすることを植物は動かずにする必要があるということになります。
そして、この生存戦略というのが、植物が薬を作ることに関与しています。動物が敵に食べられないように行動するのと同じく、植物も動物や昆虫に食べられないようにしなければなりません。また、多くの病原菌からも攻撃されます。さらに、同じ植物同士であっても栄養や場所の取り合いなど生き残りをかけた戦いが行われています。このような戦いにおいて、植物は自分の身を守る必要があります。そこで、植物は様々な化学成分を作り出し、それを使うことで生き延びています。この様々な化学成分が人間にとっての薬となるのです。
植物が自分の身を守るための3つの化学成分
植物は自分の身を守るために主に3つの種類の化学成分を作り出します。
[植物が自分の身を守るための3つの化学成分]
(1)病原体に打ち勝つための化学成分
(2)病原菌に打ち勝つための化学成分
(3)他の植物の生長を邪魔するための化学成分
⭐️1つ目は、動物や昆虫に食べられないための化学成分です。
植物は他の生物に食べられないように、有毒な化学成分を持っていることが多いです。ケシの実から取れる化学成分のモルヒネもその1つです。モルヒネには、血圧低下や呼吸抑制のような強い毒性があるため、動物がケシの実をたくさん食べると死んでしまいます。つまりモルヒネはケシが「自分の身を動物から守るために作り出した化学成分」ということが分かります。
では、果物はどうでしょうか。甘い味がするため化学成分は含まれていないのではないでしょうか。果物の場合は、実を食べられるのが本望なのです。実を食べられることで動物に種を運んでもらうことで繁殖するためです。しかし、動物に食べられて繁殖する植物でも、食べられる時期を化学成分で調整しているものもあります。
例えばリンゴのような植物の実は実が熟すまでは渋い味や苦い味がしますが、実が熟すと甘い味に変化したりします。これは、種子の準備ができるまでは、渋い味や苦い味の化学成分を出して食べられにくくし、「繁殖の準備ができたら甘い味がする成分を出し、動物に食べてもらう」という戦略を取っています。
ちなみに、実の色が時期によって変化するのも同様の理由になります。熟していない実は、自然の中で目立たない緑色をしていますが、熟すと目立つ赤色へと変化することが多いです。これも実が熟すまでは食べられないようにし、熟したら動物に見つけて食べてもらい種を運んでもらおうという戦略なのです。
⭐️2つ目は病原菌に打ち勝つための化学成分です。
植物は侵入してきた病原菌を倒せるように、色々な化学成分を作り出します。例えば、お茶に含まれているカテキンは殺菌作用や解毒作用を持つことで知られていますが、このカテキンもチャノキ(茶の木)が自分を守るために作り出している化学成分になります。このような成分を出すことで植物は病原菌から自分の身を守っています。
⭐️3つ目は他の植物の生長を邪魔するための化学成分です。
同じ植物でも争いが起こります。具体的には、周りにたくさんの植物があれば、自分には太陽の光が当たらなくなってしまうし、限られた土の中の資源も奪われてしまいます。そこで植物は周りの植物が生長するのを邪魔する化学成分を作り出します。
例えば、コーヒー豆に含まれるカフェインは、他の植物が芽生えるのを阻害する効果を持っています。このため、コーヒーの木から落ちた豆が土の中でカフェインを放出することで他の植物が周りに育たないようにしています。
このように、植物は生きるために様々な化学成分を作り出し、敵から自分の身を守るための戦略をとっています。
植物の化学成分を人間が使える理由は?
では、植物が敵から自分の身を守るために作り出しているものがなぜ人間にとっては便利に使われるのでしょうか。それには、植物が作る化学成分の性質が関係しています。
植物が自分の身を守るためには、生物に対して何らかの生体反応を起こす成分を作る必要があります。そして、ある生物へ作用する成分は他の生物にも何らかの作用を与えることが多いです。そのため、植物が自分を守るために作り出す化学成分というのは、人間に対しても何らかの作用を及ぼすことがあります。しかし、ある成分が「毒として働くのか、薬として働くのか」はどの生物が使うのかということやその摂取量によっても変わります。そこで他の生物に対して毒として働くものがどのような摂取量であれば人間に対しては薬として作用するのかという点で薬の研究が行われているのです。さらに、植物が作る化学成分はその植物ごとに異なるため、植物全体で見ればとてつもない種類の化学成分が存在していることになります。つまり、植物から薬を作るにはものすごく多くの種類の成分が存在することになります。
まとめ
植物の生存戦略が私たちにとって便利な薬に使われる理由が分かりましたでしょうか?植物の化学成分は生物に強く作用し、種類が豊富なことが特徴となります。これは、人間が薬を開発するための目標そのものになります。体を動かすことのできる動物には防御のために化学成分を作り出すものは多くありません。つまり、動物と異なり動けない植物が生き延びるために様々な化学成分を作り続けていた結果、それらが薬を作る上で適した性質を持つようになったということになります。身近な植物にどんな化学成分が含まれているのかを調べてみると面白いかもしれません!