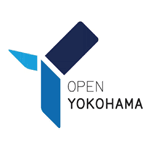「ゆめ水族園」
これは、
EPSONさんの社員参加型 社会貢献活動だそうで、
とても素敵な「バーチャル水族館」です。
しかも、薄暗くて、居心地よく…
とても心身緩む雰囲気…![]()
プロジェクター、ほしい!と思いましたよ![]()
![]()
家庭用10万位内のものでいい、とのことでしたが、
使われていたプロジェクターの一つは200万超とか。![]()
みなとみらいにかつてありました、
体験型施設、BBCワールドは、
まるでジャングルや高地などにいるような、
そんな経験ができる施設でしたが、
なくなってしまって残念だったんですよね。
常設がほしいです〜。
歩けなくても楽しめますから…。
ゆめ水族園は貸し出しもしてくださるようで、
いつかお願いして、
地域の子供達みんなと体験できたら嬉しいです!
前置き長くなりましたが…
さて!![]()
と穏やかな顔では書けない内容ですが…。。。
特別支援学校に4月に入学式して、もはや秋…。
こないだまで半袖きてましたがね、一応、秋…。
入学して見えてきたこと。
特別支援学校には、「自立のための教育がない」
ということ![]()
(↑我が子の通う学校です)
1人でできる事を増やす、ことが、
私の思う自立の中で大事なことなのですが、
我が子の特別支援学校では、
これまで1人でしていたことも、教員の介助、なのです。
移動も、立ち上がりも、指摘しないと全介助に。
これまでの個別級では
私がお教えした通りにしてくれたのですが、
特別支援学校では、みんな肢体不自由のため
重い方に合わせる…。![]()
全介助のほうが時短になる、教師も慣れている、
という理由で、肢体不自由は皆、同じ支援になります。
これは、入学前から恐れていたこと。
オンリーワンからの変化。
知的障害のお子さんに関しては、
校内の仕事としてやっている際は、移動中に壁を叩いても叫んでもいい。
とりあえず「仕事中」で授業中です。
これまでの個別級では「徘徊」に当たりますが、
ここでは「仕事中」です。
特に仕事中のマナーについて指導はありません。
これでは社会的に受け入れられそうにない状況です。
おかしい、と思うのは私だけ。
登校時にいつもの大声を出している生徒さんたち。
その保護者さんたちも、特に咎める様子はありません。
「静かにしてね」と促す様子はゼロ。
100%です。
小さな頃から言われてなければ、
そのお子様はそれが他の人にとって不快かどうかも理解できませんよね。
「叫び声や自傷行為を抑える薬がある」
と療育センターの医師が仰っておられましたが、
かかる病院の方針によって、受ける医療に差があるなら残念です。
(保護者が、薬は嫌だと拒否する場合も多いそうです)
我が子もボトックス治療は不適合の脳性麻痺型と、
かつて言われて、前医では受けられていませんでした。
とある病院にセカンドオピニオンを受けてみたところ、
なんで受けられないの?と。
転院しまして、今に至ります。
本人も介助者も快適になる医療があるなら、
一旦受けてみるのも手かと思います。
どんな人にも好かれる子に。
肢体不自由であっても、知的障害であっても、
他の障害、特性、であっても。
人との協調性の有無で、進路は変わります。
私が子育てにおいて大事にしている考えは、
「どんな子どもでも、いつか1人になる」ということ。
1人でも生きていける知恵と力を持った子に。
その時に生きていく力があるか。
親がいつまでもみてあげられません。
その日はいつ来るかわかりません。
障害だから仕方ない、と声かけもしないでいると、
行き先がなくなるのは事実なのです。
(施設側も学校側も、事実だと認めています)
他害が酷いと受け入れ先がないことも事実。
だから、
障害だから仕方ないでしょ!という保護者さんが
そう言えるのは特別支援学校高等部まで。
わかっているなら、対策するしかないのですよ。
学校にも話していることですが、
本来、特別支援学校で、
「特別支援教育を保護者に教えてほしい」と。
学校と家庭と連携して、子供をよくしてほしいと。
子供のために。
でも、しないんですよね、どっちも。
店舗目前に置かれたスクールバス停で
1時間以上も毎日話しているようなお母様方が
他者にとって不快だと感じられる、とは思えませんし
常識あるとは考えにくいです。
いろんな車が止められず困っているのに気にもされない
ご自身の子が叫んでも気にしないのはそういうこと。
夏休みが明けると外していたオムツが復活した、
直していたはずの癖が、また復活してしまった、
なんて話は、よく聞きました。
ご家庭で取り組んでないのです。
いつか1人になる日が来ることを常に想定して、
保護者が率先して人との繋がりを広く持ち、
子供が自分で生きる力を養ってあげる、
親の知恵は譲っておく、(失敗談も)
子が得意なことを探す手助けをする、
知的に重ければ、パターンをみつけたり、音のならない落ち着ける「もの」を見つけておく、
注意を受け入れられる子にする、
等々、家庭での取り組みはありますよね。
障害がある子に、必要になりそうなことは、
「支援を受けるようになること」で、
知的具合により異なるでしょうが、
知的に重くなければ、
どういう支援なら自身にとって適切か考えることも必要
身辺自立度により支援に違いがあり、
支援を拒まず利用して、自立に向かうこと、
徐々に支援から離れられるようにすればよいと理解する
これだと思います。
障害者手帳はない方が嬉しい。
これはいまだに私も思いは変わりません。
我が子が障害者でなくなってほしい。
だから頑張っている。
でも、今は障害者手帳のおかげで支援がありますし、
いつか自立するようにするために、
横浜市では訓練介助器具制度、というのもあります。
障害があっても、自立を目指す。
社会の一員として、社会の仕事の一つを担う。
何が得意か探し出し、それを仕事に繋げていく。
どんな人にも受け入れられる人に。
好かれる、とまでは言いませんが、
嫌われる人にならないよう、
しっかりと我が子も、
Nestの子供たちもみていきたいと思います。![]()
障害者や福祉、というイメージを変えたい。
ただそれだけです。
すでに染まってますけれど、ね![]()
どんな子供も生きる能力があるんだから…。
↓↓![]()
![]()
![]()
ふるさと納税の時期ですね。
あまり教えたくないのですが、![]()
わざわざ最後まで読んでくださった皆様に、
私のおすすめです。
我が家の定番、「大川屋さんのうなぎ」です![]()
ハズレが多いふるさと納税の食品ですが、
これは実店舗で美味しく頂きまして、以降ファンです。
4尾が2セット![]()
これ、毎月定期便があるといいのに。
↓↓ぜひどうぞ。![]() ↓↓
↓↓