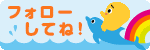再掲載です。
2年前に書いた、小説の真似事です。
前回の再掲載と時間が開いてしまったので、(1)から(8)まで、まとめ再アップです。
*********************************
4月半ば。昼下がりの明るい都内の病室。今年58歳になる竹内敏雄は妻早苗の手を握りしめていた。
意識がない妻の呼吸は浅いが静かだった。
「呼んでおきたい親戚の方がいたら連絡してください」と担当医に言われ、敏雄は今朝からずっと妻の病室で付き添っていた。親戚といっても、遠方の親戚ばかりなので、敏雄はあえて連絡はしなかった。
こうして妻の手を握りしめていると、思い出すことがある。この手で妻はいつも台所をきれいに保ち続けていた。古くなったフェイスタオルを切って縫い合わせて、台所をきれいにするための台布巾を自分で作っていたのだ。
力を込めて、台所の調理台を拭く6歳年下の妻の手が、敏雄の目の前に浮かんでいた。
「台所はいつもきれいにしておかないとね」が、妻の口癖だった。
妻の手料理は、すばらしいものだったが、敏雄は料理が苦手で、自分で作ることはなかった。しかし、洗い物の手伝いは時々やっていた。そんなときに見た、妻が台所をきれいにする姿。あの力強かった手が今は、か弱く動くこともなく。敏雄はまるで妻をこの世に引き留めておくのが目的であるかのように、妻の手をぎゅっとしっかりと握りしめていた。
いきなり早苗につながっているモニターの警報音が鳴った。不安定に揺れていた心電計の波形が、その瞬間水平な一本の直線になっていた。でも、モニターにはときおりフワッと小さな波形が立ち上がっている。微かな命の息吹を拾い上げているかのように。
敏雄は妻の手を片手で握りしめたまま、片手でナースコールを必死で押していた。「今、呼ぶから、大丈夫だ、大丈夫だ」敏雄は自分に言い聞かせるように、早苗に声をかけた。
最初に来たのは看護師。そのとき妻は、ひとつ大きく深呼吸をするように息をした。錯覚かもしれないが、唇が微かに動いたように見えた。何か言いたげな様子にも見えたが、それは気のせいだったのだろうか。
モニターは、依然として動きはなく、すべてが静かになってしまっていた。担当医がその後来てくれたが、それは「ご臨終です」という宣告をするためだけのものだった。
一人娘のさゆりは、母親の臨終にはわずかに間に合わなかった。
「おかあさん・・・」個室の病室に着いたさゆりは、それだけを言うのが精一杯だった。ぽろぽろ流れ落ちる涙。さゆりも母親の左手を握りしめた。
父親の敏雄は、母親の右手をしっかりと握りしめている。涙を必死でこらえている様子だった。さゆりが見る限り、母親の表情には平穏さが漂い、すべてに満足しているかのようにさえ見えた。
敏雄は、涙をこらえながら妻に語りかけた。
「早苗、早苗、早苗・・・愛してるよ、早苗」
次の瞬間、敏雄の目からは、涙がとめどなくあふれてきた。さゆりにも下を向いた父の目から、涙がしたたり落ちているのが見えた。
さゆりは驚いた。愛してる、なんていう言葉が父親の口から出るなんて信じられなかった。確かに仲のいい夫婦だとは思っていた。いつも一緒に買い物に行っていたし、一緒にお風呂にも入っていたし、寝る時も同じベッドで一緒だった。しかし、「愛してる」という言葉を母にかける父親は、見たことがなかった。
さゆりは、静かに病室を出た。娘のわたしでさえ、立ち入ってはいけない夫婦だけの絆があるのだと感じた。父と母をふたりだけにしてあげること。それだけが今のさゆりに出来る最高の親孝行だと。
人が亡くなると、いきなりあわただしい日常が始まる。
葬儀業者への連絡、親戚や会社関係への連絡、葬儀業者との葬式の打ち合わせ、費用の工面、葬儀用の写真の手配、通夜の来訪者への対応、役所へ出向き火葬証明書の受け取りなど、雑用に忙殺され、悲しんでいる暇がなくなる。敏雄の携帯にも見慣れない電話番号が、ずらりと並んでいた。
しかし、妻に寄り添って線香をあげ続けた通夜の夜だけ、線香のゆらゆら揺れる煙をずっと眺めつづけながら、敏雄は悲しみの底に沈み、その現実を受け入れようともがいていた。
4日後、葬儀は無事にとりおこなわれ、親戚との会食も済ませ、遺骨と共に敏雄とさゆりは自宅に戻った。
「いろいろと手伝ってもらって、助かったよ、やっぱり子供がいると心強い」
「お父さんこそ、お疲れさま。お通夜の夜だって、お父さん、あんまり寝てないんじゃないの?」
「え、いやぁ、大丈夫だよ、お母さんのそばにいてあげたかったからさ、大丈夫だよ」
「でも、これからは食事に気を付けてもらわないと」
「あぁ、そうだなぁ、お前もすぐに引っ越すしな」
一人娘のさゆりは、1年前から付き合い始めた彼氏が栃木の実家の近くに引っ越すらしく、一緒に暮らすことになったのだ。
「お父さんは、料理ぜんぜん作れないから、引っ越すまでになんか教えようか?」
「いやぁ、いいよ、俺ヘタだしさ」
「でもさあ、お母さんのきれいな台所を汚されるのも、あたしとしてはイヤだな」
「そうだ、そうだ、料理しなければ汚れないよ」
「ほんとにお母さんは、台所をきれいに使ってたね、まさに自分のお城って感じで」
「うん、そうだな・・・いつもあの自作の布巾できれいにしてた。“台所はいつもきれいにしておかないとね”が、口癖だったよな~」
「そうね」
「うん・・・」
「今夜は、お母さんに教わった味噌汁作るから」
「うれしいね、頼むよ」
その日の夜。台所に立つ娘をぼんやりながめながら、敏雄は妻との日々を無意識のうちに思い出していた。
妻に乳がんが見つかったのは1年ほど前。
「お父さん、ここなんかあるみたい、さわってみて」と、朝食後、早苗が敏雄の手を自分の左胸に導いた。
「なんか、硬いのが入ってる、あれ?これって?」敏雄は驚いた。
「そんな感じがするけど」と早苗。
ガンという言葉は、ふたりともあえて使わなかった。
「よし、俺、今日は会社休むからすぐに病院に行こう」
「え?そんな急がなくても」
「いや、いや、今日行こう」
敏雄は妻を半ば強引に近所の総合病院に連れて行った。
診断は、かなり進行してしまった乳がん。
手遅れと思われる状態だった。
手術できる状態ではなかったので、その後は抗がん剤治療による入退院の繰り返しだった。妻も自分の状況は、冷静に理解してくれていた。
そして、最後の入院となった日の朝。
「そろそろ出ないと遅刻だぞ」と、敏雄は荷物を両手に持って玄関で待っていた。妻はリビングのテーブルで小さな紙に何やら書いている。やがて、早苗はその紙を持って台所に走って行った。ほどなくして戻った早苗は、「はいはい、お待ちどうさま」といつもの笑顔で敏雄に微笑みかけた。
「よし、行くぞ」とふたりは自宅の車に乗り込んだ。今回の入院が最後になるのだろうか、と予感しながらも、そうならないで欲しいという願いを頭の中で繰り返している敏雄だった。
妻が亡くなってから1週間後には、敏雄は職場に復帰していた。仕事は物流業。倉庫に勤務してフォークリフトに乗って、商品の入荷や出荷に携わっていた。
「だいぶ落ち着いてきたか?」と、休み時間に同僚が話しかけてきた。同じ年齢の彼は1年前に同じように妻を病気で亡くしていた。
「いやあ、まだまだ、なんだかんだとバタバタしてるよ」
「お前、料理とかなんにも出来ないから大丈夫か?」
「まあ、そのあたりは、なんとかするよ」その同僚は、料理は得意で逆に奥さんより夕飯を頻繁に作っていたようだ。
「ウチは料理のほうは心配なかったけど、俺さ、あんまり掃除とか洗濯ってしたことなかったから、そっちのほうがめんどくさかった」
「掃除、洗濯ねぇ、それは俺も家じゃめったにやらなかったけどさ」
「今さ、けっこういい洗剤とか、汚れ落とすもんとかすごいんだ」
「へぇ~」敏雄は、あまり興味なさそうに返答した。
でも、休み時間のそんな会話は、なんとなく敏雄の心に残っていた。
その日の仕事帰り。何気なく近所のホームセンターへ敏雄は足を向けていた。
「新しい洗剤かぁ、住宅用のクリーナーか、床用のワックスなんてのもあるんだ」と、陳列棚をながめる敏雄。
「これ使ってみようかな」と、床用のワックスを手にとった。そして購入。
その後、休日に自宅のフローリングに使ってみた。すると、驚くほどきれいな仕上がりになり、敏雄は驚いた。そして、これがきっかけとなり、敏雄は家事というものに少しずつ目覚めていったのだ。
娘のさゆりは、葬儀の一か月後に彼氏が待つ栃木へと引っ越していった。
引っ越しの日の日曜日の朝、娘の車に荷物を詰め込むのを敏雄は手伝ってあげた。引っ越しといってもそれほどの大荷物はなく、娘の自分の車に詰めれば済む範囲内だった。
「お父さん、こんなにたくさんの荷物入るかな?」
「大丈夫だと思う、お父さんは物流が仕事だから、荷物の扱いは任せておけって」そして、ルームミラーの視界は確保しながらも、きっちりとすべての荷物を積み込んだ。
「じゃ、行ってきます、これまでお世話になりました」
「おいおい、まだお嫁に行くんじゃないんだから」と、笑う敏雄。
「でも、家を完全に離れるのは初めてだしね、けっこう遠いし」さゆりのほうは、少ししんみりした表情だった。
「入籍はいつになるんだ?」
「来年の初めには考えてる」
「そっか、お前も今年は23になるんだから、そろそろ結婚も考えろよ。誠実そうな彼なんだから、これからは彼をほんとうに大切にしないと」
「うん、それは、わかってる。お父さんも体には気をつけて、もうお母さんいないんだから」
「俺は、大丈夫だよ」
「じゃ、ありがとう」
「うん、うん」
娘が小学生の頃から、別れるときはお互いの手のひらでハイタッチをするのが習慣だった。その日も、じゃあね、と言いながら、何度も。
幸いなことに、わが家では娘との関係は思春期になっても悪化することなく良好だったのだ。その日の朝、いつもより娘からのハイタッチの回数がかなり多かったのは、別れを惜しむ気持ちが強かったからなのだろうか。
こうして、敏雄は笑顔で娘を送り出した。
娘は車に乗り込み、運転席のウインドウを開けた。右手を車外に出して、右手の甲をこちらに向けて、数回手を振って走り去って行った。
娘の赤い車が角を曲がって見えなくなる。すると、敏雄に不思議な感情がこみあげてきた。淋しい、悲しい、つらい・・・。
娘が実家から離れていくことには、それほど抵抗がなかった敏雄だった。ほかの土地であっても、元気にがんばってくれるならそれでいいと考えていた。しかし、いざその日の朝になると、事情は違った。
娘の車が見えなくなった途端、涙がどっと、どこかの栓が外れたかのように溢れてきたのだ。自分でも、あれ?なんで?どうして?こんなに涙が流れるのだろうと、不思議な感じさえした。
家に入り、シャワーを浴びた。そして、号泣した。妻を失った悲しみとは、また違った別の涙だったのかもしれない。
敏雄は、シャワーを浴びてリビングに戻った。気持ちは少し落ち着いていた。リビングのテーブルに腰かけ、ぼんやり。
すると、まだ高ぶった気持ちがくすぶっていたのか、妻との日々が、まるで映画を観ているかのように次々と思い出されてきた。
50代をこえても妻とはいっしょに風呂に入って、お互いに背中を流し合っていたっけ。買い物にいくときは、いつも手をつないでいたっけ。
あの駅前のラーメン屋でいっしょに食べた坦々麺は、おいしかったなぁ。
上野公園を散策したこともあったっけ。
なんの展覧会だったか、美術館にもよく行ったし。
そういえば、妻はカレーが好きだったから、カレー専門店に行った回数は数えきれない。
そして、いつも同じベッドでいっしょに寝ることだけが、欠かせない日々の楽しみだったっけ・・・
敏雄は、妻の笑顔ばかりを思い出していた。
ぼんやりと通り過ぎてゆくままの思い出に身をゆだねている敏雄だったが、ふと我に返った。今日は窓にクリーナーを吹きかけて、きれいにしておこうかと。窓ガラスをきれいにすると、部屋の中の空気が変わることを敏雄は、自分で家事をするようになって初めて気づいた。そして、さっそく掃除に取りかかった。
****************************************
この続きは、のちほど~~
【追記】
そういえば、この小説をわたしが書いた初日に、Cozyさんも、あの小説「ナンバーワン・カフェ」を書き始めていて、期せずして同じ日に掲載スタートしていたという偶然の一致があって、これまたソウル親戚ですね、ってコメントしあっていましたっけ(笑)。
Cozyさんのコメントは、こちらです・・・
「こんばんは(^O^)/
同じ日に小説連載開始とは!
やっぱりソウル親戚ですね(^^♪」