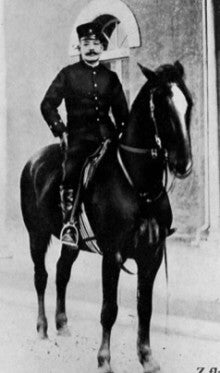
「男にとって必要なのは若いころに何をしようかと
いうことであり、老いては何をしたかということである」
「人は生計の道を講ずることに、まず思安すべきである。
一家を養い得てはじめて一郷と国家のために尽くす」
「そんなものは長じて読め。おのれの意見もない者が、
他人の意見を読むと害になるばかりだ」
「男子は生涯、一事をなせば足る 」
「身辺は、単純明快でいい 」
「のっけから運をたのむというのは馬鹿のすることぞ 」
「一個の丈夫が金というものでひとの厄介になれば、
そのぶんだけ気が縮んで生涯しわができる」
「酒をのんで兵を談ずるというのは、古来下の下だ
といわれたものだ。戦争という国家存亡の危険事を、
酒間であげつらうようなことではどうにもならんぞ」
「偉くなろうと思えば邪念を去れ、邪念があっては邪欲が出る。
邪欲があっては大局が見えない、邪念を去るということは、
偉くなる要訣だ」
「質問の本質も聞かずに弁じたてるというのは、
政治家か学者の癖だ」
「いかにすれば勝つかということを考えてゆく。
その一点だけを考えるのがおれの人生だ。
それ以外のことは余事であり、余事というものを
考えたりやったりすれば、思慮がそのぶんだけ曇り、乱れる」
「向いていなければさっさとやめる。
人間は、自分の器量がともかく発揮できる場所を選ばねばならない」
「自然の怯えを抑えつけて、悠々と仕事をさせてゆくものは
義務感だけであり、この義務感こそ人間が動物とは異なる高貴な点だ」
「軍人として、いざ戦いの場合、敵国に勝たしめるのが職分だ。
だから、いかにすれば勝てるかを考える。
兵隊の本務は敵を殺すにあり。その思考法は常に直接的だ」
秋山好古(あきやまよしふる)経歴(プロフィール)
1859年~1930年(安政6年~昭和5年)。
陸軍大将。日本騎兵隊の父。
松山藩の下級武士の家に生まれる。
陸軍士官学校卒業後、陸軍大学校を経て、明治20年フランスに留学。
日清戦争後、陸軍乗馬学校長に就任。騎兵科の確立に尽力。
日清・日露戦争では騎兵部隊指揮官として活躍した。
奉天会戦でロシア軍の敗因を作ったのは、
秋山支隊の牽制活動だったといわれる。
日露戦争後は騎兵監、近衛師団長などを歴任。
陸軍大将退役後は、郷里松山の中学校長を務めた。
71歳で没。
なべちゃりん