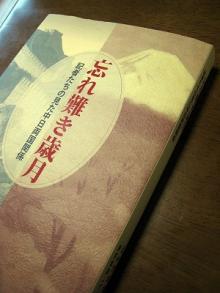第27回 国際ポットラックサロン「新おもてなし考」
最後の弟子が語る 恩師・三木成夫 ― その人となり
語り手 向川 惣一 レオナルド・ダ・ヴィンチ研究家
第19回に続いて2度目のご登場となりました向川惣一さんは、レオナルド・ダ・ヴィンチ研究家として世界的な業績も挙げておられます。
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-490-20606-7
注:論文集『レオナルド・ダ・ヴィンチの世界』《All about Leonard》

写真 三木成夫
■ 学生の力を正しく評価する三木成夫
三木成夫は向川さんが東京藝大修士課程2年目の夏、修士論文を書いている最中に亡くなられました。
向川さんは、いちばん最後の弟子です。
手を拡げた人の臍の位置と、大きな円までのところに黄金分割になっている所が3箇所あること、そしてそれを著した書物が一冊もないことを、世界で最初に気づいたのが向川さんです。
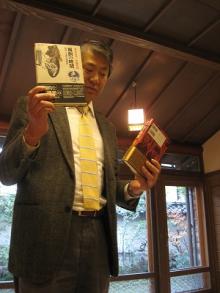
三木先生の言葉は、『僕は嬉しい』『向川君が見つけたことじゃなくて、日本人が見つけたことが嬉しい』でした。
「そのひと言を仰って下さったことが、先生が最初に認めてくれたことが、その後の苦労を苦労じゃなくしていますね」と仰る向川さんでした。
三木成夫の業績については、以下をご覧ください。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Hemingway/2397/Miki-shogaitogyoseki_0.htm
■ 今も続く「三木シンポジウム」
藝大の学生達を中心とした「三木教徒」と呼ばれる人たちがいます。
いわゆるシンパが集って年に1回開かれるのが「三木シンポジウム」です。
最近、その会場で見られるのは、茂木健一郎や荒俣 宏ら。
彼らも三木成夫の業績と研究フィールドに非常に関心を寄せています。
~~~~~~~~~~~~~~~
■ 東京藝大の駆け込み寺
藝大の学生からは、三木先生の診療室は駆け込み寺と言われていました。
在学中になくなる人が一番多いのが医学部と藝大だそうです。
藝大は音校と美校あわせても500人いない小人数の大学です。
毎年1人亡くなるというのは、たいへんなことです。
■ 医学部にも多い自殺者
医学部の場合、教養課程をクリアしたのち、実際の解剖がスタートした時期あたりが、危ないヤマなのだそうです。
それまでは勉強することに何の苦労も疑問もなく、自分でも優秀だと思い、やれば出来ると思っているような学生が、解剖という手作業で、自分の適性と限界を知ってしまうのです。
向川さんは言います。「適応できなくても止めてしまえる子はまだ強いんです。
ところが「親の期待、兄弟の期待、親戚一同の期待でもって国立大学の医学部へ入っちゃった子が、解剖が・・上手く適応できないと・・悩んでということが・・」
■ レオナルド・ダ・ヴィンチも書いています
画家に対する解剖書の中で『君、考えてみてくれたまえ、夜ひとり誰もいない部屋の中で、一人で解剖する。
ずっと集中して解剖しないと、それに耐えられる精神がないと、ここに私が残したような絵は描けないんだ』と。
その状況が学生に出てくるわけです。解剖は基本中の基本ですから、そこをクリアしないと知識の積み重ねは出来ません。
■ 「人間って弱い、非常に弱い、簡単に出ちゃう。」
将来やっていけないという、自信が無くなったときに、何かあると、例えば、失恋でもすると非常に簡単に死を選んでしまうのだそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~
向川さんは金沢大学の山田宗致先生(解剖学)のもとで5年間、解剖学を学んでいます。(因みに山田宗致と三木成夫は兄弟弟子です)
~~~~~~~~~~~~~~~~
■ 自殺者が激減
三木先生が東京藝大で講義されるようになってから、自殺者が“ごろっ”と減ったそうです。
以前なら自殺したような人たちが三木先生のところへ駆け込んできたのです。
東京藝大での授業風景についてもお話を伺いました。
■ 三木成夫の授業風景① ゲーテの原型論から
生物学の授業では「植物形態のメタモルフォーゼ」がとりあげられます。
学生達は植物の一生から、芸術の創造活動の根源がどこにあって、どういう表現が出て来て、どういうふうになるかを自分自身にあてはめて学びます。
卒業制作の自画像と、有名になった後の作品とを並べてみると学生達は分かると言います。
自分自身の美術の才と活動がどうなるか、何を一生懸命やらなくちゃならないのかが。
自分の力で掴んでいくヒントを、その授業から受け取るわけです。
~~~~~~~~~~~~~~
■ 授業風景②『胎児の世界』
―命というのはどういうものか、ということを考える授業―
写真 「胎児の世界」授業はこの本の内容そのもの
この本には「人類の地球に生命が生れてから46億年の生命のロマンは、単に地球が、今日あるところまでの生命のロマンだけではなく、人間が人間として生れてくる受精の瞬間から、46億年の時間と同じことを、その面影を、母親の胎内、子宮の中で、受精卵から胎児になる。
赤子は生れる前に経験している」ということが書いてあります。
松岡正剛の語る「千夜千冊」より
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0217.html
向川さんによる解説の一部をご紹介します。

―なぜ流産しやすいのか<魚から爬虫類へ>
向川:「多分、34日目がいちばん流産し易いはずなんです。
それは何なのか、ちょうどそれ以前の段階ではですね、胎児、赤ちゃんはまだ体がお魚の段階なんです」
「お魚の段階が34日目で、そこで両生類段階を急速に駆け上がって爬虫類になります。」
「お腹の中で、羊水の海の中にいたものが、陸上生活に適応するように体の 作り替えがおこなわれます。
それが一瞬の内におきます。
それが34日目、日にち、ちょっと間違えているかもしれませんけど、その1日で、その日のうちに全部終わります」
注:35日目から36日目にかけて
「で、その時期に重たいもの持ったり、階段から落っこちたりすると流産します」
(窒息死するわけだ! 何んらかのかたちで )
「そうです!そうです」
(34日目に陸に上がった魚か、それとも )
「海に落っこちた爬虫類か、どっちかの状態が起きるから、その時に窒息死する。だからその時が非常に大事なんです」
「学問としては、看護婦さんが習うような教え方では、妊娠34日目では、 胎児は、非常にアンバランスな状態ですから、流産し易いです、というような記述になります。そういう記述をいくら読んでも記憶に残りません。」
「ところが、そこのところを、上陸ですよ。そういう事を三木先生は授業で言っているもんだから、学生たちは絶対忘れません」。
「医学と関係ないんですよ、芸大の学生にしても。はぁーっていう、目が点になるような、命というのはどういうものか、ということを考える、そういう授業でね」
本日の参加者一同、目がテン状態でした。

~~~~~~~~~~~~~~
■ 授業風景③ 満席の階段教室、受講生には現役の医者たちも
向川さんが授業のスライド係を担当していた三木先生の授業は、いい席を取るために
始業前から階段教室がいっぱいになったそうです。
しかも最前列は「異様な集団」と表現される、東京医科歯科大などで三木先生から教えを受けた
現役のお医者さんたちが占めていました。
始業前に手描きされたという解剖図はチョーク1本で、プリントも見ないで描かれたそうです。
ダ・ヴィンチのような人物ですね。
保健管理センターのお医者さんとして週1回だけ担当していた三木成夫の授業は保健室登校のようなもの。
その授業ぶりは芸大始まって以来、最初で最後のものだったようです。
~~~~~~~~~~~~
三木成夫の経歴から、日本の解剖学の流れを伺いました。
■ 西 成甫の業績
ゲーテに始まり、ゲーゲンバウエルからヒュルブリンガーと連なるドイツの
近代解剖学(形態学)に学んだのが西 成甫です。
http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/showa.pdf#search='http://tojowww.dept.med.gunmau.ac.jp/'
西 成甫―浦 良治―三木成夫・山田宗致、そして向川さんと続くはずでした
が・・・
日本の解剖学は「解体新書」の前野良沢、杉田玄白の時代から100年を経ずして、世界の解剖学のトップレベルになりました。その頂点となったのが、西 成甫です。
写真 魚の段階から人間へ
■ 個体発生は系統発生をたどる
向川:「魚の頭と人間の頭は一緒ですよ、ね。それから、魚の尻尾と人間の尾てい骨は一緒ですよ、魚の胸ビレは人間の腕に相当します。それから、魚の腹ビレは人間の足に相当します」
「この事を、人間の体の筋肉で、どこが、どのかたちに、魚のどこの筋肉が人間のどの筋肉にかわったのか、というのを、系統的に全部明らかにしたのが、西 成甫先生の仕事、これは世界的な仕事なんです」
これは参考までに、母校に寄贈された西成甫の人骨標本
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1998Portrait/02/02100.html
■ ヒュルブリンガーから可愛がられた西 成甫
西 成甫が、留学先のイェナ大学から帰国の際に、師ヒュルブリンガーから譲られたのは、ゲーテに始まる、ドイツ形態学の頂点の大学の、その先生方のいちばん大事にしていた、学問的な、遺品の数々でした。
■ 三木成夫の勲章
その遺品を、西 成甫が東大を退官するときに貰ったのが、そのとき学生だった三木成夫です。
『これは私にとっては大変な勲章なんだ』と三木は言っていたそうです。
向川さんも三木先生から“この本は君が人体比例の研究を終えるまで使っていなさい”と渡された本があったそうですが、先生がお亡くなりになったので返されたそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~
■ 形態学者としてのゲーテを知らない何人かの参加者(筆者を含む)のために、ゲーテ学の講義をしていただきました。(詳細は割愛)
■ 見直されてきたラマルク・ヘッケル
ダーウィンとの論争に敗れたラマルクが見直されています。ラマルク説をとる三木ですが、弟子西原克成の存在が国内外でも三木の評価を高めています。
http://www.nishihara-world.jp/
「顔の科学」「内臓が育てる心」「追いつめられた進化論」など
~~~~~~~~~~~~~~
■ 金沢とのゆかり
◇ 非常に良心的といわれる勁草書房は、金沢が創業の地です。
福音館書店も、創業は金沢です。
http://www.fukuinkan.co.jp/company/ayumi.html
~~~~~~~~~~~~~~
■ 向川さんご持参のおすすめ図書
◇ 三木成夫「胎児の世界」上述のとおりです。
◇ 養老孟司「解剖の時間」
◇ 西原克成「 」(東京医科歯科大で三木成夫に私淑)上述のとおり
◇ 小林英樹「ゴッホの遺言」と「ゴッホの手紙」(東京芸大時代に 〃 )
これは世界的な研究書で、もの凄い、いい本です、とのことです。

~~~~~~~~~~~~~~
今回のサロンも、講師と参加者との絶妙なやりとりで、たいへんな盛り上がりようでしたが、多くを割愛いたしました。
「自分が三木成夫の弟子だということを意識して、皆さんに話したことはないと思っていたんだけど・・どうして?」と仰る向川さんです。
実は、向川さんの手になる追悼文から、三木成夫の存在と「胎児の世界」を知った主宰者の独断と偏見で、今回の話題に取り上げさせていただきました。
(文責 中島)