太平記〈上〉―マンガ日本の古典〈18〉 (中公文庫)/中央公論新社

¥637
Amazon.co.jp
太平記(中)―マンガ日本の古典〈19〉 (中公文庫)/中央公論新社
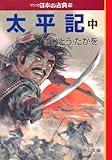
¥637
Amazon.co.jp
太平記(下)―マンガ日本の古典〈20〉 (中公文庫)/中央公論新社

¥637
Amazon.co.jp
こんにちは。
過去3回のブログでは、日本史の中でも「南北朝時代」に関することを記事にしました。
きっかけは朝日新書から出版されている「京都ぎらい」という本を読んだところ、著者の井上章一さんが本の中で、「第2次世界大戦が始まる前の大日本帝国時代には南北両朝を並列的に描く歴史教育が禁じられており、足利尊氏を評価した現役の大臣がそのせいで辞任へ追い込まれることもあった」。。。と述べられていたからです。
別にそんなところに喰いつかなくてもいい一文なのですが、私的には何でそんなことで政治家のしかも大臣クラスの人が辞任する必要があるのか不思議に思いました。この大臣が辞任した年をざっくり1900年頃として、南北朝時代は1300年頃のことなので、当時でも約600年も前の大昔のことについて発言したら現役の大臣が辞任に追い込まれるって大きな出来事だと思います。私にとって不思議でしょうがないので南北朝時代に何が起きたのか興味を持ってしまったのです。

▲四天王寺 太平記で楠正成、正行が敵を逃走させた地
そこで今回は南北朝時代に描かれた軍記物語、「太平記」を漫画で読んでみました。笑
「漫画かよっ!」と拍子抜けされる人もいるかもしれません。(^^;)
私的には太平記の内容を今回初めて知ることができましたし、漫画って素晴らしいなぁと思いました。難しい内容をさくっと理解したい時に漫画は絵なので頭にスッと入ってくるし、わかりやすくて便利と感じました。もちろん私も太平記の原文を読んでみたいと思って本屋さんで本を探したのですが、太平記の原文は40巻にも及ぶ超大作、そして現代語訳版でも量が多い。汗
私は激務で有名な業界に属する会社の会社員の身なんです。色々とやることがある中で、そこまでの時間を掛けたくありません。笑 まずは太平記の世界に触れるには漫画から。途中で挫折するくらいなら最初は簡単なものから始めてみる作戦です。

▲比叡山延暦寺 太平記で後醍醐天皇が足利尊氏との戦いの中で避難した
時代で言うと鎌倉幕府滅亡から室町幕府2代目将軍足利義詮が死ぬまでの約50年間の出来事を描いた物語で、現存する40巻は1370年頃には完成していたとされます。
あらすじをざっくり言いますと、鎌倉幕府に不満を持つ当時の天皇である後醍醐天皇は、幕府に不満を持つ武士を集めて戦争を起こして幕府を滅ぼします。後醍醐天皇は幕府を倒した後、日本の頂点に君臨して己の掲げる理想の政治を行うのですが失敗します。
鎌倉幕府を倒す時に後醍醐天皇側で大きな貢献をした足利尊氏は、後醍醐天皇の政治に不満を持つ武士と共に天皇に対して戦争を起こして勝利します。そして尊氏は後醍醐天皇を天皇の座から引きずり降ろし、新たな天皇を決めて新しい政治体制を作ります。しかし負けて幽閉されていた後醍醐天皇は奈良県の吉野に脱走して、尊氏側の政治体制を否定し正統な天皇は自分であると吉野山で主張しました。これにより天皇が同時期に2人存在するという異常事態になり、尊氏が立てた天皇側を北朝、後醍醐天皇側を南朝と呼ぶ、世に言う南北朝の対立が始まります。
しかし道半ばですが後醍醐天皇は病気で死にます。その後尊氏の弟である直義と尊氏の側近である高師直の権力争いをきっかけに、尊氏&高師直vs弟の直義で戦争が始まり尊氏側が敗北します。しかし尊氏は南朝側に降伏を申し出て南朝を味方に付けて、弟の直義に再び戦争を仕掛けて勝利するも、勝利の後は再び尊氏側と南朝側は対立し戦争を続けます。。。
話の大枠はこんな流れですが、50年間ずっと国内は戦争が起きている時代でした。太平記ではもっと細かく個々の戦争とそれに関わる登場人物達の姿が描かれている。

▲天龍寺 後醍醐天皇を祀る
最初に、漫画を担当された「さいとうたかお」さんのあとがきを一部引用させて頂きます。
【私は昭和11年生まれだ。天皇は神格を有し、その権威は絶対的なものと教えられて育った最後の世代である。しかし日本の敗戦によって、皇国史観は否定され、国民教科書の不都合な部分は墨で塗り潰されることになった。「日本歴史」に出てくる「忠臣」楠正成や新田義貞などのくだりは、ちょうど墨で消されてしまった箇所である。昨日までの英雄が突如として抹殺されたことに、私は子供心にも大きな戸惑いを感じたものだ。】
私は大学受験で日本史を専攻して京都にある同志社大学に合格したので、世の中の平均的な人よりも日本史の勉強を頑張ったという自負があります。ですが太平記で描かれる南北朝時代のことは知りませんでした。さいとうたかおさんの言う、英雄の楠正成のことは英雄どころか悪党=楠正成という単語を暗記したことを覚えています。なので日本史の教科書の内容が戦前と戦後では全く違うということ。
太平記の中で登場する人物の楠正成は後醍醐天皇に忠義を尽くす人物として描かれています。戦略家で頭も良く、自分達が少数であっても上手く戦略立案して戦争を勝利を導く武将です。そして最後の戦いの時は、負けるとわかっていても天皇に忠義を尽すために勇敢に戦って死ぬ英雄です。これにより戦前では楠正成は歴史上の人物でも人気者だったそうだ。おそらく楠正成のように天皇のために命を懸けること、忠義を尽くすことを美しいとする価値観が戦前の日本にあったのだろうと推測します。そしてこの価値観の延長線上には戦争時に特攻隊と呼ばれる、飛行機ごとアメリカ軍艦に捨て身で突っ込む行為に少しは影響を与えていると思います。
しかし戦後日本がアメリカに占領されていた時代に、アメリカの占領政策によって天皇に忠義を尽くす価値観を日本人から抹殺するために教科書の内容も改定されました。。。アメリカ人の感覚では自分の命を捨てて飛行機ごと突っ込んでくる日本人をもの凄く恐れたそうで、もう2度と日本人が戦争しないように意図的に日本の精神性を修正しようと占領政策を実施したとする説があります。

▲東寺 太平記では新田義貞が東寺の境内に陣取る足利尊氏に一騎打ちを申し込む
ではでは最初の疑問に戻りまして、
戦前に足利尊氏を肯定した大臣が辞任に追い込まれることになった理由は、天皇に刃向った足利尊氏を肯定することは、戦前の天皇に忠義を尽くすことを良しとする日本人の価値観とは真逆であり、天皇を否定することに繋がるから問題視されたのではないかと予想します。その名残なのか?私達は日本史の授業では南北朝時代のことを授業で簡単にしか触れることがありません。
もちろん細かいことをもっと勉強しないといけないと思いますが、「京都ぎらい」から始まった疑問が少し解けた気がします。笑。南北朝時代を知ることで、現代に通じる何かを学ぶことができる。ただの京都観光好きが、ちょっとだけ深い世界を知ることができました。大人になっての京都観光は学ぶことが多いのかもしれない。
つづく。

▲金剛山?を大神神社から眺める 楠正成の千早城があったのが金剛山。かすかに見える?葛城山かもしれません。。。汗

¥637
Amazon.co.jp
太平記(中)―マンガ日本の古典〈19〉 (中公文庫)/中央公論新社
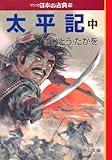
¥637
Amazon.co.jp
太平記(下)―マンガ日本の古典〈20〉 (中公文庫)/中央公論新社

¥637
Amazon.co.jp
こんにちは。
過去3回のブログでは、日本史の中でも「南北朝時代」に関することを記事にしました。
きっかけは朝日新書から出版されている「京都ぎらい」という本を読んだところ、著者の井上章一さんが本の中で、「第2次世界大戦が始まる前の大日本帝国時代には南北両朝を並列的に描く歴史教育が禁じられており、足利尊氏を評価した現役の大臣がそのせいで辞任へ追い込まれることもあった」。。。と述べられていたからです。
別にそんなところに喰いつかなくてもいい一文なのですが、私的には何でそんなことで政治家のしかも大臣クラスの人が辞任する必要があるのか不思議に思いました。この大臣が辞任した年をざっくり1900年頃として、南北朝時代は1300年頃のことなので、当時でも約600年も前の大昔のことについて発言したら現役の大臣が辞任に追い込まれるって大きな出来事だと思います。私にとって不思議でしょうがないので南北朝時代に何が起きたのか興味を持ってしまったのです。

▲四天王寺 太平記で楠正成、正行が敵を逃走させた地
ゴルゴ13の作者さいとう・たかをによる太平記の漫画版
そこで今回は南北朝時代に描かれた軍記物語、「太平記」を漫画で読んでみました。笑「漫画かよっ!」と拍子抜けされる人もいるかもしれません。(^^;)
私的には太平記の内容を今回初めて知ることができましたし、漫画って素晴らしいなぁと思いました。難しい内容をさくっと理解したい時に漫画は絵なので頭にスッと入ってくるし、わかりやすくて便利と感じました。もちろん私も太平記の原文を読んでみたいと思って本屋さんで本を探したのですが、太平記の原文は40巻にも及ぶ超大作、そして現代語訳版でも量が多い。汗
私は激務で有名な業界に属する会社の会社員の身なんです。色々とやることがある中で、そこまでの時間を掛けたくありません。笑 まずは太平記の世界に触れるには漫画から。途中で挫折するくらいなら最初は簡単なものから始めてみる作戦です。

▲比叡山延暦寺 太平記で後醍醐天皇が足利尊氏との戦いの中で避難した
太平記のあらすじ
時代で言うと鎌倉幕府滅亡から室町幕府2代目将軍足利義詮が死ぬまでの約50年間の出来事を描いた物語で、現存する40巻は1370年頃には完成していたとされます。あらすじをざっくり言いますと、鎌倉幕府に不満を持つ当時の天皇である後醍醐天皇は、幕府に不満を持つ武士を集めて戦争を起こして幕府を滅ぼします。後醍醐天皇は幕府を倒した後、日本の頂点に君臨して己の掲げる理想の政治を行うのですが失敗します。
鎌倉幕府を倒す時に後醍醐天皇側で大きな貢献をした足利尊氏は、後醍醐天皇の政治に不満を持つ武士と共に天皇に対して戦争を起こして勝利します。そして尊氏は後醍醐天皇を天皇の座から引きずり降ろし、新たな天皇を決めて新しい政治体制を作ります。しかし負けて幽閉されていた後醍醐天皇は奈良県の吉野に脱走して、尊氏側の政治体制を否定し正統な天皇は自分であると吉野山で主張しました。これにより天皇が同時期に2人存在するという異常事態になり、尊氏が立てた天皇側を北朝、後醍醐天皇側を南朝と呼ぶ、世に言う南北朝の対立が始まります。
しかし道半ばですが後醍醐天皇は病気で死にます。その後尊氏の弟である直義と尊氏の側近である高師直の権力争いをきっかけに、尊氏&高師直vs弟の直義で戦争が始まり尊氏側が敗北します。しかし尊氏は南朝側に降伏を申し出て南朝を味方に付けて、弟の直義に再び戦争を仕掛けて勝利するも、勝利の後は再び尊氏側と南朝側は対立し戦争を続けます。。。
話の大枠はこんな流れですが、50年間ずっと国内は戦争が起きている時代でした。太平記ではもっと細かく個々の戦争とそれに関わる登場人物達の姿が描かれている。

▲天龍寺 後醍醐天皇を祀る
太平記を読んだ感想
最初に、漫画を担当された「さいとうたかお」さんのあとがきを一部引用させて頂きます。【私は昭和11年生まれだ。天皇は神格を有し、その権威は絶対的なものと教えられて育った最後の世代である。しかし日本の敗戦によって、皇国史観は否定され、国民教科書の不都合な部分は墨で塗り潰されることになった。「日本歴史」に出てくる「忠臣」楠正成や新田義貞などのくだりは、ちょうど墨で消されてしまった箇所である。昨日までの英雄が突如として抹殺されたことに、私は子供心にも大きな戸惑いを感じたものだ。】
私は大学受験で日本史を専攻して京都にある同志社大学に合格したので、世の中の平均的な人よりも日本史の勉強を頑張ったという自負があります。ですが太平記で描かれる南北朝時代のことは知りませんでした。さいとうたかおさんの言う、英雄の楠正成のことは英雄どころか悪党=楠正成という単語を暗記したことを覚えています。なので日本史の教科書の内容が戦前と戦後では全く違うということ。
太平記の中で登場する人物の楠正成は後醍醐天皇に忠義を尽くす人物として描かれています。戦略家で頭も良く、自分達が少数であっても上手く戦略立案して戦争を勝利を導く武将です。そして最後の戦いの時は、負けるとわかっていても天皇に忠義を尽すために勇敢に戦って死ぬ英雄です。これにより戦前では楠正成は歴史上の人物でも人気者だったそうだ。おそらく楠正成のように天皇のために命を懸けること、忠義を尽くすことを美しいとする価値観が戦前の日本にあったのだろうと推測します。そしてこの価値観の延長線上には戦争時に特攻隊と呼ばれる、飛行機ごとアメリカ軍艦に捨て身で突っ込む行為に少しは影響を与えていると思います。
しかし戦後日本がアメリカに占領されていた時代に、アメリカの占領政策によって天皇に忠義を尽くす価値観を日本人から抹殺するために教科書の内容も改定されました。。。アメリカ人の感覚では自分の命を捨てて飛行機ごと突っ込んでくる日本人をもの凄く恐れたそうで、もう2度と日本人が戦争しないように意図的に日本の精神性を修正しようと占領政策を実施したとする説があります。

▲東寺 太平記では新田義貞が東寺の境内に陣取る足利尊氏に一騎打ちを申し込む
ではでは最初の疑問に戻りまして、
戦前に足利尊氏を肯定した大臣が辞任に追い込まれることになった理由は、天皇に刃向った足利尊氏を肯定することは、戦前の天皇に忠義を尽くすことを良しとする日本人の価値観とは真逆であり、天皇を否定することに繋がるから問題視されたのではないかと予想します。その名残なのか?私達は日本史の授業では南北朝時代のことを授業で簡単にしか触れることがありません。
もちろん細かいことをもっと勉強しないといけないと思いますが、「京都ぎらい」から始まった疑問が少し解けた気がします。笑。南北朝時代を知ることで、現代に通じる何かを学ぶことができる。ただの京都観光好きが、ちょっとだけ深い世界を知ることができました。大人になっての京都観光は学ぶことが多いのかもしれない。
つづく。

▲金剛山?を大神神社から眺める 楠正成の千早城があったのが金剛山。かすかに見える?葛城山かもしれません。。。汗