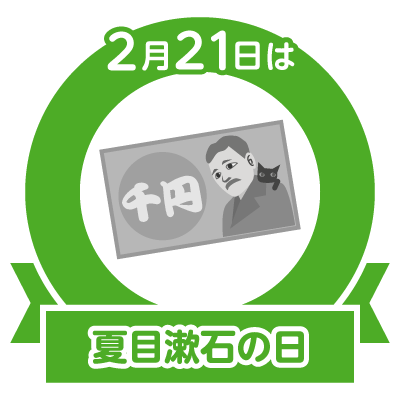※2018年4月20日に、別のアカウントで書いた記事を再編したものです。
今日は「夏目漱石の日」だそうです。
文部省が漱石に「文学博士」の称号を送ると伝えたのに対して、1911年の今日、漱石自身が、
「自分に肩書きなど必要ない」
という理由で、博士号を辞退する旨を書いた手紙を、当時の文部省専門学部局長に送ったことに由来するそうです。
漱石さんが言うと、さまになる気がします。
さて、どうして「こゝろ」について、昨年の4月20日に書いていたのかと言うと、この日は朝日新聞で連載が始まった日だからです。
1914年のことです。
最初の題名は、「心 先生の遺書」だったそうですが、後に改題し、「こゝろ」となったようです。
左が角川書店版、右が新潮社版
高校生の頃、国語の教科書にのっていて、このときばかりは授業がやたらに盛り上ったような記憶があります。
当時(30数年前)恋愛について興味津々だった私には、たまらない題材でした。
恋愛の駆け引きというか、いわゆる三角関係が原因で、結局のところ二人の男性が自殺してしまうというストーリーです。
現代ではあまり考えられないようなシチュエーションですが、そこに至るまでの心理描写が、高校生にもなると、「わからなくもない」のです。
卒業してからも何回か読み返した小説でもあります。
「こゝろ」といえば特に印象に残っているのが、
「Kは穴だらけというよりむしろ開け放し」
というフレーズです。
主人公が友人Kの、あまりにも無用心な様子を表現した言葉です。
当時、高校生にして「中二病」真っ只中だった私には、たまらない表現でした。
次女(高三)に、「こゝろ」の感想を聞いてみたことがあるのですが、
「私、あんまり良いとは思わない。
『吾輩は猫である』とか『坊ちゃん』の方が、名作だと思うけど。」
と言っていました。
現代の高校生には、この手の恋愛ストーリーはピンとこないのでしょうね。
※写真はイメージです
ネットで調べてみると、「こゝろ」は突っ込みどころ満載だからこそ議論しやすい、だからこそ教材として扱いやすい、という旨が書いてありました。
名作だから教科書に載ったのではなく、教科書に載ったから名作として扱われている、という手厳しいご意見もありました。
「わからなくもない」という気がします。
100年以上も昔、夏目漱石の作品が新聞連載されていたなんて、当時の方々はどんな風に受け止めていたのでしょうかね。
ちなみに、漱石さん、胃弱にもかかわらず、大の甘党だったそうです。
特にアイスクリームが大好物で、家族に内緒で業務用のアイスクリーム製造機を取り寄せ、奥様と大喧嘩になったことがあるそうです。
天才にして文豪とは、何一つ共通点はないと思っていましたが、一つだけありました。(笑)
こんなのごちそうしてさしあげたかったです
皆様は、「こゝろ」にまつわる思い出がありますか?
それでは、ごきげんよう!
「こころ」読んだことある?
▼本日限定!ブログスタンプ