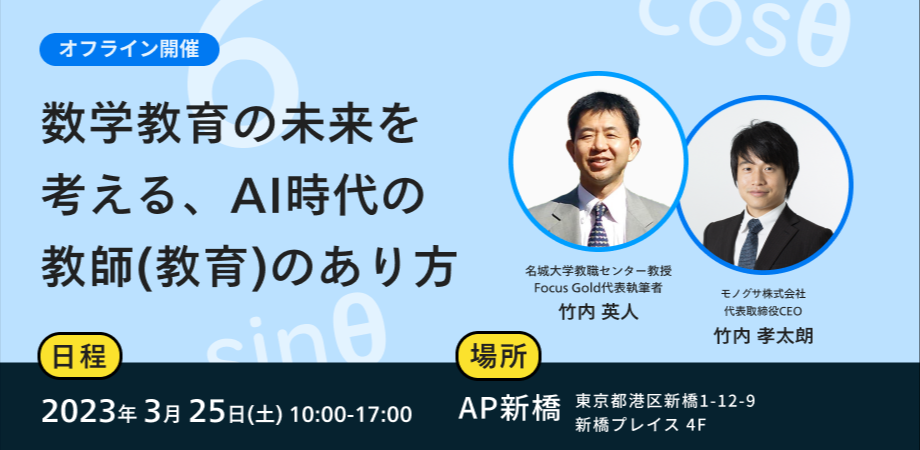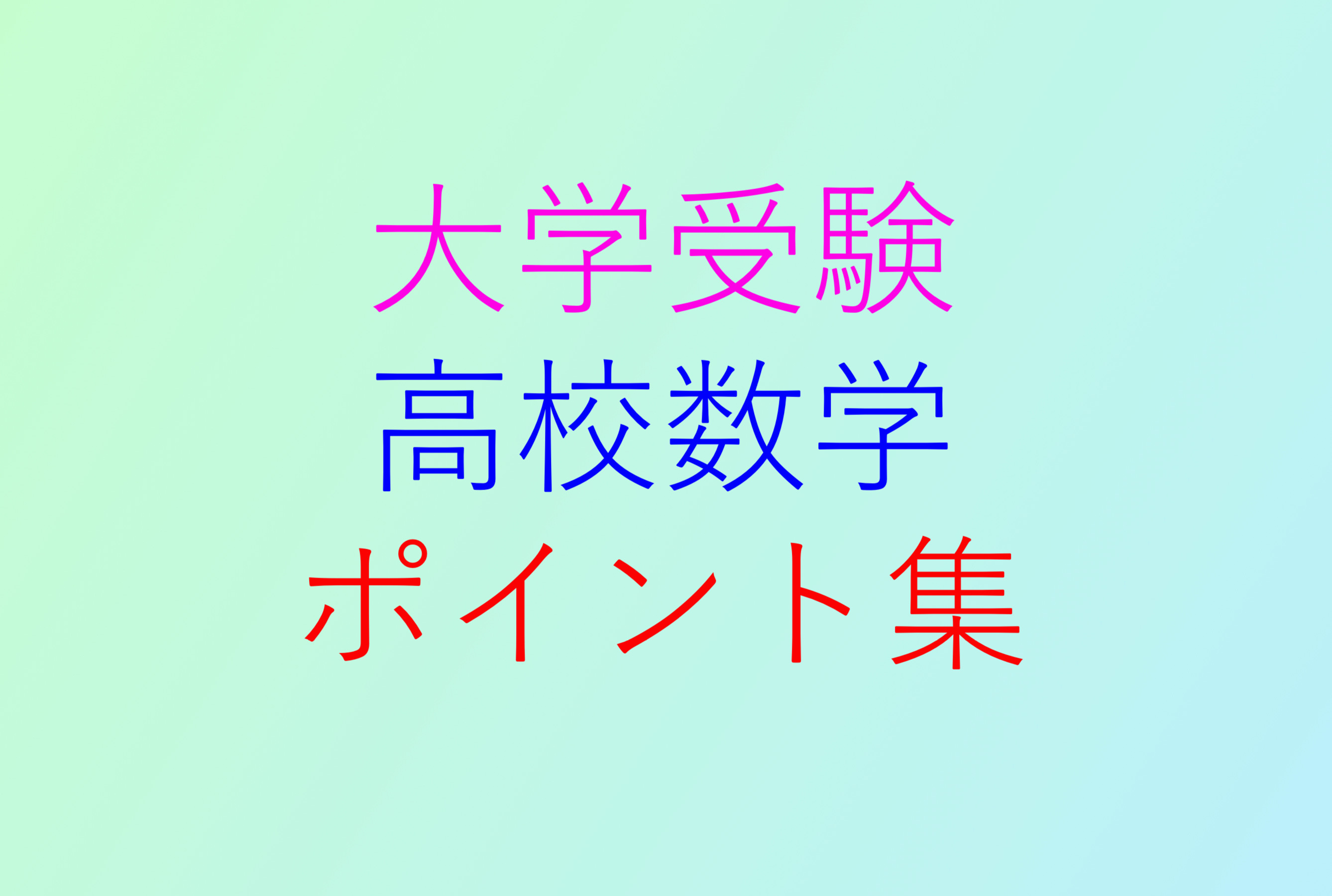いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今日はこちらに参加をしました。
モノグサ主催の「数学教育の未来を考える」という研修会。
登壇者の豪華さ…。
参加された先生方は全国各地から150名ほどでした。
この中に入れる幸せさ…。
この数週間のAIの発達については目覚ましいものがあります。
数年、ではなく、数週間、です。
↑PR TIME記事
恐らくこのまま適当なことをしていたら、私たちはAIに負けてしまうでしょう。
では、何なら勝てるのか? またはどのように共存するか、というテーマが主だったと思います。
GPTー4を使ってみると、そのレベルがわかります。
ただ数学を教えるのであれば、こちらの方がいいかもしれません。
これがその生徒の理解度を把握すれば、反復学習も可能です。
うまく使えば、個別最適の教育が実現できるかもしれません。
しかし、私たち人間にしかできないこともあります。
生徒をしっかりみること。アナログで泥臭い教育を続けること。
これはAIにはできないはずです。
例えば、点と直線の距離の公式。覚えなければならない上に、証明は面倒です。
↑ポイント集より
正しい指導は、きちっと証明することでしょう。
ですが、文系の数学苦手チームに証明を教えるでしょうか?
軽く扱って流す、なんてこともありではないでしょうか。
それがアナログです。
AIとの共存のためには「正しさ」と「分かりやすさ」が
どうしても対立します。AIは正しさ、我々は分かりやすさを
優先させます。ここをすみ分けて、うまくやることが
これからの教育の1つの形なのかもしれません。
そんなことを考えた1日でした。
続きます。