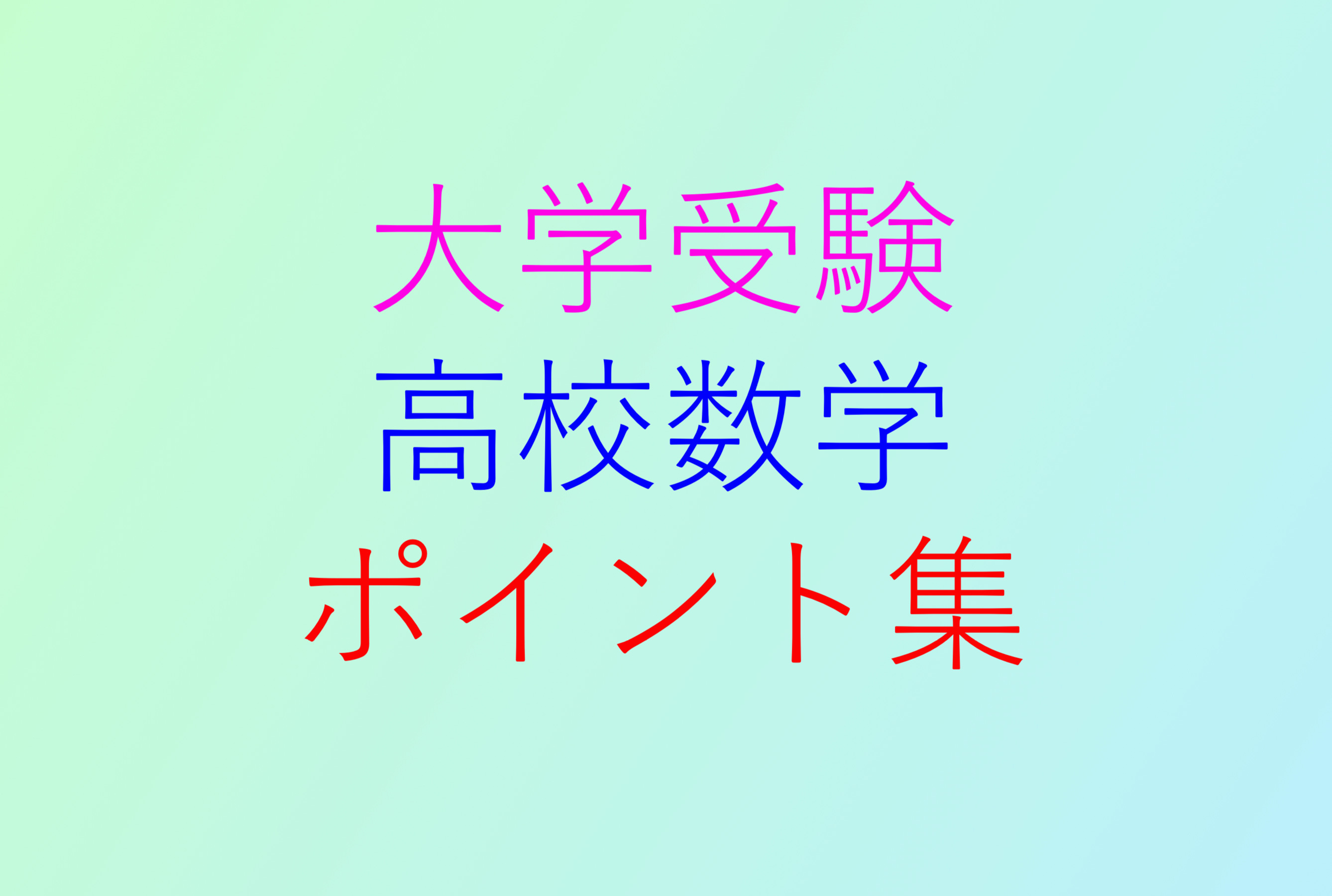いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今日は授業の話です。
授業中、教科書の問題を解いてもらうことが多いんです。
ほとんど説明もなしに、初見で。
すると、生徒は試行錯誤するわけです。
その時に幾つかの誤答が生まれるので、いいものは
その誤答を解説します。
例えば、漸化式でなんでもかんでも特性方程式を使う生徒が
出てきます。
↑ポイント集より。途中のαの式を特性方程式、と呼ぶことが多いです。
それがなぜダメか、を考えてもらいます。
この時に、生徒のノートを見てみると、
・正答を書いてくる生徒
・誤答を書いてくる生徒
・手が動かない生徒
の3パターンいることがわかります。
一番下が問題です。何も考えていないから手が動かないのか、ずっと考えて
手が動かないのかは、経過観察しないとわかりません。
個人的には前者が多い気がします。まずは代入したりしていろいろ考えてみなさいよ、
といいたいですが、言ってもなかなか動かないのです。
答えがパッ、と閃くわけではないので、間違う覚悟で手を動かしてほしいと思っています。
これって普段の習慣や考え方の癖なんですよね。そういうところを鍛えるのは
結構大変で、中学受験までで固定されきったパターンもよく見ます。
それはこちらがどんなに頑張っても成績が伸びないので、辛いです😭
かといって見捨てるわけにはいきません。
だからこちらのアドバイスを素直に受け入れてくれるだけの信頼関係を
作らないといけません。これもまた辛いんです💦
だから、生徒1人の成績をあげるって、大変な場合もあるんです。
そんなことを言いたいがために記事にしました。