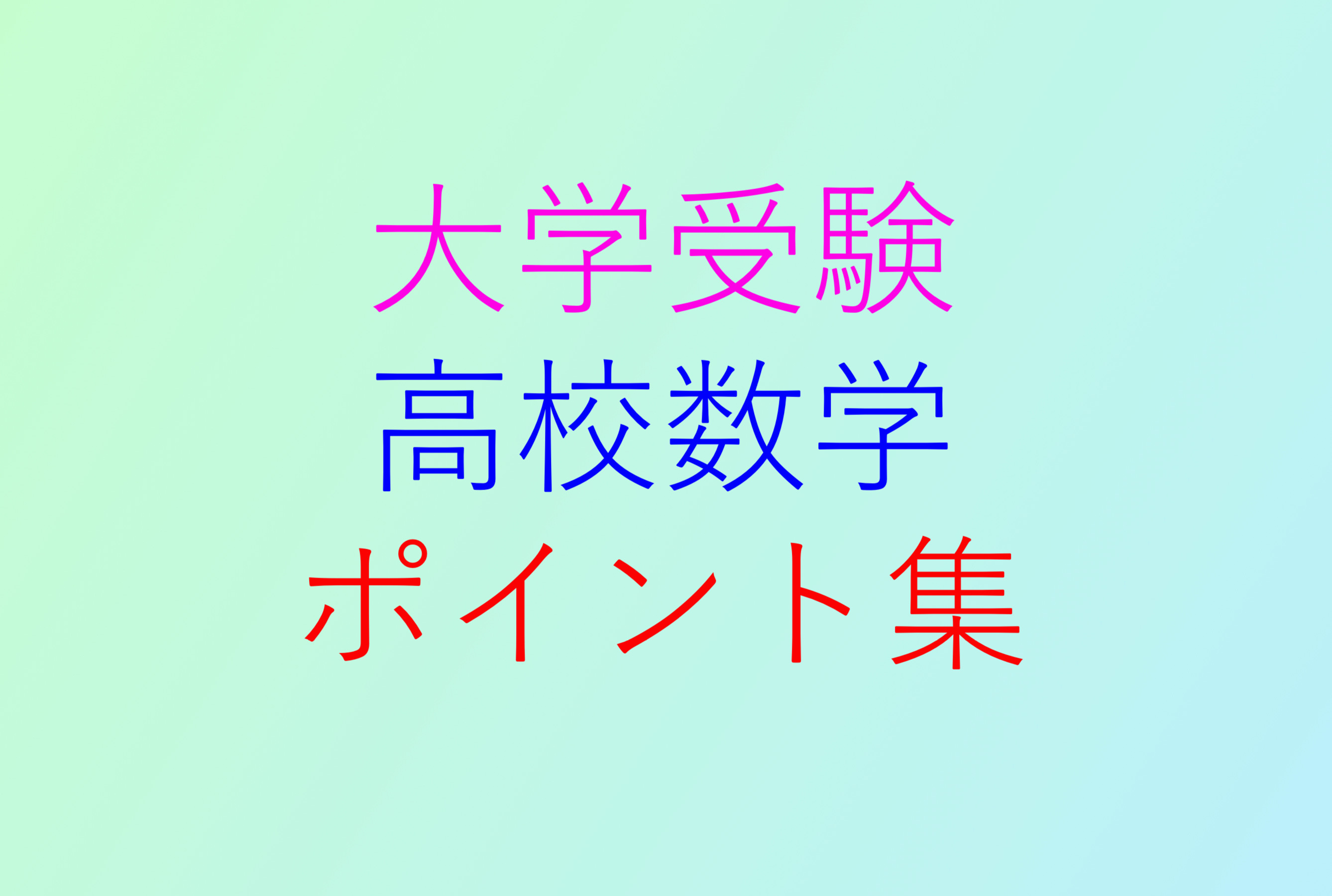いつもご覧いただき、ありがとうございます。
昨日は色々ありまして、記事をあげることができませんでした…
昨日の授業の話です。正弦定理を扱いました。
余弦定理と並ぶ、美しい定理です。
↑永島先生のポイント集より
正弦定理を教えると、「公式を覚えてもらう」ことに力を注ぎがちだった
ので、数学Aの外心と絡めて教えることにしました。
・どういう時に正弦定理を使うのか
・図形をどのように見ればいいのか
を教えるために、この日は外心の話をしました。
先日数学Aでやったはずが、生徒は忘れているものです。
「円周角の定理って何かな??」
と訊いても、正確に答えられた生徒はいませんでした。
そういう予備知識が抜けた状態で話をしても、結局は
暗記になってしまうので、論理を教えるためにも、
やはり基礎事項を教えないとなりません。
念のためですが、正弦定理等の公式を覚えることに
否定はありません。ただ、覚えることが目的となったり、
定期試験で点数を取ることだけが目的となるようでは
まずいと感じているだけです。
しかし、正弦定理が円周角の定理を拡張させたもので
ある以上、円周角の定理を知らないとまずいので、
こうして教えています(教科書にもきちんと書いてあります)。
↑高校数学の美しい物語(正弦定理)に詳しいです
なるべくは、今まで習った内容とリンクをさせたいので、
色々考えながら授業を考えています。
それが生徒の理解度の定着につながればいいなと
個人的には思っています。