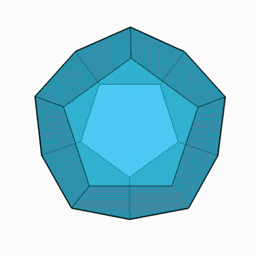いつもご覧いただき、ありがとうございます。
入試業務の間に、共通テスト自己採点で生徒が登校しました。
(予想通り)悲壮感漂う感じの生徒が多く、そのまま直接orZoom or 電話で
面談しまくりました。
とにかく私は笑顔。「何ヘマしてんだよ」くらいのノリで、
次の試験に向けてのアドバイスを入れました。
こちらが堂々としていないと、絶対に生徒のメンタルは
崩れると思ったので…。
気付いたら21時…
受験で落ちる原因の1つはセンター試験後のメンタルなので、
そこをうまくやるのが担任の役割の1つだと思います。
明日も結構な数の生徒と面談したり、共通テストの解説会をします。
そのあとでⅡBを(確率分布をのぞいて)解きました。
以下、ネタバレ注意です。
第1問
[1] 三角関数の合成ですが、cosで合成するあたりがいいです。
最初の問題はπ/3を答えるのですが、問うているのは知識ですよね。
三角関数の合成の場合、どうしてこの式になるのかを教科書で勉強すると
sinでもcosでも対応できます。要するに、加法定理の逆です。
ちなみに、私はどうしても選択肢から選ぶタイプに慣れません。
「四角に当てはまらない、どうしよう!」と絶対なります(笑)
[2] いきなり出てくるのは、双曲線関数です。
性質を知っていても、そうでなくても誘導に従えば解けます。
個人的には「太郎さんが考えた式」が好きです。
どうして他の3つが成り立たないのか、グループワークさせたい問題です。
第2問
グラフとy軸との交点における接線の一般化の問題です。
問題が進むにつれて、次数や項が上がってきます。
ⅠAのデータの分析でもそうですが、式と図の対応を考えるのは
「思考力」の1つと捉えている節があるようで、試行調査もその傾向がありました。
式からグラフを選ばせる問題が2問ありましたが、この傾向は今後も続くかもしれません。
(領域を選ばせる問題が以前に出ていますので、似た問題の出題の可能性はあります。)
ちなみに、全体的にも計算自体はあまり要求されていません。
第4問
センター試験の数列が複雑化してきていた中で、シンプルにリニューアルした印象があります。
誘導がすごく丁寧で、それに乗っていけば公差と公比が出ます。
個人的には「こういうやり方もあるんだ」と感心しておりました。
後半は、条件が変わってくるのですが、聞いてくることは単純で、
難易度は高くありません。
第5問
五角形の問題です。2016年追試が正八角形の問題で、授業でも扱ったので、
「ほほう」と思いました。生徒はできなかったようですが(泣)。
前半は平行である2直線を考えて、誘導に乗るだけです。
黄金比が出てくるので、a^2-a-1=0が出てくることが明らかです。
↑こちらのサイトで詳しく書かれています。
次は正十二面体です。
センターに比べると、内積計算もシンプルなので、解きやすいです。
正八面体に比べると、トピックは薄いですが、色々性質があるので、
授業でも使おうかと思いました。
この先は全て誘導に乗れば出てきます。
数学ⅠAよりもセンター寄りなので、
努力が報われる試験かもしれません。