昨日は、バス業界の規制緩和を取り上げました。そのなかで
タクシー業界についても利用者不在の責任の瑕疵構造が見ら
れますので、昨日に続いてタクシーの規制強化を取り上げま
す。
先日の新聞で、タクシー事業の「免許制」を復活させる法改
正案が報道されました。
タクシー業界も、貸切バス事業と同様に規制緩和で参入が増
え、ドライバーの就業環境の悪さが安全性低下に繋がってい
るのではないかと、規制強化を求める声が上がっています。
タクシー業界の問題点として指摘されるのは、運転手の給与
が歩合制のため、タクシー台数増加と景気低迷のダブルパン
チを受けたタクシー運転手が、収入確保のため長時間労働を
せざるを得ない状況に追い込まれているという点です。
タクシー業界の規制を所管する国交省は、この状況に対し需
給バランスの悪化によって安全性が低下しているとして、現
在は指定する特定地域で規制を強化しています。
今回の法改正の報道は、免許制というさらに一段進んだ規制
強化によって、行政が供給台数を直接コントロールしようと
するものです。
しかし、これも貸切バス業界と似て、消費者のニーズと供給
側とのサービス提供とにミスマッチがあります。
タクシーに対する一般的なニーズとして、希望の場所へ今い
る場所から、(車内を独占するなど)快適に移動したいという
ものです。
多くのタクシー会社も、顧客ニーズに対してこのレベルの認
識で事業を営んでいるため、個別の顧客のニーズを掘り下げ
る営業努力より、人通りの多い駅や病院、イベント施設等で
乗客を拾う「時代遅れのマスマーケティング」による商売に
よって、経営を成り立たせているように見えます。
一方、タクシーを利用する顧客の方は、
・(配車依頼から)長く待たないで乗りたい、
・(禁煙車など)快適な車内が欲しい、
・(スムーズな運転をする)上手な運転手がいい、
・同じお金を払うのなら、多様な決済手段やポイントが欲しい、
さらに、病院等への移動で使うなら、
・介助をしてくれたり、いつも同じ運転手さんだと安心だ、
(さらにさらに、同じ乗るのなら、エコドライブが上手な運転
手さんだと、燃費もいいはずだし乗り心地も良さそうだから
ぜひ選んで利用したい)
→ニーズは多様化している
ということになります。
この多様化した消費者ニーズに、タクシー会社が十分なサー
ビス提供が出来てなお供給過剰だというのなら、規制を強化
する合理性がありますが、消費者が乗りたいタクシーを選べ
るだけの十分な評価環境がないままで、行政が規制によって
サービス環境を規定してしまうのは進歩がありません。
タクシー業界に進歩がないのは、問題視されている給与の歩
合制だけではありません。もうひとつあります。順番にみて
いきますと、
給与の歩合制をタクシー会社側からみると、売上に応じて人
件費が掛かることになるので、売上に対する直接費が一定に
なる効果があるため、燃料消費過多で人件費が圧迫される程
の低稼働率にならない限り(人件費と燃料費では0がひとつ
違うのだから、そんなことはまずあり得ない)、キャッシュ
フローは安定します。
従って、タクシー会社で業績を上げたければ、出来るだけ運
行する車両の台数を増やし、許可されている営業エリアでの
台数ベースでのシェアを上げればよい、という安易な経営が
行われる環境です。
もうひとつは、サービス提供の最前線にあるタクシー運転手
さんに対する過剰と思われる規制です。
タクシー運転手は、タクシー会社に勤めて日々営業に出ます。
先述の通り、タクシー台数の増加と景気低迷で、売上確保に
苦労します。せっかく苦労して確保した売上も、給与歩合制
のため、一部は会社のものになります。
「それなら、いっそ独立して自分で営業しようか?」
他の業界なら、従業員がこう考えることも、よく見られるこ
とでしょう。しかしタクシー業界では、それが難しいのです。
その理由は、タクシー業界の過剰規制にあります。
タクシー事業を営みたい場合、タクシー会社を作って複数台
走らせる「法人タクシーの許可」と、運転手が個人事業とし
て1台を走らせる「個人タクシーの許可」の2種類がありま
す。個人タクシーの存在はおなじみだと思います。
会社に勤める条件が悪ければ、個人タクシーを開業すればい
いじゃないかと思われるでしょうが、個人タクシーの許可を
取得するには、タクシー会社でタクシー運転手を最低10年
勤めなくてはならないという規制があります。
皆さまご存知かもしれませんが、タクシー運転手になるには
普通自動車免許を保持しているだけでは不十分です。第2種
の普通自動車免許が必要です。いわゆるプロ向けの運転免許
です。
ただでさえ、プロ向けの運転免許が必要なのに加えて、更に
タクシー会社で10年以上勤めないと個人タクシー業を開業
する資格が与えられないのです。これって過剰規制ではない
ですか?
ちなみに、私が営んでいる行政書士業は、行政書士試験に合
格して登録すれば、すぐに個人事務所を開業することが可能
です。
同じような規制産業でも、これだけ規制の強弱に差があるの
です。
タクシー運転手の場合は、前提として第2種の運転免許を保
持しているのだから、タクシー運転手としてのタクシー会社
での実務経験など、せいぜい2~3年あれば十分開業できる
と思いますが、いかがでしょうか。
もし個人タクシー開業の実務経験規制が緩和されれば、タク
シー運転手が会社に就職して仕事が出来るようになれば、数
年で独立して稼げるようになりますから、運転手も高品質な
サービス提供に意識が向きます。
一方、タクシー会社も売上を上げてくれる優秀な運転手には
辞めてもらっては困るので、相応の給与を支払うようになる
でしょう。給与は一律の歩合制でなく、本来の意味での能力
給として効果的に制度運用ができるはずです。
また消費者からみれば、どのタクシー会社の運転品質が高い
とか、サービスが良いとか、エコドライブだから贔屓にした
いとか、様々な観点からの総合評価でタクシー会社を選べる
ようになります。
無論、優秀な運転手が独立したら、運転手指名で乗りたいと
か、または優秀な運転手ばかりを集めて高級車を使用したプ
レミアムハイヤー会社が生まれることだってあるでしょう。
つまり、個人タクシー開業の実務経験規制を緩和するだけで、
タクシー会社とタクシー業界を健全化させることは十分に可
能なのです。
運転手の就業環境が問題なら、就業環境を改善する規制を導
入するのが正攻法の筈ですから、安易な規制強化では安易な
経営でぬるま湯に浸かっているタクシー会社を放置・温存す
ることになり、むしろ安全性低下が進む環境を行政によって
促進させることに繋がるのではないでしょうか。
消費者がもっとタクシーを利用したくなる、
運転手が安全確実でやる気をもって働く、
タクシー会社も品質の高いサービスを売りものに競争する、
そんな三方良しの環境を作るのが、行政の役目だと思います。
※この記事は、メルマガ記事の加筆・修正版であり、ビジ
ネスに関する情報はメルマガを優先して公開しています。
いち早く最新情報をお読みになりたい方は、まぐまぐから
無料でメルマガ登録 できます。






![あのひと検索 SPYSEE [スパイシー]](https://image.space.rakuten.co.jp/lg01/28/0000102328/67/img54e4d61bzik0zj.gif)
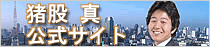
感謝!
タクシー業界についても利用者不在の責任の瑕疵構造が見ら
れますので、昨日に続いてタクシーの規制強化を取り上げま
す。
先日の新聞で、タクシー事業の「免許制」を復活させる法改
正案が報道されました。
タクシー業界も、貸切バス事業と同様に規制緩和で参入が増
え、ドライバーの就業環境の悪さが安全性低下に繋がってい
るのではないかと、規制強化を求める声が上がっています。
タクシー業界の問題点として指摘されるのは、運転手の給与
が歩合制のため、タクシー台数増加と景気低迷のダブルパン
チを受けたタクシー運転手が、収入確保のため長時間労働を
せざるを得ない状況に追い込まれているという点です。
タクシー業界の規制を所管する国交省は、この状況に対し需
給バランスの悪化によって安全性が低下しているとして、現
在は指定する特定地域で規制を強化しています。
今回の法改正の報道は、免許制というさらに一段進んだ規制
強化によって、行政が供給台数を直接コントロールしようと
するものです。
しかし、これも貸切バス業界と似て、消費者のニーズと供給
側とのサービス提供とにミスマッチがあります。
タクシーに対する一般的なニーズとして、希望の場所へ今い
る場所から、(車内を独占するなど)快適に移動したいという
ものです。
多くのタクシー会社も、顧客ニーズに対してこのレベルの認
識で事業を営んでいるため、個別の顧客のニーズを掘り下げ
る営業努力より、人通りの多い駅や病院、イベント施設等で
乗客を拾う「時代遅れのマスマーケティング」による商売に
よって、経営を成り立たせているように見えます。
一方、タクシーを利用する顧客の方は、
・(配車依頼から)長く待たないで乗りたい、
・(禁煙車など)快適な車内が欲しい、
・(スムーズな運転をする)上手な運転手がいい、
・同じお金を払うのなら、多様な決済手段やポイントが欲しい、
さらに、病院等への移動で使うなら、
・介助をしてくれたり、いつも同じ運転手さんだと安心だ、
(さらにさらに、同じ乗るのなら、エコドライブが上手な運転
手さんだと、燃費もいいはずだし乗り心地も良さそうだから
ぜひ選んで利用したい)
→ニーズは多様化している
ということになります。
この多様化した消費者ニーズに、タクシー会社が十分なサー
ビス提供が出来てなお供給過剰だというのなら、規制を強化
する合理性がありますが、消費者が乗りたいタクシーを選べ
るだけの十分な評価環境がないままで、行政が規制によって
サービス環境を規定してしまうのは進歩がありません。
タクシー業界に進歩がないのは、問題視されている給与の歩
合制だけではありません。もうひとつあります。順番にみて
いきますと、
給与の歩合制をタクシー会社側からみると、売上に応じて人
件費が掛かることになるので、売上に対する直接費が一定に
なる効果があるため、燃料消費過多で人件費が圧迫される程
の低稼働率にならない限り(人件費と燃料費では0がひとつ
違うのだから、そんなことはまずあり得ない)、キャッシュ
フローは安定します。
従って、タクシー会社で業績を上げたければ、出来るだけ運
行する車両の台数を増やし、許可されている営業エリアでの
台数ベースでのシェアを上げればよい、という安易な経営が
行われる環境です。
もうひとつは、サービス提供の最前線にあるタクシー運転手
さんに対する過剰と思われる規制です。
タクシー運転手は、タクシー会社に勤めて日々営業に出ます。
先述の通り、タクシー台数の増加と景気低迷で、売上確保に
苦労します。せっかく苦労して確保した売上も、給与歩合制
のため、一部は会社のものになります。
「それなら、いっそ独立して自分で営業しようか?」
他の業界なら、従業員がこう考えることも、よく見られるこ
とでしょう。しかしタクシー業界では、それが難しいのです。
その理由は、タクシー業界の過剰規制にあります。
タクシー事業を営みたい場合、タクシー会社を作って複数台
走らせる「法人タクシーの許可」と、運転手が個人事業とし
て1台を走らせる「個人タクシーの許可」の2種類がありま
す。個人タクシーの存在はおなじみだと思います。
会社に勤める条件が悪ければ、個人タクシーを開業すればい
いじゃないかと思われるでしょうが、個人タクシーの許可を
取得するには、タクシー会社でタクシー運転手を最低10年
勤めなくてはならないという規制があります。
皆さまご存知かもしれませんが、タクシー運転手になるには
普通自動車免許を保持しているだけでは不十分です。第2種
の普通自動車免許が必要です。いわゆるプロ向けの運転免許
です。
ただでさえ、プロ向けの運転免許が必要なのに加えて、更に
タクシー会社で10年以上勤めないと個人タクシー業を開業
する資格が与えられないのです。これって過剰規制ではない
ですか?
ちなみに、私が営んでいる行政書士業は、行政書士試験に合
格して登録すれば、すぐに個人事務所を開業することが可能
です。
同じような規制産業でも、これだけ規制の強弱に差があるの
です。
タクシー運転手の場合は、前提として第2種の運転免許を保
持しているのだから、タクシー運転手としてのタクシー会社
での実務経験など、せいぜい2~3年あれば十分開業できる
と思いますが、いかがでしょうか。
もし個人タクシー開業の実務経験規制が緩和されれば、タク
シー運転手が会社に就職して仕事が出来るようになれば、数
年で独立して稼げるようになりますから、運転手も高品質な
サービス提供に意識が向きます。
一方、タクシー会社も売上を上げてくれる優秀な運転手には
辞めてもらっては困るので、相応の給与を支払うようになる
でしょう。給与は一律の歩合制でなく、本来の意味での能力
給として効果的に制度運用ができるはずです。
また消費者からみれば、どのタクシー会社の運転品質が高い
とか、サービスが良いとか、エコドライブだから贔屓にした
いとか、様々な観点からの総合評価でタクシー会社を選べる
ようになります。
無論、優秀な運転手が独立したら、運転手指名で乗りたいと
か、または優秀な運転手ばかりを集めて高級車を使用したプ
レミアムハイヤー会社が生まれることだってあるでしょう。
つまり、個人タクシー開業の実務経験規制を緩和するだけで、
タクシー会社とタクシー業界を健全化させることは十分に可
能なのです。
運転手の就業環境が問題なら、就業環境を改善する規制を導
入するのが正攻法の筈ですから、安易な規制強化では安易な
経営でぬるま湯に浸かっているタクシー会社を放置・温存す
ることになり、むしろ安全性低下が進む環境を行政によって
促進させることに繋がるのではないでしょうか。
消費者がもっとタクシーを利用したくなる、
運転手が安全確実でやる気をもって働く、
タクシー会社も品質の高いサービスを売りものに競争する、
そんな三方良しの環境を作るのが、行政の役目だと思います。
※この記事は、メルマガ記事の加筆・修正版であり、ビジ
ネスに関する情報はメルマガを優先して公開しています。
いち早く最新情報をお読みになりたい方は、まぐまぐから
無料でメルマガ登録 できます。
感謝!