『かくれ躁うつ病が増えている〜なかなか治らない心の病気〜』
というタイトルの本を読みました。
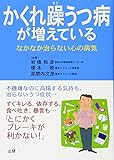 |
かくれ躁うつ病が増えている―なかなか治らない心の病気
1,620円
Amazon |
ちょっと微妙な本です。
この本は、全部で8章に分かれていて、3名の著者が分担して執筆し、まとめた本です。
【1〜4章】 石橋 和彦 著
このパートは面白いです。
著者の岩橋先生が、ご自身が双極性II型でいらして、医師と当事者の立場から執筆されています。
内容は、双極性障害を説明した多くの本と大筋は同じです。
でも特徴的なのは、抗うつ薬とベンゾジアゼピン系薬剤を否定する記載が多いことです。
私が気になった部分を引用します。
(軽度のうつ病患者に対して)
単極性のうつ病だったとしても、本当に抗うつ薬が必要かどうかを判断するために、まず認知行動療法を先に受けるのが望ましいと思います。つまり、薬の投与は認知行動療法の後でもいいのではないかと思うのです。
双極性障害の患者に抗うつ薬を使用しないのはもちろんのこと、軽度の単極性うつでも、抗うつ薬は慎重投与という姿勢です。
私は、この意見には賛成です。
またこんな記述もあります。
躁うつ病の患者さんでは、不安症状に対する抗不安薬は、あくまで期間限定か頓服で使うならいいが、1年以上抗不安薬を使って量や種類が増えていくと、躁うつの波が大きくなったり(不機嫌な高揚感)、躁とうつが入り乱れる混合状態になり、気分がより不安になる。
これは、私自身が経験していますが、ラミクタールで治療する前の半年間は、ベンゾ系だけで治療していました。
非常にイライラした気分と、抑うつ気分がない交ぜになった混合状態で、とても辛い期間でした。
昨今はベンゾ系への警戒が、医師の間でも浸透してきたようですが、8年前に出版された書籍なので、当時にしては少数派の意見だったのではないでしょうか。
【5章】榎本 稔 著
このパートはクソです。
新型うつ病を取り上げて「患者の甘えだ!」と主張していると感じ、非常に不愉快な気分になりました。
当時、新型うつ病だとされていた群の多くは、双極性障害や発達障害がベースにあったと思われます。
それを患者の甘えだと、精神論で一刀両断にする姿勢は、精神科医として如何なものかと思います。たとえ8年前であろうとも。
なんだかなぁ…という感じ。
【6〜8章】深間内 文彦 著
このパートは、うつ病や、うつ病の復職(リワークプログラム)についてまとめられています。
内容は悪くないと思います。
でも躁うつ病のタイトルの本で、何故にうつ病を扱うの???という感じです。
もっと双極性障害に絞った内容にして欲しかった。
唯一、8章の『双極性障害の家族に出来ること』の記載は、当事者の家族には有用な情報かもしれません。
という訳で、この本は前半の1〜4章と8章の一部しか読む価値がなかった。
その内容だけで、半分の¥810で売って欲しいわ!
…と言いつつ、
この本は無料で読んだので、まぁよしとしましょう(笑)
双極性障害の医師が書いた本に興味がある方は、図書館で借りて読むことをオススメします。