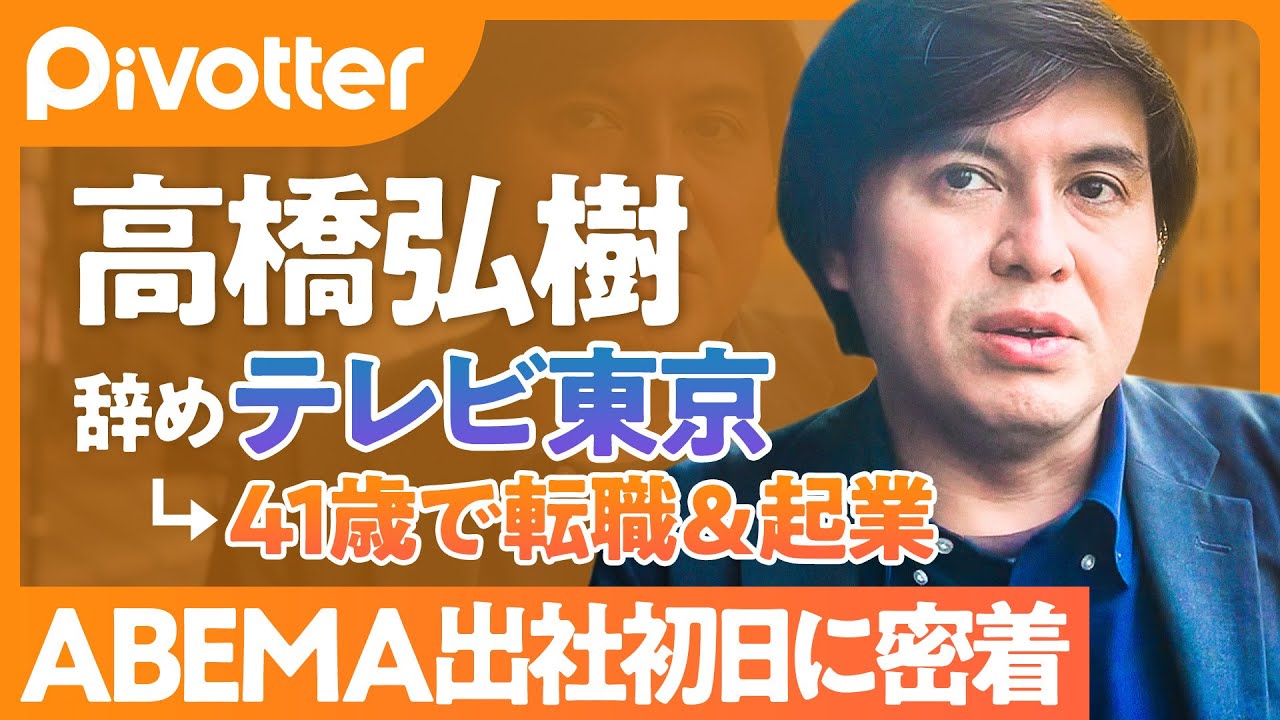こんばんは!
日経テレ東大学が終わるとショックを受けていたのですが、同番組のプロデューサーだった高橋さんが新たに【ReHacQ−リハック−】という番組をYou Tubeで立ち上げられたそうで![]()
ReHacQ−リハック−
↓なんとサイバーエージェントで社員として働きながらの起業だそうです!
社員も既に3人ほど雇っているのだとか、優秀な方は引く手あまたですね![]()
それで新チャンネルを早速拝見させて頂いているのですが↓の回がとても勉強になりました!
最近後藤さんにハマっていましてnoteも会員になりました![]()
まず今回のゲストから。
1人目が門間一夫さん
1957年10月生まれ。81年東京大学経済学部卒業。88年ペンシルバニア大学ウォートン校経営大学院MBA取得。 81年日本銀行入行。調査統計局長、企画局長を経て、2012年5月理事。金融政策担当として、白川方明総裁の下で「2%物価安定目標」の採択に至る局面を担当。13年3月から国際担当として、G7やG20などの国際会議 で黒田東彦総裁を補佐。16年5月退職。
16年6月からみずほリサーチ&テクノロジーズ、エグゼクティブエコノミスト
経歴は↓より抜粋
2人目は窪園博俊さん
時事通信社 解説委員
1989年入社、外国経済部、ロンドン特派員、経済部などを経て現職。1997年から日銀記者クラブに所属して金融政策や市場動向、金融経済の動きを取材している。
経歴は↓より抜粋。本石町日記という読み物が人気となった記者さんだそうです。
今回は日銀の金融政策、主にインフレターゲットについてのお話がメインでした!
日銀の金融政策って断片的には情報を見ていますが、しっかりと勉強したことが無かったので今回はいい機会だと思い番組を参考にしながら気づきや調べたことを以下にまとめていきました!
ご興味あれば見て頂けると嬉しいです![]()
◎インフレターゲット2%というのは世界的な経験則に基づく数値らしい
「そもそも何で2%?」というのが議論で出てきたのですが、これは初めてインフレターゲットを導入したニュージーランドが2%としたのが一つの目安となっているようです。(アメリカのFRBは2012年に2%のインフレ目標を導入、日本は2013年。)
インフレ・ターゲティングは、1988年4月に ニュージーランドにおいて採用されたのを嚆矢に、1992年10月の英国、1993年の北欧2 国等と導入が続き、1998年4月に韓国が経済立て直しの手法として IMFに導入を促されて以降も増加の一途を辿り、2002年末現在22か国で 導入されている(IMF調)
インフレ・ターゲティング導入の経緯・背景 は様々であるが、多くの場合、高インフレや通貨危機(1992年秋の欧州通貨危機、1990年代後 半のラテン・アメリカ及びアジア通貨金融危機、 等)によって損なわれた金融政策に対する信認の回復を図ることを目的として導入されており、 近年でもハンガリー、フィリピン、トルコとい った国々が採用するに至っている。
↑武内良樹氏レポート「インフレ・ターゲティング」より引用
◎なぜインフレターゲットが導入されたのか
そもそもバブル崩壊後の長引くデフレ環境下で、物価を上昇させるためには日銀の金融政策(インフレターゲット)が必要だという論調が強くなったそうです。
(金融政策による長期金利の低下⇒企業がお金を借りやすくなり投資が進む⇒投資が進むと景気が良くなり需要が増える⇒物価が上昇のような流れ)
そしてそのような声も汲み取り、2013年1月22日日銀政策決定会合で目標2%のインフレターゲット導入が決まったそうです。
◎そもそも近年は1%が0%になっただけであり、90年代はもっとドラスティックな金利の変動がある
門間さんが「そもそも近年の金利低下は1%程度であり90年代のようなドラスティックな変動ではない。よって日銀の金利政策如何によって大きく環境が変わるわけではない」というようなことをおっしゃっていたのですが、確かに90年代の10年間の金利の動きのほうがドラスティックであり、昨今の低金利下の状況での日銀の金融政策は影響が限定的であるように思います。その中で大規模金融緩和をこれでもかと続ける必要がどこまであったのだろうかと考えてしまいますね。
↑(社)日本経済団体連合会「魅力的で信頼される国債市場の発展に向けて」よりグラフお借りしました
◎現在の物価上昇はコスト高によるものであり正しい物価高ではない
現在日本でも物価が上昇していますが、これは原油価格や輸入物価が上昇しているためでありコスト上昇が落ち着くと消費者物価も落ち着いてくると予想されている。そのため、日銀としてはインフレ目標は達成されていないという理解だそうです。
◎番組を見ての感想
今回は日銀の中枢で実務をされていた方と、日銀について長年取材されているスペシャリストの方がじっくり話して頂けたのでとても勉強になりました!
私は番組を聞いていて、結局ここまでの量的緩和をする必要ってあったの?というところは「?」のままです。
ただこの番組については後ほど後半がアップされるようなので、アップされるのを楽しみにしたいと思います![]()
![]()
夜も遅い時間になったので今日はこのへんで![]()
おやすみなさい![]()
![]()
![]()