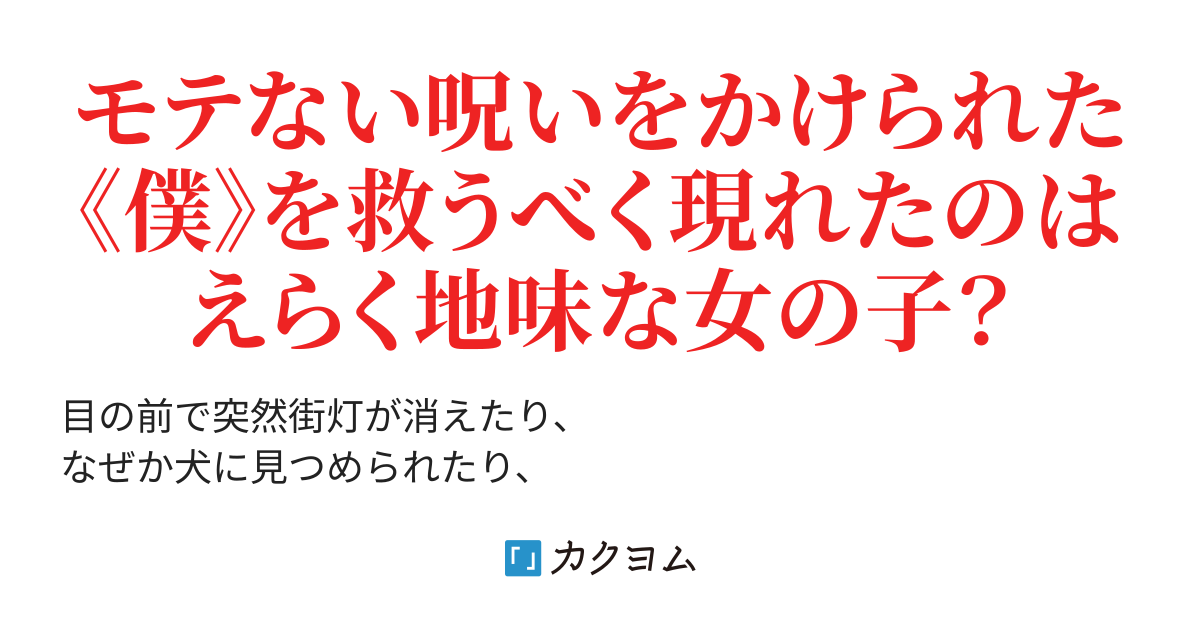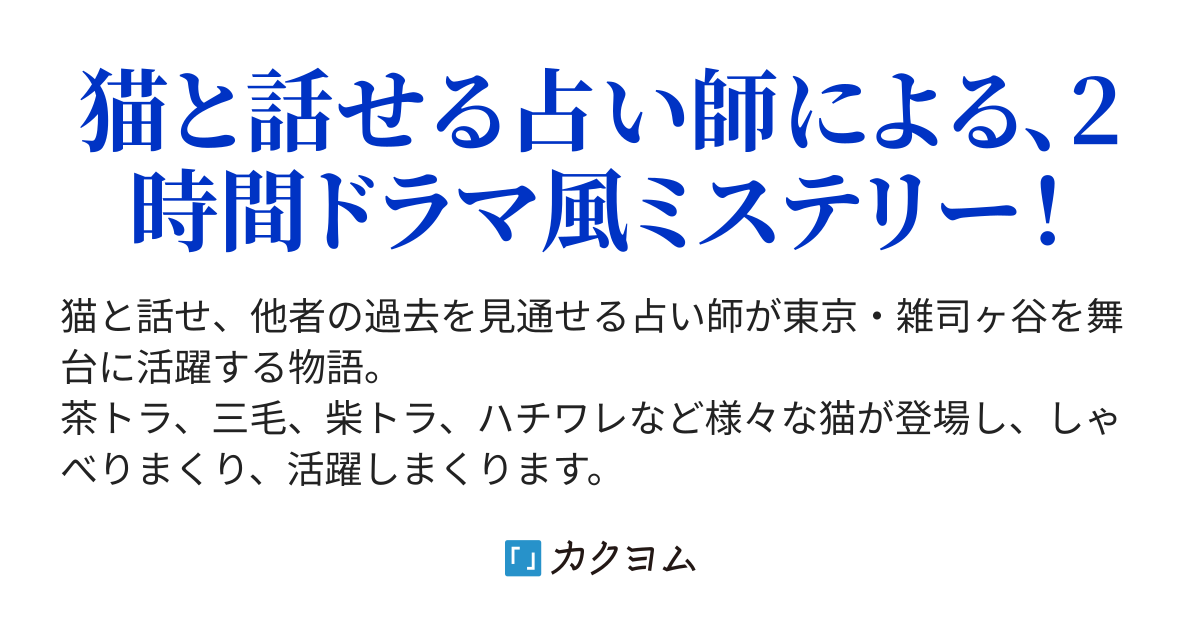しかし、あるときユキはこう言ってきた。
「ミカちゃん、今日はお茶淹れてくれないの?」
たぶん――ミカは今にして思う――そのときの私はちょっとばかりイライラしてたのだろう。仕事でゴタゴタしてるときだったし(新人が理解不能な行動をとってたのだ)、恋人とも別れた直後だった(突然振られたのだ)。いつもであれば溜息まじりではあっても姉のオーダーに応えてあげるところだったけど、そのときは違っていたわけだ。
「たまにはお姉ちゃんがやったら?」
腕を組み、ミカはそう言った。
「私? 私がやるの? だったら要らないわ」
たぶん――ミカはそのときも今も同じように思う――この人は私を便利な存在としか見ていない。それに私を振ったあの馬鹿男だって便利な女と見ていたに違いない。まあ、振られた腹いせが姉への感情にマイナスの上乗せをしたのは確かだけど、憤然たる面持ちで部屋に戻ろうとした。すぐ出ればよかったのだ。そうしていればキッチンから顔を出した母親がこう言うのを聴くことはなかった。
「あら、ミカ、今日はお茶淹れてくれないの?」
一瞬立ちどまり、ミカは辺りを見まわした。なんだか嫌な雰囲気だ。そして、それをもたらしたのは自分だと思うと居たたまれなくなった。誰かが悪いとしたら、それは私だという思いと、でも自分に悪いとこなんて一つもないという思いが交錯してわけがわからなくなった。ミカは最後にもう一度だけ父親を見た。もしかしたら救いになるようなものがありはしないかと期待したのだ。しかし、父親は「おやおや」といった表情のまま固まってる。
ミカは激しい音をたてドアを閉めた。
とはいっても、そんなことでミカはへこたれない。泣きたいことがあったら精一杯泣いて、翌日まで持ち越さないようにしてる。仕事は楽しかったし、職場も(変な新人がいるにせよ)悪くない環境だった。ミカは受け答えが丁寧で、お客様には親切で、売上げも上位の方だった。そのうちマネージャーになって、さらにそのうちエリアマネージャーになって――と野望を持って生きている。
そして、野望が実現できたら馬鹿げた家から離れ、ふたたび独り暮らしをしたいと考えていた。それに、仕事上の野望は果たせなくても、いつかはいい男に巡り会って二人暮らしをするようになるかもしれない。
まあ、とにかくどうにかなれば、この家から逃れられる。人生の目的の一つが家を離れることになるとは思ってなかったけど、内容はともかく目的があるのはいいことだ。だから、どんなに忙しくても、ひどいクレームがあってもミカは前進するのだ。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》